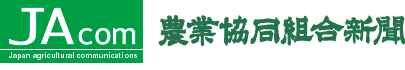農政の“観察者“として
「いはらき」という平仮名だけの新聞の題字をJR常磐線の水戸駅(茨城県都)の売店で見た時、奇妙とも、逆に面白い土地柄とも入り混じった感じをまだ覚えている。1958年、数十年も前のことである。
もっとも、「いはらき」は創刊100周年(1991年)に茨城新聞に変わったが、御一新からで、すでに一定年数を経た明治24年に敢えて「いはらき」と銘打って発刊した。“水戸っぽ”の決断力というか、その雰囲気の大きさにシャッポを脱ぎたい一瞬を感じた。
甲斐の山国育ちとして、麗峰・富士の麓というのはいいとしても、北麓は高冷の程が厳しく、足元も溶岩ばかりの空漠さで、耕地などは見つければやっとというぐらい。
次第にもっと広い、平野らしさのあるところに住んでみたいという気持ちが芽生えていた。その点、茨城は利根川・霞ケ浦を擁しながらも、調べてみると田畑がそれぞれ10万haもあるずば抜けた農業。後年、筑波学園都市プランが難なく収まったことでも、空間の広がりが分かる。
◆第2の故郷「いはらき」
ずいぶん経ってのことだが、私が第2の故郷と呼ぶようになったわけの一つは、「いはらき」はこうした感覚を与えてくれる土地のせいである。
茨城に負う、あと一つのこととは、振り返ると結局、私は農漁村の経済問題を主題に追い、自称「オブザーバー」(観察・評論家)で、糧をいただいてきたが、そのきっかけや土台を与えてくれたのも、最奥にあるものはやはり水戸だった。
日本経済新聞は、部数を誇る3紙(朝毎読)と違って、警察ダネは不要で、大新聞のようにサイドカーもなく、明治9年の「内外物価新報」(三井系)以来、「内外商況の版刻」に特化してやってきた。株や生糸の大物は別格で東京扱いだが、茨城にも蒟蒻(荒粉)から菜種・菜種粕、落花生、蒸切干し、かますまで多彩。
重点記事の「週報」はベテラン支局長の専管事項。新米記者は周辺取材と称して、市町村単協の担当者に産地の近況を聞いたり、産地問屋(加工、集荷)を尋ねたり、嵐(農地改革)の後だったので、農民組合の活動を尋ねたり、結城紬や、当時新興の古河市の洋傘工場などにも足を運んだ。
だが、やがて行き詰まりがきて、半ば、今でいう鬱っぽい毎日になった。「相場」とか「市況」といっても、株式などに見える形で存在するが、目前の商品は、需給といってもまるで雲をつかむ程度にも分かっていない。では誰が、どういう方法で決めているのか。実際上は慣行取引の中で、時間をかけて決定されるわけだが、その先に、眼前に広がる茨城の農業、都市の工場と、わが国の経済全体とはどんな関係でここまで来たのか。
書店でやみくもに手にしたのが、「日本資本主義の農業問題」(大内力著)での高率小作料、過剰人口、日本経済の後発性などの相互の関係が鮮やかで、自身、落ち着いた感じを覚えたことをいまでも憶えている。
◆根本忠氏との出会い
 ほぼ、同じ時期のこと、取材先の県経済連(現在のJA全農茨城県本部)の広報課で、一際目立つ職員と知り合い、茨城弁の懐っこさもあって、例の「相場」論を持ち出したり、農家に会うと「安くて買いたたかれて」が口癖のようだなどと、つい不躾に―。
ほぼ、同じ時期のこと、取材先の県経済連(現在のJA全農茨城県本部)の広報課で、一際目立つ職員と知り合い、茨城弁の懐っこさもあって、例の「相場」論を持ち出したり、農家に会うと「安くて買いたたかれて」が口癖のようだなどと、つい不躾に―。
嬉しかったのは、その根本忠さんが、[1]インフレが、戦後ずっと続いているのに、米価は押さえられて不満がたまっている、[2]野菜や果物、芋類も生ものという問題はあるけど、結局は共同出荷プラス共計、やり方の工夫も大事だけれど、などと正面から応じて、新米記者にあれやこれや教えてくれたことだ。間もなく、戦争中は仙台の幼年学校にいて、同期生(私は東京)だったことも分かり、終生続く友人となった。
周知の赤城宗徳(後年、農林大臣など)について評判、力量のほどを私に吹き込んでおいてくれたのも根本さんで、その後、公職追放中の思索を綴った小冊子「苦悩する農村」(昭和28年、万有社刊)を署名入りでいただいた。「農村は都市の植民地だ」とか、「増産、増産と掛け声をかけるより、テコとなる価格問題の解決が先」などと記し、結局この本も、私と一緒にいて、私を見張っていてくれたように思う。
(写真)
「苦悩する農村」の本
◆「現場を丹念に踏み…」
水戸離任時の昭和30年は神武景気で、「もはや戦後ではない」は翌年の経済白書。「現場を丹念に踏み、先輩・同僚に当たって勉強すれば―」というのが、その時の最大の印象だった。
農政ジャーナリストの会の結成、「季刊・農政の動き」による研究会記録の発刊は、そうした思いが誘われて形になったもの。農業・農村系の編集委員兼論説担当になったとき、米の構造的過剰が表面化したころで、その時私は、旧知の米ファーマーズ・ユニオン会長、ジェームス・G・パットン氏の「過剰時、大企業が生産管理に精を出すように、農業もその原理を取り入れるべき」との意見を思い出していた。
最近のアベノミクスも、多忙に無理があるのか、荒々しさを窺わせる提案がふえてきた。米国のヘリコプター稲作と東アジア・日本の稲作を素手で向き合わせることはどだい無理。地味でもここは、「人・農地プラン」の実施に素直に取り組むとき。それこそ歴史に名を刻むというものだろう。
【推薦の言葉】
農政の後輩記者育成
山地氏は農業ジャーナリストの最長老である。日本経済新聞社在勤中は、支局勤務の一時期を除き一貫して農林水産業担当記者として活躍した。論説委員・編集委員時代は社説やコラムに健筆をふるう一方、1969年には『経済評論』誌に「農産物の自由化と総合農政」と題する論考を発表。高い評価を得て、後に農山漁村文化協会の『昭和後期農業問題論集』にも収録された。
農政審議会、米価審議会の委員にもジャーナリスト代表として名を連ねるなど、多方面に影響力を発揮した。また、1981年から6年間にわたって「農政ジャーナリストの会」の会長を務めた。会長の時に設けた「農業ジャーナリスト賞」は、仲間のジャーナリストを表彰するという異色の賞は、特に地方の報道機関で働く農業ジャーナリストたちにとって大きな励ましとなっている。
【略歴】
やまじ・すすむ
昭和4年生まれ。
20年終戦で旧制都留中学に復学。28年京都工芸繊維大学卒業、同年日本経済新聞入社、44年編集委員兼論説委員、59年東海大学政経学部教授。現在農政ジャーナリストの会顧問、内外食料経済研究会代表。