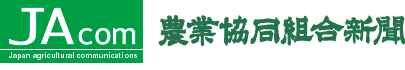「協同」こそグローバル化時代の農業・農協の使命
◆歴史は「今」を知ること
 このたび『農業・食料問題入門』(大月書店)を上梓した。『農業問題入門』(1992年)の事実上の第三版にあたる(第二版は2003年)。前半では戦後日本の農業・食料問題を歴史的にトレースした。後半は食料、価格、構造、農協、都市と農村の現状分析にあてた。本書は歴史を縦糸とし現状を横糸としている。タイトルに「食料」を入れ、また「都市と農村」で締めくくり、地域の自立と連携に21世紀の方向を求めた。
このたび『農業・食料問題入門』(大月書店)を上梓した。『農業問題入門』(1992年)の事実上の第三版にあたる(第二版は2003年)。前半では戦後日本の農業・食料問題を歴史的にトレースした。後半は食料、価格、構造、農協、都市と農村の現状分析にあてた。本書は歴史を縦糸とし現状を横糸としている。タイトルに「食料」を入れ、また「都市と農村」で締めくくり、地域の自立と連携に21世紀の方向を求めた。
執筆時は、政権交代、TPP問題、東日本大震災と原発事故に重なった。これまで営々と創り上げてきたものが音をたてて崩壊していく日本沈没の危機である。
このような混迷期の原因にメスをいれ、再生の道をさぐるには歴史を顧みるしかない。歴史とは、事件を時系列的に並べることでも、歴史的教訓の玉手箱でもない。「今」の拠って来たるところを知ることである。そこで戦後農業・農政の遺産と課題について述べたい。
◆戦後改革の遺産
アメリカは占領当初は「戦後改革」で日本の民主化を追求したが、東西の冷戦体制が顕在化しだした1947年あたりから「占領政策の転換」に舵を切った。しかしそのなかで農業は大きな転換がなかった。いいかえれば農業では「戦後改革」の良質の部分が残った。
農地改革の結果としての農地法は、農地取得の権利を耕作者(農家)に限定し、農外者や株式会社のそれを禁じた。また農地はあくまで農地として利用すべきものとして、その転用を厳しく統制した。これらは資本主義の浸透に対する農業保護制度の土台になった。今日でも株式会社の農地購入は認められていない。
そのほか、農業協同組合、土地改良、農業共済、農業改良普及制度等の骨組みがつくられた。戦後の10年は、農村が貧しくはあったが最も明るい時代だった。
先頃、26回JA全国大会が開かれたが、決議に初めて「協同組合原則」が掲げられた。原点に立ち戻ろうというわけである。農協と自治体・普及員制度等との連携強化も唱われた。これらは戦後改革の良き遺産だが、今日それを規制緩和で洗い流す動きが強まっている。
◆高度経済成長と農業
高度成長=重化学工業化は、日本の国土を大平洋ベルト地帯とその他の地帯に二分し、後者を過疎に追い込み、兼業稲作を普遍化し、穀物自給率を半減させた。農業基本法は、そのような高度成長に寄りかかりつつ農業の近代化を果し、もって高度成長に貢献することを目的とした。
しかし他方で、農業基本法は農業総生産の増大、輸入制限・関税引き上げを唱った。その結果は無残で、国境保護はグローバル化のなかで今や風前の灯火だが、それでも新基本法は「国内の農業生産の増大」を引き下げることは出来ず、日本はWTOでは「多様な農業の共存」を主張している。その主張からはTPP参加は絶対に出てこない。
基本法農政の構造政策というと、個別の規模拡大、自立経営の育成一本槍に理解されるが、協業の助長が同列に置かれており、後者の方が生産組織、集落営農等の展開として、その後の構造変動の主流になった。農業基本法の立案者たちがほんとうはどちらを重く見ていたのかは今もって謎であり、我々は歴史からみていく必要がある。
◆転換期と農業・食料問題
本書では、1970年代を高度成長期からグローバル化期への転換期とした。この時期は短いにもかわらず今日の農業・食料問題と農政の基調を作った。
まず「農業問題」から「農業・食料問題」への転換が始まった。1970年は、大阪万博へのファストフードやファミリーレストランの出展、すかいらーく1号店の開店をもって「外食元年」とされた。加工食品、外食、ついで中食のウエイトが増し、生産者と消費者の間が遠くなった。消費者の直接の関心が農業から食料にシフトするなかで、農業問題も農政も食料に主戦場が移りだした。農業者も食料問題を通じて農業問題を訴える必要が生じ、消費者との連携、産直等も登場した。
農政は、地域や農協の調整力を活用して生産調整と農地流動化を進める「地域農政」に転じた。この頃から農業経営の多数が農業を自己完結的に営めなくなり、作業受委託や賃貸借が本格化し、他方では生産組織化に取り組むようになった。 「点」としての自立経営の育成もさることながら、日本農業、とくに水田農業は、地域として面的に取り組まねばならないことが明確化した。そこで改めて地域ぐるみ組織としての農協の役割が注目され、また「自治体農政」が強調されるようになった。
「点」としての自立経営の育成もさることながら、日本農業、とくに水田農業は、地域として面的に取り組まねばならないことが明確化した。そこで改めて地域ぐるみ組織としての農協の役割が注目され、また「自治体農政」が強調されるようになった。
またこの時期にエネルギーの原子力依存体制が固まった。日本は、核武装の潜在能力を保持するために、アメリカが1953年に打ち出した「原子力の平和利用」に飛びついたが、高度成長期には石炭から石油へのエネルギー革命に依存した。
しかしその石油が73年のオイルショックで高騰すると、原発に決定的に依存するようになった。そのツケが40年後に回ってきて、人と大地と食料を放射能で汚染することになった。日本は今、エネルギーでも新たな「転換期」をむかえている。
(写真)
集落営農などの“協業”が農業構造変動の主役になっている(写真提供:JA加美よつば)
◆グローバル化期の農業・食料問題
1980年代後半からグローバル化が始まる。それには二つの捉え方がある。一つは、ポスト冷戦=アメリカ覇権の下でのグローバル化であり、アメリカ流資本主義のやり方をグローバル化することだ。もう一つは、世界が一つに結ばれるグローバル化を歴史の必然としつつ、グローバル化するから逆に地域個性が際だつのだとして、その共存を求める方向だ。
スティグリッツ『世界の99%を貧困にする経済』(徳間書店)は、今日のグローバル化の弊害を、市場メカニズム一般ではなく、市場メカニズムに対する規制撤廃の問題、すなわち市場メカニズムを「野放し」にする政治政策の問題だとする。グローバル化時代だからこそ、政治あるいは主権国民国家が果すべき役割が重要だというわけだ。
ポスト冷戦=アメリカ覇権型グローバル化を代表するのがTPPだ。TPPは今や、一農業問題から国家・国民主権をアメリカ多国籍企業に委ねるかどうかの問題になっている。国家・国民主権よりも個別の多国籍企業の利益を上位に置くのがTPPのISD(投資家・国家間紛争解決)条項である。
朝日新聞の世論調査(8月28日付け)によると、TPPについて「日本経済に良い影響」35%、「悪い影響」37%。農業へは「良い影響」20%、「悪い影響」60%。「コメを関税ゼロから外すべき」60%、「必要ない」32%。「日本の交渉力に期待できるか」については「あまりできない」58%、「全くできない」20%、である。にもかかわらずTPPに「賛成」が44%で、「反対」37%を上回る。 なぜか。国民はTPPが経済的に損なことも、政府に交渉力がないことも十分に承知している。にもかかわらず賛成に追いやられるのは尖閣諸島問題だ。尖閣諸島をめぐる日中対立が、TPPを安全保障問題にすり替え、国民を日米同盟・日米安保強化に傾かせている。
なぜか。国民はTPPが経済的に損なことも、政府に交渉力がないことも十分に承知している。にもかかわらず賛成に追いやられるのは尖閣諸島問題だ。尖閣諸島をめぐる日中対立が、TPPを安全保障問題にすり替え、国民を日米同盟・日米安保強化に傾かせている。
しかし、本紙7月10日号に登場いただいた孫崎享氏は、中国のミサイルがアメリカ本土を直撃しうるようになった今日、アメリカは自国民を危険にさらしてまで日本を守らない、と警告している。とすれば、TPPは、安保問題から切り離して、冷静に通商上の損得問題として考えるべきである。グローバル化の潮流は、アメリカの覇権国家としての凋落と、中国を初めとする新興国の急台頭を促した。日本の貿易相手は、TPP諸国が1/4なのに対して東アジア共同体をめざす国々は5割だ。経済の深い連携がある限り、国境問題はいずれ沈静化する。
グローバル化対応の小泉構造改革は、財政や公共事業を通じる地方への所得再配分を切り捨てた。その結果、この時期に日本の地域間格差は再び高まった。ここにも国が果すべき役割がある。
(写真)
第26回JA全国大会が開かれたNHKホールで参加者によびかける全青協の盟友
◆地域自立は人づくりから
「日本が原発導入に向かった最大の理由はアメリカの世界戦略です」(9月4日の朝日新聞における吉見俊哉東大教授の発言)。また朝日新聞は9月25日付けで、「原発同盟 維持迫った米」を載せている。2030年代に原発ゼロを閣議決定しようとした野田内閣に、アメリカが「ノー」を突きつけたというものだ。食料にしてもTPPにしても原発にしても、問われているのは国家・国民主権だ。
同時に国の自立は地域の自立に支えられる必要がある。自立の基礎には食料とエネルギーの自立がある。食料は太陽エネルギーの有機質エネルギーの転換である。再生可能エネルギーは、太陽光にせよ、風力・水力にせよ究極には太陽エネルギーに依存する。そして太陽エネルギーを受光するソーラーパネルが敷かれるのは首都圏、大平洋ベルト地帯ではなく、その他の地域・農村だ。食料とエネルギーは地産地消こそがふさわしい。
いま、集落営農やその法人化として地域協業が追求されている。それはグローバル化の地域浸透に対する意図せざる対抗でもある。基本法農政の「協業の助長」は今も生きている。ただし助長の主体は、国ではなく農協や自治体になった。
農業や農協には、そういうグローバル化時代の人類史的使命がある。高齢化のなかでそれを担うには「人づくり」、広い意味での教育しかない。本紙10月10日号の対談で、種市一正・三沢市長は、「市民自らがどういう町でありたいか」を提案してもらう「協働のまちづくり」を提起している。課題はそういう提案ができる主体的な「人づくり」だ。これには時間をかける必要がある。
折からJA全国大会は支店拠点化を打ち出した。支店は中学校区、昭和村のエリアが多い。そこらを一つの地域単位として、「広域合併農協のなかに『小さな農協』」を創る」、自治体・地域住民と連携して地域自立を強める。地域からの日本再生、そのための協同づくり、人づくりが歴史的課題である。