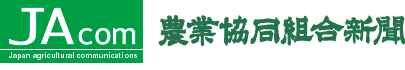鈴木 地域の経済社会の在りようについて内橋先生はかねてから「共生経済」、神野先生は「分かち合いの経済」という言葉で提起されています。東日本大震災の経験を踏まえ、改めて、その提言の本質をまず内橋先生から語っていただきたいと思います。 内橋 被災地を訪ね、被災者の方々の不安やいらだち、さらには怒り、そして何をなすべきかわからぬまま放置されている、そういう現実の苛酷さをひしひしと感じています。
内橋 被災地を訪ね、被災者の方々の不安やいらだち、さらには怒り、そして何をなすべきかわからぬまま放置されている、そういう現実の苛酷さをひしひしと感じています。
大震災の前後から、「自助・共助・公助」とか、「絆」「新しい公共」といった言葉がよく使われるようになりました。が、それらの言葉の中にはたくさんの落とし穴があります。
自助、共助はなるほど大切ですが、しかし恐慌、巨大複合災害など国家的危機に際しては、何をおいても公的支援の発動こそ緊急の要です。ところが国・政府は自ら「なすべきをなさない」まま、定義も定かでない「共助」を指して「新しい公共」などといいはじめました。「がんばれ日本」とか「日本の力 信じよう!」「日本はひとつ」など、空疎な言葉だけが氾濫する・・・。
むろんのこと、互いの助け合い、善意、ボランティアのたいせつなこと、いうまでもありません。しかし、「戦争」「恐慌」「巨大災害」においては、「正統な政府機能」の発揮こそが正義です。今回のような巨大複合災害からの人間復興には、国・政府による「公的支援」のほかに真に実効性ある対応など、とてもできるものではありません。個人の善意、ボランティアはむろんたいせつですが、明らかに限界がある。
それを、公的支援もないまま助け合いとかボランティアなど「共助」だけを強調し、肝心の「公助(公的支援)」は放置されたまま。メディアもまた美談づくりに精を出す。これで被災者はほんとうに救われるのでしょうか。どのような巨大災害でも人間の基本的な人権、生存権は侵されてはならない。そういう透徹した人権感覚というものが国・政府の側になければ、辛い日々に耐えておられる被災者にとって希望の灯が点るはずがない。甘い言葉、実態のともなわない責任逃れの言葉の氾濫に、私は危機感を深めています。
(写真)内橋克人氏・経済評論家
◆協同組合が救い
また、自然災害と人災の重なり合う巨大複合災害なのに、受けたショックの度合い、深刻さの認識に、列島の東西で温度差があります。関西、四国、九州と被災地から離れれば離れるほど危機感の程度に明らかな格差が出ています。いちばん大きな温度差があるのは、被災地と霞ヶ関、永田町、もっといいますと、被災地と首相官邸の間ではないでしょうか。
これでは被災者は救われません。震災から100日過ぎてなお避難所に11万人。その中には病気を抱え生命の危険にさらされている被災弱者も少なくない。
振り返ってみますと、阪神・淡路大震災から16年経ちます。震災は終わったのか、といえば、決してそうではない。たとえばこの16年の間に、誰にみとられることもなく「復興住宅」で亡くなった孤独死が累計で900人を超えています。高齢者を中心に・・・。災害のひどかった神戸市長田・灘・東灘区ではいまだに自殺率が突出して高い。16年経ってなお震災は終わっていないのです。
この間、協同組合は確かに被災地でよく頑張っていると思います。協同の精神がほんとうに生きる支援活動を展開されてきた。被災者にとっては大きな救いです。残念なことに国・政府が真に「公的支援」の名にふさわしい活動をなさないまま、助け合いとか絆とか、個人や団体の「個別的善意」に頼らざるを得ない苦境に、いまもなお多くの被災者が放置されている。真の危機がここにあるのではないですか。
いつの間にか降ってきた放射能に追い立てられた計画的避難区域、あるいは20キロ圏内の警戒区域の人びとに、集落全体の移住、たとえば首都圏の郊外地などへの集団移住、つまり「新しい村づくり」など、真の公的支援の名にふさわしい対応が、なぜできないのでしょうか。この苦難のときにあって、あいも変わらず財政危機ばかりを叫ぶ連中がいる。彼らは人間の顔をした“財政モンスター”ではないですか。
阪神淡路大震災では、いまは亡い小田実さんが先頭に立ち、私たちも一緒になって被災者支援法をつくらせる「市民・議員立法」の運動を始めました。市民が声をあげることによって、何年も後のことですが、一応の法律ができました。それまでは私たちの国には被災者を救う公的支援の概念も制度も、何ひとつなかったのです。
阪神・淡路大震災から4カ月後、村山富市首相は国会で「自然災害等によって生じた被害に対して(国は)個人補償をしない、自助努力によって回復してもらう」(95年5月19日、参院予算委員会)と言明しました。
そのような現実のなかで、被災者自らがまず声をあげていかないと、公的支援は永遠にやってこない、ついには社会的孤絶、棄民の運命が待っている、そういった阪神・淡路大震災でのせっぱ詰まった経験を話しますと、現地では「やはりそうか」と初めて気づかれる被災者の方々も決して少なくありません。
◆救済の基盤なし
あのとき(阪神・淡路大震災時)、事実として行政の中には「(震災は)チャンスだ」とまで表現したものがいたのです。それまで市民の反対で滞っていた区画整理事業、基幹道路や行政による街づくりを進める好機だという・・・。
そういう考え方が存在する国だということをしっかりと認識して事に当たらなければならない。被災者の方々を社会的に救済する基盤、条件というものが、いまなお確立されていない日本。被災地救援をいうのであれば、それなりの覚悟をもって事に当たるほかにない。被災者もまた自ら声をあげなければならないのではないでしょうか。
鈴木 国がなすべきことをなしていない、だから被災者は救われる状況にないということですが、神野先生はそのあたりをどうみておられますか。 神野 内橋先生のおっしゃる通りで、そもそも財政の使命は、こういう非常時に危機を解消することにあります。
神野 内橋先生のおっしゃる通りで、そもそも財政の使命は、こういう非常時に危機を解消することにあります。
ドイツの財政学にある租税原則の第一は十分性の原則です。公共サービス・公共事業をやるために十分な税収を確保しなければならないというものです。第二は可動性の原則です。これは戦争とか大災害が起きた時、ただちに財政需要をまかなえるように、わずかな税率操作だけで増収に応えられる税体系をつくっておかなくてはならないというものです。
今回の日本の場合、関東大震災の時に比べて対応が遅すぎます。関東大震災のころは法律と同じ効力を持つ勅令というのを出せたので、これをすばやく連発しました。まず戒厳令が出ます。このため思想家の大杉栄と伊藤野枝らが憲兵将校に殺されるという犠牲者も出ました。次いで、税の減免・執行猶予、やがてモラトリアムとかが打たれていくわけです。
ところが、財政が復興事業に応えられなかったために、逆にデフレを深刻化させて金融恐慌に陥るという経験を私たちは持っています。
◆最高の価値は人命
今回を見ても復興事業と財政再建との調和がいわれますが、財政が危機だというのは、経済的、社会的な危機を財政が解消できない状態をいうのであって、収支バランスのことをいうのではないのです。
私はスウェーデンのオムソーリという言葉をもとに、「分かち合いの経済」を唱えています。このオムソーリとは、公共サービス、社会サービスを意味しますが、そもそもは“悲しみの分かち合い”の意味なんです。
スウェーデンモデルの考え方は1929年の世界恐慌に苦しみ、1932年に社会民主労働党が初めて政権を取り、ハンソン首相が「国民の家」構想を掲げます。
この構想は、国家は家族のように組織化されなければならないというものです。家族の構成員はどんなに障害を負っていようと、家族のために貢献したいと願っている。国民も同じようにだれもが、国民のために貢献したいと願っているにも関わらず、その切なる願いを失業は打ち砕いてしまう。それだから失業問題を解消しなくてはいけない、といった考え方を基盤にしています。そうした考え方を「分かち合い」という言葉で表現しました。
今度の震災では、生きるか死ぬかという厳しい現実を眼前にして、誰しもが人間が生きるということの大切さを改めて見直し、社会は人間の生命に最高の価値を置く価値体系のもとに、形成されなければならないというように思っているはずです。
生命に最高の価値を置くと、「共に生きること」、内橋先生の言葉を使えば「共生」ということが重要となります。「共に生きる」ためには、自分も社会に「参加」することが大切です。市場なら退出するかしないかですが、共生では決定参加しなければなりません。つまり国民は「生命」と「共生」と「参加」という3つの論理が大切だとの自覚をしたのではないでしょうか。
協同組合の原理原則は、この3つの論理とつながっていくと思います。しかも、こうした大災害から見出した価値を持続していくことが大切です。
関東大震災前後の財政を書いた『最近日本財政史』いう本は大震災の“成果”として、日本をはじめ世界中から義援金が集まったことを挙げ、この恩は世界平和のために重要だと述べています。
ところが、現実には恩返しどころか日本は、金融恐慌に入っていって、よその国へ攻め込みました。だから大災害から見出した価値は、持続させないといけません。
阪神淡路大震災ではボランティア元年といわれるほど支援活動が高揚しましたが、今回はそれが3分の1ほどに減っており、近年は“無縁社会”といわれるほどの事態に陥りました。
(写真)神野直彦氏・東京大学名誉教授
◆“ゴーストタウン”
神野 “がんばろう”と掛け声を掛けるのはいいのですが、東大が招聘した韓国の学者は、こんなことをいっていました。
日本人の住宅は小さくてみすぼらしく、韓国の新築マンションよりも狭いけれど、小学校の教科書には日本が経済大国であるとは書いてあるが、国民は住居の狭さに苦しんでいるとは書いていない。これでは庶民は“がんばろう”を叫ばないと生きていけない。その言葉の意味合いが日本人の生活を見て初めてわかったという話でした。確かに“がんばろう”という言葉には気をつけないといけませんね。
さらに、これからの社会保障は公助ではなく共助であるという社会保障・税一体改革の方向も指摘しておきたいと思います。そこでは家族やコミュニティの共助だけでなく、社会保障も共助になっています。 鈴木 自助・共助・公助の区分けがあいまいだったということを私自身も自覚しました。もう1つは国家観が欠けたまま何となく過ごして来たということです。政治家の中にも、国家としてどうあるべきかの考え方がないまま政治家になっている人が多く、だからリーダーシップを発揮できない総理が何代も続くのではないかと思います。
鈴木 自助・共助・公助の区分けがあいまいだったということを私自身も自覚しました。もう1つは国家観が欠けたまま何となく過ごして来たということです。政治家の中にも、国家としてどうあるべきかの考え方がないまま政治家になっている人が多く、だからリーダーシップを発揮できない総理が何代も続くのではないかと思います。
内橋 阪神淡路大震災では復興の看板を掲げさえすれば何でもできるというやり方がまかり通りました。被災者救援のためでなく、公共事業などのチャンスをつくるというものでした。「復旧でなく復興を」の象徴として巨大ビルに神戸空港、幹線道路の建設・・・。それらはいまどうなっているか。巨大な資金でつくられた神戸空港は採算がとれず、もはや手の打ちようがない。全焼した新長田駅南地区で進められた面積20ヘクタール、総事業費2700億円という巨大再開発事業も、いまは壮大なビル内のほとんどがシャッター通りではないですか。
これはすでに書いたところですが、今回の被災地のほとんどはことのほか地域経済力が弱っている地域でした。震災前の平時の長期予測でも宮古、気仙沼、釜石、いずれも人口規模にしろ域内総生産にしろ、近い将来、大幅な減少が予測されていた地域ばかりです。
2030年の予測がフィルムを早巻きして今に立ち現れたようなものですね。その自治体に国は的確な財政的支援を与えることもなく自助を求める。
(写真)鈴木利徳氏・農林中金総合研究所常務
◆夢物語の日本像
内橋 宇沢弘文先生(経済学者)は私との対談のなかで、世界大恐慌に対処した米ルーズベルト大統領の決断について話されています(『始まっている未来』2009年 岩波書店刊)。
世界大恐慌の発生4年後、大統領に就任したルーズベルトは、その昔、つまり独立戦争時代の「対敵取引法」という古い法律を活用しました。国家的危機に際して、議会の審議を経ることなく大統領の通達ひとつで新しい法律や制度をつくることができる。1933年、就任と同時に取りかかったのが、よく知られるニューディールでした。一つがグラス・スティーガル法(金融・証券業務の峻別)。そしてもう一つが著名なTVA(テネシー川流域開発公社)構想でした。流域の南部7州を農業中心に開発を進める。全て連邦政府の資金と責任で、失業の解決、雇用の創出、貧困の社会的救済を求めて・・・。
大恐慌も戦争も巨大災害も、すべては国家的危機である、とみなしてのことでした。
これは、例によって市場原理主義者らの激しい抵抗に遭い、結局は連邦政府資金ではなく、地方政府の資金で事に当たらざるを得なくなりましたが、しかし、若ものたちを中心にルーズベルト連合が立ち上がり、大きな効果をあげました。宇沢先生は「社会的共通資本の形成とその安定的な運営を通じて二度と大恐慌のような大惨事が起こらないようにしようということだった」とその意義を評価しておられます。私は、国家的危機に臨む政府のあり方として、こうした責務の遂行こそ「正統な政府機能」だと思います。
この国では黙っていて、公的支援の手が伸びてくることはありません。原爆医療法の制定でも、さまざまな公害訴訟でも、阪神・淡路大震災でも・・・。
鈴木 危機の時に国家がなすべきことをしないというのは、平時においても国家に大きな欠陥があったということになりませんか。
内橋 国家のあり方について、昨今は「・・・の誇り」といった日本自賛論がベストセラーになる世になってしまいましたが、たとえば生きて行く人間の基本的人権ひとつ、ほんとうに大切にされてきましたか。自賛本のほとんどは「あらまほしき日本像」、つまり「こうあって欲しい」と願う類の夢物語です。武士道などといいますが、武士の切り捨てごめんがまかり通った封建時代がそんなに理想社会なのか。また東北大飢饉時での娘の身売り、戦前・戦中の赤紙一枚の徴兵・・・。
過去の日本は克服の対象であって賛美の対象ではない。「古き良き日本」のフィクションにまどわされて、結局は上からの「権論」に加勢している。そうではなく、人びとの現実の暮らし、働きの場をしっかりと見据えて、国・政府の欠陥を糾していく、それが「民論」の基本です。緊急時にも平常時モードでしか対応しようとしない国・政府が、どうして「あるべき統治の姿」といえるのでしょうか。
◆復興ファシズム
内橋 政府の復興構想会議にしても、目の前で命の危機と闘っている人びとのことが視野に入っていない。その姿勢のまま港の周辺の建物は何階以上に、だとか、高台に住宅を、とか、ご託宣が並べられている。「これは2次災厄」と神戸大学教授の塩崎賢明さん(阪神・淡路大震災の際、多くの活動を続けたことで知られる)は『“創造的”復興で2次災厄も』と批判を展開しておられる(『週刊エコノミスト』5/24)。
復興構想会議の打ち出した基本方針、その他「創造的復興」などの言葉とその由来―もともとは阪神・淡路大震災で当時の兵庫県知事が唱えた言葉であること―などを紹介したうえで、「現時点では、多くの被災者が避難状態で、日々、生命・健康が脅かされており、そのニーズがきちんと捉えられているとは思えない」と書いておられる。全く同感ですね。
復興構想会議にしても、その中には住民の立場に立つ学者もおりますが、なかに行政の立場で、阪神・淡路大震災後においても住民の救済でなく、道路や区画整理事業など行政のプロジェクトを裏付けた学者がいる。案の定、復興財源は増税で、とはやばやと建議しました。復興ファシズムの先導役ではないですか。
平常時において正統な政府機能というものを発揮できない政府・行政に、非常時に迅速な被災者救援は可能か、と。時代を横につないで、ほんとうに国民、市民を守る立場を貫いた政府がこの日本に存在したことがあるのなら、その歴史的事実を教えて頂きたい。
鈴木 次に原発問題ですが、誰しもが原発事故が復興問題を複雑にしていると思っています。これについては神野先生、いかがですか。
神野 (原発の危険性について余り発言してこなかったことについて)私のような者の責任は重いと感じています。
福島の原発は私たちの大学時代から建設が始まりました。当時、原発の寿命は20年といわれていましたが、その後をいかに解体し、使い終わった燃料棒をいかに措置するか、全く見通しがないのに、この狭い日本に54基もつくってしまった。
原発は危険だということを十分認識している人がつくってこそ、ようやくリスクから逃れられるかも知れないというのに、危険ではないという人が進めたらとんでもないことを知っていながら、結局は無力にもこういう事態を招いてしまった、という責任は非常に大きいと思います。
リーマンショックは経済社会の百年に1度の「TSUNAMI」に例えられますが、今回は本物の津波に襲われて日本社会の危機をあぶり出すようなことになって、この2つの危機の接点に福島原発がそびえ立っているのではないかと感じます。
◆国民的合意なく
鈴木 原発については多くの日本人が反省していると思います。私も知らない間にこんなにも原発が増えていたのか、もっと関心を持つべきだったと思います。内橋先生はどうですか。
内橋 私は29年前に、『原発への警鐘』(1987年刊 講談社文庫)という本をまとめています。あるメディアに連載を始めたのが1982年(昭和57年)秋からでした。今回、その一部を、緊急復刻版ということで、『日本の原発 どこで間違えたのか』(朝日新聞出版)と題して出しました。『原発への警鐘』をまとめたころ、「原発一〇〇基構想」と言われ、それがいつのまにか「原発一二二基構想」にまで膨れあがっていた時期もありました。この狭い日本列島に少なくとも一〇〇基もの原発基地をつくる、と言っていたのです。国民的合意もないままに・・・。
私にとりましては、フクシマに至る原発に警鐘を鳴らすのも、リーマンショックにたどり着いた市場原理主義に批判の声をあげるのも、またいま、TPP開国論を糾すのも、すべては一列の、同じ問題意識のつながりのなかです。90年代半ばからは、ヨーロッパ諸国、とりわけ北欧における再生可能エネルギーについて多くの事例を紹介してきました(『共生の大地』1995年 岩波新書など)。むろん、私はそれぞれ個別領域の専門家ではありません。が、人間生存の基盤というものを全体的に見つめてきた結果です。
いま、胸に甦りますのは、『原発への警鐘』のなかで紹介しました、米ピッツバーグ大学教授トーマス・F・マンクーゾ博士の言葉です。「マンクーゾ報告」で著名な彼は、原発のほんとうの怖さを「スロー・デス(slow death)」という言葉で表現しました。「サドン・デス(sudden death)」は、いきなりやってくる突然死のことです。これにたいしてスロー・デスは、20年も30年もかけてゆっくりと緩やかに、長い時間をかけてやってくる晩発生の死のことです。今回の巨大複合災害はその両方を同時にもたらしました。 マンクーゾさんは、日本からやってまいりました取材者にたいして、きわめて誠実に次のように話しました。
マンクーゾさんは、日本からやってまいりました取材者にたいして、きわめて誠実に次のように話しました。
「日本は、アメリカに比べて国土も狭いし、人口も密集しています。この広いアメリカでさえ、原発の危険性がつねに議論されているのに、あの狭い日本で、もし原発事故が各地に広がった場合、いったい日本人はどこに避難するつもりでしょうか。あなたがた日本人は、ヒロシマ、ナガサキ、2度も悲惨な核の悲劇を経験しているではありませんか」
(後編に続く)
※後日更新いたします。