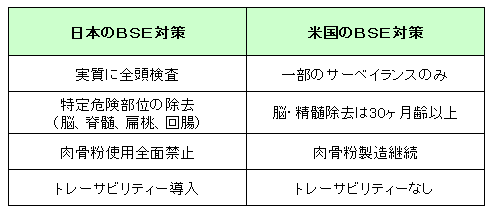輸入再開された米国産牛肉に特定危険部位が混入していたことが1月20日に発覚し、米国産牛肉は再び全面輸入禁止となった。米国政府はこの問題の原因と再発防止策についての報告書を日本政府に提出しているが、日本は疑問点があるとして内容を精査している。米国側は「輸出プログラム」の遵守体制が確保されれば輸入再開は実現できるとして長期間の禁輸にはならないとみているようだ。
日本側が具体的にどのような対応を求めるのかは今後の課題だが、今一度、BSE対策と食の安全について根本的に考えることが求められているのではないか。私たちが問われていることを改めて整理しておきたい。 |
◆本当に例外的なケースなのか?
 |
| 福岡伸一 青山学院大学化学・生命化学科教授 |
日米で合意した輸入再開条件は(1)全頭からの特定危険部位(SRM)の除去、(2)20か月齢以下の牛であることなど、そしてこれらの条件を満たしていることを政府が証明していること、が要件となっている。
1月20日に発見された脊柱付き牛肉の混入問題について、米国政府の報告では輸出業者と米農務省職員がこの条件を熟知していなかったと報告しているが、米側は「例外的なケース」との位置づけだ。
米国の安全確保体制のずさんさが露呈したとの批判が噴出し、「米国と日本では安全に対する感覚が違うのではないか」との趣旨の答弁を国会で小泉首相もした。
今後、米国にどのような対応を求めるかが課題だが、その際、SRMの確実な除去といった輸入条件の遵守のみに焦点が絞られてしまっていいのだろうか。
◆SRM除去だけでよいとする発想の危険性
青山学院大学化学・生命化学科の福岡伸一教授は、昨年11月に刊行された『プリオン説はほんとうか?』(講談社ブルーバックス)で、BSEの病原体は異常型プリオンタンパク質、とするのは不完全な説だというデータをいくつも紹介している。
長崎大学の研究グループは病原サンプル(ヤコブ病を発症したヒトの脳の物質)をマウスの脳に注射する実験を行った。時間経過を追った分析の結果、唾液線や脾臓では、異常プリオンタンパク質がほとんど蓄積されていない時点でも感染性が認められたり、時間とともに感染力が下がっていくのに逆に異常プリオンタンパク質は大量に蓄積されていく、といった両者の蓄積にズレがあることが分かった。
牛のBSE、ヒトのヤコブ病(CJD)など脳がスポンジ状になってしまう病気が「感染する」ことは、病気になった脳をすりつぶして健康な個体の脳に注射したり食べさせたりすると発症することで証明された。そして、感染力が認められた部位には、必ず異常プリオンタンパク質が蓄積していたことから、この病原体は異常プリオンタンパク質である、とされている。
しかし、福岡教授が同書で指摘しているのは、実は今のところ「純粋な100%異常プリオンタンパク質を使って感染が起きることは証明されてはいない」ということだ。
そして、仮に別にウイルスなどの病原体が存在するとして、それが病原サンプルに混じっているとすれば、先の長崎大学の実験結果はつぎのように考えることもできるのではないかという。つまり、何らかの病原体によって感染が起こり、その結果として異常プリオンタンパク質の蓄積が起きた、そう考えれば、感染性が高まる時期と異常プリオンタンパク質が蓄積されていく時期にズレが生じることも理解できる――。
その他のデータも含めて詳しくは同書を参照してもらいたいが、長崎大学の研究グループは異常プリオンタンパク質がBSEなどの病原体そのものであるという考え方に論文で疑義を表明している。
◆全頭検査は必要な体制
こうした研究結果が出ていることから福岡教授は、「特定危険部位だけ除去すれば牛肉の安全は確保できる」という考え方に改めて警鐘を鳴らす。BSEに感染した牛のさまざまな場所を調べて、異常プリオンタンパク質が検出できないからその組織や臓器は安全である、という考え方は「現段階では危険」と指摘している。米国の基本的な対策は検査の実施数はわずかで、SRMの除去で安全確保ができるという考え方だ。
むしろ異常プリオンタンパク質の蓄積とは、BSEに感染していることを示す唯一の「指標」。だからこそ、この指標を検査のために使うことがまず重要だということになる。
そして検査の結果、感染が判明すればその牛は廃棄する。これはWHOも勧告していることで日本はもちろん実施している。福岡教授はさらに検査の精度を高めるには、全頭検査を維持し、現時点では実施されていない部位(リンパ組織)にも検査を広げていくことが安全確保策の方向だと提言する。
このような研究から理解しなければならないのは、日本のように実質的な全頭検査が基本であり、特定危険部位の除去はその検査の精度を補うものとして位置づけることが適切だということだろう。もちろん全頭検査はBSE研究のデータ収集と根絶対策にも貢献する。
もうひとつ確実なことは病原体がかりに不明であったとしても、これまでのBSE研究で示された確実なこととは、病原体を摂取すると感染するということだ。いうまでもなく飼料規制の重要性だが米国では肉骨粉は鶏や豚には使用されており「負のサイクル」が止まっているわけではない。この点は日本政府もさすがに飼料規制強化を求める意向を示しているが、このように整理すれば日本と米国のBSE対策の思想の違いがはっきりする。(1面の表)
◆米国内で危機感の高まりも
今回の件で、米国の安全性に対する考え方は信用できないという風潮が日本にはある。しかし、福岡教授によると一部では危機感も高まっているという。
昨年、米国マクドナルド社と7人の著名な研究者が、米国食品医薬品局(FDA)に対して過去20年間に発生したヤコブ病患者の調査について、再調査を求める意見書を出した。
ヤコブ病は100万人に1人の割合で発生するとされているが、ニュージャージー州やコロラド州に発生数の多い地域があった。これまでFDAは通常の発生数の範囲内としてきている。その発生状況について再検討を求めた。
福岡教授は「現地で調査をすると市民はBSEの実態についてほとんど知らない。しかし、一部でこうした動きがあるように危機意識も高まっている。国民性の違いではなく、いまだ情報が十分知らされておらず自分の問題と考えていないからだと感じた」と言う。
さらに安全な畜産生産に切り替えている生産者もいる。
マラソンランナーが高地トレーニングすることで知られるボルダーにあるコールマン・ビーフという家族経営農場は、成長ホルモンや抗生物質を使用せず、有機栽培の植物性飼料しか与えない肥育法で出荷。価格はやや高いもののボルダーを中心に消費者に支持されレストランでも高く評価されているという。飼料など生産の方法を消費者に開示、消費者の支持で畜産を続けている。米国でもこのような食と農のあり方が模索されている。
「SRMを除去すれば安全性が確保できるという発想、つまり、出口だけでリスクを管理するという考え方ではBSEの実態が把握できず、牛のいろいろな部位で自由に存在できる病原株が出現してしまうこともあり得る。そうなれば牛そのものが食べられなくなる」と強調。そのうえで加工品、外食での原産地表示が不備ななか「食べたくないものを知らない間に食べさせられるのは、基本的人権を奪うこと。再開するなら日本向け輸出分は全頭検査が最低条件」と指摘する。
「出口だけで管理するのではなく、求められているのは生産からのプロセス全体が見えるようにすることではないか。そうすれば消費者もサポートし、相互で生産のあり方を変えていくことが可能になる」。
日本でのBSEは今年になっても確認されている。感染経路がいまだ不明ななかで食の安全のためには何が求められるのか考える必要がある。
|