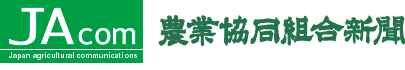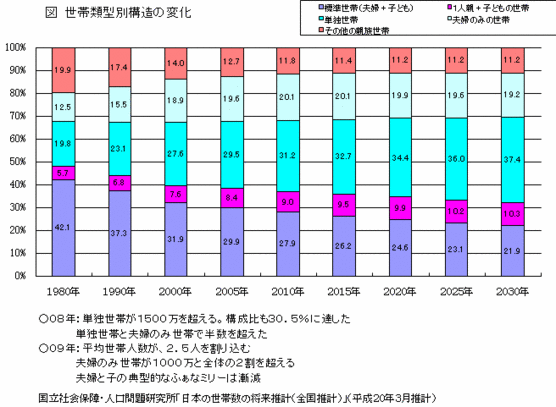「高齢化」「独り暮らし」増加にどう対応するのか
生産者と売場のジョイントで新たなビジネスを
◆小さな商圏で過酷な競争を戦う
 現在、食品スーパー(SM)は、全国に約1万8000店(2007年現在)、これにGMS(総合スーパー)の食品売場もSMと同じだと見て加えればおよそ2万店舗あることになるという。人口密度の高い地域や低い地域などあり一様ではないが、日本の人口を1億2000万人とすると6000人に1店舗という計算になる。
現在、食品スーパー(SM)は、全国に約1万8000店(2007年現在)、これにGMS(総合スーパー)の食品売場もSMと同じだと見て加えればおよそ2万店舗あることになるという。人口密度の高い地域や低い地域などあり一様ではないが、日本の人口を1億2000万人とすると6000人に1店舗という計算になる。
食品スーパーを出店するためには、1坪100万円くらいの投資が必要だと大塚明日本スーパーマーケット協会(JSA)専務はみている。その投資の3倍くらいの売上げをあげないと利益が出ない。つまり坪当たり年間300万円。休業日もあるので1日およそ1万円/坪が売上げの目安となる。
企業数は地域で小規模に展開している企業もあり正確には分らないが、1300社弱と推定されている。コンビニエンス(CVS)業界は上位5社で売上高の約9割、GMSは5社で8割弱を占めているが、SM業界の上位5社の売上高シェアは9%に過ぎない。
つまり小さな商圏で「過酷な戦いを強いられている」のが現在の食品スーパーだと、大塚専務はいう。
他の業界では企業統合などが進んでいるが、この業界はどうなのか。これまで「他業界のように上位集中が進んでこなかった」のは「2〜3店舗規模でも、地域にしっかり根ざした企業なら、それなりに生き残ってこれた」からだとみている。そしてこれからは「資本の統合化が進む一方で、小規模でも地域に根ざした企業の二つに二極化する」と分析する。
◆かつてのような成功モデルはもうない
そうしたなかで、食品スーパーはどのような方向に進むのか? 「大きな曲がり角にきているが『“モデルなき時代”』」だと大塚専務はいう。どういことなのか、歴史的に振り返ってみたい。
日本にレジスターを備えたセルフサービスの米国型スーパーが誕生して60年が経つ。最初の30年は米国スタイルをモデルに進め、およそ30年が経過していずれのSMも同質化した時期にPOSレジが導入された。その後は「データでの勝負」の時代が続き、販売データを分析して重点商品の管理をするようにもなった。
そしていまやポイントカードを全企業が導入し「あなたが何月何日に何と何を買ったか」というデータまで調べようと思えば調べられる。そういう競争になってきたが、これから先にはかつての米国のような手本になるモデルはもうない。「それぞれの企業が自分たちの生き様を、商売のやり方を明確にして戦っていかないといけない時代になった」ということだ。
◆商売を変える3つの要素
 「個々の生き方を明確にする」ときに考えなければいけない要素は3つあると大塚専務は指摘する。
「個々の生き方を明確にする」ときに考えなければいけない要素は3つあると大塚専務は指摘する。
まず第一は、「お客様の変化」だ。お客の変化とは、(1)人口構造の変化と、(2)価値観の変化で、これが「商売に一番大きなインパクトを与えてくる」。
二つ目は、小売業を取り巻く法律が変わることだ。人件費の増大を招きかねない短時間労働者の厚生年金問題や消費税値上げもここに含まれる。
三番目は「ITの変化が商売を変える」ことだ。SMやGMSがこれまで成長してきた要素の一つに、新聞折込チラシの有効な活用がある。
しかし、IT技術の発展で、タブレット端末で新聞を読んだり、メールだけでいいと新聞の宅配を必要としない層が増えている。そういうなかで従来からのチラシマーケティングをどう伝えるのか、マーケティングのあり方が問われる。
「いまのように、モノを集めました。お客様は店に来てください」という「商売はだんだんダメになる」のではと大塚専務は危惧する。
◆ファミリーユースからパーソナルユースへ
「この3つの要素によって商売をどんどん変えていかなければならない」が、一番の問題は「人口構造の変化」とりわけ「高齢化」にどうアプローチするかだ。
さらに高齢化の影響もあって、家族構成が大きく変化している。下図のように、1980年に夫婦と子どもという「標準世帯」は全世帯の42%を占めていたが、独り暮らしや夫婦だけという世帯が増え、08年にはこの二つで半数を超え、30年には7割近くを占めると推計されている。さらに独り暮らしの中でも高齢者の割合がどんどん増えてきている。「これに商売としてどう対応するのか、極めて大きな課題」だ。
60年前にスーパーが誕生したときのターゲットは、夫婦と子ども2人とか、それに舅姑が同居している5〜6人のファミリー層だった。その後、核家族化が進むが「家族なので3人とか4人のユニットで考え、量目にしろ店内のすべてをファミリーユースで運営してきた」。しかし、いまはこうした「ファミリーユースからパーソナルユースに移り始めている」。
「パーソナルなら量目を小さくすれば」という意見があるが「独りで作っても食事は面倒だし美味しくない」。そうすると「素材よりも加工度をあげたものを提供する必要がある」。加工度といってもさまざまで、泥が着いているよりは泥を落としたりとか、白菜を1個売りから半分や4分の1にカットしたり、ざく切りにパックし「一人前鍋物」用にすることもそうだ。さらにすぐに火にかけられる状態にしたり、最後はそのまま食べられる惣菜まで、加工度を上げたものにするというのも一つの方法だ。
(↑ クリックすると大きく表示します)
◆生活を楽しむ「こだわり」商品を提供する
一方で前にもふれたが、IT化でチラシマーケティングにも変化が求められている現在のキーワードは何か。
大塚専務は「どれだけお客に近づいていけるか」だと考える。
もっとも究極は「御用聞きをして届ける」ことだが「非効率的で企業的ではない」のでネットを上手く活用できないかとか、分配するための簡単な店舗をつくりそこに卸すとか、エリアや年齢構成によって方法にも違いはあるが「いまよりも近づく商売」を考えなければという。
そういう商売は昔からCVSがやってきたことだともいえる。だから「これからの敵はCVSとかドラッグストアや宅配業者だったりする」とみている。
そして「近づく商売」ではいままでのように本部が一括して100店舗あればみな同じ品揃えにするというビジネスは通用しなくなる。「近づく」とはそのエリアに住んでいる人に合わせた品揃えをするということだからだ。
その時には、価格・味・売る期間・品種といった「こだわり」がクローズアップされてくる。なぜかといえば、いままでのビジネスモデルは、人が生きていくために必要で便利なモノを提供する店、つまり「みんなが同じモノを求める店」だった。
しかしこれからはそれにプラスして生活をもっと楽む、「私だけが楽しめる」こだわり商品をどれだけ提供できるかが勝負になるからだ。
「こだわり」というと高いモノと思われがちだが違うと大塚専務はいう。景気が悪いので安いものを買うけれど、いつも同じでは面白くない。だから「私は魚にこだわる」。あるいは「私は野菜だけは」とか「使い勝手の良いモノ。タイムリーに食べられたり、使えるモノ」を含めた「こだわりの時代」になってきている。そういう消費者のこだわりにどう応えるかが大事になるということだ。
◆「存在」から「状態」へ
そうなるとマーケティングの仕方も変わる。いままでは、年齢や年収、家族構成とか何を食べるなど「存在」で考え、それほど間違いはなかった。
しかしいまは、人は楽しいと思うときには「妙にお金を使ったりする」ように、「お客は昨日も一昨日も同じではない。いつも動いている」から「その動きに対応できるような商品や品揃えを提案する時代」になってきている。つまり「存在」ではなく「状態」をどうキャッチアップするかがポイントになる。だから小商圏で「近づく商売」が必要になり、「100店舗あれば100通りの売場があっていいし、そういう売場にしなければいけない」ということになる。
◆農産物が持っている物語性を売る時代に
そういう時代に農産物の生産者に求められてくることは何か。
いままでは生産者は「最高のモノを作れば売れる」と考えてきただろうが、いまは農産物に限らずあらゆる商品で、「良いもの」と「売れるもの」は違い始めてきていると大塚専務は指摘する。いまは「モノ離れ」の時代になり、「最高の品質」というより、「喉が渇いたときに気楽に飲める商品ですよ」といった方が売れる。
だから農作物の場合も「誰に、どこで、どれだけを、いくらで、いつまでに売りたい」かを明確にし、売場の人たちと生産者が話し合いながら、商品提案をしたり、栽培する。そこにこれまで培ってきたノウハウを投入して欲しいと大塚専務は考えている。
そのときに大事なのは、商品の質もさることながら、「農産物が持っている物語性とか、こだわり、これを食べるとどうなるとか、ここまで来るまでにこんな苦労があった」という商品周辺にある「エピソード=ストーリーをしっかり売る感覚が大事になってきている」。
「産地直売という感覚ではなく、生産者と売場がジョイントして商品を作り出していく」ということだ。
そうしたことを実現するためにも、JAに望みたいことは「お互いの情報交換」だと大塚専務は考えている。もちろん「店頭の情報をどう生産者に伝えるか」を店側は考えなければいけないが、同時に、価格や出荷時期・生産量、さらには「こういうモノが作れるといった技術情報」を含めて「生産者の情報を的確に伝えて欲しい」という。そこから、コミュニケーションが生まれ、新たなジョイントビジネスが誕生するのではないだろうか。
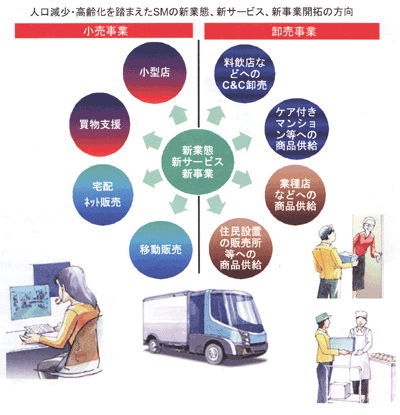
(写真)
JAS「シナリオ2020」(要約版)より