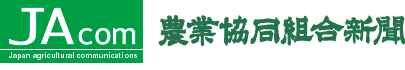国家戦略としての農業政策の確立を
◆なぜ戸別所得補償制度が期待されたか
 戸別所得補償制度は、農村現場の声に応えるものとして、大きな期待を集めて登場した。
戸別所得補償制度は、農村現場の声に応えるものとして、大きな期待を集めて登場した。
その流れを振り返ると、まず、2007年の「戦後農政の大転換」において、(1)一定規模以上の経営体への収入変動を緩和する所得安定政策(産業政策)と、(2)規模を問わない農家全体に対する農が生み出す多様な価値を評価した直接支払い(社会政策)とを「車の両輪」として位置づけるという政策体系が打ち出されたが、その後、現場では、改善を求める声が出てきた。
それは、(1)規模は小さいけれども多様な経営戦略で努力している経営者をどうするのか、(2)農村への直接支払いは役立っているものの、「車の両輪」といえるだけの大きさには遠い、(3)さらには、経営所得の補填基準が趨勢的な米価下落とともにどんどん下がってしまい、所得下落に歯止めがかからず経営展望が開けない、というものであった。
これに応えるべく、自公政権においても、(1)「担い手」の定義を広げる、(2)その「担い手」に所得の最低限の「岩盤」が見えるようにする、(3)「車の両輪」となる農の価値への支援は10倍くらいに充実する、その上で、(4)コメの生産調整の閉塞感を打破するための弾力化を図り、現場の創意工夫を高める、ことが議論されたが、この議論は完結する前に政権が交代した。
そして、民主党政権によって、これらの課題に集約的に応える、つまり、規模で担い手を区切らずに、多様な経営者の所得に最低限の「岩盤」を提供する「戸別所得補償制度」が登場した。これは、「生産調整から販売・出口調整へ」の流れも含んでおり、経済的メリットに応じた経営判断を促進するようコメ政策を弾力化するものである。
一方、農の価値への直接支払いは、戸別所得補償制度に加えて「環境直接支払い」の充実でも対応する、というものである。これらを組み込んだ『食料・農業・農村基本計画』も策定された。
こうした流れからもわかるように、最終的に政策を動かしているのは現場の声だということは忘れてはならない。現場の大きな期待を集めて登場した以上、逆に、結果として、いかに現場の声に応えているかが厳しく問われる。
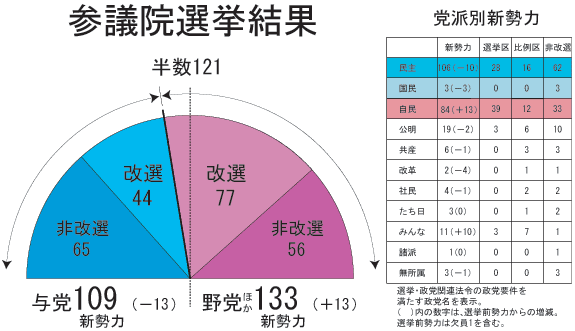
◆意図的安売り問題を超えられるか
所得の岩盤の必要性は、まさに現場の声であった。所得の岩盤対策には、モラルハザード(意図的な安売り)論による根強い反対があったが、これを克服して岩盤が実現した。
関係者の間で「ミスター岩盤」というニックネームで呼ばれていた筆者にとって、所得の岩盤を実現する『基本計画』の策定にかかわれたことは感慨深いが、しかし、すでに、「安くても補填される」ことを盾にした「買いたたき」傾向などから、コメのモデル事業さえも、今秋の補填額の増大に耐えきれずに維持できなくなるのではないかという懸念が出てきている。これでは、「そら見たことか」ということになりかねないし、農村現場ももたない。
◆国家戦略なき予算削減の壁
そもそも、すべての問題に予算の壁がある。たとえば、農村への直接支払いを10倍にしようとしても、従来なら、財務当局から一笑に付されて終わりである。なぜなら、農水予算は、毎年数パーセントずつ減らすことが前提に査定されるからである。
こうした単純な国家戦略なき予算査定システムを打破するために、自公政権下では、省庁の制約を超えた「6大臣会合」が組織されたわけだが、政権が交代し、期待は国家戦略局(室)に移った。しかし、これは機能していない。
コメ備蓄の問題もそうである。販売・出口調整を充実し、過度の米価下落を抑制して、モデル事業を軌道に乗せるためにも、世界貢献も視野に入れた備蓄運営の充実はポイントであり、民主党政権では、マニフェスト等にも棚上げによる備蓄米の増大が明記されていたが、その話は出てこなくなってしまった。
我が国が世界の食料危機に備えて、また、普段から10億人を超えようとしている栄養不足人口の軽減に貢献することは、洞爺湖サミットでも表明した我が国の重要な世界貢献であり、そのためには、最も潜在生産力の高いコメを増産し、備蓄し、機動的に運用していくことが必要である。これは世界貢献であり、「余ったから買う」という議論ではない。世界の食料安全保障に貢献するための大義名分の大きな基本的システムとして、体系的な制度に確立すべきである。
それなのに、「そんな予算があるわけがない」という議論にしかならないのはおかしい。思い切った予算の再編や拡充ができない現行の予算査定システムを見直し、世界貢献のための国家戦略として、省庁の枠を超えた一段高いレベルでの国家全体での予算配分を行うべきときがきている。それが可能になるかと思ったら、むしろ事態は悪化し、国家戦略なき予算査定が強まっている。
◆日本の食と農の未来は?
『基本計画』もそうであった。『基本計画』は、「10年後、20年後に向けて、現場の農業者が希望と誇りを持って経営計画が立てられるような、そして国民が食の未来に安心できるような、日本の食料政策の持続的で明確なメッセージを示す」ことを意図している。
この観点から見ると、前文において、食料・農業・農村政策を国家戦略として位置づけ、国民全体で食料・農業・農村を支える社会をめざすと力強く宣言しているが、具体的な施策の部分では、「検討する」という表現が多く、表現の弱さと具体性の不十分さを指摘する声もある。
これには財政当局との調整の結果が反映されている。残念ではあるが、背後にあるメッセージが弱まったわけではないと理解してもらいたいが、現場での受け止め方は心配である。
また、今回の『基本計画』では、米粉用米、飼料用米、小麦、大豆等の大幅増産によって、2020年度に50%の自給率を達成することとし、それに要する財政負担は、総額で約1兆円と見込んでいる。2010年度に2000億円のコメ所得補償予算を増額、2011年度以降の本格実施でさらに2000億円の増額で総額1兆円の所得補償を想定しているが、農水予算の総額は毎年数パーセントずつ減額するという制約が課されたままでは、すでに2010年度に大きな問題となったように、所得補償予算が増額されても、一方で、それ以上に、それ以外の予算の大幅な減額が必要になり、機械が買いにくい、暗渠排水ができなくなった等、現場のコストはむしろ増えて、差し引き所得減少ではないか、ということにもなりかねない。
こうした中で、酪農・畜産、果樹・野菜等への所得補償の拡大も本当に可能なのだろうかと、現場が懸念するのもやむを得ないところである。かりにも、さまざまな改革のメッセージが、結局、「お金がないからできませんでした」で終わってしまったら、現場の失望も大きく、日本の食と農の未来は暗い。
◆予算の壁は超えられるか
「食料・農業・農村政策は国家戦略である」と『基本計画』は宣言したが、これは世界的には常識であり、そのことを改めて宣言しなくてはならないことが我が国における問題といえる。食料は人々の命に直結する最も基本的な必需財であり、農業政策は単なる農家保護政策なのではなく、国民一人ひとりが自らの食料をどう確保するか、そのための政策だという認識が必要である。
しかし、食料危機を経験し、国内農業の重要性が再認識されたといわれながら、それは国民の具体的行動につながったか。現実には、飼料・燃料・肥料高騰にもかかわらず上がらない生産物の販売価格の下で、廃業の危機に直面する農業経営が続出した。
欧米では、生産物の価格も大幅に上昇し、生産コスト上昇の影響を吸収したが、日本では、そうした動きが鈍かった。小売・流通部門の取引交渉力が生産部門に対して相対的に強すぎることも影響していることは間違いないが、それ以上に国民の「冷たい目」が問われる。
我が国は、世界的にも過剰なほどの「優等生」としてWTO(世界貿易機関)等による農業保護削減に対応してきた。
政府の価格支持政策をほとんど廃止したのは日本だけであり、農産物関税も平均で11.7%と低く、農業所得に占める財政負担の割合も15.6%で、欧州諸国が軒並み90%を超えているのに対してはるかに低い。
それにもかかわらず、消費者の国産への評価を反映した内外価格差(国産プレミアム)が「非関税障壁」と見なされるような誤りもあって、いまだに最も価格支持政策に依存した遅れた農業保護国と内外で批判されており、こうした誤解が消費者・国民の「冷たい目」につながり、食料関連予算も減り続けている。
欧州では生物多様性が農業補助金の具体的根拠になっているが、我が国での漠然とした多面的機能論は「保護の言い訳」としか映っていない。
◆何のためにどこを変えるべきか
我が国では、農業・農政に対する様々な誤解もあり、国家戦略としての食料政策が確立されていない。そのため、農水省予算の枠を超えた国家戦略的予算の増額を行おうとしても、農水予算は、毎年削減していくものというような単純な論理から抜けられず、米国型の所得補償予算や、欧州型の直接支払い予算を増やしたとしても、一方で、それ以上に予算を削減しなくてはならないことになり、所得増加以上に現場農家のコスト増加が生じてしまいかねない。
関係者は、筆者のような研究者も含めて、日本農業・農政に対する様々な誤解を嘆く前に、世論の誤解を許したことへの共同責任を痛感する必要がある。食料生産はまさに国土環境を健全に保ち、国民の心身を守り育む、そして世界の貧困問題の軽減にも貢献するという大きな社会的使命を担っているが、これを国民一人ひとりが自らの問題として理解してもらわなくては、日本の食の未来は開けない。そうした視点を持てば、食料政策の予算は、農水予算の枠内で、ただ削減すればよいという議論の誤りも理解される。
食料政策予算には、ODA(政府開発援助)予算、防衛予算、環境政策予算、教育予算の側面もあり、高齢者の雇用創出による社会保障費の節減にもつながる等、様々な側面が理解されてくる。こうした理解の下で、国家戦略なき予算削減に早く歯止めをかけることに対して、自らが責任を取る覚悟を決めてリードする人たちがいなかったら、誰がやっても何も変えられず、現場は失望し、日本国民の食の未来は開けないだろう。