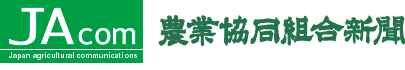◆「国は富めるも、民は貧し」
 「国は著しく富めるも、民は甚だしく貧し。げに驚くべきは是等文明国に於ける多数人の貧乏なり」。
「国は著しく富めるも、民は甚だしく貧し。げに驚くべきは是等文明国に於ける多数人の貧乏なり」。
河上肇の著名な『貧乏物語』(注1)は、当時、世界最高の富裕国とされたイギリスが、その実、世界にも稀な貧富の「格差大国」であった現実を指弾している。
首都ロンドンでは、その日の労働を支えるのに必要な食事もままならぬ貧乏人(貧民・細民・最下層民の合計)が労働者総数の43%、人口総数の28%にも達していた(注2)。
産業革命以降の剥き出しの初期資本主義に抗して、同じイギリス・ランカシャーに「ロッチデール公正開拓者組合」が生まれたのは1844年のことだ。河上の紹介する「超・格差社会イギリス」は、それからさらに半世紀以上、「よりよい社会」をめざすべく歴史を刻んだはずだった。現実は「よりよい社会」からますます遠ざかった。
去年秋、米NYに吹き荒れた「ウォール街を占拠せよ」の舞台・ズコッティ公園でジョセフ・スティグリッツ(米コロンビア大教授、ノーベル経済学賞)が若ものに説いた。
「利益の私物化、損失の社会化。これは資本主義ではない」
世界経済を破綻の闇に連れ込むマネーとその操り手たち。「巨大金融資本(家)は壮大な賭け事に成功すれば、巨大な利益を独り占めにし、失敗して損失が出れば公的支援での救済を要求する。膨大なツケ(帳尻)はいつも弱者に回る」と。いま、アメリカにおいては、平均所得の中位以下の個人所得の合計に相当する巨富を、わずか400人の超富裕者らがわしづかみにしている。
「ロッチデール」から「ズコッティ公園」まで170年。強い者はより強く、大きいものはより大きく―野放しの自由を求めての「強者連合」が「改革」を叫び、「グローバル化」を旗印に掲げる。市井に生きる「呼吸する人間」が恐怖のリスク社会におびき出される。
ワイルドな資本主義と、グローバル化を旗印とするマネー資本主義に対して、私たち個人は、いまも素手で立ち向かうほか有効な対抗手段を獲ちとっていない。
◆深まる「不安社会」の様相
新たな世紀を迎えて10年余、暗い森のなかで日本人は途方に暮れている。
自然災害だけではない。市井に生きる人びとの細やかな日常性は脅かされ、「不安社会」の様相は深まった。勤労の正当な報酬、社会の安全、老後のあんしん、細やかな日常性、それらすべてが手荒な市場原理主義の荒野に引きずり出されて久しい。
最新の「国民生活基礎調査」(注3)が暴く。「生活が苦しい」が全体の62%に。子どもがいる世帯では70%に。雇用者総数5111万人のうち、十全たる社会保障から排除された非正社員が1755万人に。預貯金など金融資産ゼロ世帯29%。単身世帯では40%以上に(注4)。「貧困マジョリティ(貧困多数派)」生成の時代へと、私たちの社会は、間違いなく突進している。求める「あんしん社会」はいよいよ遠い。
いま、あらためて「貧困の撲滅」を掲げる国連は、第一に「行き過ぎた市場原理主義の制御」、第二に「グローバル化がもたらす恩恵・対価が極めて不平等に配分される現実の是正。先進国での“内なる貧困”の解決」、第三に「経済安定・成長の新たな経済モデルが必要」と訴える。「ミレニアム宣言」(注5)の再確認を迫られてのことだ。
こうして設定された「2012国際協同組合年」への必然を私たちは自らのものとしなければならない。すべての協同組合人に求められているのは、ここに至る資本主義の歴史と、「日本社会のいま」を自らの胸底深く刻み込み、沈思の末に「一人ひとりの思想性」を絞り出すほかにない。
「社会転換」の方向性さえ明らかにすることなく、「協同組合がよりよい社会を築きます」と、いく度、唱えようと無力に終わるだろう。ここに一端を示したに過ぎない歴史的背景、現代社会の苛烈な構造、その両軸を見透す。余言を重ねるまでもない事柄に違いない。
◆「共生セクター」を担う「使命共同体」が協同組合
第2次大戦後、ホンの短期間、イギリスはじめ少なからぬ国で「福祉社会」は現実のものとなった。だが、冷戦構造の崩壊とともに、「秩序形成者」からの「譲歩」はアッけなく召し上げられた。福祉社会解体に至る過程をたどり直すことを協同組合人に薦める(注6)。
ドイツの社会学者F・テンニース(注7)の社会発展説には、しばしばゲマイン・シャフト、ゲゼル・シャフトが登場する。日本では多く前者を「地縁共同体」、後者は「利益共同体」と呼ぶ。私はこの2つの「共同体」を超える「第三の共同体」があると考え、「使命(ミッション)を同じくする人びとの共同体」を指して「使命共同体」と呼んできた。
協同組合こそは最適の「使命共同体」モデルである。使命共同体が達成すべき至高の課題、それは以上に述べた構造そのものの変革、すなわち真の「社会転換」のほかにない。
かつて小泉構造改革の時代、さる閣僚は「格差ある社会は活力ある社会」と雄叫びをあげた。労働の解体を進め、非正規雇用を増やせば、「グローバルズ」(日本型多国籍企業)の国際競争力が増す、と。他方で、列島に固着して生きるほかない農業、地域商店街、中小・零細企業、地場産業、何よりも私たち呼吸する人間、すなわち「ローカルズ」は不安社会のただなかに置き去りにされた。新自由主義、市場原理一辺倒の「不安社会」へと連れ込まれた歴史を、いま「正気」で否定できるものはいないはずだ。
彼らは、日本のコメは高いではないか、と地方の生産者と都市の消費者を分断して対立させ、過剰な競争を煽った。その隙間に利益獲得のチャンスを置く。「規制緩和とグローバル化追随」万能論の延長上に、いまTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)がある。分断、対立、競争が原理の「競争セクター」が日本社会を乗っ取る。「不安社会」の由来である。
◆人が人らしく生きられる社会へ
 「競争セクター」追随でなく、参加、連帯、共生を原理とする「共生セクター」の足腰を強くする。「あんしん社会」を取り戻すには、新たな地域コミュニティを立ち上げねばならない。かねて私が呼びかけてきた「FEC自給圏の形成」(F=食・農、E=自然・再生可能エネルギー、C=介護、医療、福祉を一定地域内で自給)が地域主権を実あるものとするだろう。運動性と事業性を両立可能な協同組合。それら協同組合間の連携が「共生セクター」を立ち上げる。被災地を含む幾多の実践例が全国各地につづいている。
「競争セクター」追随でなく、参加、連帯、共生を原理とする「共生セクター」の足腰を強くする。「あんしん社会」を取り戻すには、新たな地域コミュニティを立ち上げねばならない。かねて私が呼びかけてきた「FEC自給圏の形成」(F=食・農、E=自然・再生可能エネルギー、C=介護、医療、福祉を一定地域内で自給)が地域主権を実あるものとするだろう。運動性と事業性を両立可能な協同組合。それら協同組合間の連携が「共生セクター」を立ち上げる。被災地を含む幾多の実践例が全国各地につづいている。
「使命共同体」を担う協同組合と協同組合人が「あんしん社会」を創る。「人が人らしく生きられる社会」への道案内人に、いま私たちは最後の希望を託している。
(写真)
地元の保育園児や小学生と一緒にそばやひまわりを植えた神門地区農地と水と環境を守る会はその花の鑑賞会を9月末に開いた。鑑賞会後、地元そば粉で手打ちしたそばに子どもたちは大喜びした(JAいずもHPから)
注1 1916年=大正5年=大阪朝日新聞に連載開始された。単行本は岩波文庫だけで40万冊を超えるベストセラーとなったが、後に自ら絶版とし、13年後、改めて『第二貧乏物語』を世に問うた。
注2 1899年=ボウレイ、ハースト2人の共同調査によって明らかにされた。
注3 今年7月発表。2011年6〜7月調査。被災3県を除いた全国44都道府県の4万6千世帯が対象。「生活が苦しい」と答えたものは、1986年の調査開始以来、過去最高を記録した。
注4 金融広報中央委員会「家計の資産保有額調査」。今年2月発表。
注5 1999年9月、国連本部において開かれた「国連ミレニアム・サミット」で21世紀に向けての国連の決意(8項目にわたる)が発せられた。2010年9月、国連は改めて同宣言にうたった「貧困の撲滅」を繰り返さざるを得なくなった。「2012国際協同組合年」の背景事情である。
注6 イギリス福祉社会の象徴、NHSの解体がどのように進められたか。宇沢弘文・内橋克人対談集『始まっている未来』(岩波書店)に詳しい。
注7 ドイツの社会学者、F・テンニース・キール大教授(1855―1936)の主著『ゲマイン・シャフトとゲゼル・シャフト』。前者は「本質意思」を、後者は「選択的意思」を結合原理とする。因みに利益追求の株式会社は「利益共同体」。テンニースは協同組合運動に積極参加し、台頭するナチスに抵抗、キール大名誉教授の座を追われた。