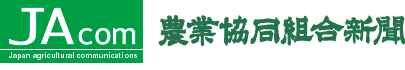◆新基本計画における「農業構造の展望」
新基本計画はこれまでの基本計画にならって、2020年の「農業構造の展望」を提起し、地域農業の基幹的担い手としての主業農家(1経営当たり7.7ha)4割と法人経営(1経営当たり18ha)1割の農地集積合計5割をもって、2005年の4割からの構造改革を展望している。
そこでは第1に、家族農業経営から法人経営(集落営農を含む)への組織化と他方での法人経営雇用者(常雇)の主業農家化という形での連携と循環に注目して経営者の確保を図り、第2に、兼業農家や小規模経営を含む意欲ある多様な農業者が農業を継続できる環境を整備するとともに(戸別所得補償の本格的実施)、新規就農者を幅広く確保し、第3に、これらの規模が小さい経営でも加工や販売を通じた6次産業化によって特色ある経営を展開するといった努力を積み重ねた結果として、経営体が地域農業の担い手として継続的に発展を遂げた姿である「効率的かつ安定的な農業経営」がより多く確保されることをめざすとしている。
◆構造政策は放棄されたか
注目されるのは、「効率的かつ安定的な農業経営」それ自体の育成目標は示されておらず、その育成に向けて特定の担い手に施策を集中するといった「選別的」・「誘導的」な政策体系は採用されていないこと、これとは反対に「意欲あるすべての農業者」が農業を継続できる「環境整備的」・「後押し的」な政策体系を採用していることである。ここから、米戸別所得補償モデル事業に対して投げかけられたのと同様に、基本計画に対しても「構造政策の不在」という批判が投げかけられつつある。
だが、この批判は二重の意味で問題を含んでいる。第1に、米戸別所得補償モデル事業から新基本計画に至る民主党農政に「構造政策的な要素」がないとはいえないからである。第2に、今日では従来の「構造政策」の思想には転換が必要だからである。米戸別所得補償モデル対策の構造改革促進的な性格については連載の第4回で検討した。基本計画に関するそれは次回に触れることにして、今回は第2の問題点について掘り下げてみよう。
◆日本農業における担い手の存立・展開構造
図に示したように、今日では広義の「日本農業」に関わる生産主体は実に多岐に及んでいる。家族農業経営が中心にあることはいうまでもないとして、これが企業的発展を遂げた生産農協的な農事組合法人や会社法人は部門ごとの大きな差違を含みつつも一定の地歩を占めている。そして、農業基本法以来、一貫して農業構造改革の本流に位置づけられてきたといってよい。これに対して、家族農業経営の補完から始まり、徐々に代替に向かった(1)集落営農、(2)JA出資農業生産法人、(3)市町村農業公社などは1992年の「新しい食料・農業・農村政策の方向」で法的に認知されたものの、(2)の本格的展開は2000年以降、(1)のそれは品目横断的経営安定対策の検討・導入に対応した2005年以降に持ち越された。また、市民農園は1989〜90年の制度整備を契機に着実に発展し、その延長線上で2002年からは神奈川県などで「中高年ホームファーマー」と呼ばれる300平方m程度を上限とする自給的市民農業経営を生み出すとともに、2007年には30aを上限とする「かながわ農業サポーター」に発展している。重要な点はこうした神奈川県での先発的な動きは2009年の農地法改正によって一挙に全国展開する条件が与えられたということである。
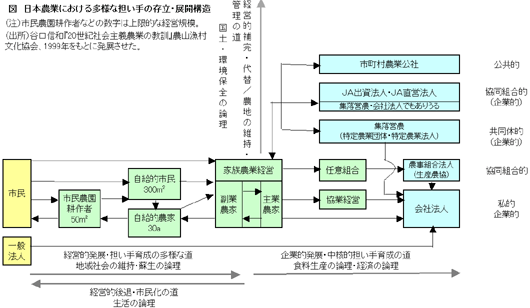
◆これからの農業構造政策の新たな視点
したがって、今後の農業構造政策を構想するにあたってはこうした現段階の農業構造を前提にしつつ、以下のような視点を導入することが不可欠であろう。
第1は自給率向上に資する構造改革であることだ。現在の日本農業の基本問題の基点が低い自給率にあることからすれば、大規模な経営では効率的に利用できないような零細・不整形農地や耕作放棄地をも含めて最高度の土地利用が求められており、集落営農・JA出資法人・市町村農業公社などと並んで、副業農家や自給的農家、さらには様々な市民的農業経営の育成・奨励が欠かせないといってよい。
第2は耕作放棄地を解消し、農地の外延的拡大を図るとともに、零細分散農地の団地的土地利用の実現によって農地利用の内包的拡大を実現することが重要であり、集落営農?市町村農業公社など地域の土地利用調整に関与できる経営体の育成が大きな意義を有することである。
第3は麦・大豆転作を内包化した水田二毛作経営の育成が自給率向上の鍵を握ることからすれば、麦・大豆・飼料用米(米粉用米)については従来の規模をはるかに超える大規模な経営体の創出が必要であることだ。それは家族経営の枠内では効果的な団地的転作が組織できない中で集落営農が生まれ、発展してきた経緯を踏まえ、従来の集落営農の枠をも超える粗放作物の輪作単位の創出という新たな課題の解決を求めている。他方で、食用米は自家用米も視野に入れながら相対的に小規模な経営がこれに取り組むという分業が必要になってくるであろう。
第4は地球温暖化への対応など、多面的機能の十全な発揮を保証する地域農業の存立が不可欠な時代的要請に応える上で、全国一律の規模とは異なって、地域の農地のカバー率といった指標に基づく支援方策を通じた担い手の育成・確保が必要となる。
第5は図にも示されたように、一方では市民や一般企業の農業参入が見通され、他方ではJA出資法人や集落営農などでの新規就農者育成機能の発揮がみられる中で、多様な担い手育成の多様なルートの確保が益々重要になってくることである。
第6は、以上のような構造改革をめぐる多様な取り組みの中で、総体として生産コスト引き下げにより、ある程度の「国際競争力」をもつ経営の育成という伝統的な構造政策の課題が実現されるという視点である。
次回は以上の視点から基本計画における構造政策を論じることにしよう。
(お詫び)第5回(5月30日号)の表1で、2008年の生産量に誤りがありました。小麦88万トン、大麦・裸麦22万トンに訂正して、お詫び致します。
【著者】谷口信和東京大学大学院農学生命科学研究科教授