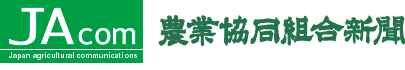◆零細経営は宿命ではない
日本農業の未来に夢を託す人でも、水田の土地利用型農業では大規模経営創設を通じて他産業なみの所得水準や労働条件を実現することは無理だと考える人の方が多数派であろう。今回はこうした常識を吟味する。
表1は2005年農林業センサスが捉えた農家以外の販売目的の農業事業体のうち、経営面積100ha以上で水田経営面積(稲のほか、麦や大豆などの作付も含む)を有する79事業体を地域別に示したものだ。北海道や南九州で1事業体当たりの水田経営面積が100haを下回っているのは、わずかな水田経営面積しかもたない大規模畑作経営が含まれているからだが、その他の地域では水田を中心とした100ha以上の大規模経営が成立していることが確認できる。
すなわち、都府県や東北から四国までの地域では、第1に、1事業体当たりの水田経営面積は100haを大幅に超えており、第2に、水田経営面積をもつ事業体数(42)と稲・麦・大豆が1位部門の事業体数合計(41)がほぼ同じになっているからだ。
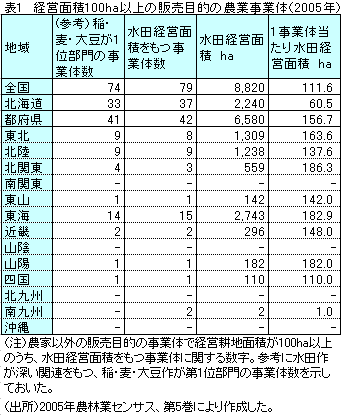
◆はるかに多い大規模経営
だが、センサスはこうした大規模水田農業経営の実態を十分には捉えきれていない。例えば、稲作の全作業受託や、部分作業受託であっても基幹作業を全てカバーする場合には実質的な経営面積とみても差し支えないし、麦・大豆などの「水田転作」では転作受託という名の実質的な経営面積が存在しており、これらを考慮すると100haを超える水田農業経営数が飛躍的に増大することは各地の実態調査の知見からも明らかである。すなわち、水田農業の大規模経営は全国にわたって形成されており、特定地域の点的な存在ではなくなっているのである。
◆地理的決定論とは異なる現実
こうした大経営は予想されるように東北・北陸・北関東といった東日本の中核的水田農業地帯に多く立地している。
しかし、表1が示す興味深い現実とは、第1に、都市化や兼業化が著しく進んだ東海地域が大規模経営の形成では突出した地位を占めていること、第2に、近畿・山陽・四国といった「農業後退地域」と規定されることが多い地域でもそれなりの健闘がみられることだ。
つまり、都市化・兼業化・過疎化といった農業後退に結びつきやすい条件下にある地域でも、取り組み方如何によってはかなりの大規模経営の創出が可能だということが事実をもって示されており、決して地理的決定論では現実は割り切れないのである。
◆大規模経営に託されたもの
今日の局面で水田農業の大規模経営に期待されるものは、私経済的にみれば「農業」で自立できる経営体を創出し、持続的な農業を実現することである。
国民経済的にみれば、単に「儲かる」経営体を創出するだけではなく、高度な水田的土地利用を可能にする〔米+麦・大豆二毛作〕型大規模経営を創出し、食料自給率向上を実現することに他ならない。コストダウンはその過程での主産物ではなく、副産物に過ぎない。
◆他産業なみの農業経営とは
前者の「農業」で自立できる条件とは、古くは農業基本法で提起された「生産性と所得の農工間格差」の是正であり、今日的に翻訳し直せば、農業において周年就業を達成し、雇用労働力に依存する経営をも実現できる規模の達成となる。露地生産の季節性が依然として克服できない土地利用型農業における周年就業は、一方ではいわゆる「6次産業化」と総称される非農業部門の垂直的な統合を通じて、他方では施設園芸などの周年農業部門の導入を通じて実現がめざされつつある。
にもかかわらず、土地利用型農業自体における周年農業の実現を通じた周年就業の達成は十分に追求されてきたとはいえず、ここでの本来的「農業問題」の解決は先送りされてきた。
◆周年農業を通じた周年就業の実現
だが、2000年を前後する麦・大豆本作化政策の過程で、北関東以西の最先端の大規模経営の間に重大な転換が起きたことが指摘されねばならない。
表2は愛知県の農事組合法人A経営(出資者8人)の毎月の労働時間の推移を長期的に示したものである。ここから、以下のような興味深い事実が読み取れる。
第1に、1人当たり作付面積が25ha程度までで、大豆作に本格的に取り組んではいなかった1988〜95年までは、年間労働時間は製造業労働者より560〜450時間程度少なく、1〜3月には明らかな農閑期が存在していた。周年就業が完全には実現されていない下で、月別労働時間の変動係数は0.40を超えていた。
しかし、第2に、1人当たり作付面積が35haを超え、麦あとの54%に大豆作が導入される1999年になると、年間労働時間は製造業労働者に146時間差にまで接近するとともに、1〜3月の冬期労働が増加して、月別労働時間の変動係数は0.28にまで低下し、周年就業の実現に向けた大きな一歩が踏み出された。
そして、第3に、農地流動化が急進展し、転作が強化される中で1人当たり作付面積が45ha超となる2002〜08年には、年間労働時間は製造業労働者を120〜140時間程度超えるとともに、農閑期が事実上消滅して、月別労働時間の変動係数は0.20を割り込むところにまで縮小し、周年就業が周年農業の形で実現している。
注目すべき点は上述の全期間にわたって、A経営の組合員の所得水準は地域の大企業労働者の水準を大幅に上回っていたことであり、所得水準・労働条件の両者で「他産業なみ」の土地利用型農業経営が成立したことである。こうした実態を初めて本格的に解明した李侖美氏の研究(表2の出所参照)においては、2007年現在で277haの経営面積に達するA経営のほか、148haのB経営(滋賀県)、68haのC経営(兵庫県)についても検討が行われ、類似の実態が指摘されている。今まさに、日本の水田農業経営は新たな地平に到達しつつあるということができよう。
◆地域的特性に応じた営農類型で
たしかに、以上の3事例はいずれも東海〜近畿の米・麦二毛作地帯ものであり、北陸から東北に至る水田単作地帯の多くには当てはまらない側面を有している。にもかかわらず、麦・大豆二毛作体系の本格的定着は3事例の地域でも初めての本格的な挑戦である。大切なことは外的条件の困難性を指摘することではなく、困難性を打破できる可能性を見出すことである。
本稿では経営面積100ha超の経営に着目したのだが、販売目的の農業事業体50〜100haには247の経営が存在しており、稲・麦・大豆が1位部門の事業体数合計222と極めて接近していて、100ha超の水田農業経営には広範な予備軍が存在していることが明らかである。2010年センサスがこうした大規模経営の最新局面を的確に捉え、日本農業の可能性に一筋の光明を見いだすことができることを切に願うところである。
東京大学大学院農学生命科学研究科教授