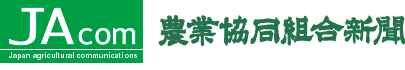JAいわて花巻
◆「復興」へ、に対する気持ちの違い
 「沿岸部と内陸では被害の認識がぜんぜんちがうよ」とため息まじりに語るのは、JAいわて花巻理事の佐々木耕太郎さんだ。釜石南部の唐丹在住で、沿岸部から離れていたため幸い大きな被害には遭わなかったが、毎日のように被災現場に出向き遺体捜索やがれきの撤去作業などに携わっている。日々の活動の中で感じるのは、被災者と被害が軽微な人との意識の差だ。
「沿岸部と内陸では被害の認識がぜんぜんちがうよ」とため息まじりに語るのは、JAいわて花巻理事の佐々木耕太郎さんだ。釜石南部の唐丹在住で、沿岸部から離れていたため幸い大きな被害には遭わなかったが、毎日のように被災現場に出向き遺体捜索やがれきの撤去作業などに携わっている。日々の活動の中で感じるのは、被災者と被害が軽微な人との意識の差だ。
「どんなカタチで復興したいか、なんてよく聞かれるが、そんなことを聞くのはまだ酷だよ。3カ月も経ってるのに、依然がれきの山が積みあがってる。毎日こんなのを見ていたら、復興しようなんて気持ちにはなれない」と疲れた表情だ。
被害の大きかった釜石とJAの本店がある花巻は距離にしておよそ100km離れている。そのちょうど中間ほどにある遠野は、支援物資の流通やボランティア団体の拠点にもなっているため被災地の緊張感を肌に感じられるが、花巻の辺りではすでに青々としたイネが植えられ例年と変わらない6月の風景が広がっている。震災があったことを忘れてしまうのどかさだ。支援活動にある程度のメドをつけ復興に向けて歩み始める段階に入ったと見る内陸部と、まだ踏み出せる状態ではないという沿岸部の意識の差は、単純に風景の違いからも窺い知れる。
釜石市で被災し、家は全壊、計70aほどの水田と畑も津波に飲まれたという元JA職員の橋本信行さんは、自身も含め被災した農業者は営農を再開するか、諦めるか、態度を決めかねているのが現状だという。最大の問題は「行政の復興ビジョンがまるで見えてこない」ことだ。
釜石の沿岸部は、10〜30aほどの農地の合間に家が立ち並び、ほとんどの農家組合員は半農半漁、または兼業農家だった。しかし、家も農地も施設も一切合財が流失したこの場所で営農を再開するならば、基盤整備と農地の集約・大規模化、集落営農組織の構築が必須条件だ。
「従来の形に戻すのは非現実的。居住区と農地をしっかり区画整備して、農業者の組織化をすすめなければ地域農業の復旧は不可能だ。そういう形を構築するなら、ぜひ参加して営農を再開したい」という意見の人は多い。しかし「行政からの補助や支援がなければ、動き出せない」のが現状だ。
(写真)道の左側は津波被害をうけた水田、右側は津波に襲われずに田植えが行われている
◆JAに求められる地域リーダーづくり
 佐々木さんも「行政が早く復興ビジョンを示さないと、ヨソから入ってくる企業などに地域が食い物にされかねない」との不安を抱く。農林水産業を軸にした強い地域基盤をつくるためにも、「JAに求められるのは、集落の組織化などを支援する地域リーダーづくり」だと指摘する。
佐々木さんも「行政が早く復興ビジョンを示さないと、ヨソから入ってくる企業などに地域が食い物にされかねない」との不安を抱く。農林水産業を軸にした強い地域基盤をつくるためにも、「JAに求められるのは、集落の組織化などを支援する地域リーダーづくり」だと指摘する。 釜石までを管轄するJAいわて花巻の川野政光遠野統括支店長も、「(復興のためには)地域の核となる組織づくりが必要」だと認識を一にするが、現状では人手不足や公用車の損失などで地域や組合員を廻ることすらままならない。「JA合併が進み財務状況などは健全化したが、改めて小回りの効く地域ネットワークづくりをどうするかを考えるべきだ」と、大震災をうけて顕在化したJAの課題に対応していきたいと述べている。
釜石までを管轄するJAいわて花巻の川野政光遠野統括支店長も、「(復興のためには)地域の核となる組織づくりが必要」だと認識を一にするが、現状では人手不足や公用車の損失などで地域や組合員を廻ることすらままならない。「JA合併が進み財務状況などは健全化したが、改めて小回りの効く地域ネットワークづくりをどうするかを考えるべきだ」と、大震災をうけて顕在化したJAの課題に対応していきたいと述べている。
全壊したJA釜石支店で支店長を務めていた見世百合子さんは、組合員の安否確認や金融・共済の相談のため、避難所も含めた訪問活動を行っている。被災者の多くは「この大震災にあっても、やはりこの地を去ろうと考えてる人はほとんどいない」という。
現在は沿岸部から10kgほど離れ、昨年廃止した旧甲子支店を臨時店舗として営業しているが、被災者からは以前の生活に戻るためにも一日でも早くJAが元の場所に戻ってほしいとの要望が強い。
職員9人中3人が被災し金融・共済の相談にのれる専門職員もいなくなり、本店からの人的支援も限られているが、「これまでずっと地域密着でやってきた成果だと思うが、感謝の声とともに強い期待も感じる。店舗が遠くなってもすべての組合員の面倒をみられる環境をしっかりつくり、地域で頼られるJAを復活させたい」と意気込みを語った。
(写真)
上:(左から)橋本さん、佐々木さん、見世さん
下:JAいわて花巻・川野政光遠野統括支店長
JA新いわて
◆国の方針に振り回される農業者

管内が広いJA新いわてでは、宮古、久慈といった被災地の営農経済センターを中心に復興へ向けた被害や組合員の意向調査を行っている。
被害の大きさとその対応は4段階。(1)被害が軽微ですぐに復旧、(2)半年から1年後に復旧、(3)復旧までに3〜5年かかる、(4)復旧の見込みがない、の4つだ。
宮古営農経済センターの舘崎浩明センター長は、(1)、(2)についてはJAの支援もあり、塩害に強い作物を植えたり用排水路を整備するなどしてすでに営農を再開している組合員もあるが、問題なのは(3)、(4)だという。
区画の境界線すら消えてしまった地域では再基盤整備が必要不可欠だし、重さ何トンというブロックが突き刺さったまま放置されている農地や、何日も海水に浸かってしまった水田の除塩は、JAや組合員の努力だけではどうにもならない。そもそも、国の描く復興ビジョンの中で、農地の再整備や企業の進出、工業団地の誘致などの案が出されているが、仮に手間をかけて農地を復旧させても、国の方針が変わればその努力は水泡に帰す。 舘崎氏は復興にかかる市の説明会に参加したが、具体的な方針や対策はまったく語られず憤りを感じた。
舘崎氏は復興にかかる市の説明会に参加したが、具体的な方針や対策はまったく語られず憤りを感じた。
現状は、農業者が国に振り回され、復旧に向けて舵を切っていいのかどうかすらわからない状態だ。
組合員の多くは毎日避難所から畑や田んぼに出かけ、掃除や今できる作物を植えるなどできる限りの作業をやるしかなく、JAとしても被害の大きいところに対しては「JA単独でできることは限られる。残念だが、行政の指針が決まらなければ何もできない」のが現状だ。
(写真)
上:JA新いわて青年部北部中央支部が手作り立て看板で被災地を応援(5月3日、写真提供=JA新いわて)
下:女性部による宮古市赤前仮設団地での炊き出し(写真提供=JA新いわて)
◆全農家回り、野菜を調達
 一方、震災直後の緊急支援活動ではJAの結集力が地域を救い、改めてその存在価値を高めた。
一方、震災直後の緊急支援活動ではJAの結集力が地域を救い、改めてその存在価値を高めた。
「系統の力がこれだけすごいとは、正直思わなかった」と、舘崎氏は震災後1カ月間の活動を振り返って語った。この間、通常の業務は手つかず、日々支援物資の仕分けや配達に追われ、記憶も定かではないという。
特に被災者や行政に驚きとともに感謝されたのは、野菜の調達だ。
JA新いわては農家組合員から被災地への拠出米を募り、合計46.5tのコメを被災地へ届けた。また全国のJAグループからもコメの支援があったが、震災後1週間ほどして問題になったのは野菜不足だ。
宮古市は県などに対して、野菜や生鮮品の提供を要望したが、流通ルートの破断などがあり、いつ届くか分からない状態。そこでJAが要請を受けた。「とにかくなんでもいいから集めよう」と、3月22日から4月上旬まで毎日、職員が被害の少なかった管内の全農家を訪ね、1日400kgほどの野菜類を買い取って回った。組合員には、市場価格よりも若干高い値段を払い、規格外品や包装なども不問でコンテナのままで受け付けた。もちろん手数料はもらわない。中には、1カ月以上かけて順次出荷する予定だったホウレンソウを、たった2日ですべて出した組合員もいたという。
4月中ごろには流通が復活しこの活動は終わったが、舘崎氏は「この仕事を始めて何十年もたつが、今回ほど結集力を感じたことはなかった」と感心した。行政の担当者に「自衛隊も、県も、こんなことはできなかった。なぜJAはできるんですか」と驚かれたが、「なぜもなにも、それがJAだというしかない。私たちは当たり前のことをやっただけだから」と笑みをこぼした。
(写真)JA新いわての支援活動、青年部による復興応援自転車リレー、沿岸地域を自転車で縦断した(写真提供=JA新いわて)
◆「本当に大変なのは来年」
被災地の人たちが口をそろえて言うのは、「復興への道筋が見えない」という焦燥と不安だ。そして必ずその後に続くのは、「本当に大変なのはこれからだよ」という言葉だ。
被災者の多くには共済金が支払われ、また農業や漁業ができなくてもがれき撤去などの作業で当面の収入は得られる。避難所に居れば衣食住の心配はなく、仮設住宅に入ってしまえば公共料金や食費は自己負担になるが、少なくとも住居の心配はなくなる。
しかし仮設の入居期限は2年間。来年には新しい家を建てなければいけないし、何より今年、農地・漁港など生産にかかるシステムを復旧し、または加工施設など雇用の受け皿を作らなければ、来年の収入はゼロだ。
岩手県では、9月ごろに復興ビジョンを策定し、10月から計画を実施する予定だが、「それでは遅すぎる。いますぐにでも復興の青写真を提示して動きはじめなければ、来年を迎えられない」とのとの不安は募る一方だ。
被災地の焦り、疲労、憤り、不安を少しでも解消しようと支援の輪が広がっているが、その気持ちを無にしないような施策を早急に打ち出さなければならない。
田老町漁協
◆漁場も船も共有協同経営で危機を乗り切る
 「漁業は再開したいが船も港も施設も何もない。震災直後から何も変わってないし、復興なんて考えられない。それなのに、企業を入れて水産復興特区をつくるとか、陸に打ち上げられた船をモニュメントとして残そうとか、現場の人間の気持ちを完全に無視している」と怒りの声をまくしたてたのは宮古市北部にある田老町漁協(JFたろう)理事の高屋敷登さんだ。話をしながらも時折口をつぐみ、「どんな時も頭の中は、明日はどうなるんだろうっていう不安でいっぱいだよ」と苦しい表情を見せた。
「漁業は再開したいが船も港も施設も何もない。震災直後から何も変わってないし、復興なんて考えられない。それなのに、企業を入れて水産復興特区をつくるとか、陸に打ち上げられた船をモニュメントとして残そうとか、現場の人間の気持ちを完全に無視している」と怒りの声をまくしたてたのは宮古市北部にある田老町漁協(JFたろう)理事の高屋敷登さんだ。話をしながらも時折口をつぐみ、「どんな時も頭の中は、明日はどうなるんだろうっていう不安でいっぱいだよ」と苦しい表情を見せた。
田老は古くからの漁業の町で、沿岸部には1000戸ほどの家が立ち並んでいたが、今は跡形もなくすべて流されてしまい、ただひたすら何もない平地が広がるばかりだ。復興のことなんかとても考えられない、といった言葉が現実味を帯びる。
普段であればこの時期、田老町ではウニ漁が最盛期を迎え、7月末から8月にかけては来春の収穫をめざしワカメの種付けをする時期だ。しかし、漁船も養殖台もほとんどが流出してしまい、生産基盤は失われたまま。ようやく6月下旬から損壊した養殖台の撤去作業が始められるという状態だ。
JFたろうの組合員数は707人。そのうち養殖業者は94人いたが、およそ8割ほどの76人が漁業の再開を希望している。震災直後は半数ほどだったが、時が経つに連れ、「やはりもう一度」と思う人が増えてきたという。
田老町は過去に何度か大きな津波を経験しているが、とくに明治29年に10mを超える大津波が襲ったとき、田老の漁業は存亡の危機に陥った。そこで地域内のできるだけ多くの漁師が生き残るようにとはじめたのが、漁船・漁場・施設などの共有と協同経営だ。 今回の漁船の共有とは、養殖関連で残ったわずか14隻の漁船を漁協が借り、また国や県の補助を受けて漁協が新たに買った50隻を含めた計76隻の船を各養殖班に無償で提供し、班内の組合員で共同利用するもの。
今回の漁船の共有とは、養殖関連で残ったわずか14隻の漁船を漁協が借り、また国や県の補助を受けて漁協が新たに買った50隻を含めた計76隻の船を各養殖班に無償で提供し、班内の組合員で共同利用するもの。
協同経営とは、各人が獲ったものをすべてまとめて全員に再分配する仕組みだ。例えばアワビを100杯獲った人と50杯しか獲れなかった人がいても、2人とも75杯分の収入を得られるようにすることで、脱落者を出さないようにする仕組みだ。
明治29年にはこれらの方式を地域内で徹底させ、存亡の危機を乗り越えた記録がある。今回もこの方式を最低1年は続ける方針だ。
漁協では、船の共有と地域内の協同経営で「組合員負担ゼロ」の復興をめざし、協同経営を実行した場合の個人の収入の目安や、将来的に個人経営へ移行するための工程表などを全12段階で示し、組合員の全員参加を呼び掛けている。畠山康男副組合長は、「協同組合ならではの相互扶助の精神で、地域みんなで危機を乗り越えたい」と力を込める。
地域が一体とならなければ養殖業の復興はあり得ない。だから、震災や協同経営を理由に脱退するような組合員もいない。畠山副組合長は、「なんとしてでも真崎わかめを復活させる。地域の人たちも想いは一緒。来年の春には日本一のワカメを食べに来てよ」と復活を約束した。
(写真)
上:「自分の家があったところだ」と、何もない平地を指す高屋敷さん
下:「日本一の真崎わかめ」復活をめざす田老町漁協の畠山副組合長
おおさかパルコープ
◆大阪の生協が岩手に常駐し支援
 JAいわて花巻と姉妹提携を結ぶJA紀の里(和歌山)、JA横浜(神奈川)による独自の支援や、JAグループも各県連合会の職員が直接現地入りして救援活動を行うなど、被災地には県内外から支援が集まっている。
JAいわて花巻と姉妹提携を結ぶJA紀の里(和歌山)、JA横浜(神奈川)による独自の支援や、JAグループも各県連合会の職員が直接現地入りして救援活動を行うなど、被災地には県内外から支援が集まっている。
その中で大阪からきて、釜石を中心に独自の支援活動を継続的に行っているのが「おおさかパルコープ」だ。
JAが合併してJAいわて花巻となる以前の遠野農協時代から、産直指定米の取引をしていた経緯があり、震災後すぐに遠野市を支援活動の拠点にし、被災地に寄り添い見守りながら地元生協の共同購入再開支援や、指定取引工場などの被災・営業状況を逐一大阪の組合員へ広報し支援を呼び掛けるなどの活動をしてきた。
5月21日からは、釜石への支援・復興活動の拠点となっている遠野市で社会福祉協議会の「遠野まごころネット」に参加し、毎週5〜10人の職員が交代で遠野へ赴き、がれき撤去などのボランティア活動や移動販売などに従事している。参加する職員はみな、1週間の夏期休暇を交代で使って参加。現在、女性職員や女性パート職員も含め約170人の希望者が集まり、すでに8月のお盆まで参加メンバーが決まっているが、活動はそれ以降も続けていく考えだ。
5月から現地のおおさかパルコープ常駐事務局をしている林輝氏は「復興にむけての課題はまだまだ山積み。16年前に阪神淡路大震災で被災した経験を活かして、継続的な支援をしていきたい」という。また、「このような助け合い活動こそが協同組合運動の原点だ」として、職員に協同組合運動の精神を学ばせるという人づくりの観点からも支援を続けていきたいとしている。
(写真)
おおさかパルコープでは皿、フライパン、アルミホイルなど台所用品一式をまとめた「家族セット」を救援物資として提供。被災者にもっとも喜ばれているという。(写真提供=おおさかパルコープ)
(関連記事)
・ ルポ・宮城県―復旧あってこそ地域は再生(2011.07.11)