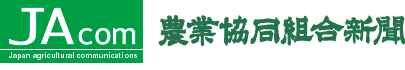◆大手にはない独自の“色”を持つ
 「中小企業は、“なんでもできます”ではなく、“これだけは”他社に負けないという“色”をもたなければ生き残れません」。年商23億円の食料品販売会社(株)ホーム食品の社長である多田浩さんは、自らの事業を振り返りながら語ってくれた。
「中小企業は、“なんでもできます”ではなく、“これだけは”他社に負けないという“色”をもたなければ生き残れません」。年商23億円の食料品販売会社(株)ホーム食品の社長である多田浩さんは、自らの事業を振り返りながら語ってくれた。
(株)ホーム食品は長野に本社を置き、販売する製品の製造工場(子会社の(株)北日本ホーム食品)は、風力発電で有名な新潟県新発田市藤塚浜(旧 北蒲原郡紫雲寺町)にある。
営業は製品開発と製造拠点の工場とともにあるほうが都合が良いという理由で、多田さんはほとんどを新潟で過ごし「たまに長野に帰ります」という状況だ。
多田さんが言うホーム食品の他社に負けない“色”とはどういう色なのだろうか。
惣菜加工食品の製造販売会社といいながら、量販店や食品スーパーには一切販売していない。販売先は、全国各地の生協の共同購入が売上げの半分。食材宅配会社が3割前後、JAグループの食材宅配部門が2割前後となっている。つまり小売店舗では、ホーム食品の商品は買えないということだ。
「広告宣伝にお金をかけませんし、包装資材にも必要最低限のコストしかかけません」という。
◆機械を設置しないからできること
 工場(北日本ホーム食品)の製造現場を見せてもらった。工場に入るために、クリーニングされた専用のズボン、上着、帽子、マスクを着用して長靴に履き替え、手洗い消毒をして、何重にもわたる衛生チェックを受け、漸く内部に入ると、誰一人いないように見える質素な建物外観とは風景が全く異なって、記者と同じ白色の作業着に防水用前がけを付けた女性が沢山いることに驚かされた。
工場(北日本ホーム食品)の製造現場を見せてもらった。工場に入るために、クリーニングされた専用のズボン、上着、帽子、マスクを着用して長靴に履き替え、手洗い消毒をして、何重にもわたる衛生チェックを受け、漸く内部に入ると、誰一人いないように見える質素な建物外観とは風景が全く異なって、記者と同じ白色の作業着に防水用前がけを付けた女性が沢山いることに驚かされた。
原料のスライサー・カット・最終包装機を除いて、機械類が極端に少ない。代わりに人が沢山いていくつかの作業台を囲んで所定のレシピに基づき、手作業で商品をつくっている。所定数量の商品づくりが終了すると、荷台に積まれた一山の未封品を保管・包装ラインに移動させて、道具と作業台を湯洗し、次の商品づくりを始める。
ラインに機械を据え付けるということは「製品を大量につくってコストを下げる」ことが目的となり、採算が取れる最低ロットが必要になってくる。幸い食材宅配用食品は、概算から確定数、出荷までの時間が短くその数量も振れる。すなわち、発注数がわかってから製造すれば良いことと、人的製造ラインが多品目少量生産にも、一時的な大量注文にも柔軟にフィットして効率良く製造できることから、機械に支配されることがない。「人がつくるので少量でもつくれます」。もし大量に注文が入ればその商品をつくる人手を集中させて増やせば良いということだ。
◆手作業を苦にしない地域の人たちと共に
 ホーム食品は、魚屋を営んでいた多田さんのお父さんが、これからは消費が伸びる肉の時代だと考え、昭和42年に長野市に設立された会社だ。当時は、魚の卸売市場で味付け豚や焼き鳥などを販売していた。その後、昭和59年に長野市から新発田市に工場を移転(北日本ホーム食品)し、中堅食品会社のPB商品の受託製造などをしていたが、独自の道を確立する必要があると考え、平成2〜3年ごろに現在の路線をスタートさせた。
ホーム食品は、魚屋を営んでいた多田さんのお父さんが、これからは消費が伸びる肉の時代だと考え、昭和42年に長野市に設立された会社だ。当時は、魚の卸売市場で味付け豚や焼き鳥などを販売していた。その後、昭和59年に長野市から新発田市に工場を移転(北日本ホーム食品)し、中堅食品会社のPB商品の受託製造などをしていたが、独自の道を確立する必要があると考え、平成2〜3年ごろに現在の路線をスタートさせた。
「料理を提案する」スタッフも含めて、新発田の工場で働く社員は約120名。ラインで製品を造る人たちは地元の主婦が多いという。機械を使わないことは雇用を創出し、継続して、地域の経済に貢献している。
多田さんは、高校卒業時にお父さんから食肉の基本を学ばないかとすすめられ、昭和53年に全国食肉学校に入学する。そして卒業後は中堅ハムメーカーに就職するが、新発田に工場ができたのを機に、昭和60年にホーム食品に入社する。
全国食肉学校で学んだ原価計算の考え方などの基本を活かしながら、資金力や人材面で中小企業は「大手と競争しても勝てない」のだから「大手にできないことを」と考えたという。営業で各地を回るうちに地元新潟新発田の工場にも周辺にも「手作業を苦にしない地域の女性が沢山いる」ことに気がついた。それが地域の人たちと共に、生協の共同購入や食材宅配に特化しようと考えたきっかけだったという。
(写真)衛生管理を徹底した「大きな台所」のような製造現場
◆ニッチな部分をさらに掘り下げて
 量販店や食品スーパーを紹介するという話がよくあるが、多田さんは全て断っている。「平面への拡大ではなく、狭いニッチ(隙間)の部分を掘り下げる」ことで他社に負けない“色”をさらに鮮明にしようと考えているからだ。
量販店や食品スーパーを紹介するという話がよくあるが、多田さんは全て断っている。「平面への拡大ではなく、狭いニッチ(隙間)の部分を掘り下げる」ことで他社に負けない“色”をさらに鮮明にしようと考えているからだ。
ニッチな部分で生き残るための重要な要素が商品提案だ。生協は味噌漬けの豚肉など「素材中心」だが、食材宅配は毎日食卓にのる「夕食」そのものを、調味料を含めた材料の全てを宅配するのだから、それは「主婦の目線で料理を提案している」ことに等しい。
ホーム食品の開発部隊は、利用者が食べたことはあるが、自分では作れない料理や、パスタの代わりにうどんを使ったカルボナーラなどの珍しくておいしいオーダーメイド料理を提案しなくてはならない。過去のものを含めると膨大なレシピの数々を若いスタッフが毎日考えており、その提案数は年間300アイテムにものぼる。多田さんも試食し意見を言う。
全国食肉学校で学んだ食肉の基本技術と知識が、その後の社会経験と会社入社後の豊富な経験が商品開発とその指導に役立っている。
(写真)試食をする多田社長
◆最終的には人だから人を育てることが
経営者の多田さんは、今までこのシリーズで紹介してきた全国食肉学校の卒業生とは、多田さん自身も認めているように“色”合いが違う。しかし、経営のベースとなる食肉の技術と知識、そして人間の基本を全国食肉学校で学んだうえで、置かれた環境に的確に対応してきたという点では他のOBと同じだと言えるだろう。
恒例の後輩へのメッセージをお願いすると「自分ひとりでやるのには限りがある。自分と同じ志をもつ人が一人でも多くいて、自分と同じあるいは自分以上に情熱をもってもらえるように努力すれば、自分のしたいことが実現できる」そして「最終的には人だから、人を育てなければ自分たちがやりたいことは実現できない」と、まさに多田さんとホーム食品の人たちのこれまでの経験を踏まえた言葉が返ってきた。
機械ではなく人に活路を見出した多田さんらしい言葉だと聞いた。
(株)ホーム食品 代表取締役社長