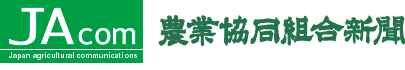◆消費者という存在
中国産冷凍ギョーザの有機リン系農薬「メタミドホス」中毒事件が、輸入食品依存の「食」の危うさを浮き彫りにしています。食料自給率39%という数字の持つ意味がいかなるものかを、国民にいっきょに突きつけたともいえるでしょう。野坂昭如氏は、これまでも一貫して食糧輸入大国であることに警鐘を鳴らしてきましたが、毎日新聞のコラム「七転び八起き」(連載第22回、08年2月11日)で、「輸入頼り黙認の危うさ」と題して、「生産者と消費者の距離が遠すぎる。本来、島国は自給自足が筋。自分の国の食べ物を大事にしろ」と訴えています。まったく同感です。
ところで、農薬中毒を起こした冷凍ギョーザが、何と日本生活協同組合連合会(日本生協連)傘下の生協の人気商品「CO・OP手作り餃子」であったことが、たいへんな衝撃を広げています。生協は、「安全安心な食」を掲げて組合員を結集してきたからです。大学生協や地域生協の理事の経験のある私には、「それ見たことか」と言う資格はありません。しかし、スーパーマーケットとの安値競争に勝ち抜くには安価な海外商品の調達が避けられないとして輸入に走ってきた生協陣営は、この冷凍ギョーザ中毒事件で、実は「安全安心」を担保するシステムを確立してはいなかったこと、海外商品はそもそも「安全安心」を100%担保することはできない事業であったことを、まず組合員に謝罪しなければなりません。
日本生協連には、つい先ごろ、すなわち2005年4月に発表された「『農業・食生活への提言』検討委員会答申」(委員長・山下俊史日本生協連現会長)という、たいへん物議を醸した提言文書があります。というのも、この検討委員会には、農水省の食料・農業・農村政策審議会企画部会長で構造改革農政の「品目横断的経営安定対策」をまとめあげた生源寺眞一東大大学院教授が加わっていました。
そして、何とこの文書は選別的構造改革農政を支持するとし、WTOの自由貿易体制のもとでは高関税の低減はもはや避けられない国際的潮流である。消費者としては、財源の投入により農業者を支援する政策の展開にあたっては、高関税の低減による内外価格差の縮小を求めるとするものであったからです。これは日本生協連傘下の多くの生協に対して、海外商品事業に活路を求めるようリードするとともに、それを理論的にバックアップする戦略的文書でした。そして、そのような理論武装をしたうえで突っ走ってきた事業戦略であるだけに、今回の冷凍ギョーザ中毒事件という痛い目にあっても、「目を覚まし、初心に帰ってほしい」という生協組合員の声においそれとは応えられないでしょう。
問題にしたいのは、日本生協連の主流が80年代に始まるグローバリズムを消費者の利益と捉え、海外商品事業の展開で、安価な輸入品も含めた商品の選択性を確保することは消費者への保証であり、消費者利益にかなうことだとしてきたことです。
そこで、取り上げたいキーワードが「消費者利益」または「消費者主権」です。
◆「消費者主権という欺瞞」
つい最近、2006年4月に亡くなったジョン・K・ガルブレイス/ハーバード大学名誉教授(1908年カナダ生まれ)が、最晩年に執筆したコンパクトな著作に、『悪意なき欺瞞―誰も語らなかった経済の真相』(原題を直訳すると佐和隆光訳、ダイヤモンド社、2004年刊、『悪意なき欺瞞の経済学・われわれの時代の真実』)があります。ガルブレイス教授は、わが国では『ゆたかな社会』(58年)、『不確実性の時代』(77年)など、数多くの著作が翻訳され、アメリカを代表する制度学派のリベラル経済学者として多くの読者を得ています。
この『悪意なき欺瞞』を取り上げるのは、そこに「消費者利益」ないし「消費者主権」についてたいへん示唆的な指摘があるからです。この本の意図するところは、経済学の通説と現実の間には深い溝があること、その中心問題は、「企業と企業経営者が現代経済社会を統治しているという現実」であることを暴露することです。
ガルブレイス教授が問題にしているのは、誰が「市場における本当の主役」であるかです。教授は、「消費者主権、すなわち消費者が何を買うかの選択こそが、資本主義経済を動かす根本的な動力源に他ならない」とすることは、まさに「悪意なき欺瞞」だといいます。
アメリカでは19世紀末に独占企業が成立し、商品を独占価格で供給するようになると、消費者の選択が入り込む余地はまったくなくなり、独占にどう対処するべきかが、したがってアンチトラスト法と呼ばれる独占禁止法が、一時期、最大の政治的関心事となったといいます。しかし、その後の経済成長で企業の新規参入が活発になるにつれて、独占への関心がすっかり薄らぎ、「独占資本主義」という言葉が姿を消し、経済学教科書には、いまや消費者は主権者であって独占資本の支配下にあるのではないと書かれるようになったというのです。ところが、教授がいうように、現実はそれほど単純ではありません。消費者に対しては、広範かつ巨額を投じての「実効性あるコマーシャル・メッセージが、市場を操作することを狙ってメディアに登場」します。「消費者主権」などというのは、「企業と企業経営者が現代経済社会を統治しているという現実」、そして「企業自身のできること、必要とすることに、人々の嗜好を適合させてゆく力を備えた」企業によって「消費者はコントロールされる存在」であることから目を逸らさせる欺瞞に他ならないと厳しく指摘します。
アメリカでは60年代に自動車会社の安全軽視を糾弾したラルフ・ネーダーの消費者運動がきっかけになって、消費者主権のバイブルといわれる「ケネディ教書」が、(1)安全である権利、(2)知らされる権利、(3)選択できる権利、(4)意見が聞かれる権利、の4つの権利を消費者に認めました。これはわが国の68年の消費者保護基本法の制定にも影響を与えたものです。だからといって、80年代になって「消費者ニーズ」ということばが幅を利かせるようになったこととあいまって、あたかも消費者が市場の本当の主役であり、保護されてしかるべき存在だと誤解して、企業との闘いを放棄してよいわけではなかったのです。ガルブレイス教授が遺言のように書き残したのは、「私利私欲の飽くなき追求を旨とする企業システムの支配、これこそが21世紀の基本的な事実」であり、イラク戦争もまさにそれがもたらした災厄であって、企業システムとの闘いを私たちに求めることだったのです。
さて、冒頭で取り上げた日本生協連の提言が罪深いのは、政府の国内農業・農業者への力ずくの選別と構造調整政策に対して、農業生産者と消費者の連携なり同盟をもって対抗するのではなく、農業に構造調整のための財政支出をするなら、関税を低減させて食料の内外価格差を縮小させる、すなわちより国際価格に近い安価な食料を消費者に寄越せと要求していることです。それは、必然的に国内農業生産者の出荷価格を引下げさせよという要求になります。独占企業商品の値下げではなく、すでに輸入農産物の圧力のもとで価格低下に苦しむ農家、すなわち小商品生産者の商品である農産物とそれを原料とする加工食品の価格引下げの要求です。私は、これは何とも見苦しい「その日暮らし消費者」のグローバリズムと構造改革路線への屈服とみます。私は、生協陣営は今でも消費者運動の一翼を担う存在であると考えています。わが国において、「消費者利益」とはいかなるものであるべきか、消費者運動は何をめざすべきかについての深刻な議論が求められます。