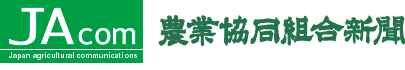◆源泉は河内長野の病虫害研究農場に
 |
同社の研究開発体制構築の流れを整理しておくと、1930(昭和5)年の河内長野における河内病虫害研究農場の開設に源泉があり、当時は硫黄や銅のような天然素材が如何に防除に役立つかを研究していた。
戦中、戦後の食糧増産が国家的な重要施策であった時代に、それらの背景のもと海外メーカーの原体を輸入し、その原体を日本の農業にフィットさせる研究の先頭に立って奮闘しているが、それは日本農業の現場を熟知した同社ならではの取組みだった。
しかしながら、他社化合物の導入に依存する事業形態は、研究開発型企業を目指すには決して満足のいくものではなく、当時の日本農薬技術陣らは農薬の研究開発から原体製造、製剤、販売を一貫して実施したいとの悲願をもっていた。
◆フジワンの発明により悲願の一貫体制果たす
 |
|
神山社長
|
その悲願は、殺菌剤フジワンの発明(登録年度:1974年)によって成就されることになる。
いもち病の防除に水銀剤が中核的な位置を占めていた当時、より安全な農薬への社会的な要求の高まりにも後押しされた成果でもあったが、この発明は同社の飛躍の礎になったと同時に、同社研究陣のかえがたい貴重な経験となった。
以降、この経験は殺虫剤アプロード(同:1983年)、殺菌剤モンカット(同:1985年)、殺ダニ剤ダニトロン(同:1991年)、除草剤エコパート(同:1999年)、殺菌剤ブイゲット(同:2003年)、そして殺虫剤フェニックス(同:2007年)などに生かされていった。
現在では、殺虫剤アクセル(有効成分:メタフルミゾン)、同コルト(同:ピリフルキナゾン)を登録申請中であり、いち早い農薬登録が期待されている。
また、今後の殺虫剤(ダニ剤)、殺菌剤、除草剤の3分野においても開発に向けた準備がすすめられており、注目される。
◆技術陣の献身的姿勢が事業発展の重要な要因
これまで見てきたように、フジワンの発明は多くの自社剤の研究開発に繋がりを見せたが、いっぽうで医薬品分野事業への拡展をも果たしたことを忘れてはならないだろう。
例えば、それらは外用抗真菌剤アスタット(同:1994年)、同ルリコン(同:2005年)、イヌ用ノミ駆除剤プラク‐ティック(同:2006年)などとして市場投入された。
今日の展開を神山社長は、「当社技術陣の献身的ともいえる研究姿勢が事業発展の重要な要因の1つとなったことは間違いない」とし、また「この間の大学、研究機関、行政当局、農家の方々の忌憚のない意見、激励が当社を育んでいただいた」と感謝の意を表した。
そして、「今後も国内外の農業に貢献する製品、牽いては世界のひとびとの豊かで健康な生活に少しでも寄与できるグローバルニッチ製品の創出を目指していく」と将来の研究開発のあり方を展望した。
重要な4演題で記念学術講演会 80周年超え新たな1歩踏み出す
京大会館
|
日本農薬の80周年記念学術講演会は『新農薬創出を支える科学の現状と展望』のテーマのもとに、創薬と安全性研究に関する4演題で行われ、80周年記念事業を締めくくるに相応しい講演会となった。80周年という重みを超え、新たな一歩を踏み出したとの印象を受けた。 |
 |
I.『創薬ターゲットとしてのイオンチャネル』
(京大大学院工学研究科教授・森泰生)
フルベンジアミドのRyR(リアノジン受容体)に対する詳細な作用分子機構の解明を目指した結果、フルベンジアミドがRyRに直接結合していることが強く示唆された。今後の詳細な機構解明は、動物のRyRを含む広範なイオンチャネルを標的とした創薬開発において重要な知見を与えると期待される。
 |
II.『有機合成の新システム』
(京大大学院工学研究科教授・吉田潤一)
マイクロリアクターは今後、合成化学の研究・開発において強力な道具となるだろう。精緻な流れの中で不安定な反応活性種を発生させ、それを別の場所に高速に移動させて反応させるといったように、マイクロリアクターを用いなければできない形式の反応が可能となり、様々な新反応の開発が期待される。
 |
III.『化学物質による発がん性評価の変遷と問題点』
((財)残留農薬研究所理事・原田孝則)
一般に変異原性発がん物質にはイニシエーション作用があり、非変異原性発がん物質はプロモーション作用を有するとされているが、真の発がん物質はいずれの作用も保有していることが知られている。化学物質による発がんメカニズムは複雑多岐でいろんな要因が相互に絡み合っている。多方面にわたる高精度な検討が望まれる。
 |
IV.『農薬の環境動態とリスク管理』
(日本農薬学会会長、日植防技術顧問・上路雅子)
農薬を有効に活用していくためには、最大限の効果(ベネフィット)を獲得しながらリスクを可能な限り小さくすることが必須。環境保全型の優れた新規農薬が開発されるとともに様々な規制が行われ農薬の負の側面は大きく解消している。一方、十分なリスク管理とはどのようなものかなど、いまだ検討課題が残っている。