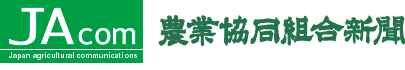農協はモンスーン・アジアの農業や
地域社会の守護神である
文芸アナリスト・大金義昭
JAは「内に蓄積する力」を外に開け!!
広げよう JAグループの力
◆飢餓に苦しむ国民を「食糧増産」で救う
 65年という歳月は、短いのか長いのか。受け止め方は、人や組織や地域によってさまざまである。仮に人なら還暦を経て、古希へ向かう道半ば。国民年金の受給開始年齢や介護保険の「第1号被保険者」とみなされ、「高齢者」への扉を開く年齢である。その65歳以上の「高齢者」が、去る9月15日の時点でついに3000万人を突破。総人口に占める割合がおよそ4分の1を占めるに至った。戦後の第1次ベビーブーマー、いわゆる「団塊の世代」が「高齢者」に仲間入りし、その割合を急激に押し上げている。
65年という歳月は、短いのか長いのか。受け止め方は、人や組織や地域によってさまざまである。仮に人なら還暦を経て、古希へ向かう道半ば。国民年金の受給開始年齢や介護保険の「第1号被保険者」とみなされ、「高齢者」への扉を開く年齢である。その65歳以上の「高齢者」が、去る9月15日の時点でついに3000万人を突破。総人口に占める割合がおよそ4分の1を占めるに至った。戦後の第1次ベビーブーマー、いわゆる「団塊の世代」が「高齢者」に仲間入りし、その割合を急激に押し上げている。
世界の先端を走る高齢社会だから、こんな言葉がまかり通る……「50、60、洟たれ小僧。70、80、働き盛り。90になって迎えが来たら、100まで待てと追い返せ」。きょうの自分がいちばん若い。若いと思えば、いつまでも若いのである。
われらが愛すべきJAも、当年とって65歳。かの「団塊の世代」と同年代である。ともに戦争を知らない“戦後っこ”ではあるが、JAは敗戦に伴う占領政策によって、前身の組織が生まれ変わった。その端緒となったのは「農地改革に関する覚書」。占領軍が発した別名「農民解放指令」が地主・小作制度を解体する。農協法は、解放された農地を手にした農民が、ふたたび小作人に転落することを防ぐねらいを持っていた。
土地に対する“千年の飢え”を満たした農民が、生産意欲に燃えあがる。燃えてJAに結集する。農協法はその第1条で「農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もって国民経済の発展に寄与する」と謳っている。飢餓に苦しむ国民を、この陣形で救済する。
占領軍の「戦後民主化政策」は、この国の戦前の軍国主義を根絶やしにすることを目論んだ。国民も時の政府も、内外に3千数百万人の犠牲者を出した凄惨な戦争を反省し、“平和日本の確立”のために再出発する。新たに誕生したJAは1万3100余。「貧しさからの解放」を求め、そこに700万人の農民が結集する。あれから幾星霜。艱難辛苦を乗り越え津々浦々に根を張りめぐらせたJAは、豊かな樹形を誇る710本の巨樹となり野太い枝に葉を繁らせ、東アジアの風の中で屹立している。
◆「内に蓄積する力」を外に向かって開いていく
松本健一の著作に、ユーラシア大陸の文明を3つの類型に区分した『砂の文明 石の文明 泥の文明』(岩波現代文庫)がある。その著作の中で松本は、モンスーン・アジアの「泥の文明」の本質を「内に蓄積する力」と説いている。それは、水の多い泥土が数多くの生命を育む豊饒な風土の上に成り立っている。
この島国もその文明の中にあり、広く取り組まれてきた稲作が、1粒の米、1枚の水田、1戸の家、1つの村の中に農本的な文化のノウハウを蓄積。勤労・忍耐・正直・節約などを旨とする、いわゆる勤勉革命によって、生産工程における品種改良や品質管理などの集約的な技術革新を成し遂げてきたというのである。松本の指摘を待つまでもなく、この国の農業技術が世界の最先端技術であることは言うまでもない。
松本の主張は、和辻哲郎や大塚久雄などの先学を批判的に継承しながら、3つの文明の特質を対比的かつ現代的に浮き彫りにした。小論は、松本が追求する「泥の文明」の可能性をヒントに、戦後のJAの軌跡をたどり、持続可能な農業や地域社会を担って輝くJAの近未来像に迫る。 なぜならJAこそ、モンスーン・アジアの「泥の文明」の本質を「体現」してきた、典型的な組織・事業・経営体にほかならないからである。その近未来像に迫る課題をあらかじめ言ってしまえば、JAは「内に蓄積する力」をいかに外に向かって開いていくかに尽きる。外に開くと言っても、誤解のないように断わっておくが、あのさかしらなTPP推進論者たちが、かしましく唱える愚論とは全く無縁であり、その対極にある。あくまでも「土に立つ者は倒れず。土に生きる者は飢えず。土を守る者は滅びず」(横井時敬)である。
なぜならJAこそ、モンスーン・アジアの「泥の文明」の本質を「体現」してきた、典型的な組織・事業・経営体にほかならないからである。その近未来像に迫る課題をあらかじめ言ってしまえば、JAは「内に蓄積する力」をいかに外に向かって開いていくかに尽きる。外に開くと言っても、誤解のないように断わっておくが、あのさかしらなTPP推進論者たちが、かしましく唱える愚論とは全く無縁であり、その対極にある。あくまでも「土に立つ者は倒れず。土に生きる者は飢えず。土を守る者は滅びず」(横井時敬)である。
「泥の文明」がそもそも「内に蓄積する力」を蓄えることになったのはなぜか。「砂」や「石」の文明の母胎となった風土とは比べものにならない、豊饒な自然に恵まれていたからである。その豊かな自然の恵みを有効に活用し富を蓄積するために、相互扶助による技術集約的なシステムがコミュニティーの中に生まれ、自然との共生を図りながらこれを巧みに育んできた、と松本は唱える。
加えて、アジア的な農耕社会はその根本において、自然の生産力を「体現」する女性を尊重し、男女平等の思想を生み出してきた。お気づきのことと思うが、小論はここで「体現」という言葉を連用し、「泥の文明」すなわちアジア的な農耕社会とその本質として松本が規定する「内に蓄積する力」とJAの基本的価値と女性の底力とを重層的に捉えている。
(写真)
1946年5月19日 東京・皇居前広場(毎日新聞)
(続きはこちらから)