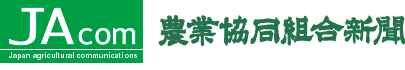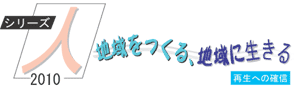
『農業ほど男女差のない仕事はない』
◆出稼ぎの町からニンニクの町へ
にんにくの植え付けは10月中旬までに終える。種は厳しい冬を土のなかで過ごす。
「雪の量は少なくても根雪になって土が凍ることが大事。土の中がぐずぐずだと身の締まったものにならないんですよ」 田子町の冬はマイナス15℃にもなるというが、にんにくにとってはこの寒さが肝心、と佐野。春が訪れ日差しを浴びるとグンと育ち始め、6月下旬から7月始めに収穫する。
田子町の冬はマイナス15℃にもなるというが、にんにくにとってはこの寒さが肝心、と佐野。春が訪れ日差しを浴びるとグンと育ち始め、6月下旬から7月始めに収穫する。
田子町のにんにくは「福地ホワイト六片種」という寒冷系品種である。昭和30年代後半に青年部員が近隣の旧福地村から種を買い付け栽培を始めた。身の締まった6つの分球からなる真っ白な球根、それが特産品となった。
ここは山間地で稲作は少なく、もともと畑作の雑穀地帯だった。ほかには薪炭業と出稼ぎぐらい――。現在は津軽地方のりんごも消費減と価格低下で苦境にあるが、「昔は津軽の女の人たちと話すと、生活費が一ケタ違うのでは、と思ったほど」と佐野は、県南部のここ田子町でのかつての暮らしの実感を話す。
今、にんにくは町の経済を支えその生産量は昭和60年代には、文字どおり日本一となった。
◆農業者として複合経営をめざす
佐野房は、昭和57年に38歳で全国でもっとも若い農協婦人部長となる。平成8年からは6年間県女性協会長を務め、この間、全国女性協の理事のほか、地元では農業委員も務めた。その後、JA田子町の営農経済担当の常勤理事、さらに平成21年のJA八戸との合併直前には専務にまで選任された。
こうした経歴から「リーダー」としての側面が強調されがちだが、改めて話を聞いて思うのは、原点はあくまで「農家」を背負ってきたということだ。
戦前から戦後の一時期まで、自作農で酪農も営んでいたほか、山林も持つなど「大きい農家だった」。それが佐野が小学校低学年のころに手放す事態に。その後の営農と生活をやりくりしたのは母。「拾って、片づけるのが女」という姿を見て育ち、長女だったことから家業の手伝い。
婦人部役員の母に連れられて部員になったのは15歳のときだ。「部会費が年30円だったころから知っているんですよ」。だから、若妻部会の部会長を経て、38歳で全国最年少の農協婦人部長になったといっても、入会からすでに23年ものキャリアがあった、ということになる。
婦人部では野菜栽培の講習などを母と一緒に受けた。30aの畑を母から借りて農業を始め、昭和55年には70aを自分の所有地にして独立、「兼業農家」となる。なぜ、兼業農家かといえば、「連れ合いは、家具工場で働いていた」からである。
子どもも成長し長女、長男にも手伝ってもらいながら、トマト、きゅうり、にんにく、枝豆など多彩な作物をバランスよくつくる農業をめざす。すでに若妻部会の部会長に選ばれ婦人部活動にも力を入れており、昭和52年の「若妻の主張全国コンクール」では最優秀賞に輝く。
その主張こそ、自ら実践し始めていた米やリンゴばかりに頼らない「年間を通じて収入があるような複合経営」であった。「冬には育苗ハウスで原木しいたけ栽培もしてました」。
このころ佐野が思ったのは、「農業ほど男女差のない仕事はない」ということだという。確かに男が作った農産物だから高いということはない。良い農産物を作れば男女差なく同じ収入を得られる。
考えてみれば当たり前のことだが、自分で経営計画を立て生産、販売に取り組むなかで得たこの確信は、その後の農協の運動、事業との関わりのなかでも佐野の芯となるものだった。
◆部会設立委員長と選果場のパートタイマー
自らの農業経営と婦人部活動に関わるなか、生産部会の設立委員長も任される経験もした。
田子町農協には、昭和50年代始め、稲作、にんにく、リンゴ、キュウリを始め長いも、ブドウなど生産部会があったが、さらに地域では品目を増やそうとトマト栽培に佐野をはじめ20人ほどが取り組み始めた。
反収で100万円ほどになったことから部会を設立することになった。そのとき農協の小笠原参事から「トマトは若い農家が多い。お前が職員と一緒になって設立準備をしろ」と言われる。背景には農協の方針もあった。稲作やリンゴなどは農家の親世代が中心で部会運営もその世代が担っていた。一方、キュウリやトマトなどの品目は若い世代が多い。農協としても若い夫婦を中心に新しい作物振興をし、同時に彼らに収入が入るような仕組みを考えていた。
部会設立準備のために、農協に顔を出し、小笠原参事を始め職員と話し合いを重ねた。
「あのおっかない参事と対等に話をする若いお母さんは強いおなごだ、と職員は思っていたと後で聞きました。本人は緊張してたんですがね」と今は笑う。
「ただ、農協というものがどんな人たちの集まりでどういう組織なのか。たとえば参事という人はどんな人なのかを知る機会もありましたから、対等に話もできたんでしょうね」。
その機会とはリンゴの選果場でのパート仕事である。
30代のころ、佐野は冬の間だけリンゴの選果場で働いた。そこにはリンゴを出荷する組合員はもちろん組合長、参事、そして職員もやってくる。ときに彼らも現場の作業員と一緒に作業をすることがあった。そこで出会ったのがベテランの女性の主任職員。選果作業について佐野らパートにてきぱきと仕事を指示するだけでなく、設立以来の農協の歴史や、個々の農家組合員の考え方なども聞かされたという。役職員に至っては、事務所で仕事をしているだけではない姿も目の当たりにした。
「この選果場で農協のあり方を学んだような気がします」。
パートは37歳まで8シーズン続けた。そして、その翌年、婦人部長に選任されたのであった。
(後編に続く)