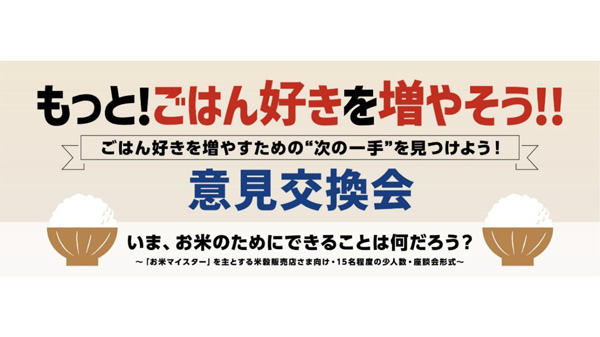【新連載・スマート農業の風(1)】費用対効果考え 効率経営を2024年2月19日
スマート農業という言葉を聞く機会が増えてきた。ドローンを使った農薬散布、ロボットトラクタといわれる無搭乗自動運転、気象・環境センサーを利用したほ場や施設の無人管理など、労力軽減を目指したいろいろなスマート農業がある。

実践から管理まで
確かに、ドローンを導入すれば動力噴霧器を担いでほ場に入らずとも農薬散布が可能になる。また、ロボットトラクターを使用すれば作業に不慣れな人も耕うん作業や畝たてなど今までベテランといわれていた人と同等の仕事ができる。加えて、気象・環境センサーがあればほ場や施設の状態をスマートフォンで確認でき、見回り数を削減し、ほかの仕事に回すことができる。ただそこには、コスト増という問題が付いてくる。
経営者は、導入による費用対効果を考慮して、自分の農業経営にあったスマート農業が何かを考える必要がある。
スマート農業というと、先のドローンやロボットトラクタなどの最先端技術が思い出されるが、日々の記録をメモ書きから電子媒体に変えるのも、立派なスマート農業だ。若い農業経営者に人気のほ場管理アプリは、スマートフォンに必要事項を入力することで、除草や農薬散布など日々の管理内容を記録することができる。また、オプション料金を払えば、出荷管理、伝票管理までおこなうことが可能だ。
別の話とはなるが、アンテナの高い農業者は、ポッドキャスト、YouTube、Facebook、Instagramを活用し、自らの農業のアピールをおこなっている。その先に販路拡大という目論見はあるのだが、『農業』という、知っているようで知らない職業を一般に知らしめる効果がある。さらに、同業者の注目を浴び、同じ悩みを共有するコミュニティーが構成される。いままでの近所の農家友達という狭いコミュニティーから、日本全国の様々な農業者とつながる広いコミュニティーに移行している。
"幽霊"ほ場の状況共有
農業経営の悩みは様々である。ある農業経営体は、管理するほ場300枚を毎年大きな白地図を広げ、色鉛筆を駆使しながら作付け計画を作成する、作業の面倒くささを解消したいと悩む。また、管理する組合員の高齢化に伴うほ場の承継にも悩んでいる。
親元就農した若い農業者は、全ほ場の把握に悩む。親はいまままでのルーチンで作業し、口頭で指示を与える。指示を受けた若い農業者は、親のルーチンもわからず、ほ場の場所もすぐに覚えられず悩む。昔から「俺の背中を見て仕事を覚えろ」とはよく言うことだが、集約され経営面積の広がった現在のほ場数では、見て覚えられるものではない。子供はほ場が解らず、「親しか知らないほ場がある」の状態になってしまう。
そもそもほ場を系統立てて、管理をしなければ、収支が判明するわけもなく、ほ場のポテンシャルをはかることもできない。
まず必要なのは、記録をすることだ。カレンダーに書いたメモではなく、ほ場を把握し、ほ場の面積、栽培品目、栽培品種、作業日を記録した情報を残すことで、親しか知らないほ場は消えるはずだ。口頭による指示だけでなく、ほ場ごとの作業記録を確認し、毎年同じ時期に何をおこなっていたかを把握することで、営農計画書や基本台帳への転記も容易となる。このようなやり方ではハードルが高いと感じる農業者は、まずは田植え日と稲刈り日だけで記入するなど、出来るところから始めることも重要だ。
少し先進的な農家は、ノートに表を作り、ほ場ごとの栽培記録・農薬散布日・散布農薬の種類などを記入している。ノートに代わり、パソコンを駆使すれば、デジタルデータで記録することができる。
ただ、ここで悩んでしまうのが、表に書き込まれたほ場がどこか解らないという問題だ。経験豊富な生産者は、テンジンシタ(天神下)やハシムコウ(橋向)など、固有の名前でほ場を特定できるが、新規参入者や営農団体に就農したばかりの従業員には、チンプンカンプンの呪文にしか聞こえない。ほ場の場所を明確にするには、ほ場の場所を明記し、地図に紐づけた管理表が必要だ。
少し前までは、白地図に色鉛筆を使って毎年印をつけていたが、今ではパソコン上の地図にマークを入れ、マークの場所と管理表を紐づけデータ管理ができるようになった。使用料も格安で、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスでも閲覧することができる。ほ場の栽培情報と地図上の自分の場所が確認できれば、ほ場への案内や現地確認が不要となり、自分の力で「親しか知らないほ場」をなくすことができるのだ。
情報印刷で世代選ばず
アプリケーションを選べば、高品位の地図情報とともに印刷できるものもある。適度なアナログテイストは、スマートフォンやタブレットを使えない世代にも優しく、印刷した地図を提供することでデジタルデータの共有ができる。
このようにスマート農業は、ドローンやロボットトラクタなどのハードだけでなく、農業管理アプリケーションなど、身近に使えるソフトウェアなどの技術も含まれる。「自分の経営に何が必要か」は、JAやスマート農業を先に進めている農業者に相談することが望ましいが、自分で試し、自分が新たなスマート農業の先駆者になることも、これからの農業経営には必要なことだと言える。
重要な記事
最新の記事
-
 【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日
【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日 -
 和牛農家と海外バイヤーをつなぐオンラインプラットフォーム「WAGYU MARKET」提供開始2026年1月30日
和牛農家と海外バイヤーをつなぐオンラインプラットフォーム「WAGYU MARKET」提供開始2026年1月30日 -
 酪農業の地域特有の課題解決へ 酪農家との情報交換会「第5回MDA MEETING」地域別開催 明治2026年1月30日
酪農業の地域特有の課題解決へ 酪農家との情報交換会「第5回MDA MEETING」地域別開催 明治2026年1月30日 -
 抹茶といちごの季節限定パフェ 関東・東北のフルーツピークスで販売 青木フルーツ2026年1月30日
抹茶といちごの季節限定パフェ 関東・東北のフルーツピークスで販売 青木フルーツ2026年1月30日 -
 東京生まれの納豆を食べてオリジナルカードをゲット「ネバコレカード トーキョー」開始2026年1月30日
東京生まれの納豆を食べてオリジナルカードをゲット「ネバコレカード トーキョー」開始2026年1月30日 -
 生産者のこだわり紹介「姫路いちごフェア」2月4日に開催 兵庫県姫路市2026年1月30日
生産者のこだわり紹介「姫路いちごフェア」2月4日に開催 兵庫県姫路市2026年1月30日 -
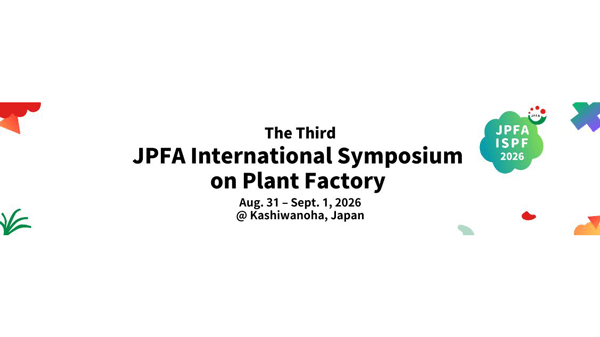 持続可能な未来へ植物工場の可能性「第3回JPFA植物工場国際シンポジウム」開催2026年1月30日
持続可能な未来へ植物工場の可能性「第3回JPFA植物工場国際シンポジウム」開催2026年1月30日 -
 ドラクエとコラボ「亀田の柿の種」2月3日から期間限定で発売 亀田製菓2026年1月30日
ドラクエとコラボ「亀田の柿の種」2月3日から期間限定で発売 亀田製菓2026年1月30日 -
 AgVenture Lab主催「2.6オープンイノベーションマッチングイベント」に登壇 Carbon EX2026年1月30日
AgVenture Lab主催「2.6オープンイノベーションマッチングイベント」に登壇 Carbon EX2026年1月30日 -
 【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日
【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日 -
 【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日
【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日 -
 米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日
米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日 -
 2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日
2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日 -
 続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日
続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日 -
 第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日
第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日 -
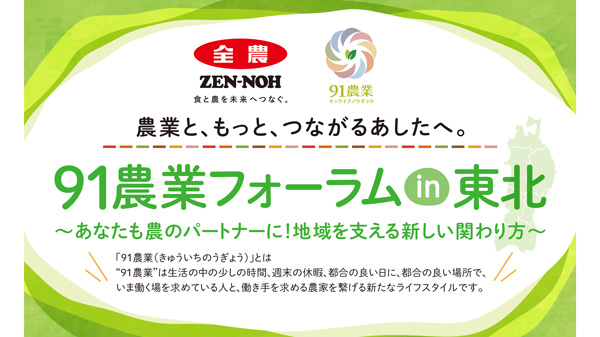 中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日
中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日 -
 希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日
希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日 -
 神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日
神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日 -
 フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日
フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日 -
 「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日
「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日