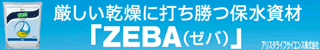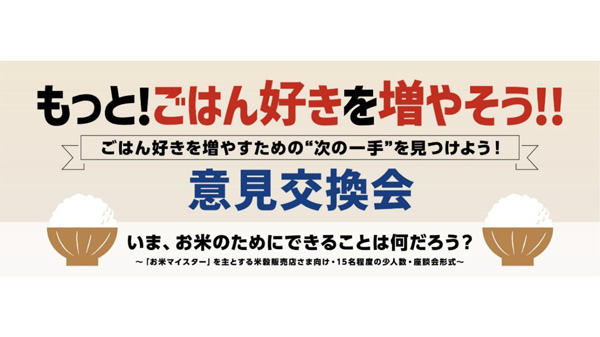農薬:サステナ防除のすすめ2025
【サステナ防除のすすめ2025】施設イチゴ 低温好み病害多く2025年9月22日
冬場に向けた、イチゴ栽培では、うどんこ病や灰色かび病など比較的低温を好む病害の発生が多くなるなど、暑い時期とは異なる防除対策が必要だ。冬場のイチゴ施設栽培に絞って、その防除対策を紹介する。

予防散布で先手
発生状況に応じた対策を
冬場の施設イチゴにおいて、病気では、比較的低温で発生が多くなるうどんこ病や灰色かび病など、害虫では、一年中発生するイチゴネアブラムシや2月下旬より発生が増加するナミハダニやカンザワハダニが要防除対象だ。いずれも、果実の生育や品質に大きく影響するので、発生状況に応じて、確実に防除したいものである。
以下、主要病害虫ごとに防除対策を紹介するので参考にしていただきたい。
なお、登録農薬を紹介しているが、これらは選択の参考になる情報に絞って記載しているため、実際に使用する際には、使用する農薬のラベルをよく確認し、正しく使用してほしい。また、本文中の薬剤の紹介は、作用機構(あるいは成分系)で紹介している。これは耐性菌や抵抗性対策の一環でローテーションを意識しやすくするための処置であるので、対応する薬剤名については面倒ではあるが一覧表で確かめて頂きたい。
また、開花後に農薬を使用する際には、ミツバチの安全使用基準をよく確認し、影響のないよう十分に注意してほしい。
果実に発生して商品価値を落とす うどんこ病
うどんこ病は、ポドスフェレアという糸状菌(子のう菌類)が引き起こす病害で、果実、葉、茎などイチゴのあちこちの部位に白い粉状のカビを発生させる。白い病斑の上にはおびただしい数の分生胞子を作り、風に乗ったり作業者の服に付着したりして感染域を拡大させる。病斑が果実に発生した場合は、商品価値がなくなり、被害が大きい。
周年発生し、多湿でも乾燥でも発生するので、冬場のハウスでは発生が多くなる。空気伝染し、一度発生すると多くの場所に拡散するので、発生前に重点をおき、予防散布を心がけたい。
薬剤は、SDHI殺菌剤やDMI殺菌剤、QoI殺菌剤、その他系列のキノキサリン系やAP殺菌剤などの効果が高い。しかし、DMI殺菌剤やQoI殺菌剤では強い耐性菌が発生している地域が多いので、殺菌剤の使用は、異なる系統の薬剤をローテーションで使用し、使用する薬剤も地域の指導機関の指示に従って選ぶようにしてほしい。
また、ハダニ類防除で使用される物理的防除剤(還元澱粉糖化物、オレイン酸ナトリウム、グリセリンクエン酸脂肪酸エステル、調合油)は、いずれもうどんこ病にも活性があり、しかも使用回数制限が無いので、適宜ローテーションの1剤に加えるか他の殺菌剤と混用して使用すると効率的な防除が可能となる。
その他、ケイ酸カリ肥料を施用すると、植物体の細胞が強固になり、うどんこ病の侵入阻止効果が高くなる事例が紹介されているので試してみるとよい。
胞子が伝染源 灰色かび病
灰色かび病は、ボトリチスという糸状菌(不完全菌類)が起こす病害で、葉や花弁、果こうに発生するが、どちらかというと花弁や果実などの柔らかい組織に侵入することが多いため、被害が大きくなる。下葉の枯死した部分や花弁などでいったん増殖し、これが伝染源となって、胞子を飛散させまん延していく。病斑の表面にはビロード状のこんもりとした見た目の分生胞子を大量に発生させ、風や作業者の衣服等を介して感染を拡大していく。
低温多湿条件で多く発生するので、棚間を広くして通風をよくしたり、防湿ファンを回してハウス内の防湿対策を徹底すると、かなり発病を抑えられる。
薬剤防除は、発病初期に重点をおいて、系統の異なる薬剤を果実を中心に丁寧にローテーション散布する。この病害も多くの薬剤に耐性菌が発生しているので、指導機関の情報に従って薬剤を選んでほしい。SDHI殺菌剤やジカルボキシイミド系、AP殺菌剤、PP殺菌剤が多く使用されている。
バチルス属細菌が灰色かび病に効果のあることから、同菌を成分とする生物農薬も登場している。しかし、効果を安定させるためには、繰り返しの散布が必要なため、近年は、生物農薬の効果を補完し、他の病害にも効果を示すようバチルス菌に銅剤を加えた薬剤も登場している。
ハダニ類
ハウス栽培のイチゴでは、休眠性のあるナミハダニ(黄緑型、赤色型)とカンザワハダニが発生する。ナミハダニは体長が0・35~0・4mm、楕円形で体色は黄緑や赤色をしており、年間7~10回発生し、雌成虫が支柱の継ぎ目や植物残さなどで越冬する。カンザワハダニは体長が0・5mm、赤色楕円形をしており、年間10~11回発生し、雌成虫が植物残さや支柱の結び縄の下などで越冬する。
施設栽培での発生は、2月下旬から多くなるので、発生時期の前の予防散布を実施するか、発生の少ない発生初期に確実に防除を行う。
施設内の植物残さはできるだけ取り除くなど越冬場所を極力減らすとともに、発生初期にハダニ防除剤を使用する。ハダニ類は抵抗性の発達リスクが非常に高いので、化学農薬は同系統の薬剤の連続使用は避け、異なる薬剤系統のハダニ剤でローテーション防除を行う。できるだけ、同じ系統の薬剤は1作期1回の使用に止めるほうが望ましい。
また、地域によっては抵抗性の発達により使用できない薬剤もあるので、あらかじめ地域の指導機関に確認の上、使用する薬剤を選定するようにしてほしい。
なお、抵抗性ハダニの発達防止のため、物理的防除剤(マシン油、還元澱粉糖化物、グリセリンクエン酸脂肪酸エステルなど)を適宜ローテーションに加えるか他剤との混用で使用するとより効率の良い防除が可能となる。
早めの防除で収量確保 イチゴネアブラムシ
この害虫は地際の茎や根冠部に集団で一年中寄生して青緑色をしている。イチゴの生育が悪くなり、収量や品質を低下させる被害が起こるので、発生を確認したら早めの防除が必要だ。
ネオニコチノイド系の粒剤を定植時に処理し、その上で、ピレスロイド系やピリジンアゾメチン誘導体、フロニカミド剤などの散布剤を必要に応じて散布するとよい。
ただし、散布剤をミツバチを導入する時期に使用する場合は、安全日数を十分に考慮して使用してほしい。
重要な記事
最新の記事
-
 【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日
【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日 -
 【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日
【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日 -
 米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日
米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日 -
 2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日
2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日 -
 続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日
続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日 -
 第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日
第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日 -
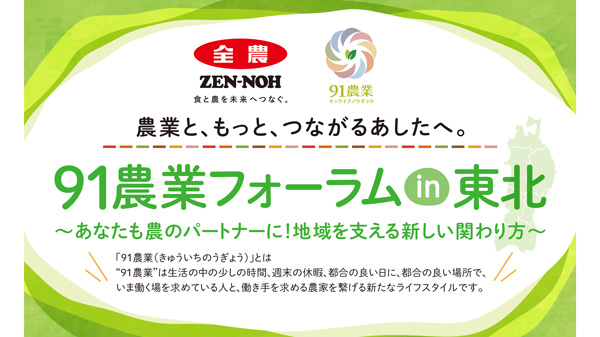 中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日
中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日 -
 希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日
希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日 -
 神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日
神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日 -
 フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日
フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日 -
 「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日
「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日 -
 東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日
東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日 -
 鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日
鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -
 鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日
鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -
 調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日
調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日 -
 佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日
佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日 -
 国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日
国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日 -
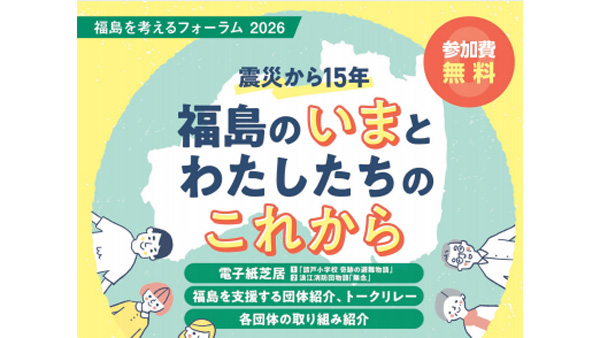 原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日
原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日 -
 牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日
牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日 -
 ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日
ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日