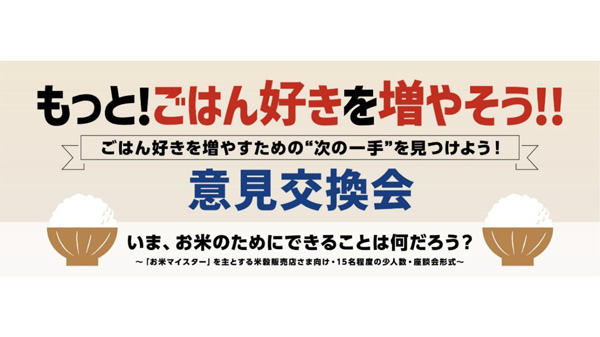JAの活動:女性協70周年記念 花ひらく暮らしと地域
【花ひらく暮らしと地域―JA女性 四分の三世紀(11)】エンパワーメント<上>「自給・自立」の先頭に2022年1月22日
「国破れて山河あり」と言われた飢餓の夏から、コロナ禍を乗り越えて新しい時代に挑むこの新春まで76年。その足どりを、「農といのちと暮らしと協同」の視点から、文芸アナリストの大金義昭氏がたどる。
■手づくりの価値再発見
映画「ローマの休日」(昭和28〈1953〉年米国製作)に、オードリー・ヘップバーン扮する「王女」がスペイン広場でジェラートを食べるシーンがある。公式訪問中の宿舎から抜け出して髪を切った「王女」の解放感溢れる姿が爽やかだった。
ローマ観光の名所の一つであるこのスペイン広場に、ファストフード店のマクドナルドが進出。これに反対して、イタリア北部の小さな町ブラから始まったのがスローフード運動だ。昭和61(1986)年のことである。
運動の目的は、ファストフードからイタリアの食文化を守るために①伝統的な食材や料理、質のよい食品やワインを守り②消費者に「食育」を勧め③質のよい素材を提供する小規模生産者を守る、というものだった。現在は160を超える国々で「Good(おいしい)・Clean(きれい)・Fair(ただしい)」をスローガンに「健康的で環境に負荷を与えず、生産者が正当に評価される」食文化やフードシステムを目ざす草の根の運動として世界に広がっている。
平成16(2004)年には、「スローフードジャパン」(「スローフード日本」の前身)も発足した。ちなみに、イタリアの近年の食料自給率(カロリーベース)は60%、日本は37%である。
実は、イタリアでスローフード運動が始まる16年も前の昭和45(1970)年から、「農産物自給運動」に着手していた農協があった。秋田県仁賀保町農協だ。
背景にあったのは、「米+兼業」に特化した農家が野菜や卵などをスーパーから購入するようになっていたこと。さらには化学肥料や農薬などを多用して生産した農産物の安全性を問題視する声が社会的に高まっていたこと。そして何より衝撃だったのが、有史以来の米の減反政策(生産調整)が打ち出されたことだった。加えて昭和48(1973)年秋には、第1次オイルショックが勃発している。
同年に仁賀保町農協組合長に就任した佐藤喜作に、こんな一文がある。(『手づくりの幸せ~むらを変える自給運動』昭和57〈1982〉年12月・家の光協会)
わたしは組合長に就任すると、その年、農協の新しい大方針として、「仁賀保町農産物自給運動」というのを打ち出しました。
この運動は、それまで進めてきた農家だけの自給運動から大きくひろげ、町人一万二〇〇〇人の食べる農産物を、わたしたち仁賀保の農民の生産でまかなっていこうというものです。そうすれば、消費者は安全なものを安心して食べられ、農民はほどほどの収入を得られます。また、消費と生産を通じて生まれるはずの、同じ土地で生きている者同士という連帯感。それを力に仁賀保の農業を再生させ、守っていきたいと願ったのです。
佐藤の願いを受けとめたのが、生活指導員の渡辺広子や農協婦人部のメンバーだった。
「ニワトリ10羽・マメ植え・自給菜園利用」などを謳(うた)った「20万円自給運動」は、やがて物価上昇を反映させて米を含めた40万円から50万円に目標額が引き上げられ、「青空市場」を開設して野菜や加工・保存食品などの販売にも手を広げていく。
本シリーズの一覧は以下のリンクからご覧いただけます。
【女性協70周年記念 花ひらく暮らしと地域】
この運動から、昭和54(1979)年には農協有機農業研究会も立ち上げられた。
■百花繚乱の広がり
提唱者の佐藤が火をつけた「農産物自給運動」は、昭和50~60年代に全国に広がった。
その第一線を担ったのが、農協婦人部だ。なぜ津々浦々に広がったのか。
自然学の泰斗・今西錦司に、次のような言葉がある。
形態的・機能的ないしは体制的・行動的に同じようにつくられた同種の個体は、変わらねばならないときがきたら、また同じように変わるのでなければならない。(中略)
種とは、環境に適応するため、たえずみずからを作りかえることによって、新しい種にかわってゆく。これが進化であるとすれば、進化とははじめから、種レベルでおこる現象である。(中略)
種と個体とははじめから二にして一のものである。(中略)したがって、種が変わるときがくれば、個体もまた同時に変わらなければならないし、個体が変わるときがくれば、同時に種もまた変わらなければならない。(『進化とはなにか』昭和51〈1976〉年6月・講談社学術文庫)
「種に属する個体のどれもこれもが」「みな同じ方向にむかって変わる」という意味で、組合長の佐藤を中心とする仁賀保町農協の婦人部の取り組みは、優れた先駆をなした。後年に、本紙を刊行する農協協会の会長や日本有機農業研究会理事長などを歴任した「社会運動家」としての佐藤の面目躍如といったところだ。
バラエティーに富んだ運動は、百花繚乱(りょうらん)の様相を呈した。その盛況ぶりは『農産物自給運動~21世紀を耕す自立へのあゆみ』(荷見武敬・鈴木博・根岸久子編、昭和61〈1986〉年8月・御茶の水書房)に詳しい。この書が世に出た同年に、北イタリアを発祥地とするスローフード運動が始まっている。同書には、佐藤と奮闘を共にした渡辺広子の手記もある。
土を離れた文化はない。そして人間も土から離れて生きることはできない。土の上にくらし、土に帰るくらし、そのくらしそのものが文化である。
自給運動は、決して改めて物を作り出す新しい運動ではない。不自然で非常識な今のくらしに気づいてもらい、目を覚ましてもらう、目覚し運動でもあるのです。(中略)
それは生産者のみの運動ではなく、消費者も一体となった人間すべての運動でもあるのです。食べ物のみでなく、生き方までも他人の手にゆだねている今の日本人すべてにもっと自主・自立の心を。それは自給の心をもってもらうことであり、狂っている世の中を当り前の世の中にとりもどす運動です。
『論語』に「温故知新」という言葉がある。「自給」にせよ「有機」にせよ、初期には「時代錯誤」と酷評され、一見、復古主義的な色彩を帯びた運動が、歪(ゆが)んだ社会を映し出す鏡の役割を果たした。今やJAの十八番(おはこ)とも言えるファーマーズマーケットや地産地消(国消国産)・6次産業化などの取り組みも、この運動が母体になっている。副題にある「エンパワーメント」とは、「力をつけた女性が輝きを増す」といった意味合いだ。
◇
山茶花の紅い花が燃えるようだ。
(文芸アナリスト・大金義昭)

重要な記事
最新の記事
-
 【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日
【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日 -
 【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日
【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日 -
 米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日
米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日 -
 2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日
2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日 -
 続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日
続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日 -
 第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日
第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日 -
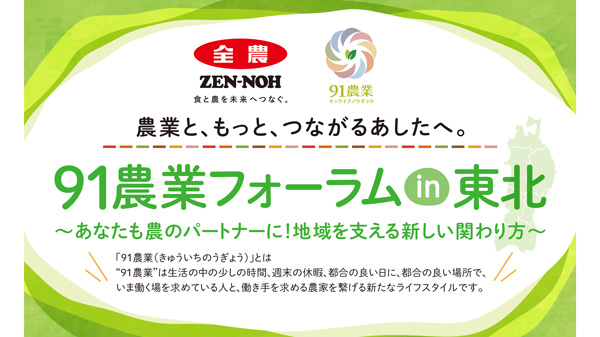 中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日
中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日 -
 希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日
希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日 -
 神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日
神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日 -
 フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日
フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日 -
 「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日
「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日 -
 東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日
東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日 -
 鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日
鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -
 鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日
鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -
 調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日
調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日 -
 佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日
佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日 -
 国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日
国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日 -
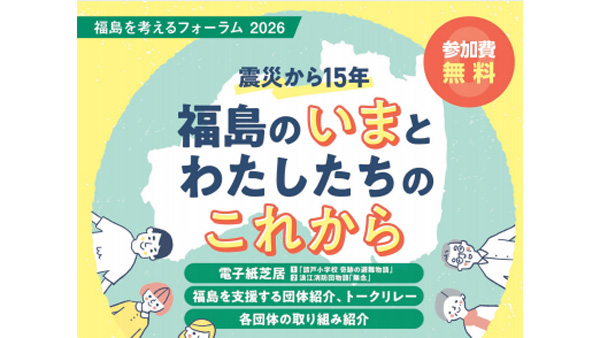 原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日
原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日 -
 牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日
牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日 -
 ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日
ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日