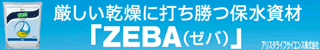農薬:サステナ防除のすすめ2025
【サステナ防除のすすめ2025】水稲の本田防除(1)育苗箱処理剤が柱2025年6月17日
令和の米騒動の騒ぎの中でも本年も水稲栽培が本格化し、水稲生育期防除、いわゆる本田防除が必要な時期がやってきた。水稲栽培で少しでも収益を増やそうとすれば、1等米を出来るだけ多く収穫することが必要で、それを実現するには、斑点米カメムシなど穂を侵す病害虫の防除が必須な作業だ。
サステナ防除的には、気候変動による病害虫の発生状況の変化に対応した効率的かつ継続性を持った防除を組み立てることが重要だと考えており、それに沿ったおすすめできる防除の考え方を整理してみようと思う。
育苗箱処理剤が柱

1.近年の病害虫発生状況とその変化
近年の傾向として毎年天候の変動が大きく、その影響を受けて、水稲の本田期の防除でも「例年どおり」が通じないことが多くなっている。また、作付けされる品種も、各県が開発や導入した推奨品種や多収の飼料用米品種など出穂時期が異なる品種が複数作付けされるようになり、出穂・開花時期が長期間続くようになるなど作物の生育状況も変化している。これで何が起こるかというと、イネカメムシのように主として出穂前後に発生が多くなる害虫が長期間水田にとどまることになり、不ねんや品質不良の被害を長期に受ける地域が多くみられるようになった。
このように、気候の変化と栽培環境の変化が、発生する病害虫雑草の発生消長や種類まで変化させており、その変化に対応するために目を光らせておかなければならない期間が長くなってしまっている。
2.病害虫雑草の発生状況の変化への効率的な対応とは
そんな状況で病害虫の発生に常に目を光らせるというのは、かなりの労力がかかる作業であり、経営規模が大きいとさらに負担が大きくなってしまう。
近年では、農薬の使用量低減のためにドローン等によるスポット散布が推奨されているが、残念ながら、スポット散布では十分に防除効果を得られない事態が想定される。なぜなら、病害虫の発生に気づいた時には、既に広範囲に病害が潜伏していたり、害虫の増殖が進んでいたりしていることが多いからだ。
なぜスポット散布を繰り返すことはかえって不効率で難しいかというと、例えば病害であれば、病斑が見つかった時点でその周りには既に潜伏している病原菌が存在しており、病斑だけを頼りに農薬散布しても病害を一網打尽にはできない。また、潜伏している病害虫に効果を発揮させるためには、使用する農薬には浸透移行性があって、治療効果のあるものを選ばなければならないなどといった制約が出てくる。
AI活用などの技術が大きく進化して、どんな微細な胞子や害虫、雑草であっても、全自動で判別できて、それら対象病害虫に対して害虫の加害前や病害の発病前に全自動でスポット散布できるのなら話は別だが、残念ながら、まだ発展途上の技術である。
そうすると、何時どこから病害虫がやってきても迎え撃てるようにするには、予防的に全面散布するしかなく、これが結果的には最も効率の良い防除法になる。
特に今の時期は、本田で発生する病害虫の発生密度を減らすためにも、初期防除を徹底しておくためにも重要な時期である。
3.予防散布が効果的な理由とは
予防散布が効果的な理由の一つが、防除適期を逃してしまうリスクを減らすことだ。前段で紹介したように、病害虫の発生時期や増殖速度が早まると、従来どおりの防除タイミングでは、防除適期を逃してしまうリスクが高くなる。例えば、病害の場合、感染したかどうかは、病徴(病斑)が見つかった時に確認されるわけだが、病害には、感染してから発病するまで症状が出ない期間(潜伏期間)があるので、目の前の病斑以外にも、発病はしていないがすでに感染している稲株がある可能性が高い。つまり、病斑が見つかった時に見つかった部分だけ防除しても、実は、隠れた病害を取りこぼしてしまうこともあり得るということだ。
それでは、潜伏していた病害が病斑として出現した時、再び農薬を散布しなければならず、散布回数が増えてしまう。農薬の使用回数は、ほ場に対してカウントされるので、こうした防除を行っていれば、多発時には、農薬の使用回数があっという間に回数上限に達してしまうだろう。
また、稲の表面を保護する、いわゆる保護剤を使えば新たな感染を防ぐことはできるが、既に潜伏している病害には効果がなく、取りこぼした病斑から胞子の飛散を許してしまう。このため、保護剤での防除は、効果の持続期間が切れる前に繰り返し散布する必要があり、また、新葉が出ればそれに対しても散布する必要がある。それをきっちり実行して病害虫がやってくる前の備えを万全にすることができれば、防除適期を逃すことなく確実な防除が可能になる。
4.本田期の予防散布は育苗期処理などとの体系がベスト
1回の散布で長期に効果が持続し、しかも安定した防除効果を得る防除体系を組むためには、長期持続型の有効成分を含む育苗箱処理剤が最も適していると思う。なぜなら、病害虫にまださらされていな育苗段階から稲体中に有効成分の必要濃度を維持できていれば、外敵への備えを済ますことができるので、重要な防除時期を逃すことがなく、安定した防除効果を発揮することができる。この長期持続型育苗箱処理剤を処理してあれば、本田での病害虫の発生が低く抑えられているので、仮に病害虫が発生したとしても、本田防除を少ない回数で仕上げることができるというメリットもある。
つまり、毎年発生する病害虫に対しては、長期に効果が持続する農薬をあらかじめ用法・用量を守って施用しておいた方がより効率的だといえる。もちろん、地域単位で全く発生しない病害虫を防除する必要はないが、発生の可能性がある場合は、できるだけ予防散布を中心に防除を組み立ててほしい。予防中心の防除体系としては、病害虫の発生状況に合わせて育苗箱処理1回+出穂期予防散布1回の計2回を必須防除とし、カメムシや穂枯れ性病害の発生状況に応じて出穂1週間~10日後にもう1度予防散布というところが理想である。
5.本田散布のみで防除する際も予防散布を基本にする
箱剤などを使用せず本田散布剤(空散含む)のみで防除する場合も防除適期(病害虫発生前)の予防散布が基本である。
もし、どうしても病害虫の発生後に散布せざるを得ない場合は、出来るだけ発生初期の病害虫の発生密度が少ないうちに、できるだけ早く散布することが重要だ。病害の場合は、発生量が少ない方が治療効果も出やすくなるし、害虫も小さな幼虫の内に防除できれば効果も高く、被害も少なくて済む。発生前に保険的に散布する予防散布は無駄な散布と判断される方もいるにはいるが、発生前に計画的に散布する方が、発生後の臨機防除よりも効果も安定するし、結果的に効率的な防除が可能になることを知っておいていただきたい。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(176)食料・農業・農村基本計画(18)国民一人一人の食料安全保障・持続的な食料システム2026年1月17日
シンとんぼ(176)食料・農業・農村基本計画(18)国民一人一人の食料安全保障・持続的な食料システム2026年1月17日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(93)キノキサリン(求電子系)【防除学習帖】第332回2026年1月17日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(93)キノキサリン(求電子系)【防除学習帖】第332回2026年1月17日 -
 農薬の正しい使い方(66)植物色素の生成阻害タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第332回2026年1月17日
農薬の正しい使い方(66)植物色素の生成阻害タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第332回2026年1月17日 -
 【地域を診る】能登半島地震から2年 復興法人制度活用の提案 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年1月16日
【地域を診る】能登半島地震から2年 復興法人制度活用の提案 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年1月16日 -
 スーパーの米価、2週ぶりに低下 前週から149円下がり5kg4267円に 米からパン、めん類にシフトか2026年1月16日
スーパーの米価、2週ぶりに低下 前週から149円下がり5kg4267円に 米からパン、めん類にシフトか2026年1月16日 -
 「2026年 ISEKI Global Awards」開催 井関農機2026年1月16日
「2026年 ISEKI Global Awards」開催 井関農機2026年1月16日 -
 近づく限界、米価に暴落懸念 「2014年の再来」防げるか2026年1月16日
近づく限界、米価に暴落懸念 「2014年の再来」防げるか2026年1月16日 -
 (469)なぜタイのエビは主役ではなくなったのか?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月16日
(469)なぜタイのエビは主役ではなくなったのか?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月16日 -
 岩手県の直営飲食店舗で「いわての牛乳ありがとうフェア」20日から開催 JA全農2026年1月16日
岩手県の直営飲食店舗で「いわての牛乳ありがとうフェア」20日から開催 JA全農2026年1月16日 -
 縁起が良い赤い食べ物「冬土用未(ひつじ)の日フェア」17日から開催 JA全農2026年1月16日
縁起が良い赤い食べ物「冬土用未(ひつじ)の日フェア」17日から開催 JA全農2026年1月16日 -
 バッテリー診断・価値向上によるEVコンバージョントラック普及へ 共同実証開始 JA三井リースグループ2026年1月16日
バッテリー診断・価値向上によるEVコンバージョントラック普及へ 共同実証開始 JA三井リースグループ2026年1月16日 -
 日本の蚕糸 消滅していいの? 3月にフォーラム開催 大日本蚕糸会2026年1月16日
日本の蚕糸 消滅していいの? 3月にフォーラム開催 大日本蚕糸会2026年1月16日 -
 【浅野純次・読書の楽しみ】第117回2026年1月16日
【浅野純次・読書の楽しみ】第117回2026年1月16日 -
 「花・緑ガイドボランティア」募集200人に3493人が応募 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月16日
「花・緑ガイドボランティア」募集200人に3493人が応募 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月16日 -
 トラクタ「JAPANシリーズ」BJ65・74・90・105を新発売 無段変速ミッション搭載で2026年6月投入 井関農機2026年1月16日
トラクタ「JAPANシリーズ」BJ65・74・90・105を新発売 無段変速ミッション搭載で2026年6月投入 井関農機2026年1月16日 -
 北海道の暮らしと仕事セミナー「一次産業(農業・林業・水産)のお仕事編」開催2026年1月16日
北海道の暮らしと仕事セミナー「一次産業(農業・林業・水産)のお仕事編」開催2026年1月16日 -
 防災力アップ体験イベント「もしもFES大阪2026」3月に開催 こくみん共済 coop2026年1月16日
防災力アップ体験イベント「もしもFES大阪2026」3月に開催 こくみん共済 coop2026年1月16日 -
 推しいちごに投票「天下分け目のいちご戦国時代2026」開催 食べチョク2026年1月16日
推しいちごに投票「天下分け目のいちご戦国時代2026」開催 食べチョク2026年1月16日 -
 フルーツ王国ふくしま「ゆうやけベリー・県産いちご」フェア開催 福島県2026年1月16日
フルーツ王国ふくしま「ゆうやけベリー・県産いちご」フェア開催 福島県2026年1月16日 -
 「いちごさんどう2026」開幕 相武紗季をゲストに迎え発表会 佐賀県2026年1月16日
「いちごさんどう2026」開幕 相武紗季をゲストに迎え発表会 佐賀県2026年1月16日