JAの活動:農協があってよかった-命と暮らしと地域を守るために
【現地レポート・JA士幌町(北海道)】大手資本の搾取排し「農村ユートピア」創造(2)<JA士幌町の挑戦>2018年1月10日
・農民自ら加工・流通作物・乳製品で高付加価値
・確固たる“使命”で
・米国酪農にショック
◆確固たる"使命"で
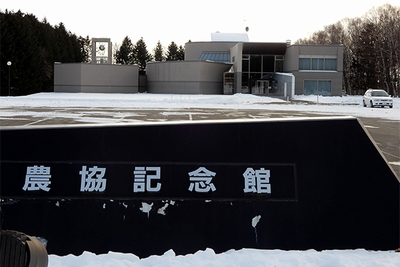 JA士幌町のスローガンである「農村ユートピアの創造を目指して」の取り組みは昭和10年代に始まる。後にJA士幌町の組合長、ホクレン会長、そして全農の会長を務めた太田寛一氏や太田氏を支えて組合長を引き継いだ安村志朗氏をはじめとする青年たちで、彼らは「農畜産物の原料生産をするだけではなく、加工から流通・販売を農民自身が担い、付加価値を得ることで他産業と同じ所得を得られるようにしたい。それを実現するのが組合の使命である」と考えた。この青年たちが、戦後の新生農協のリーダーとなり、今日のJA士幌町の礎(いしづえ)をつくった。
JA士幌町のスローガンである「農村ユートピアの創造を目指して」の取り組みは昭和10年代に始まる。後にJA士幌町の組合長、ホクレン会長、そして全農の会長を務めた太田寛一氏や太田氏を支えて組合長を引き継いだ安村志朗氏をはじめとする青年たちで、彼らは「農畜産物の原料生産をするだけではなく、加工から流通・販売を農民自身が担い、付加価値を得ることで他産業と同じ所得を得られるようにしたい。それを実現するのが組合の使命である」と考えた。この青年たちが、戦後の新生農協のリーダーとなり、今日のJA士幌町の礎(いしづえ)をつくった。
付加価値を付ける取り組みの第一歩は、昭和21年のでん粉工場の買収から始まった。まだ戦時体制の農業会の時代である。JAが自ら加工事業を行うことで分かったことがある。それまで歩留まり率が8分の1といわれていたでん粉が、実際には4分の1だということだった。その分、生産者が不利な取引を余儀なくされていた。農協の加工事業によって原価が公になったことで、村内に多くあったでん粉工場の収益性が低下し、やがてこれらの工場が農協の傘下に入っていくことになる。 ここから、「加工工場を自営することによって原価を把握し、メーカーとの価格交渉に反映させるという手法と、それを確立するため、企業に負けない厳格な経営管理を行うという運営方針が次第に明確になった。まさに"太田イズム"の原点であった」(『士幌農協70年の検証』)のである。つまり農民自らが農産加工によって付加価値を得るという農村工業化路線を展開していくことになる。これが、その後の太田-安村体制による「農村ユートピア創造」への出発点となった。
ここから、「加工工場を自営することによって原価を把握し、メーカーとの価格交渉に反映させるという手法と、それを確立するため、企業に負けない厳格な経営管理を行うという運営方針が次第に明確になった。まさに"太田イズム"の原点であった」(『士幌農協70年の検証』)のである。つまり農民自らが農産加工によって付加価値を得るという農村工業化路線を展開していくことになる。これが、その後の太田-安村体制による「農村ユートピア創造」への出発点となった。
(写真)美濃(岐阜県)から43戸が入植した士幌町発祥の碑
農業会から農業協同組合に移ってからもでん粉工場は順調で、原料バレイショの供給に合わせて規模を拡大し、昭和29年には士幌村すべてのでん粉工場を士幌農協の傘下に収めた。そして昭和30年には高能率の連続式合理化でん粉工場を建設し、バレイショ生産農家の経営安定に大きく貢献することになる。さらに48年には食品工場を建設し、ポテトチップス、コーン、コロッケなどの食品加工に取り組み、さらに販路を広げるため、関東食品開発研究所、関西食品工場開設など、大消費地に進出した。
こうした加工食品への取り組みの成果は、JAの事業実績に明確に現れている。同JAの販売高の推移をみると、昭和43年16億円だったものが、48年には44億円になった。この年は食品工場をつくり、加工食品の販売を始めた年である。その後、53年には109億円。平成に入って25年322億円、28年435億円と、右肩上がりの驚異的な伸びを示している。
◆米国酪農にショック
 こうしたJAの状況から、士幌町で搾乳牛約170頭を含む350頭を飼育する酪農家の鈴木洋一さん(75)は、「"農村ユートピア"は完成の域に入っているのではないか」と考えている。鈴木さんは、昭和40年、22歳で父親の酪農経営を引き継いだ。このころ、十勝地方で生乳の共販を行っていた8農協が、酪農民による乳製品工場建設の話が具体化しようとしていたころであり、これがその後、北海道協同乳業(株)、よつ葉乳業(株)に発展するのだが、この流れと鈴木さんの酪農人生が重なる。
こうしたJAの状況から、士幌町で搾乳牛約170頭を含む350頭を飼育する酪農家の鈴木洋一さん(75)は、「"農村ユートピア"は完成の域に入っているのではないか」と考えている。鈴木さんは、昭和40年、22歳で父親の酪農経営を引き継いだ。このころ、十勝地方で生乳の共販を行っていた8農協が、酪農民による乳製品工場建設の話が具体化しようとしていたころであり、これがその後、北海道協同乳業(株)、よつ葉乳業(株)に発展するのだが、この流れと鈴木さんの酪農人生が重なる。
(写真)士幌の酪農をリードした鈴木洋一さん
JA士幌町の農畜産物販売のなかで、牛乳は畜産物(主に個体販売)に次いで大きい。トップの畜産物が約239億円で、次いで牛乳87億円となっている。これを67戸の酪農家が支えている。牛乳がここまで大きくなるまでには、でん粉工場と同じような加工事業への取り組みがあった。それも「より広範囲に」である。
士幌村農協時代の昭和31年に北海道で最初の生乳共販を始めた。当時、加工原料乳生産者補給金制度(不足払い法)はあったが、実際に乳業メーカーとの交渉では、法で定める安定基準価格を下回ることが多く、地域・季節によって取引価格に格差があったことから、現場では集乳合戦の様相を呈し、「封筒乳価」の現金攻勢による酪農家の取り込みも珍しくなかった。
同農協はでん粉工場の運営で、加工段階において「いかに搾取されるか」を身に染みて経験しており、既存の乳業メーカーの反対は当然ながら、農水省や北海道、ホクレンなどからの積極的な支援も得られないなか、当時組合長だった太田寛一氏の呼びかけで、昭和42年十勝地方8農協による協同乳業(株)の設立にこぎ着けた。
そのころ鈴木さんは就農したばかり。42年には士幌町酪友会の初代会長になり、その後、士幌町の議員などを務め、酪農や地域農業の振興に貢献する。その鈴木さんを酪農に結びつけたのが太田寛一氏であった。
畑作中心の農家の後継者に生まれ、江別市野幌にある酪農学園機農高校を卒業して就農したが、士幌町一帯は湿性火山灰土で生産性が低く、冷害を受けやすい地域だったことなどから、いくら働いても負債が重なるばかりの農業に疑問を持っていた。そうした時、当時の士幌町農協の太田寛一組合長から突然、「アメリカに行って、近代的な酪農の勉強をしてこい」とハッパを掛けられた。
当時、経営は破綻状態にあったが、資金カンパも募ってもらい、十勝から初めての酪農派遣実習生に選ばれた。父親の辰治さんは農協の理事をしていたこともあり、太田寛一氏と懇意だった。旅費のほか、当時としては障壁の多い渡米の手続きなど、全て太田氏に手配してもらったという。 アメリカの研修先はイリノイ州の牧場だったが、そこで大きなカルチャーショックを受けた。搾乳牛4~5頭で手絞りの十勝の酪農と違って、いまの十勝にある最先端の設備・技術が50年前のアメリカにはあったのである。また週1回は家族そろって外食するなど、酪農家のゆとりある生活。また農場には芝生が植えられ、牛舎の周辺もきれいに整備されていた。1年中、家族全員が休み無しに働き、糞尿と雑草だらけの牛舎の環境などが当たり前だった十勝の酪農とは大きな格差があった。
アメリカの研修先はイリノイ州の牧場だったが、そこで大きなカルチャーショックを受けた。搾乳牛4~5頭で手絞りの十勝の酪農と違って、いまの十勝にある最先端の設備・技術が50年前のアメリカにはあったのである。また週1回は家族そろって外食するなど、酪農家のゆとりある生活。また農場には芝生が植えられ、牛舎の周辺もきれいに整備されていた。1年中、家族全員が休み無しに働き、糞尿と雑草だらけの牛舎の環境などが当たり前だった十勝の酪農とは大きな格差があった。
(写真)JA士幌町には"積小為大"の尊徳思想が根付いている
(二宮尊徳の像が建つ鈴木さんの自宅の庭)
研修先の牧場は、当時アメリカでもトップクラスだったが、「これが酪農のあり方だ」と、合理的酪農経営とゆとりある生活、これを士幌町で実現するというという目標が、鈴木さんの帰国後の酪農経営に大きな影響を与えることになる。
1年8か月余りの研修で帰国、父親から経営移譲を受けたとき、203万円の貯金と、負債残高が約524万円あった。当時、サラリーマンの平均年収が40~50万円だったころである。昭和46年の一番苦しいときは、収入の75・7%を借金返済に当てたという。この負債を10年で返済した。
いま、鈴木さんの農場をみると、自宅と牛舎の周辺はきれいに整備され、電線はすべて埋設。将来の拡充や建て替えを見越して、建物の配置には充分な余裕をもたせている。また独自で家畜糞尿を原料としたバイオガス発電装置を敷地内に設置しており、これがきっかけとなって、農協リースのバイオガスプラントが町内に13か所ある。もちろん妻の玲子さんと一緒の旅行も、毎年1回必ず実行している。
アメリカで夢見た酪農はほぼ実現し、「農村ユートピア」は完成の域にある...。鈴木さんがそう思うのは他にも根拠がある。JA士幌町は、生産活動だけでなく、生活面でもフォローする体制ができている。同JAの信用事業には、他のJAには見られない「自賄貯金制度」というのがあるのだ。
重要な記事
最新の記事
-
 【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日
【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日 -
 【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日
【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日 -
 【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日
【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日 -
 【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日
【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日 -
 【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日
【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日 -
 【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日
【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日 -
 歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日
歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日 -
 共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日
共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日 -
 新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日
新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -
 JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日
JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日 -
 JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日
JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日 -
 「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日
「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日 -
 「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日
「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -
 「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日
「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日 -
 初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日
初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日 -
 【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日
【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日 -
 虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日
虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日 -
 良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日
良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日 -
 「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日
「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日 -
 全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日
全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日







































































