JAの活動:米価高騰 今こそ果たす農協の役割を考える
【米価高騰・今こそ果たす農協の役割】分断絶つ協同社会 「ともに生きる」胸に 哲学者・内山節氏2025年10月16日
国連は相互扶助の組織として持続可能な食料生産と消費、人間の健康や福祉の向上などに貢献している協同組合を評価し2025年を国際協同組合年と定めた。一方、わが国では「令和の米騒動」で国民の農業や食への関心が高まり、農協の役割発揮が期待されている。本紙ではこうした情勢のなかで、国際協同組合年の意義を踏まえ農協がめざすべき方向を考えるべく特集を企画した。巻頭では内山節氏に協同組合関係者への提言を寄稿してもらった。
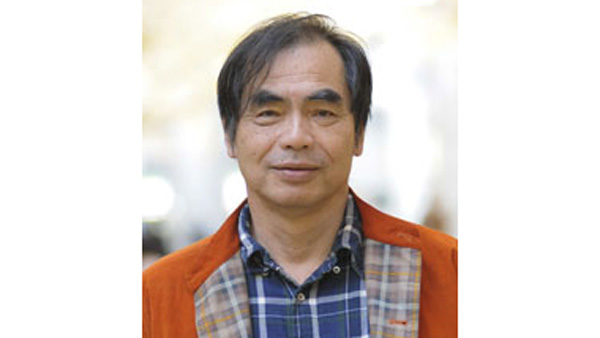 哲学者・内山節氏
哲学者・内山節氏
資本主義偏重 格差要因にも
日本の農村、とりわけ稲作地帯は、協同組合組織ができる前から協同組合的な一面をもっていた。水管理は協同の仕事だったし、田植えや稲刈りも集落の人々が集まって、一軒ずつこなしていった。春祭り、夏祭り、秋祭り、田の神祀(まつ)りなどではみんなの五穀豊穣を願った。ここには自然に芽生えた、ともに生きる社会があった。
資本主義の原理は投資と利回りである。株などに投資して高い利回りを得ようとするのと同じように、生産活動もまたひとつの投資の仕方とみなされる。生産に必要な投資をし、高い利回りでの回収をめざす。それは金融商品などへの投資と原理的には同じことで、ゆえに短期的な利回りを確保しようとすると、生産活動に投資するより、株を含む国際金融商品に投資する方が効率がよいということになる。
資本主義は投資と利益
こうして生まれてきたのが、今日のグローバル資本主義である。この資本主義の下では、投資と利益の確保以外の価値は存在しないかのごとくである。だからこのシステムは、社会をズタズタにして壊していく。労働者は利益を得るための道具にされ、それが実質賃金の低下や低賃金労働者の導入を促進させてきた。世界のどの国でも格差社会が生まれ、安易な移民労働者、外国人労働者の導入によって、一定の部門の労働の低賃金化が固定されたばかりでなく、そのことに反発する動きが国家主義的勢力の伸張を許し、分断化された社会が生まれていった。
農業や米、小麦などの保存の利く作物も、今日では投資の対象にされている。日本では農業自体を投資の対象にする動きは、まだ一部の傾向にすぎないが、現在の米の出荷価格が維持されると踏めば、農業を投資対象のひとつとみなす動きは広がりをみせはじめるかもしれない。米については、取扱業者などの数量確保のための高値買いが横行したが、現代資本主義の下では、この買い取りも投資活動と位置づけられていく。投資行動として米を買い取った以上、その結果一定の利回りを確保できなかったら経営的には失敗であり、それがつづけば倒産というかたちで市場から撤退させられる。それが資本主義の法則である。
資本主義の下でも、事業を営む経営者や労働者は、自分の仕事に対する理念や目的をもっていることが多い。米を適切な価格で買い取ることによって農家を支え、消費者には安定した価格の米を提供する。だがそういう気持ちで仕事をしていたとしても、資本主義はその行為をも投資と利回りとみなし、投資に見合った利益をもたらさなければ市場から撤退させる。
問題は資本主義の下では、働く人々の理念や思いがそのままでは実現できないところにある。だから昨年の米不足の折には、卸売業者などは米の確保に動かざるをえず、それが米価格を高騰させるといった現象が生まれた。
資本主義は事業体ごとの投資利回りを問う経済であり、ともに生きる社会をつくるには不適切な経済なのである。手を携えて、みんなでよりよい社会をつくるというようなことは、この経済システムの下では成立することができない。
かつての高度成長期のように、ほとんどの企業が成長した時代には、そのことによってみんなに利益が分配されるといったことも起こるが、それは特殊な成長期がもたらした一時的な現象にすぎない。だからそのような時期が終われば、それぞれの事業体が自分の企業の投資利回りの確保を目指して、社会に格差や分断をもたらしていくようになった。
私たちはもっと強く、資本主義が社会を壊していくことを意識すべきなのである。このシステムに委ねていけば、ともに生きる社会などつくりだしようもない。
協同の理念社会が模索
ゆえに協同組合の理念は、農業や漁業、林業といったある部門で必要な理念ではなく、社会全体にとって必要なものになってきているといってもよい。だから最近では、消費者を組織化した生活協同組合や、さまざまな職場を協同組合の理念で創造する労働者協同組合=ワーカーズコープなどの動きも活発化している。資本主義に任せておいたのでは、未来の光がみえないと考える人々は、ともに働き、ともに生きることができる社会を模索するようになった。
自己完結避け 有機的連帯を
だが協同組合運動の歴史は、そのすべてを成功させてきたわけではなかった。協同組合運動発祥の地であるヨーロッパをみても、失敗した組合の例がいくつもある。
その原因は、協同組合の理念を実現することと、協同組合組織の活動が必ずしも一致しないことにある。たとえばある国では、住宅協同組合が大きな力をもった時期があったが、低家賃で住める住宅を造り、組合員に提供するというこの協同組合は、住宅難の時代が過ぎると、低品質で少し安い住宅を供給する不動産業と代わらないものになっていった。しかも自己完結的に事業を拡大した結果、職員の維持や管理する不動産の維持費などの固定費が増大し、債務超過に陥ってしまった。
協同組合的動き広がる
こうした現実からみえてくるものは、協同組合は自己完結型の事業展開組織であってはならず、協同組合の理念を共有できるさまざまな協同組合や伝統的な地域共同体とも有機的につながりながら、その理念の実現を図っていかなければいけないということである。農村には「村」というともに生きる社会がある。さらには漁業協同組合や森林組合といった協同組合が存在する地域もある。そして街には生活協同組合があり、労働者協同組合も新しい事業所を生みだしている。さらには障害者が健常者とともに自分たちの事業体を立ち上げる協同組合的動きもひろがっている。
こうしたさまざまな動きとどのように有機的連携を図っていったら、協同組合の理念を実現できる社会が生まれるのか。課題は協同組合の理念が実現する社会の創造であって、それぞれの協同組合の維持が目的ではない。なぜなら今日の協同組合運動への期待は、限界をみせはじめた横暴な資本主義とは異なる経済や社会のあり方を、協同組合が指し示していくことにあるからである。
協同組合の理念を基礎においた活動によって農業、農村を守り、消費者の食文化も支える。そのためには、どんな活動をしている人々との有機的連携が必要なのか。そういうことを示しながら力強く活動する協同組合が、いまこそ求められている。
重要な記事
最新の記事
-
 日本農業賞 集団の部大賞 飛騨蔬菜出荷組合 倉吉西瓜生産部会 吉備路もも出荷組合2026年1月27日
日本農業賞 集団の部大賞 飛騨蔬菜出荷組合 倉吉西瓜生産部会 吉備路もも出荷組合2026年1月27日 -
 スポット取引価格が暴落、一気に2万円トビ台まで値下がり【熊野孝文・米マーケット情報】2026年1月27日
スポット取引価格が暴落、一気に2万円トビ台まで値下がり【熊野孝文・米マーケット情報】2026年1月27日 -
 【速報】千葉県で鳥インフルエンザ 今シーズン国内18例目2026年1月27日
【速報】千葉県で鳥インフルエンザ 今シーズン国内18例目2026年1月27日 -
 「全農全国高等学校カーリング選手権」優勝チームに青森県産米など贈呈 JA全農2026年1月27日
「全農全国高等学校カーリング選手権」優勝チームに青森県産米など贈呈 JA全農2026年1月27日 -
 3月7日、8日に春の農機・生産資材展 ミニ講習会を充実 JAグループ茨城2026年1月27日
3月7日、8日に春の農機・生産資材展 ミニ講習会を充実 JAグループ茨城2026年1月27日 -
 農業の持続的発展や地域の活性化へ JAと包括連携協定を締結 高槻市2026年1月27日
農業の持続的発展や地域の活性化へ JAと包括連携協定を締結 高槻市2026年1月27日 -
 農研植物病院と資本提携 事業拡大ステージに向けたパートナーシップ構築 日本農薬2026年1月27日
農研植物病院と資本提携 事業拡大ステージに向けたパートナーシップ構築 日本農薬2026年1月27日 -
 半自動計量包装機「センスケール(R)」をリニューアル サタケ2026年1月27日
半自動計量包装機「センスケール(R)」をリニューアル サタケ2026年1月27日 -
 「TUNAG エンゲージメントアワード2025」で「ENGAGEMENT SPARK COMPANY」受賞 ヤマタネ2026年1月27日
「TUNAG エンゲージメントアワード2025」で「ENGAGEMENT SPARK COMPANY」受賞 ヤマタネ2026年1月27日 -
 【役員人事】クボタ(2月1日付)2026年1月27日
【役員人事】クボタ(2月1日付)2026年1月27日 -
 大豆・麦など作物ごとの適応性を高めた普通型コンバイン「YH700MA」発売 ヤンマーアグリ2026年1月27日
大豆・麦など作物ごとの適応性を高めた普通型コンバイン「YH700MA」発売 ヤンマーアグリ2026年1月27日 -
 夜にヨーグルトを食べる 健康づくりの新習慣「ヨルグルト」を提案 Jミルク2026年1月27日
夜にヨーグルトを食べる 健康づくりの新習慣「ヨルグルト」を提案 Jミルク2026年1月27日 -
 北海道民のソウルドリンク「雪印ソフトカツゲン」発売70周年プロモーション始動2026年1月27日
北海道民のソウルドリンク「雪印ソフトカツゲン」発売70周年プロモーション始動2026年1月27日 -
 農研植物病院に出資 農業の新たなサプライチェーン構築を推進 鴻池運輸2026年1月27日
農研植物病院に出資 農業の新たなサプライチェーン構築を推進 鴻池運輸2026年1月27日 -
 鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月27日
鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月27日 -
 栃木県産「とちあいか」使用の春色ドリンク2種 期間限定で登場 モスバーガー&カフェ2026年1月27日
栃木県産「とちあいか」使用の春色ドリンク2種 期間限定で登場 モスバーガー&カフェ2026年1月27日 -
 深谷ねぎを素焼きでまるかじり 生産者と交流「沃土会ねぎ祭り」開催 パルシステム埼玉2026年1月27日
深谷ねぎを素焼きでまるかじり 生産者と交流「沃土会ねぎ祭り」開催 パルシステム埼玉2026年1月27日 -
 鹿児島「うんめもんがずんばい!錦江町うんめもんフェア」東京・有楽町で29日に開催2026年1月27日
鹿児島「うんめもんがずんばい!錦江町うんめもんフェア」東京・有楽町で29日に開催2026年1月27日 -
 四国初「仮想メガファーム」構想 地元農家と横連携で構築 ユニバース2026年1月27日
四国初「仮想メガファーム」構想 地元農家と横連携で構築 ユニバース2026年1月27日 -
 埼玉の人気5品種を食べ比べ げんき農場 羽生農場「いちご狩り」31日から2026年1月27日
埼玉の人気5品種を食べ比べ げんき農場 羽生農場「いちご狩り」31日から2026年1月27日






































































