JAの活動:第44回農協人文化賞
【第44回農協人文化賞】つながりを大切に前へ 信用事業部門 愛知県・JAみどり組合長 小島教正氏2023年12月22日
多年にわたり献身的に農協運動の発展などに寄与した功績者を表彰する第44回農協人文化賞の表彰式が11月30日に開かれました。
JAcomでは、各受賞者の体験やこれまでの活動への思い、そして今後の抱負について、推薦者の言葉とともに順次、掲載します。
 JAみどり組合長
JAみどり組合長
小島教正氏
緑信用農業協同組合(以下「JAみどり」)は名古屋市の南東部緑区を管内とする都市農協である。昭和の時代はダイコン・ハクサイなどの露地野菜に加え、酪農・養鶏なども多く営まれていた。しかし、昭和44(1969)年にほぼ全域が市街化区域に指定されると、土地区画整理事業が盛んに行われ、農地のほとんどが宅地化されてしまった。先祖からの農地は賃貸住宅などの都市的な土地利用に変わり、組合員ニーズも賃貸活用、税務相談が主流となっていった。
私は、昭和55(1980)年にJAみどりに入組し、不動産部に配属され、賃貸施設などの斡旋、管理、所得税の確定申告、そして組合員の賃貸施設の建設、相続対策、相続後の納税等も親身になって対応してきた。農業を継続できる農家には、生産緑地を推奨し、都市農業の振興にも努め、常に「組合員の利益を優先」した事業を心掛けてきた。その結果、多くの組合員が「俺が死んだら農協へ行け」と次世代に伝えてもらえるようになった。こうした日々の相談事業が県内外にも広がり、さまざまなJAからも不動産部への研修生や視察が相次ぎ、組合間協同にも献身的に尽力してきた。後に参事兼務理事、代表理事組合長に就任してから、信用事業では、JAとのパイプ役を担っている貯金渉外課(7人、うち女性5人)が「御用聞き」として組合員訪問を毎月継続するとともに、最近では、貯金窓口職員もコアな組合員との顔つなぎをさせるため幹部の組合員訪問に同行させている。窓口に組合員が来組した折には「いつも来てくれる子」として、会話も弾み、お困りごとの問いにも話がつながり、大きな役割を担っている。さらに本支店の幹部職員には大口貯金者、貸付幹部には大口貸出先、本支店長には生産農家を訪問させており、組合員の意見を事業に反映させている。
 正組合員・大口利用者を対象とした経営内容説明会
正組合員・大口利用者を対象とした経営内容説明会
超低金利が続く中では、年金受給や組合員への家賃収入が(家主への口座へ)自動的に入るようにし「集まる貯金」をさらに広げ、貯金の量の拡大に貢献している。また、地域で一番高い金利として准組合員の利用も多く、正組合員と大口利用者を対象とした「経営内容説明会」を毎年7~9回開催し、毎回自ら1時間程度説明するなど、JAみどりの経営の見える化、貯金高の維持に大いに貢献している。さらに、今も年金受給口座獲得については大々的な特別キャンペーンにより実績を伸長させ、当座性比率を大きく向上させた。貸出においては地域住民に幅広く提供する「住宅ローン」は、毎週土日に全職員が輪番で出勤して休日相談会を継続開催することで、特に住宅資金需要のある若い世代が、休日に充実した借入相談を行えるようにした。また、不動産業者と提携し、大量の住宅ローンの獲得、賃貸住宅建設資金や住宅ローンの借り換えなど、市況に応じた対応を課に指示している。これにより住宅ローンは当JAの貸付事業の主要な収益源として安定的に伸長している。准組合員にも教育ローン・マイカーローンなど、取引相手の裾野を拡大しており、近年のマイナス金利政策・景気後退等の影響による金融機関の収益減少の中にあって、貸出金利息の低下傾向に歯止めをかけることに成功しつつある。
これら貸出事業・貯金事業への適確なかじ取りにより、信用事業職員1人あたり貯金残高は72億円(県平均の2・38倍)、貸出金残高は14億円(県平均の2・68倍)と非常に高い生産性を実現している。自己改革では、令和元(2019)年より以下の四つの柱を軸とした自己改革に取り組んでいる。そして三つのS「Speed(スピード)」「Small(スモール)」「Social(ソーシャル)」をモットーに、持続可能な経営基盤の確立・強化を進めている。
❶「農業所得の向上」
付加価値の高い野菜等の生産支援や販売支援等を通して、農業所得の向上につなげている。
❷「デジタル化で効率UP」
職員(パート職員含む)全員にスマホを貸与させ、LINE WORKSアプリを使い、連絡や出張報告、日程調整や出欠管理を効率的に行うことにより、会議・業務の時間短縮に結びついている。
❸「人材育成強化で業務の質を向上」
職員の資格取得を支援。宅地建物取引士(93・5%)、FP資格(80・6%)、農協内部監査士(79%)と職員1人当たり平均14資格を保有。さらに組合員からの相談が多いものは、毎日の朝礼研修等でYouTubeによる動画研修を行い、〝組合員の困った〟の解決につなげている。
❹「経営基盤の強化」
各部門長を集めた会議を四半期ごとに実施(「横ぐし会議」と称す)、PDCAサイクルによる増収対策や部門間連携の強化、また、各部門No.2幹部を集め四半期ごとに会議(「第2の横ぐし会議」)を実施し、全部門でデジタル化、組合員の相談等を検討させ経営基盤の確立・強化につなげている。日常も貯金渉外課や貯金窓口でも不動産活用、税、くらしの相談を受けたり、その場で即答できることは回答、それぞれ専門部署へつなぐことも含め「組合員の困った」に対応したりしている。
資格取得や毎日の朝礼研修で、職員一人ひとりの知識力を上げ、アナログとデジタルを融合し、職員だれでも、いつでも声をかけてもらい、困ったことを解決することで、組合員とのつながりが深まっている。私自身は全職員が知識の向上や組合員が相談できる環境を作ることを心掛けており、令和6(2024)年からはさらに四つ目のS(スマート)を加え、この先も"頼れるJA"を目標にして邁進していきたい。
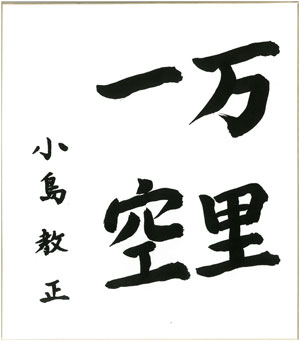 【略歴】
【略歴】
こじま・のりまさ
1957年6月生まれ。80年愛知学院大学法学部卒業。同年3月緑農業協同組合(のちに緑信用農業協同組合に改称)へ入組、不動産部へ配属。2001年4月不動産部長。05年6月参事兼務理事就任(10年3月まで不動産部長も兼務)。17年6月代表理事組合長就任、現在に至る。
【推薦の言葉】
地域の連携も強固に
小島氏は、1980年に大学を卒業後、緑農業協同組合(改称前)に入組し、不動産部に配属となる。不動産部では賃貸住宅、貸店舗、貸駐車場などの斡旋、管理、所得税の確定申告など組合員が所有する賃貸物件、その後は組合員の土地利用(賃貸施設の建設)、相続対策、相続後の納税等も献身的に対応した結果、組合員から次世代に「俺が死んだら農協へ(相談に)行け」と伝えてもらえるようになる。相続相談を通して次世代とのつながりにも大きな役割を担い、組合員の土地活用を積極的に進め、賃貸収入がJAの口座に振り込まれるようにし、「集める貯金から集まる貯金」を唱え、貯金量の拡大に貢献した。
先進的な不動産事業には県内外JAからも視察や研修生が相次ぎ、組合員だけでなく、組合間協同にも献身的に尽力している。
また、貸出においては不動産業者と提携した住宅ローンの獲得を図るとともに、小島氏が自ら所有する特定生産緑地に体験農園を設置し、農業融資も利用。社交的な人柄で地元商工業者との交流も多い。
重要な記事
最新の記事
-
 百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日
百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日 -
 将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日
将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日 -
 【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日
【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日 -
 【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日
【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日 -
 【GREEN×EXPOのキーパーソン】グリーンを活用したイノベーションへ 東邦レオ・小山田哉氏2026年2月12日
【GREEN×EXPOのキーパーソン】グリーンを活用したイノベーションへ 東邦レオ・小山田哉氏2026年2月12日 -
 アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日
アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日 -
 振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日
振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日 -
 愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日
愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日 -
 葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日
葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日 -
 「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日
「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日 -
 初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日
初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日 -
 【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日
【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日 -
 農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日
農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日 -
 食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日
食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日 -
 まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日
まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日 -
 クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日
クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日 -
 「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日
「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日 -
 邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日
邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日 -
 藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日
藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日 -
 東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日
東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日





































































