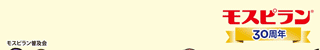【TPP】協定から離脱を-大学教員の会が緊急声明2016年11月28日
「TPP参加交渉からの即時脱退を求める大学教員の会」は11月28日、「TPPの国会承認手続きを中止し、TPP協定からの離脱を要求する」と題する緊急声明を発表した。
緊急声明では、米国のトランプ次期大統領がTPPからの離脱を明言した今も安倍政権は日本主導でTPPの発効にこぎつけると公言し、国会承認手続きを強行しようとしているとして、政府与党の動きに強く抗議し、TPP協定の国内承認手続きを直ちに中止するとともに、日本がTPP協定からすみやかに離脱することを要求している。
理由は以下のとおり。
○国会で承認を求められているTPP協定には、わが国がTPP交渉に参加するにあたって衆参農林水産委員会で決議された事項に反する内容が随所に含まれている。そのような協定文書を国会が承認することは国権の最高機関として自殺行為に等しい。
また、TPP反対を公約に掲げて当選した国会議員がTPP協定の承認を強行する「数の力」に加担するのは国民に対する重大な背信行為であり、とうてい許されない。
○国会で審議されているTPPのテキストだけでは不明な懸念事項が山積している。協定文書には、「物品の貿易に関する小委員会」、「農業貿易に関する小委員会」、「政府調達に関する小委員会」などの設置が明記され、多くの分野で追加協議が行われることになっている。政府は再協議には応じないと語っているが、かりにTPPが発効した場合、これら小委員会の場で日本に対し、目下の最終テキストを上回る市場開放要求ならびに規制・制度の改変・撤廃の要求を突きつけられる公算が大である。そのように不透明な要素をはらむTPPを前のめりに承認することは、わが国の国民益をグローバル企業に売り渡す危険を顧みない暴挙であり、許されない。
○米国の離脱が確定的になったことから、TPPの発効はもはや不可能となった。そのような死に体のTPP協定をわが国が国会で承認しようとするのは無意味というにとどまらず、危険で愚かな行為である。
なぜなら、トランプ次期米国大統領はTPPに代えて、今後はアメリカ第一主義の立場に立った二国間協議に注力すると明言している。日本がこの二国間協議の最大のターゲットになることは明らかである。となると、日本が各国の動向を顧みず、協定文書を国内で承認すれば、たとえ、TPPが発効に至らないとしても、各国から「日本はここまで譲歩する覚悟を固めた」という不可逆的な国際公約と受け取られ、日米二国間協議の場で、協議のスタートラインとされる恐れが多分にある。このような懸念は以下の事項で特に大である。
すでに日本はTPP協定交渉に参加するにあたって「入場料」としてBSEの輸入制限を30か月齢以下まで緩めた。この先、米国は「科学的根拠を示せない輸入制限は撤廃すべき」と迫ってくることは必至である。
遺伝子組み換え食品の表示やポスト・ハーベストの規制についても同様の論法で撤廃を迫られる恐れが強い。
TPP協定文書では、農業・畜産の分野で関税ゼロに向けた片道切符の市場開放の協議を約束させられている。TPPの発効を待たず、「自主的に」米国の理不尽な要求に屈して市場を「開放」してしまった汚点は消えないが、TPP協定の国会承認を思いとどまることは、これ以上、米国の要求を飲まされる「アリ地獄」にはまらないための歯止めとしての意義がある。
と同時に、国会決議に反して約束させられた市場開放を無効化し、今後の日米二国間協議で理不尽な市場開放・規制撤廃要求を拒む足場となる。
○もう一点は医療の分野での懸念事項である。わが国では超高額医薬品の登場が大きな社会問題(限度を超える患者負担、医療保険財政への過重負担)となっている。過日、市場拡大再算定制度を発動して緊急の値下げが図られた事例があるが、米国は日米経済調和対話の場で、「成功した製品の価値を損なう」として、この薬価再算定ルールの撤廃を要求してきた。
わが国が「自由貿易主義の旗手」を気取って国民のいのちと健康を守る規制の撤廃を受け入れる意思を表明したり、国内の審議機関への外国資本の参加に道を開いたりすることは、米国第一主義の餌食となる恐れが強い。
○当会は、対等平等、互恵の精神に立った国際的な経済連携の実現を期待する立場から、それとは相容れない、食の安全と自給、国民のいのちと健康、国と地方自治体の経済主権を多国籍資本の営利に明け渡すTPPの国会承認の中止、TPP協定からの離脱を政府と国会に要求する。
(呼びかけ人)
磯田宏(九州大学准教授/農業政策論・アメリカ農業論)、伊藤誠(東京大学名誉教授/理論経済学)、大西広(慶応義塾大学教授/理論経済学)、岡田知弘(京都大学教授/地域経済学)、金子勝(慶応義塾大学教授/財政学・地方財政論)、楜澤能生(早稲田大学教授/法社会学・農業法学)、志水紀代子(追手門学院大学名誉教授/哲学)、白藤博行(専修大学法学部教授/行政法学)、進藤栄一(筑波大学名誉教授/国際政治学)、鈴木宣弘(東京大学教授/農業経済学)、醍醐聰(東京大学名誉教授/財務会計論)、田代洋一(横浜国立大学名誉教授/農業政策論)、萩原伸次郎(横浜国立大学名誉教授/アメリカ経済論)、日野秀逸(東北大学名誉教授/福祉経済論・医療政策論)、廣渡清吾(東京大学名誉教授/ドイツ法)、 山口二郎(法政大学教授/行政学)、渡辺治(一橋大学名誉教授/政治学・憲法学)。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日
シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日 -
 農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日
農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日 -
 米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日
米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日 -
 (471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日
(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日 -
 スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日
スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日 -
 【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日
【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日 -
 【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日
【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日 -
 【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日
【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日 -
 【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日
【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日 -
 令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日
令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日 -
 「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日
「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日 -
 2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日
2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日 -
 【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日
【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日 -
 福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日
福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日 -
 いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日
いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日 -
 三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日
三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日 -
 【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日
【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -
 【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日
【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -
 【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日
【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日