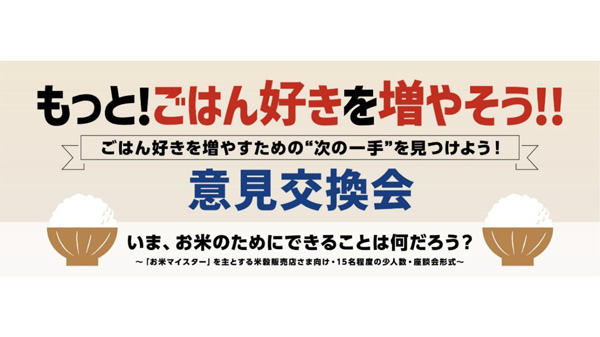武蔵野の平地林と風雪、田畑【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第200回2022年6月9日
森や林は山にあるもの、したがって森林とは山林である、と子どものころ(1940年代)の私は思っていた。私の育った山形では森林は山にしかなく、平地には神社や寺、河川敷にほんとに小さい林があるだけ、耕せるところはすべて田畑にしていたからである。
しかしそうではなかった。平地にも林があった。それを実感したのは1950年代後半、東京に行く機会が増えてからだった。

東北本線で関東平野に入ると雑木林が多くなる。中央線や小田急線などに乗るとさらにそれを感じる。まだそのころは都市化が進んでおらず、広々と畑が広がっていたのだが、そのところどころに林があるのである。
そういえばこのへんは武蔵野、私たちの中学の国語の教科書に載っていた国木田独歩(明治期の作家)の随筆『武蔵野』に雑木林の風情が書いてあった。
それにしてももったいない。どうして田んぼにしないのか。こんな平らな土地をどうして林のまま放っておくのか。水がなければ畑にすればいい。林になっているなだらかな丘だって畑にしようと思えばできる。なぜそうしないのか。関東の農家は怠け者なのか。それとも人口の割に土地がたくさんあり過ぎて全部耕地にできないからなのか。こんな疑問をもったものだった。それが解けたのは大学に入ってからだった。
東京の西部に田無という町(現・西東京市)がある。この地名は田んぼが無いことからつけられたと言われているが、実際に田んぼは少なかった。これは田無ばかりではない。関東平野のかなりの部分がそうである。漏水しやすい関東ローム層に覆われ、しかも灌漑の困難な台地が広がる関東平野は水田にしにくく、川の近くの沖積土壌の堆積するところにしか田んぼはつくれなかったのである。
それで畑作を中心にせざるを得なかった。ところが畑は水田よりも多くの養分補給を必要とする。この養分は、水田からの稲わらと山林からとってくる山野草・落ち葉を堆肥にして投与することで補給するのが一般的なのだが、何しろ田んぼは少なく、山林は遠い。そこで土地のすべてを畑とせず、条件の悪い土地などは開墾せずに雑木林(=平地林)とし、台地や傾斜地の一部は開墾可能であっても里山として残す。そこから草葉、落ち葉、若木をとって肥料とする。そればかりでなく、薪炭等の燃料を得るためにもこうした雑木林を利用する。何しろ山は遠く、薪炭を買うのも大変だからだ。それから農具や生活用具の原材料としての木々もそこから手に入れる。
したがってどこの農家も雑木林を必ず持っていた。
そしてそこにはたくさんの人の手がかけられていた。だからとてもきれいだった。
明治の代表的な日本画家菱田春草が描いた『落ち葉』という絵がある。当時はまだ郊外だった代々木近辺の雑木林を描いたとのことだが、林のなかの土地は掃除されたようにきれいで、そこに紅葉がひっそりと何葉か落ちており、本当にきれいである。最初見たとき、これは春草が想像で書いたのだろうと思った。現実はこんなにきれいなわけがないからだ。茶色の落ち葉が山のように積み重なって下土がよく見えず、歩くとがさごそと音がし、落ち葉の一部は黒く腐っているというのが普通の林である。しかし、この絵は頭で考えてつくった風景ではなかった。堆肥にするために農家が本当にていねいに落ち葉拾いをしたらしく、下土は本当にきれいだったとのことである。しかも春草の絵は写実を基本にしていると言われているよう。それでこのようなすばらしい絵になったのではなかろうか。
このように雑木林は堆肥確保対策から必要だったのだが、もう一つ、空っ風対策からも必要不可欠だった。
葉っぱの落ちた冬の桑畑の中を浪人姿の三船敏郎が歩いてくる。空っ風が彼の髪の毛を着物を揺らす。近くの宿場町でも空っ風がすさまじい土ぼこりをまきあげている。黒沢明監督の映画『用心棒』(注)の一場面だ。冬の関東平野の情景をよく映している。乾燥する冬、粒子の細かい関東ローム層の土は北西から山を越えて吹いてくる季節風で舞い上がるのである。
これではせっかく肥やした畑の土が飛ばされてしまう。また、家の中がほこりだらけになってしまうなど、生活にも困る。これを防ぐためにも防風林・堆肥供給林としての雑木林が、また屋敷林が必要だったのである。
しかし、高度成長以降の東京の膨張で農地ばかりでなく雑木林、屋敷林もなくなってきた。これを保護緑地として認定し、遺して行こうとしている地域もあるが、ぜひそうしてもらいたいものだ。
(注)監督:黒澤明、脚本:菊島隆三・黒澤明、東宝スコープ、1961(昭36)年。古い映画の話をしてしまったが、これが関東ローム層と農業の話をするときにもっともいいし、何よりも面白い、もしもレンタルがあれば借りてぜひ見てもらいたいものである。
重要な記事
最新の記事
-
 【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日
【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日 -
 【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日
【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日 -
 米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日
米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日 -
 2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日
2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日 -
 続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日
続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日 -
 第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日
第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日 -
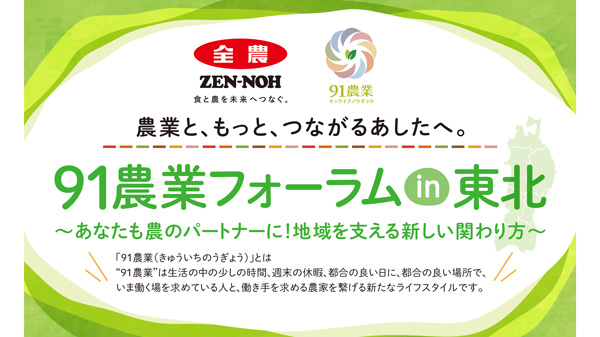 中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日
中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日 -
 希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日
希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日 -
 神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日
神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日 -
 フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日
フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日 -
 「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日
「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日 -
 東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日
東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日 -
 鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日
鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -
 鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日
鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -
 調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日
調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日 -
 佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日
佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日 -
 国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日
国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日 -
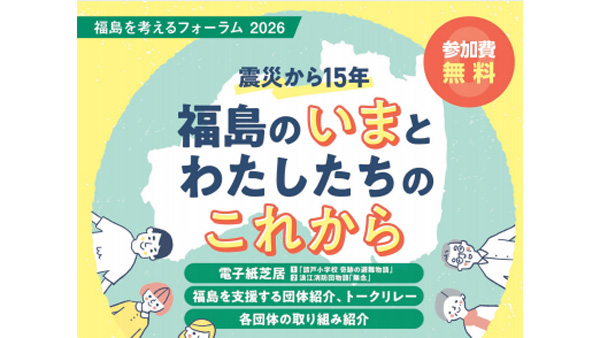 原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日
原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日 -
 牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日
牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日 -
 ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日
ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日