米:CE品質事故防止強化月間
【現地ルポ JA兵庫南・稲美CE】集荷推進 安定供給の要に おいしく、安全管理心掛け(1)2025年8月29日
米穀の集荷・販売の拠点施設であるカントリーエレベーター(CE)では、ほどなく1年で最も多忙な米の収穫期を迎える。全国CEの管理・運営改善に取り組む全国農協カントリーエレベーター協議会、JA全農、公益財団法人農業倉庫基金の3団体は、毎年8月1日から10月31日までの3カ月間を「米のカントリーエレベーター品質事故・火災防止強化月間」と定め、品質事故と火災防止の徹底を呼びかけている。この取り組みの一環として、今回は、JA兵庫南の稲美CE(兵庫県稲美町)を取材した。
 JA兵庫南・稲美CE。規模5000t、1日の最大荷受け能力312・5t、貯蔵サイロ17本
JA兵庫南・稲美CE。規模5000t、1日の最大荷受け能力312・5t、貯蔵サイロ17本
自然乾燥風に仕上げ
JA兵庫南は、明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町内の7JA(魚住・二見・加古川・稲美野・はりま信用・たかさご・米田町)が合併し、1999年4月1日に誕生した。管内は、大規模な稲作農家を中心とした北部と、京阪神のベッドタウンとして発展した南部で構成されている。山、川、海と自然も多く、温暖で、多くの作物栽培に適している。
正組合員は個人1万3867人、法人39、准組合員は個人5万1925人、その他団体108(いずれも24年度末)である。販売品取扱高合計は、45億3645万円(24年度)であり、うち米・麦・大豆の取扱高は9億9641万円となっている。
また、地産地消にも積極的に取り組み、農産物直売所を運営し、米の直売にも力を入れている。
JA管内のCEには、今回訪ねた稲美CEのほか八幡CE(加古川市八幡町)がある。2024年産米では、二つのCEで4985t荷受けした。生育期の記録的猛暑で穂数が少なく、カメムシ被害もあり、前年対比89・8%だった。また、転作作物では、JA管内は大麦の産地であり、大豆も作付けしている。25年産の麦は3~4月の天候がよかったため、稲美CEの大麦の荷受け量は、1943・5t(同157・7%)であった。
同JAに入ってから20年以上、米麦一筋に歩んできたベテランの営農経済部米麦施設課の堀内計宏副課長に話を聞いた。
 現場を案内する営農経済部米麦施設課の堀内計宏副課長
現場を案内する営農経済部米麦施設課の堀内計宏副課長
役員先頭に集荷推進
「令和6(24)年産は報道で『米が消えた』と言われ、一般消費者等から苦情や問い合わせが来るなか、JAとしても集荷に注力しました。今年産米の集荷に向けては、今年3月から常勤役員と一緒に大口農家を中心に訪問するなど集荷推進を行いました。具体的には、JA独自の活性化支援金や全農兵庫県本部によるボーナス加算金による生産者の手取りアップに加え、最低保証価格設定を行いました。これらの対策もあり、生産者の米作付け意欲は高まっていると感じます」
担い手の動向については「営農組合も高齢化により、世代交代が課題となっていますが、『もう作られへんから田んぼ預けるよ』という人がいると、営農組合は頑張って作業委託を引き受けています。兵庫県は生産地と消費地とが混在し中山間地もあるので、大区画化が容易には進みません。地域に合った方法で考える必要があります」。
高い利用率
CEの位置づけについては「CEはとても大事です。個々の農家さん、特に兼業農家は乾燥設備を持っていません。そのため、うちのCEは利用率が高いです」と話す。稲美CEの利用農家は500戸を超える。
「乾燥機を持っている大規模な農家でも、所有している乾燥機で処理しきれない分をCEに持って来ることもあります。JA兵庫南では出荷米の90%以上が施設出荷でありCEは地域農業にとって不可欠な存在となっています」
自然乾燥に近く好評
稲美CEの特徴は、ソフト・ドライング・システム(SDS、もみ殻混合常温吸湿乾燥方式)という、農家から荷受けした生もみに、乾燥したもみ殻を混ぜ生もみの水分をもみ殻に吸わせることで乾燥を進める乾燥方式を採用している。
「生もみの乾燥には火を使わず、自然乾燥に近い。灯油の使用量が少なく、脱カーボンを先取りしていました。数字に表れるほど食味の差はありませんが、組合員が親戚などに送ると、『おいしい米だな』と言われているそうです」
新品種デビュー間近
品種は「コシヒカリ」「キヌヒカリ」「ヒノヒカリ」。全農兵庫県本部が推す「3ヒカリ」だが、JA兵庫南では2026年産から「キヌヒカリ」を「コ・ノ・ホ・シ」に切り替え、直売所でも販売する予定である。「コ・ノ・ホ・シ」は、兵庫県オリジナルで高温耐性、良食味の新品種で、試験ほ場では昨年の暑さでも品質も良く収量が落ちなかった。
利便性をモットーに
毎日、農家が玄米や白米を持って帰れるのも特徴だ。「利用者さんの利便性を考えてのことです。JA兵庫南は農家、利用者に喜んでいただくことをモットーとしています。このことで、担当者は生産者と接する機会がすごく多くなり、様々な話が聞けます」と笑顔を浮かべた。
CEの1年間の仕事は、4月の「麦の荷受け準備」から始まり、5月から6月上旬にかけて麦を荷受け、乾燥し、その後、8月上旬まで麦の出荷が行われる。取材日は、麦の出荷が終わった直後だった。
その後は、清掃など米の荷受け準備に入り、8月下旬からコシヒカリの荷受けが始まる。9~10月は、キヌヒカリ、ヒノヒカリの順で収穫した米を荷受け、乾燥していく。乾燥後、サイロに貯蔵し11月からもみ摺り、出荷作業が始まって翌年3月までに終えるようにして、また次の麦の荷受け準備を待つ。
重要な記事
最新の記事
-
 日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日
日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日 -
 【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日
【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日 -
 加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日
加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日 -
 全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日
全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日 -
 鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日
鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日 -
 「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日
「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日 -
 「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日
「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日 -
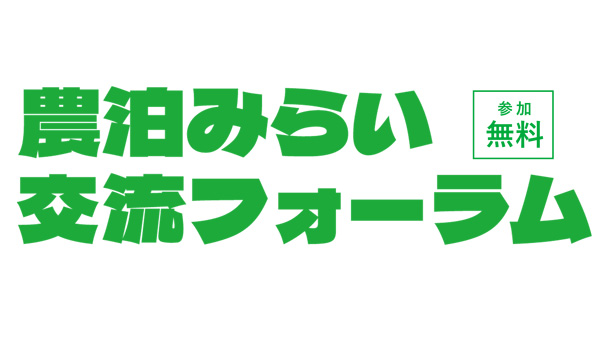 農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日
農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日 -
 冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日
冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日 -
 全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日
全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日 -
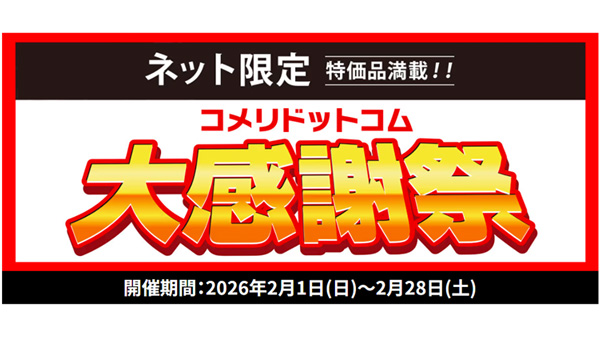 「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日
「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日 -
 「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日
「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日 -
 満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日
満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日 -
 生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日
生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日 -
 子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日
子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日 -
 国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日
国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日 -
 居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日
居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日 -
 ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日
ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日 -
 2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日
2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日 -
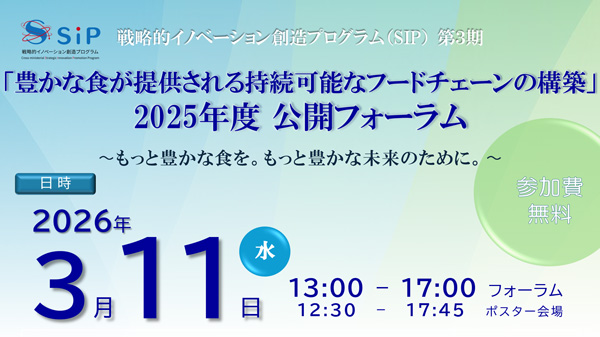 「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日
「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日








































































