【解題】基本法改正は食料安保をめぐる現場での課題にどう応えようとしているのか 谷口信和東大名誉教授2024年4月23日
農業協同組合研究会が4月20日に東京都内で開いた2024年度研究大会「基本法改正の下でわがJAと生協はこの道を行く」の解題と各報告の概要を紹介する(文責:本紙編集部)。
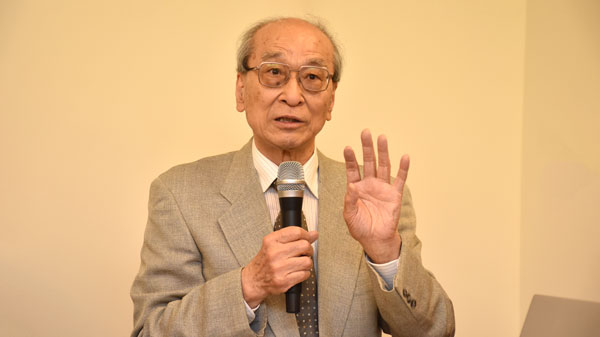 谷口信和 東大名誉教授
谷口信和 東大名誉教授
並ぶ抽象的な言葉
改正基本法の致命的な欠陥を3点挙げる。
1つ目は「食料自給率向上と積極的な備蓄論を欠いた食料安全保障論」であることだ。国内でどれだけしっかり食料を作るか、作る能力を持つかを抜きにした食料安保はあり得ない。これはイロハのイ。それから備蓄をどうするか、正面から議論をしないまま食料安保論を語れるわけがない。しかも備蓄を議論するときには、商社や穀物倉庫がどれだけ持っているかも大事だが、一軒一軒の家庭でどのように備蓄を考えていくのかを抜きに食料安保などあり得ない。
災害問題でも家庭にどれだけ備蓄をするかを前提に備蓄の議論は始まる。つまり、今回は国民的な議論を欠いているということ。当たり前の原点のところが失われていることが大きな問題だと思う。
2つ目は地産地消と耕畜連携の位置づけがほとんどないこと。こういう言葉がないまま農業の持続的発展という抽象的な言葉が並んでいる。実態のない「農業の持続的発展」となっている。
3つ目は「農業の多様な担い手」と耕作放棄地復旧や農地確保の問題について正面から捉えていないこと。将来、担い手は減っていくという認識に立っているだけでなく、では、担い手はどうするのかという理念を持つことが重要だ。
そのうえで「多様な農業者」について考えると、実は2020年3月に閣議決定した現行基本計画のなかにすでに「多様な農業者」は位置づけられていた。それから4年経ったが、何か状況が変わったのだろうか。何も検証されていない。にも関わらず今回の基本法改正で「多様な農業者」という言葉を入れたということだが、それはどんな位置づけなのか。
改正法案の第26条第2項は「......多様な農業者により農業生産活動が行われることで農業生産の基盤である農地の確保が図られるよう...」となっている。つまり、多様な農業者がいれば、やがて彼らが高齢になって農業をやめたときに担い手が引き受ける、それまでがんばってもらえばいいという位置づけでしかない。
そうではなく、その間、多様な農業者をどう支援するかという話につながって初めて、食料安保を担保できる多様な農業者という位置づけとなり、それなら、なるほどと納得できるようになる。しかし残念ながら、そうはなっていない。つまり、ただの農地の管理者でしかない。農地の管理であれば作物を作らなくてもいい。現在でも保全管理という方法があり、少なくとも草を生やさないようにすればいいということはある。しかし、それでは食料安保は担保できない。
もっとも大きな問題は「選別的な担い手政策に変更はない」と繰り返し言っていることだ。これは農水省だけでなく残念ながら大臣もこれに近いことを言っている。つまり、担い手政策は基本的に変わらないということだが、法案には多様な担い手を位置づける。そうなると説明と法案にズレがあることになるが、その厳密な検証はしないまま法案を通そうというのが実際だと思う。
消えた「適正な価格」
今日のテーマの一つでもある「適正な価格」については、生産者も消費者も期待したが、改正法案には一言も出てこない。すべて「合理的な価格」で押し切っている。
実は議論の時に使われた言葉は、生産資材価格が高騰した分の「価格転嫁」だった。その結果、適正な価格形成問題が出てきたと皆思っている。
しかし、改正法案では「合理的な価格」であり、それは現行法のまま。つまり現行法を変えてないことを意味する。
「合理的な価格」の含意は、農産物価格は需給事情と品質評価を適切に反映して形成されるということだが、これは価格形成のなかに農家の所得を保障するような文言を含んではいけないということであり、現行基本法を制定したときの理念、価格政策と所得政策は分離するという考えが貫かれている。
「適正な価格形成」という言葉の意味は、実は「適正な形成」なのであり、価格は「合理的」に決めるというのが農水省の考え。つまり、「合理的な価格を適正に形成する」ということである。担当者によると、適正な形成という意味は、費用について、きちんと誰にも説明がつく合理的なものであるかどうかを確認することであり、確認した費用について関係者の間で協議し、どのように価格に反映していくかを検討することだという。
そこには農業者の所得はどうなるのかという問題はない。本来大事なことは、合理的であるかどうかではなく、費用等の議論を通じて農業者の再生産が図れるような水準に価格が設定されるかどうかだろう。
しかし、消費者がアクセスできる食料価格と農業者の再生産保障価格は一致する保障はない。しかも最大の問題は価格は変動するものだということを前提にすれば、価格だけで所得を保障することはできない。それを踏まえると価格の変動にとらわれずに安定した所得が得られるように財政的な所得保障をどこまで国が行うのか、これを考えていくべきだろう。
重要な記事
最新の記事
-
 兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日
兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日 -
 【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日
【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日 -
 持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日
持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日 -
 5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日
5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日 -
 米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日
米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日 -
 おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日
おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日 -
 コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日
コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日 -
 農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日
農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日 -
 本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日
本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日 -
 日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日
日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日 -
 2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日
2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日 -
 【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日
【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日 -
 売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日
売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日 -
 電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日
電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日 -
 宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日
宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日 -
 宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日
宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日 -
 「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日
「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日 -
 累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日
累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日 -
 養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日
養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日 -
 農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日
農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日





































































