JAの活動:今村奈良臣のいまJAに望むこと
第36回 牛の放牧により中山間地域の農業を蘇らせよう2017年11月19日
いま一つ大分県下でかつて牛の放牧について実態調査を行った事例について紹介しておこう。
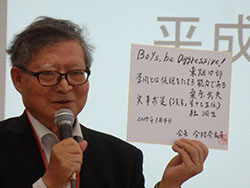 九州でもっとも高い久住山の山麓にある朝地町温見(ぬくみ)にある温見畜産振興会という54人の組織で、和牛繁殖牛経営を主体とした畜産の生産者組合である。その代表をしていた小野大蔵さんが「うちの牛は一言でいえば"した刈り"をさせているんだ」と言った。私は牛に下刈りさせているとはどういうことですか、と聞いたら「牛の舌で刈らせている。舌刈りだ」と言われて、なるほどと手をたたいて理解できたことをいまでも忘れられない。
九州でもっとも高い久住山の山麓にある朝地町温見(ぬくみ)にある温見畜産振興会という54人の組織で、和牛繁殖牛経営を主体とした畜産の生産者組合である。その代表をしていた小野大蔵さんが「うちの牛は一言でいえば"した刈り"をさせているんだ」と言った。私は牛に下刈りさせているとはどういうことですか、と聞いたら「牛の舌で刈らせている。舌刈りだ」と言われて、なるほどと手をたたいて理解できたことをいまでも忘れられない。
その"舌刈り"という言葉のなかに、未利用資源をいかに利用し活かすかという知恵と実践が含まれていたのである。
具体的にその実践を紹介すると、久住山麓の草原はもちろん、クヌギ林、あるいは7~8年生までのスギ林にも、牛を4月から11月頃まで放牧していた。もちろん、クヌギ林やスギ林にはバラ線で牧区を切ってあり、牛が遠くへ行かないように、また順序良く草を食べるように牧区を切り牛を回しているわけだ。牛は自分のエサは自分で確保するという仕掛けになっている。子牛は、山の入り口に丸太で組んだトタン屋根の非常に安価に見える小屋につないであり、親牛は乳を飲ませに定時的に戻ってきていた。
要するに、牛を飼うのに非常に人手がかからない。夕方、親牛が乳を飲ませに帰ってきた時に、牛の体温を測ったり眼の色を見たり、体の色つやを見たりして健康状態を観察しているという。ここのところだけは非常に注意して、あとはすべて牛まかせであるという。
クヌギの木は、シイタケ栽培のホダ木としてもっともすぐれているが、それにヤマイモのつるなど巻きつくと非常にシイタケ原木としては価値が落ちてしまう。ところが、逆に牛はそういうツル草などがいちばん好きで、全部引きずり落して食べてくれるという。おまけに雑草の下草もちゃんと食ってくれ、さらに蹄で土を適当に耕してくれ、さらに糞尿も肥料として山林にすべて還元してくれる。そういうわけで、クヌギの育ちも以前より非常に良くなり品質も向上したという。クヌギはこの辺りでは、だいたい伐期が12~14年、平均して13年ぐらいだが、牛を放牧したクヌギ林はだんだん短縮されて10年、あるいはいいところでは9年という伐期になってきたといっていた。
さて、クヌギは伐ったあと翌年その株から芽がたくさん出てくるが、その中でどれを残すかというのが「芽かき」というが、その芽かきを
行うのに人手がかかるくらいで、あとは「牛の舌刈り」にまかせているのだと、小野さんは言っていた。
<改良草地と野草の草地>
ところで、農林水産省は、かねてより畜産振興ということで飼料基盤を造成するという名目で、山をはがし谷を埋め、機械の入る平らな草地を大量につくることに大変多くのお金をつぎ込んできた。そこに、日本在来のものでない海外から輸入された牧草の種子をいろいろ植えて大規模草地造成をすすめてきた。
そこで、さきの小野さんの話によると、改良草地に牛を放牧してみたが、牛が仔をはらむのがどうもうまくいかない、種がとまらないということが経験的にわかってきたという。そこで、和牛は改良牧草と野草のどちらを好むのか、と聞いてみたら、「野草を好む」と言った。クヌギ山にも蹄耕法を利用して牧草をあちこちに栄養剤みたいにまいてあるが、カヤの新芽が出た頃、牛を山に追い込むと、牛は争ってカヤの新芽に飛びついて牧草の方には見向きもしないと言っていた。カヤの新芽が無くなってくると仕方なしに改良牧草の方に行って食うと言っていた。このような話からすると、日本の和牛を前提に考えた場合には、どうも嗜好性などからみても、野草の方が具合がよいし、健康状態もよいし、種のとまりもよいと言っていたことが未だに頭の隅に残っている。
そういうことを考えているとき、小野さんから次のような質問をされたことを想い出した。
「今村先生は何でも知っているみたいだけど、改良草地でやった牛のクソと野草地でした牛のクソの違いを知っていますか?」
「いや、そこまで知りません」と答えた記憶がある。そこで山へつれていかれた。たしかに改良草地にある牛のクソは下痢便というかベタッと広がった便であった。それに対して野草地のは、丁度まんじゅうがもりもりと盛り上がったような牛のクソであった。つまり、ホルスタインのように改良を重ねてきた乳牛にはたぶん改良牧草が必要だと思ったが、和牛には野草の方がよいのだということを実感したことを改めて想い出した。
かなり以前の温見畜産振興会での現地調査を改めて想い起して記したが、改めて結論として「クヌギ山に林間放牧して、牛に野草を食わせ、耕させ、糞尿もそこで処理させれば、クヌギもよく太ってくれるし、シイタケ経営にも非常に良い。一石何鳥ともいえる実践を通して中山間地域に活力をもたらして頂きたい」というのを、メッセージとして中山間地域の皆さんに贈りたい。
<福島原発の震災事故と放射能禍に見舞われた福島の宝の山をいかにすべきか>
かねてより椎茸の全国有数の生産地である大分県は、特に福島県より、椎茸の原木としてクヌギをはじめナラやブナなども大量に輸入していた。それだけ福島県は椎茸の原木に恵まれていた地域であった。それが、放射能禍によって、一瞬にして消え去ったのである。水田や畑などはどうにか除染対策でその被害は薄れつつあるが、山林には、未だに全くと言ってよいほど手が及んでいない。私が塾長をしている三春町にも震災後二度訪ねたが、かつてのクヌギの美林は目をそむけたくなるような荒廃した森林になっていた。私も、せめてクヌギ山だけでも昔の姿に帰らないものかと念じて色々の方々に相談してみたがなお名案は浮んで来ない。チップにして発電用にどうか、チップをさらに微細にして競走馬の敷ワラ代りにどうか、など色々と智恵を出してきてくれる方々もいるが、いまなお、救済すべき途は見つからないでいる。どうか放射能汚染した福島の森林、なかでもクヌギの用途を志ある方々に教えてもらいたい。
重要な記事
最新の記事
-
 百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日
百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日 -
 アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日
アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日 -
 振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日
振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日 -
 愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日
愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日 -
 葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日
葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日 -
 「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日
「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日 -
 農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日
農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日 -
 食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日
食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日 -
 まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日
まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日 -
 クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日
クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日 -
 「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日
「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日 -
 邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日
邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日 -
 藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日
藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日 -
 東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日
東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日 -
 鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月12日
鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月12日 -
 首里城再建 組合員からのカンパ金に感謝 沖縄県知事が生活クラブに来訪2026年2月12日
首里城再建 組合員からのカンパ金に感謝 沖縄県知事が生活クラブに来訪2026年2月12日 -
 坂ノ途中 国連開発計画(UNDP)スリランカ事務所とMOU締結2026年2月12日
坂ノ途中 国連開発計画(UNDP)スリランカ事務所とMOU締結2026年2月12日 -
 国産農業用ドローン普及拡大へ 住友商事とマーケティング連携開始 NTTイードローン2026年2月12日
国産農業用ドローン普及拡大へ 住友商事とマーケティング連携開始 NTTイードローン2026年2月12日 -
 映画「生きて、生きて、生きろ。」視聴でオンライン座談会開催 パルシステム2026年2月12日
映画「生きて、生きて、生きろ。」視聴でオンライン座談会開催 パルシステム2026年2月12日 -
 高市旋風で自民圧勝 農政は課題山積、「一強国会」でも熟議を2026年2月10日
高市旋風で自民圧勝 農政は課題山積、「一強国会」でも熟議を2026年2月10日





































































