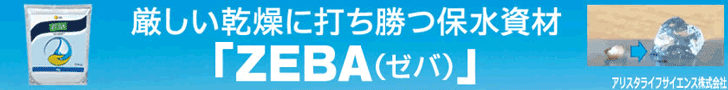農薬:防除学習帖
【防除学習帖】第13回 虫の防除方法(生物的防除I 微生物農薬)2019年8月2日
前回のおさらい
農作物を加害する害虫は昆虫がほとんどで、その生態を逆手にとって、害虫が生活しにくい、生きていきにくい環境を作ることが害虫防除の第一歩。各種防除法を効率的に組み合わせて総合的に防除を行うIPMが重要であることを紹介した。今回は、各種防除法の第3弾、生物的防除を紹介する。
◆生物的防除
この防除法は、天敵や微生物など天然に存在する生物を利用して害虫を抑える防除法で、近年様々なものが出ている。微生物、天敵線虫、天敵昆虫・ダニ、フェロモンを利用して行う害虫防除のことを総称して生物的防除と呼んでいる。この生物的防除のメリットは、人畜への安全性が高いこと、抵抗性害虫が発生しにくいこと、開発費用が安くすむことなどが挙げられ、徐々にその数を増やしている。一方、デメリットとしては、天敵などのように防除できる害虫が限られること、すぐに効かないこと、大量製造が難しいこと、効果を発揮させるための技術が難しいことなどが挙げられる。
ただ、近年はバンカーシートなど欠点を補う技術も開発され、害虫防除の分野でもだいぶ市民権を得てきているが、やはり使い方を誤ると全く効果が出ないこともあるため、特性を良くつかんだ上で正しく使う心構えが必要だ。
(1)微生物由来の生物農薬とは
ここでいう微生物は、ウィルス、細菌、糸状菌のことを指す。その作用は、大きく分けて、微生物が害虫に感染あるいは寄生して死亡させること、微生物が害虫にとっての毒性物質を生み出しその毒作用により死亡させることの2つがある。現在使われている生物農薬は、害虫の天敵となり得る微生物を見つけてきて、その微生物を大量増殖し、ほ場で処理しやすいように製剤化したものである。
(2)ウィルスが有効成分であるもの
まず、ウィルスでは、チョウ目害虫の核多角体病ウィルスや顆粒病ウィルスがあげられ、害虫にウィルスを感染させることによって発病させ、死亡させる。この方法の成否は、どうやって害虫の病原ウィルスを害虫に感染させるかにかかっている。というのも、ウィルスは、自分では侵入できず、傷口や自然開口部(害虫でいえば気門など)からしか侵入できないため、ウィルス製剤をいかに害虫の身体に接触させることができるかが鍵だ。
ちなみにウィルスは、生きた細胞の力を借りないと増殖できない存在であるため、半生物的な存在であるが、害虫の生物防除においては、微生物として扱っている。
(3)細菌が有効成分であるもの
殺虫活性のある細菌では、Bacillu thuringiensis(略してBT)がよく知られている。この菌は、もともとは蚕の卒倒病菌で、アルカリ性であるチョウ目害虫の消化管の中でのみ毒性を発現する結晶タンパクをつくる。この菌を生きたまま使うのが生菌製剤、菌を死滅させ、菌が作った毒性成分(結晶タンパク)のみ使うものを死菌剤という。一般的に、生菌の方の効果が高いと言われている。なぜなら、BT菌が作物体上に定着し、作物の分泌物などを餌に生きていく過程で、さらに毒性成分をつくり続けるからである。
このBTを成分とする農薬(BT剤)は多数あり、現在でも多く使われている。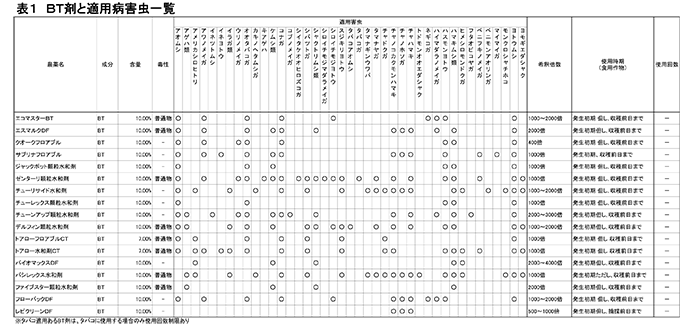
※画像をクリックするとPDFファイルが開きます
特に、有機栽培や減農薬栽培におけるチョウ目害虫防除には不可欠な農薬である。
それは、BT剤が、<1>使用回数制限が無く、何回でも使用できること<2>収穫前日まで使用できること<3>抵抗性の発達する心配が少ないことなどが理由だ。
ただし、防除できる害虫はチョウ目のみで、しかも発生の初期に使用しないと十分な効果が期待できない。これは、BT剤が散布された農作物を害虫の幼虫が食べて、その消化管の中で毒性を発揮するためで、葉などを食べる幼虫にしか効果がないからだ。
また、チョウ目だけなので、他の重要害虫を防除しなければならない時には、他の農薬と組み合わせて使用することが必要になる。
(4)糸状菌が有効成分であるもの
害虫の天敵微生物である糸状菌を有効成分とするもの。糸状菌とは、いわゆる「かび」の仲間のことで、粉状の胞子(分生子)と呼ばれる。植物でいえば種子のようなものを沢山つくって拡散していく。
表2(天敵微生物農薬一覧)に示したものが害虫防除に使用される生物農薬だ。
これらも、いかに害虫に糸状菌の胞子(分生子)を付着させて、感染させるかが成否の鍵である。表中の使用方法には、害虫の生態に合わせて微生物製剤を散布あるいは設置する方法が記載されているが、高い効果を得るためには、この使用方法を確実に守る必要がある。間違った方法では、うまく害虫に菌を感染させることができず、折角使っても十分な効果が期待できないことがある。各処理方法は、成分である微生物の生態と害虫の生態をうまく合わせて設定されているので、微生物農薬を使う時は、ラベルや説明書をよく読んで、それを確実に実践するようにしてほしい。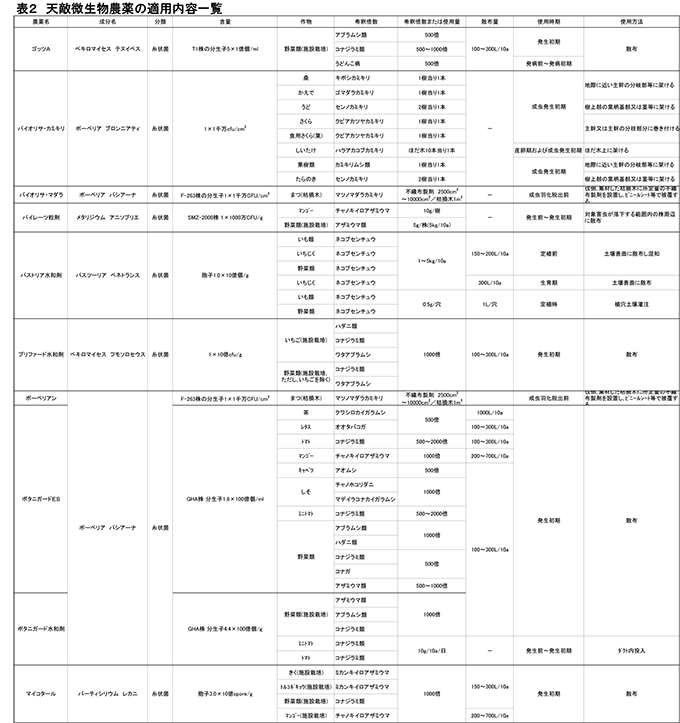 ※画像をクリックするとPDFファイルが開きます
※画像をクリックするとPDFファイルが開きます
本シリーズの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。
防除学習帖
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日
シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日 -
 農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日
農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日 -
 米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日
米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日 -
 (471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日
(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日 -
 スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日
スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日 -
 【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日
【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日 -
 【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日
【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日 -
 【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日
【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日 -
 【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日
【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日 -
 令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日
令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日 -
 「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日
「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日 -
 2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日
2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日 -
 【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日
【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日 -
 福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日
福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日 -
 いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日
いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日 -
 三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日
三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日 -
 【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日
【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -
 【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日
【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -
 【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日
【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日