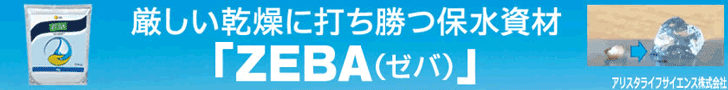(377)食中毒1万人は多いか?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2024年3月29日
日本の食中毒患者数は年間どのくらいだと思いますか?食生活が豊かになり、いつでもどこでも好きな食事を楽しめる生活が続く中で、意外と忘れられがちです。
食中毒の本格的統計調査が開始されたのは割と新しく、昭和27(1952)年のようだ。初期の記録は『伝染病及び食中毒精密統計年報』に残されている。全てではないが、一部の年についてはインターネットでも確認できる。
また、当時の状況をまとめた記述として、元国立公衆衛生院の疫学部長である松田心一氏の「食中毒の疫学的考察」(1962)※1 という論文がある。
これによると、調査開始から9年間の食中毒患者数合計は298,361人である。年平均で3万人を超える。年次別に昭和30(1955)年が65,746人と突出しているが、他は概ね3万人前後である。筆者が生まれた昭和35(1960)年は35,695人が記録されている。
以下、この論文の中に見られる興味深い点を1~2点紹介したい。
第1は、「1959年アメリカ全国で発生した食中毒について見ると、件数323件で、わが国に比し1/5~1/8、患者数10,541人で、わが国に比べ1/3~1/4である」という点だ。
「もはや『戦後』ではない」と経済白書が示したのは昭和31(1956)年であり、松田論文の調査対象時期に概ね該当する。『戦後』の混乱期はともかく、白書の宣言から数年を経た時点ですら、実は日米間の「食の安全」には大きな違いが存在したことがわかる。
ちなみに、東京都下水道局の資料を見ると、昭和36(1961)年の下水道普及率は東京都区部(23区内)ですら22%であり、33年後の平成6(1994)年にようやく100%に到達している。※2
東京都下や地方の状況は想像に難くない。当時の一般的状況を肌で理解している世代は別として、除菌シートで完全防護することが常態化した世代には下水道普及率2割の生活環境など想像できないのではないだろうか。
第2は、当時の食中毒の増加理由について松田氏は食品関係施設の大幅増加を指摘している。「このことは、昭和35年度の『厚生白書』が教えるように、食品衛生面での危険度がそれだけ高まったことを示すと同時に、また同業者の間に過度の競争が行われ、その結果衛生基準を守ることが困難となってきていることも考えられる。さらに原因食品不明の割合が増加している事実は、外食、給食等による食中毒が増加しているにもかかわらず、その反面に限られた職員でその処理に当たるため、調査上の手不足をきたし、調査の時期を失して、原因食品の追求が困難であったり、また不徹底であったりするためではないかと考えられる」と述べている。
半世紀前の指摘だが、今、読み返しても参考になる。
* *
ところで最近の状況はどうか。日本における食中毒患者数を見ると、平成18(2006)年に39,026人が記録された後は若干の変動はあるもののほぼ毎年のように減少し、令和4(2022)には6,856人、令和5(2023)年には11,803人と半世紀前、というか平成前期の1/3に減少している。グラフ化すると一目瞭然、過去15年間で患者数が3万人を超えた年はゼロである。
もちろん発生件数や原因物や原因施設などの違いはある。ただし、総じて言えば、昭和後期から平成前期あたりまで、つまり20年前までは毎年3万人を超える食中毒患者が発生していた。平成18・19(2006・07)年は3万人を超えているが、これは細菌(サルモネラ属菌)およびノロウイルスによるもので、原因となる施設・食品・加工方法などが明確に特定されたため、その後の発生防止につながっている。
振返って見れば徹底的に「食の安全・安心」を意識した20年であったが、人々の意識と具体的行動が伴えば、確実に効果は出るということであろう。
* * *
絶対数としての1万人は多いですね。それでも以前の3分の1に減少した、これはしっかりと理解しておく必要があると思います。
※1 松田心一「食中毒の疫学的考察」『食品衛生学雑誌』、3巻1号、7-16頁。アドレスは、https://www.jstage.jst.go.jp/article/shokueishi1960/3/1/3_1_7/_article/-char/ja/ (2024年3月25日確認)
※2 東京都下水道局「100 Years' History 都区部下水道・下水処理100年史」, 2022年、128頁。アドレスは、https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/business/pdf/01_honpen.pdf
重要な記事
最新の記事
-
 スポット取引価格が暴落、一気に2万円トビ台まで値下がり【熊野孝文・米マーケット情報】2026年1月27日
スポット取引価格が暴落、一気に2万円トビ台まで値下がり【熊野孝文・米マーケット情報】2026年1月27日 -
 【速報】千葉県で鳥インフルエンザ 今シーズン国内18例目2026年1月27日
【速報】千葉県で鳥インフルエンザ 今シーズン国内18例目2026年1月27日 -
 「全農全国高等学校カーリング選手権」優勝チームに青森県産米など贈呈 JA全農2026年1月27日
「全農全国高等学校カーリング選手権」優勝チームに青森県産米など贈呈 JA全農2026年1月27日 -
 3月7日、8日に春の農機・生産資材展 ミニ講習会を充実 JAグループ茨城2026年1月27日
3月7日、8日に春の農機・生産資材展 ミニ講習会を充実 JAグループ茨城2026年1月27日 -
 農業の持続的発展や地域の活性化へ JAと包括連携協定を締結 高槻市2026年1月27日
農業の持続的発展や地域の活性化へ JAと包括連携協定を締結 高槻市2026年1月27日 -
 農研植物病院と資本提携 事業拡大ステージに向けたパートナーシップ構築 日本農薬2026年1月27日
農研植物病院と資本提携 事業拡大ステージに向けたパートナーシップ構築 日本農薬2026年1月27日 -
 半自動計量包装機「センスケール(R)」をリニューアル サタケ2026年1月27日
半自動計量包装機「センスケール(R)」をリニューアル サタケ2026年1月27日 -
 「TUNAG エンゲージメントアワード2025」で「ENGAGEMENT SPARK COMPANY」受賞 ヤマタネ2026年1月27日
「TUNAG エンゲージメントアワード2025」で「ENGAGEMENT SPARK COMPANY」受賞 ヤマタネ2026年1月27日 -
 【役員人事】クボタ(2月1日付)2026年1月27日
【役員人事】クボタ(2月1日付)2026年1月27日 -
 大豆・麦など作物ごとの適応性を高めた普通型コンバイン「YH700MA」発売 ヤンマーアグリ2026年1月27日
大豆・麦など作物ごとの適応性を高めた普通型コンバイン「YH700MA」発売 ヤンマーアグリ2026年1月27日 -
 夜にヨーグルトを食べる 健康づくりの新習慣「ヨルグルト」を提案 Jミルク2026年1月27日
夜にヨーグルトを食べる 健康づくりの新習慣「ヨルグルト」を提案 Jミルク2026年1月27日 -
 北海道民のソウルドリンク「雪印ソフトカツゲン」発売70周年プロモーション始動2026年1月27日
北海道民のソウルドリンク「雪印ソフトカツゲン」発売70周年プロモーション始動2026年1月27日 -
 農研植物病院に出資 農業の新たなサプライチェーン構築を推進 鴻池運輸2026年1月27日
農研植物病院に出資 農業の新たなサプライチェーン構築を推進 鴻池運輸2026年1月27日 -
 鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月27日
鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月27日 -
 栃木県産「とちあいか」使用の春色ドリンク2種 期間限定で登場 モスバーガー&カフェ2026年1月27日
栃木県産「とちあいか」使用の春色ドリンク2種 期間限定で登場 モスバーガー&カフェ2026年1月27日 -
 深谷ねぎを素焼きでまるかじり 生産者と交流「沃土会ねぎ祭り」開催 パルシステム埼玉2026年1月27日
深谷ねぎを素焼きでまるかじり 生産者と交流「沃土会ねぎ祭り」開催 パルシステム埼玉2026年1月27日 -
 鹿児島「うんめもんがずんばい!錦江町うんめもんフェア」東京・有楽町で29日に開催2026年1月27日
鹿児島「うんめもんがずんばい!錦江町うんめもんフェア」東京・有楽町で29日に開催2026年1月27日 -
 四国初「仮想メガファーム」構想 地元農家と横連携で構築 ユニバース2026年1月27日
四国初「仮想メガファーム」構想 地元農家と横連携で構築 ユニバース2026年1月27日 -
 埼玉の人気5品種を食べ比べ げんき農場 羽生農場「いちご狩り」31日から2026年1月27日
埼玉の人気5品種を食べ比べ げんき農場 羽生農場「いちご狩り」31日から2026年1月27日 -
 高圧洗浄機のラインナップ拡充 カタログギフトプレゼントキャンペーン開始 丸山製作所2026年1月27日
高圧洗浄機のラインナップ拡充 カタログギフトプレゼントキャンペーン開始 丸山製作所2026年1月27日