【クローズアップ 酪農の状況とJA全農】鈴木富雄酪農部長に聞く 生産基盤を強化し酪農生産に貢献2019年7月11日
わが国の酪農生産基盤は酪農家戸数の減少とともに飼養頭数も減少するという状況が続いてきたが、ここにきて都府県の生産基盤には課題は多いものの、飼養頭数が増え令和元年度は4年ぶりの増産となる見込みとなった。一方、昨年4月に施行された改正畜安法による生乳流通制度の見直しは2年目を迎える。こうした情勢の変化と今後の見通し、JA全農酪農部の役割などについて鈴木富雄部長に聞いた。
 ー最近の生乳生産の動向と牛乳乳製品の需要動向についてお聞かせください。
ー最近の生乳生産の動向と牛乳乳製品の需要動向についてお聞かせください。
平成30年度の生乳生産は北海道101.2%・都府県98.4%と全国計では前年比99.9%となり、3年連続で前年割れとなりました。これに対して令和元年度は100.5%と増加に転じるとJミルクは見通しています。これは2017年9月から2歳未満の頭数が増加し始めて、その傾向が続いているからです。雌雄判別精液の活用・普及も含めて、少し状況が変わりつつあり、令和元年は4年ぶりの増産となり、さらに今後増えていく期待があるということです。
(写真)鈴木富雄JA全農酪農部長
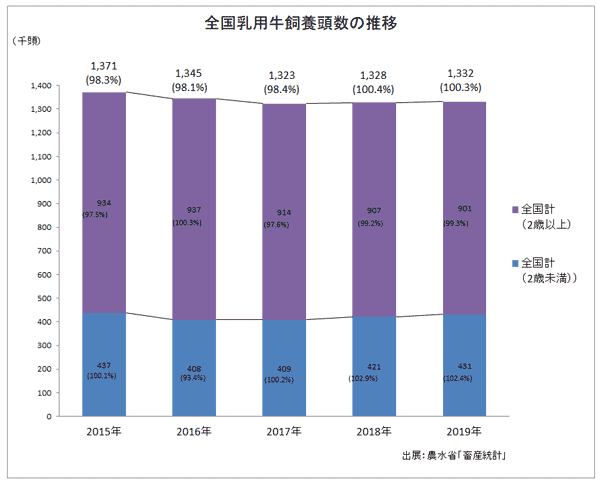 図1 全乳用牛飼養頭数の推移
図1 全乳用牛飼養頭数の推移
一方、需要については、今年4月から飲用向け乳価改定にともなう牛乳等の小売価格が改定されましたが、今のところ心配された需要の大幅な減少は見られません。このような状況の中、飲用の最需要期、特に9月に向けては、例年どおりしっかりと対応していくことが大事です。また、乳製品についてはここ数年、関係者が、節目節目で対外的にアナウンスをしたうえで、国がバターや脱脂粉乳の輸入を実施していることから、需給は安定的に推移しています。ただし、品目によっては、国産への要望が強いことや、一昨年よりヨーグルト需要が前年割れとなるなど、用途によっても差がありますので今後の動向に注視する必要があります。
ー酪農を取り巻く主な課題についてお聞かせください。
都府県の生産基盤の維持・拡大が大きな課題となっております。生乳生産量は北海道では少しずつ伸び続けて、令和元年は400万tの大台に乗る見通しです。一方、都府県は前年比2%程度のマイナスが続いており令和元年も前年比98.6%の見込みとなっております。
我々の業務の一つに北海道広域生乳(以下、道外向生乳という)による需給調整があります。9月を中心に夏場は、都府県の生産量では飲用向需要量を全てカバーすることができないため、道外向生乳を増量することで需給調整を行っております。近年は、都府県の生乳生産が漸減傾向となる一方、飲用向需要は堅調に推移しているため、その不足分を道外向生乳の増加により対応している状況です。
このような環境下、昨年9月には、北海道で胆振東部地震、その後の道内ブラックアウトが発生しました。出荷工場の停電などにより、道外向生乳が満度に届けられない状況となり、結果的に、都府県では、店頭で一時的に牛乳が品薄となる状況となりました。我々は、被災者でもあったホクレンをはじめ全国の指定団体や乳業の協力を得ながら、特定の地域や取引先での決定的な不足を回避できたと考えております。
ここ数年、自然災害が頻発する中、都府県の飲用需要を守るためにも、北海道だけに頼ることなく、都府県の生産基盤を維持・拡大していくということが大変重要であると考えております。
ー生乳生産・流通の特徴と生乳流通制度改革への対応について改めて聞かせてください。
生乳流通制度の見直しがおこなわれ、今年で2年目を迎えました。
生乳は、初期投資が多額な上に、牛が生乳を搾れるまで約3年かかり、毎日生産され腐敗しやすく貯蔵性が極端に低い品目特性のため、一戸一戸の酪農家は乳業者との取引上、非常に弱い立場となります。国は、昭和41年に指定団体制度を作り生乳の出荷先を指定団体に集める共同販売をすることにより、(1)価格交渉力の強化、(2)集送乳の合理化、(3)需給調整力の強化などを図り、酪農を発展させてきました。
当初、指定団体は、都道府県に1つずつでしたが、平成12年頃に広域化され全国に10団体となり、酪農家の手取り乳代である総合乳価が上昇しています(図2)。
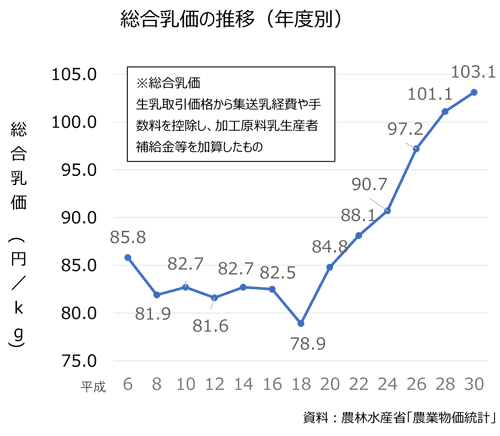
図2 総合乳価の推移(年度別)
ちなみにイギリスでは共販体制が崩壊し生産者と流通、乳業メーカーが直接取引するようになって結果として競争が激しくなり、交渉力が弱くなり酪農家の手取りが減少したと聞いております。
昨年4月に、生乳等の需給や酪農経営安定を図ることを目的に改正畜安法が施行されましたが、生乳を取り扱う新たな事業者や指定団体以外への出荷や部分委託をする生産者が出ております。このような動きは、結果的に市場での過当競争やいいとこ取りにつながる可能性があるため、我々としては、指定団体へ出荷している生産者の不利益とならないように対応していく必要があり、中央酪農会議や指定団体とともに取り組んでいきたいと考えています。
ーそれではJA全農酪農部としての今年度のおもな取り組みについてお願いします。
従来からの需給調整機能を強化していく必要があると考えています。指定団体が実施する需給調整を補完することにより、乳業者との広域流通生乳の取引を通じて、市場が混乱しないように取り組んでおりますが、ドライバー不足など日々厳しくなる物流環境下においても、指定団体や全農物流と連携して、例えば、ホクレンのタンク大型化への対応や都府県の集送乳合理化に取り組むことで生産者への負担とならないよう対応を進めております。
また、生産基盤対策では北海道の乳用初妊牛の購買事業を行っています。都府県の生産者が自分で後継牛を育てられない、あるいは規模拡大したいという時に北海道の牛を供給する事業で、北海道に常駐している選畜の専門家が都府県の注文に応えています。また、Jミルクの輸入牛事業を積極的に活用した取り組みも行っています。
その他、酪農経営体験発表会や、2015年からは日本コカ・コーラと共同で女性の活躍と自立を促進する5by20プロジェクト活動の取り組みも行っています。この活動は、農業高校などで酪農についての理解醸成を図り、酪農に関わる仕事に就職してもらえるような働きかけです。地道ですがこうした理解醸成活動にも取り組んでおります。また、乳業者と連携して「農協牛乳」を通して牛乳の価値向上への取り組みや、将来的な需要の確保・国産牛乳乳製品の価値を普及させるための乳製品の輸出などにも取り組んでおります。
こうした取り組みを通じて、酪農生産者が安心して生産し続けることができ、国内の酪農生産基盤の維持・拡大に貢献していきたいと考えています。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日
シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -
 農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日
農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -
 【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日
【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -
 【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日
【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -
 (474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日
(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -
 和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日
和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -
 築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日
築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -
 幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日
幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -
 「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日
「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -
 大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日
大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -
 築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日
築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -
 栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日
栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -
 秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日
秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -
 農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日
農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -
 日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日
日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -
 中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日
中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -
 持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日
持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -
 札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日
札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -
 高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日
高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日









































































