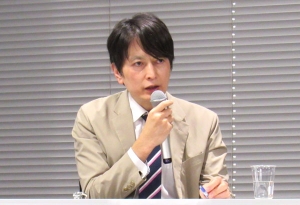地域と共に歩みつづける企業経営 地域資源を生かした新たな価値創造 大和川酒造店9代目当主佐藤彌右衛門 全中オンラインJA経営者セミナー2023年11月9日
JA全中は11月2日、今年度5回目のオンラインによるJA経営者セミナーを開き、福島県喜多方市・大和川酒造店の佐藤彌右衛門(やうえもん)9代目当主と、静岡県立大学経営情報学部の落合康裕教授が対談した。佐藤氏は、本業のみならず、酒造りをベースに稲作や自然エネルギー創生など地域循環事業を手がけ、地域に雇用を創出している。
足元をみよ
帝国データバンクによると、日本で100年以上続いている企業は約4万社。業種としては酒造業が最も多く、旅館業、和菓子業が続く。落合教授は、これらの企業が長続きする理由について、「地域資源の存在」と「地域資源を生かす力」の2点を指摘した。
 大和川酒造店の佐藤彌右衛門氏
大和川酒造店の佐藤彌右衛門氏
大和川酒造店は1790年創業で、まさにそうした老舗企業の一つだ。落合教授の「大和川酒造店では地域資源をどう発見してきたのか」という問いに対し、佐藤氏は、「足元をみる」ことだと答えた。
大和川酒造店のある喜多方市は、福島県の会津盆地に位置する。昼夜の寒暖差が米・麦・大豆を安定的に実らせ、飯豊連峰に降った雪は伏流水となり、周辺の山野の樹木は燃料となった。「食料・水・エネルギー」が揃っており、昭和前半ごろまでは自給自足の生活を営むことができた。
「足元をみる」というのは、東京電力福島第1原子力発電所の事故を契機に親交ができた民俗学者の赤坂憲雄氏の言葉。近くから入手できる四季折々のものを活用する術を、祖先から受け継いできた。酒屋は昔から「他所から何も持ってこなくてもいい」と言われており、米や麹菌など原材料やエネルギーもすべて地元にあるもので完結する。つまり、「地域の価値」は当たり前のように目の前にある、ということだ。
自らの手で、つくる、守る
では、その価値をどう生かしているのか。佐藤氏は、家業を営む傍ら「会津電力」を立ち上げ、地元エネルギー自給率の向上を図っている。
日本は、エネルギーの主流が石油になって、海外への依存から抜け出せなくなってきた。資源が乏しいため原子力政策に舵を切ったが、原発の「安心・安全」神話は、東京電力福島第1原子力発電所のメルトダウンで崩壊し、周辺住民に全村避難を強いた。
事故現場から直線距離で100㌔以上離れている会津地方でも、避難を余儀なくされるのかと不安におびえた。佐藤氏は、「長い歴史で培った風土や文化が奪われるような恐怖感と、先祖から受け継いできた資産を、子孫に引き継げないという危機感があった」と話す。
エネルギーを国や海外に依存していては地域の資産を守ることができない――。そう考えた佐藤氏は、自分たちで使うエネルギーの創出を考えた。
太陽光、風力、水力、木質バイオマスなど、再生可能エネルギーでの小規模発電であれば、「足元」にある資源で賄える。発電や再生可能エネルギーの動向をドイツやデンマークからも学んだ佐藤氏は、経済産業省の補助金に加え、地元自治体や企業・金融機関、個人からも広く出資を集め、2013年に会津電力を設立することができた。同社グループ全体で、約90カ所になる発電所の発電量は6000㌗余にのぼり、地域のエネルギー供給元となっている。土地の資産を守ることが、結果的に地域の価値の向上につながった。
本業の酒造業のほか、酒造りの原料を得るための農業や電力事業など、佐藤氏が手がける事業に多くの人が集まる。同県郡山市出身でIT企業の「クアルコムジャパン」で社長を務めていた山田純氏は、エネルギーの地産地消というアイディアに賛同し、現在、会津電力の取締役会長を務める。山田氏は、耕作放棄地でブドウを育て、ラーメン工場の跡地でワイナリーの運営にも乗り出した。「やりたいことを実現できる場を用意することで、人が集まってくる」と佐藤氏は言う。
先人の教え、次世代へ
佐藤氏の祖父にあたる7代目の口癖は「財産は3つに分けろ」だった。一つ目は「土地・建物」で、最低限自分のすみかなどを準備しておくこと。二つ目は「現金」で、事業の運転資金や生活費など、当座の資金を手元に置くこと。三つ目は「信用」で、お金を払っても得られるものではないと言って聞かされた。
地元の人たちは佐藤氏の「先代、先々代の地域活動から恩恵を受けた」と、佐藤氏自身の功績のように信頼を寄せてくれる。信用という財産は末代まで引き継がれることを実感したという。
高度成長が終わり、高齢化と人口減少という社会の構造問題に直面する日本で、右肩上がりの成長は期待できない。その中で、経営者の人材育成について落合教授に問われた佐藤氏は、「環境」をキーワードに挙げた。
とくに東日本大震災後、SDGsに敏感な若者が増えた。酒造業は、酒造りの工程で搾りかすなどの大量の残滓(ざんし)がでるが、大和川酒造店では、酒粕は甘酒や粕漬けに、ぬかは飼料などに転用するため、廃棄物がほとんどでない。残滓を資源として活用することを「おさめる」と呼び、循環するシステムを構築している。佐藤氏は、この「おさめる」システムを他の企業でも取り入れていけば、若者の関心が高まり、経営者候補として育っていくのではと期待を寄せる。
地域資源を守るために必要なのは「やる気」と「不易流行」。いつまでも変わらない本質を守りながら、変わるものを受け入れる姿勢だ。大量生産・大量消費の時代は終わり、身の丈にあった量を生産、消費しながら、非常時のための最低限の備蓄を怠らないようにすることが大事だと佐藤は強調した。
セミナーの最後、司会者から「学生時代に上京し、家業を継ぐために戻った故郷の景色はどう見えたか」という問いかけに、佐藤氏は「当時の東京は学生運動が盛んで、三島由紀夫の割腹自殺、光化学スモッグによる公害や交通事故死者が数万人にのぼるような状態で、混沌としていた」と振り返りつつ、「故郷に戻ると、飯も、味噌汁も、漬物もうまい。故郷は輝いて見えた」と顔をほころばせた。
重要な記事
最新の記事
-
 百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日
百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日 -
 将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日
将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日 -
 【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日
【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日 -
 【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日
【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日 -
 【GREEN×EXPOのキーパーソン】グリーンを活用したイノベーションへ 東邦レオ・小山田哉氏2026年2月12日
【GREEN×EXPOのキーパーソン】グリーンを活用したイノベーションへ 東邦レオ・小山田哉氏2026年2月12日 -
 アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日
アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日 -
 振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日
振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日 -
 愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日
愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日 -
 葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日
葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日 -
 「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日
「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日 -
 初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日
初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日 -
 【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日
【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日 -
 農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日
農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日 -
 食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日
食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日 -
 まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日
まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日 -
 クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日
クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日 -
 「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日
「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日 -
 邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日
邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日 -
 藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日
藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日 -
 東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日
東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日