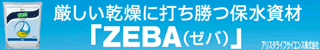【農協研究会】准組合員問題にJAはどう向き合うか?2025年11月17日
農業協同組合研究会(会長:谷口信和東大名誉教授)は11月15日、農協協会の「サロンJAcom」で「准組合員問題にJAはどう正面から向き合うか」をテーマに2025年度研究会を開いた。
 農業協同組合研究会
農業協同組合研究会
食料安保と准組合員
研究会ではJA松本ハイランドの田中均組合長が准組合員問題について「その経緯・重要性・今後の解決策」と題して「解題」を行った。
2015年の政府の「農協改革」では「中央会制度の廃止」か、「准組合員の事業利用規制」か、の二者択一を迫られ、JAグループは「中央会制度の廃止」を差し出し、一方、准組合員の利用規制問題は5年の経過措置の後、棚上げされたかたちとなっている。
ただ、2021年の政府の規制改革実施計画には、JAの自己改革実施状況を農水省が指導・監督することが盛り込まれ、さらに「准組合員の意思反映」を求めた。具体的に反映すべき事項が明示されたわけではないが、自己改革のPDCAサイクルのなかで、准組合員の意思反映に取り組まざるを得なくなった状況にあると田中氏は指摘する。
これまでは員外利用制限をクリアするために准組合員制度を利用してきた面があるが、実際に准組合員が増え続けるなか、准組合員問題へのJAの取り組みが求められるようになっており、各JAが共有すべき課題となっている。
ただ、准組合員の意思を反映するといっても、農業振興に関わること以外の意思を反映すれば「JAはJAでない組織に変質していく」。一方、准組合員を地域農業の「応援団」と位置づける考え方をJA全国大会決議などでJAグループは打ち出しているが、田中氏は「准組合員自身も多くは金融商品利用など便宜的に准組合員になっただけで、農業振興に貢献するという意識はない」と指摘した。
つまり、准組合員の声を聞こうといっても「なんとなく意見を聞く」レベルにとどまっており、「准組合員制度は農業振興のためにある」という理論武装と実績づくりに欠けていたと課題を提起した。
そのうえで課題を解決するには、農業者だけでは農業を守れない時代になっていることを踏まえ、食料の安定供給のためには農業を消費者も含めた広い国民的な関心事にすることが求められおり、准組合員の農協事業利用は食料安全保障の確保に資する、と整理することを提起した。
准組合員も生産組合加入
事例報告は神奈川県のJAはだのと千葉県のJAいちかわが行った。
JAはだのは、正・准組合員一体となったJA運営を実践している。准組合員も集落組織の基礎組織である生産部会に加入し、正組合員とともに地域の協同活動に取り組んでいる。総会や集落での座談会などに准組合員の参加が多いのは正・准一体での地域組織の運営のためだと宮永均組合長は話す。
また、農業者だけでなく多様な地域住民の参加によって地産地消を進め、自給率向上を図っている。とくに非農業者が本格就農をめざす「はだの市民農業塾」は2006年からこれまでに100人以上が研修を受け、90人が新規就農している。新規就農者の経営面積は約20haとなっており、野菜づくりで年収1000万円を超す人もいるという。
こうした新規就農者は准組合員から正組合員となっているが、そのほかにも農家が特定農地貸付事業による農園での栽培や、体験農園などで准組合員も農業の担い手となっている。宮永組合長は市内の農地を「一農場」と捉え、「みんなでコモンズを盛り上げようと考えている」と話す。
准組合員拡大運動を推進
JAいちかわでは、准組合員の拡大運動に取り組んでいる。2022年からの3年間で5000人の加入目標を立てた。結果は初年度で4800人に達し、3年間では8000人を超えた。
拡大運動にあたって今野博之組合長は職員に対して、管内の多くの消費者に地域農業振興の応援団として総合事業利用と協同活動へ参画してもらうことが「質の高い自己資本」の獲得につながると強調した。来店者への働きかけだではなく、JA祭りなどのイベントも准組合員拡大の機会としている。
同時に准組合員への還元、新たなサービス提供にも力を入れている。JA役職員とその家族を対象に、がん医療コーディネーターによる医師紹介など相談事業を始めたが、これを正組合員と准組合員にも提供していく。昨年は「准組合員の集い」を開催した。
また、自然災害に備えて災害用井戸の設置を進め、昨年は本店に県内JAで初めて設置し、その後、支点にも広げている。災害時にJAが水と農産物を提供する拠点となることを准組合員、地域住民に示すことでJAは「相互扶助の精神」の組織であることへの理解も広めようとしている。
准組合員向けの広報誌を年3回発行している。今野組合長は、JAにも時代の波を的確に捉え、新たなビジネスモデルを構築するイノベーションが求められていると強調した。
討論では都市的地域だけでなく、農村部でも准組合員が増えている実態があるが、同時にそれは地域住民への農産物提供など、農業の貴重な価値を提供することにつながるほか、地域のインフラとしてのJAの役割を地域理解してもらう機会にすべきなどの議論があった。
一方では金融商品の利用などで准組合員になった場合は、ローン返済が終わればJAから離れるなど、組合員資格を維持するために、情報発信や教育活動、子どもを対象にした農業体験などの仕掛けも必要だと強調された。
また、女性部組織はそもそも食と農に関心を持つ女性であれば加入できることになっており、准組合員をJAの事業運営にどう役割発揮してもらうかの参考にすべきとの指摘もあった。
その一方で、准組合員を「農業振興の応援団」と位置づけることについては、JA側から一方的に「応援席にいてください」と役割を割り振っているのではないかとの意見もあり、今後ともその役割について議論が必要な時期に来ているとする議論もなされた。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(176)食料・農業・農村基本計画(18)国民一人一人の食料安全保障・持続的な食料システム2026年1月17日
シンとんぼ(176)食料・農業・農村基本計画(18)国民一人一人の食料安全保障・持続的な食料システム2026年1月17日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(93)キノキサリン(求電子系)【防除学習帖】第332回2026年1月17日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(93)キノキサリン(求電子系)【防除学習帖】第332回2026年1月17日 -
 農薬の正しい使い方(66)植物色素の生成阻害タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第332回2026年1月17日
農薬の正しい使い方(66)植物色素の生成阻害タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第332回2026年1月17日 -
 【地域を診る】能登半島地震から2年 復興法人制度活用の提案 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年1月16日
【地域を診る】能登半島地震から2年 復興法人制度活用の提案 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年1月16日 -
 スーパーの米価、2週ぶりに低下 前週から149円下がり5kg4267円に 米からパン、めん類にシフトか2026年1月16日
スーパーの米価、2週ぶりに低下 前週から149円下がり5kg4267円に 米からパン、めん類にシフトか2026年1月16日 -
 「2026年 ISEKI Global Awards」開催 井関農機2026年1月16日
「2026年 ISEKI Global Awards」開催 井関農機2026年1月16日 -
 近づく限界、米価に暴落懸念 「2014年の再来」防げるか2026年1月16日
近づく限界、米価に暴落懸念 「2014年の再来」防げるか2026年1月16日 -
 (469)なぜタイのエビは主役ではなくなったのか?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月16日
(469)なぜタイのエビは主役ではなくなったのか?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月16日 -
 岩手県の直営飲食店舗で「いわての牛乳ありがとうフェア」20日から開催 JA全農2026年1月16日
岩手県の直営飲食店舗で「いわての牛乳ありがとうフェア」20日から開催 JA全農2026年1月16日 -
 縁起が良い赤い食べ物「冬土用未(ひつじ)の日フェア」17日から開催 JA全農2026年1月16日
縁起が良い赤い食べ物「冬土用未(ひつじ)の日フェア」17日から開催 JA全農2026年1月16日 -
 バッテリー診断・価値向上によるEVコンバージョントラック普及へ 共同実証開始 JA三井リースグループ2026年1月16日
バッテリー診断・価値向上によるEVコンバージョントラック普及へ 共同実証開始 JA三井リースグループ2026年1月16日 -
 日本の蚕糸 消滅していいの? 3月にフォーラム開催 大日本蚕糸会2026年1月16日
日本の蚕糸 消滅していいの? 3月にフォーラム開催 大日本蚕糸会2026年1月16日 -
 【浅野純次・読書の楽しみ】第117回2026年1月16日
【浅野純次・読書の楽しみ】第117回2026年1月16日 -
 「花・緑ガイドボランティア」募集200人に3493人が応募 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月16日
「花・緑ガイドボランティア」募集200人に3493人が応募 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月16日 -
 トラクタ「JAPANシリーズ」BJ65・74・90・105を新発売 無段変速ミッション搭載で2026年6月投入 井関農機2026年1月16日
トラクタ「JAPANシリーズ」BJ65・74・90・105を新発売 無段変速ミッション搭載で2026年6月投入 井関農機2026年1月16日 -
 北海道の暮らしと仕事セミナー「一次産業(農業・林業・水産)のお仕事編」開催2026年1月16日
北海道の暮らしと仕事セミナー「一次産業(農業・林業・水産)のお仕事編」開催2026年1月16日 -
 防災力アップ体験イベント「もしもFES大阪2026」3月に開催 こくみん共済 coop2026年1月16日
防災力アップ体験イベント「もしもFES大阪2026」3月に開催 こくみん共済 coop2026年1月16日 -
 推しいちごに投票「天下分け目のいちご戦国時代2026」開催 食べチョク2026年1月16日
推しいちごに投票「天下分け目のいちご戦国時代2026」開催 食べチョク2026年1月16日 -
 フルーツ王国ふくしま「ゆうやけベリー・県産いちご」フェア開催 福島県2026年1月16日
フルーツ王国ふくしま「ゆうやけベリー・県産いちご」フェア開催 福島県2026年1月16日 -
 「いちごさんどう2026」開幕 相武紗季をゲストに迎え発表会 佐賀県2026年1月16日
「いちごさんどう2026」開幕 相武紗季をゲストに迎え発表会 佐賀県2026年1月16日