JAの活動:日本農業の未来を創る JAの課題
【紀ノ川農協と生協おおさかパルコープの連携】生・消ともに地域農業再建2013年7月26日
・「一株トマト」を第一歩に
・調査で農家の実態把握
・有機農業に生協が共鳴
・農の現場知ってもらう
和歌山県の紀ノ川農協は販売に特化した農協である。効率化のスローガンのもとで広域合併を進めて大型化してきた全国のJAと真逆で、県下一円を対象にした専門農協の路線を歩み、地域の農業とくらしを守る活動を展開してきた。事業の中心は農協設立以来40年の歴史を持つ産直事業だ。生協など消費者との連携で育った紀ノ川農協の取り組みは、協同組合の将来のひとつのあり方を示唆している。
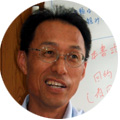 紀ノ川農協のある紀の川市は、県北部を流れる紀ノ川沿いにあり、温暖な気候と肥沃な沖積平野を生かしたかんきつ、野菜の農業地帯だ。ここに紀ノ川農協が誕生したのは1983年。歴史は浅いが今日までの取り組みは、ころころ変わる農政に振り回されながらも生協・消費者と連携して地域と農業を守り、安全で安心な農産物の生産に取り組んできた歴史がある。
紀ノ川農協のある紀の川市は、県北部を流れる紀ノ川沿いにあり、温暖な気候と肥沃な沖積平野を生かしたかんきつ、野菜の農業地帯だ。ここに紀ノ川農協が誕生したのは1983年。歴史は浅いが今日までの取り組みは、ころころ変わる農政に振り回されながらも生協・消費者と連携して地域と農業を守り、安全で安心な農産物の生産に取り組んできた歴史がある。
農協設立の背景には、1972年グレープフルーツの輸入自由化や豊作などによるミカン価格の大暴落がある。そのとき、安さに耐え兼ね、当時の那賀町農協青年部が独自販売の検討を始めた。この時の中核メンバーが農協の共販から抜けて、76年に農民組合を結成して産直を始めた。
当時、組合員は16人ほど。取引先開拓のため“行商”から始め、売り先を拡大していった。5年後、和歌山県農民組合産直センターを設立。これが1983年、販売事業を専門とする紀ノ川農協になった。当時の組合員は377人。その翌年、総会で定款を改定し、組合の地区を県下全域とした。2013年3月末現在の組合員は925人である(准組合員25人)。
(写真)
宇田篤弘・紀ノ川組合長
◆「一株トマト」を第一歩に
 スタート時、生協との産直は順調だった。特に84年から始めた予約注文の「一株トマト」は、一株からとれる4?5kgの完熟に近いトマトを6?8週にかけて配達。「おいしい」という評価を受けて、現在、注文数はおおさかパルコープ、よどがわ生協合せて10万3000件に達する。だが事業が順調だったのは1990年ごろまで。その後バブル経済の崩壊、80年代末からのミカンの減反などの影響で事業量が伸びず、脱退する組合員も出てきた。産直先である生協の事業が伸び悩み、産地の生産も止まってしまったのである。
スタート時、生協との産直は順調だった。特に84年から始めた予約注文の「一株トマト」は、一株からとれる4?5kgの完熟に近いトマトを6?8週にかけて配達。「おいしい」という評価を受けて、現在、注文数はおおさかパルコープ、よどがわ生協合せて10万3000件に達する。だが事業が順調だったのは1990年ごろまで。その後バブル経済の崩壊、80年代末からのミカンの減反などの影響で事業量が伸びず、脱退する組合員も出てきた。産直先である生協の事業が伸び悩み、産地の生産も止まってしまったのである。
これを切り抜けるため、多様な販売チャンネルの開拓に転換。農協の事務所前で95年から「日曜市」を始め、これが今、1億3000万円を売りあげる「ファーマーズマーケット紀ノ川 ふうの丘」になった。野菜ボックスやスーパーのインショップなど、生協との共同購入依存型の販売体制からの脱却を目指した。
(写真)
「一株トマト」“株主”の家族との交流会
◆調査で農家の実態把握
こうした新しい取り組みだけでなく、90年代初めのバブル崩壊は紀ノ川農協の運営にとって大きな転機になった。宇田篤弘組合長は「当時、生協産直が順調で、みんな産直の“閉鎖ロマン”に陥って保守化していた。おごりがあったのかもしれない」と振り返る。この反省のもとに取り組んだのが、組合員の状態と要求をつかむための地域調査である。
農家一軒一軒、ノートと鉛筆を持って聞き取り調査した。「われわれが、地域や農家のことを感動を持って受け止められるかどうかが重要。アンケートや数字では分からない発見が多くあった」と言う。調査結果をもとに討議するなかから得た確信は、「地域経済を再建していく中でしか農家の経営とくらしを守ることはできず、地域農業の発展のなかでしか、紀ノ川農協の発展はない」ということだった。この考えをベースにして、いまの紀ノ川農協の事業がある。生協との連携、環境保全型農業、新規就農・担い手の育成などに取り組んだが、特に地域農業を再建するうえで導入した有機農業は大きな転機になった。
ミカンが暴落し、事業も伸び悩んでいた93年に有機農業をすすめる会を発足させ、行政、農業委員会、農協などとともに、95年、那賀町「有機農業の町づくり宣言」し、地域ぐるみの農業再建の体制をつくった。エコファーマー・特別栽培・JAS有機の認証取得を勧め、2011年度の特別栽培農産物の認証は、188人が取得し、いま有機キウイフルーツの生産量は全国トップクラスにある。GAP(適正農業規範)も導入した。
◆有機農業に生協が共鳴
 有機農業を中心とする環境保全型農業に取り組む農協の動きに、事業量の伸び悩みから生協らしい事業を求めていた生協が応えた。現在、メイン取引先の生協おおさかパルコープの商品統括担当の栖村藤夫常勤理事は、「地理的に近い紀伊半島を大消費地である大阪の食料基地として位置付けている。組合員に提供するものは低価格が全てではない。おいしい農産物を安定して組合員に提供できる産地との取引を求めていた。単なるサプライチェーンとしてではなく、地域単位の経済規模で地産地消の関係をつくり、お互いの気付き、発見を大切にして、お金を域内で回す仕組みづくりが必要だ。紀ノ川農協とはこうした議論ができ、新しい関係がつくれると思った」という。紀の川市は地理的にも紀伊半島の入口にあるが、生協・農協間提携の入口にもなった。
有機農業を中心とする環境保全型農業に取り組む農協の動きに、事業量の伸び悩みから生協らしい事業を求めていた生協が応えた。現在、メイン取引先の生協おおさかパルコープの商品統括担当の栖村藤夫常勤理事は、「地理的に近い紀伊半島を大消費地である大阪の食料基地として位置付けている。組合員に提供するものは低価格が全てではない。おいしい農産物を安定して組合員に提供できる産地との取引を求めていた。単なるサプライチェーンとしてではなく、地域単位の経済規模で地産地消の関係をつくり、お互いの気付き、発見を大切にして、お金を域内で回す仕組みづくりが必要だ。紀ノ川農協とはこうした議論ができ、新しい関係がつくれると思った」という。紀の川市は地理的にも紀伊半島の入口にあるが、生協・農協間提携の入口にもなった。
この考えは生協、農協で共有されており、組合員を中心とした相互交流が活発だ。年間、収穫体験に参加する生協の組合員は400人余り。おおさかパルコープの組合員活動委員などと紀ノ川農協の青年部、新規就農者、若手理事など相互に訪問しながらの意見交換、店舗農産担当スタッフの産地見学、生産者による店頭販売など、さまざまな交流が定着している。
(写真)
遊休農地を整備してトウモロコシ定植作業を指導
◆農の現場知ってもらう
 「生産と消費が分断されている今日、このままでは将来、子どもたちはいいものが食えなくなるおそれがある。産地のいいところだけでなく、農業・農村の実態を学び、認識を共有することが重要だ」と栖村理事は指摘。また宇田組合長も「農村はくらしの場である。なにもかもビジネスにしてほしくない。効率でなく生きていくために協同しているのであって、このことを知ってもらいたい」という。交流を単なるイベントにせず、紀ノ川農協の取り組みや地域のことを学習する機会をつくるようにしている。
「生産と消費が分断されている今日、このままでは将来、子どもたちはいいものが食えなくなるおそれがある。産地のいいところだけでなく、農業・農村の実態を学び、認識を共有することが重要だ」と栖村理事は指摘。また宇田組合長も「農村はくらしの場である。なにもかもビジネスにしてほしくない。効率でなく生きていくために協同しているのであって、このことを知ってもらいたい」という。交流を単なるイベントにせず、紀ノ川農協の取り組みや地域のことを学習する機会をつくるようにしている。
1980年代から産直に取り組み、今日のおおさかパルコープの産直に基礎をつくった藤永延代理事は、産直の意義を「消費者は生産者の生活に責任を持つ。生産者は消費者の健康に責任を持つことだ」と言う。紀ノ川農協と生協の産直は、モノの取引に終わらず、生産者の農業とくらし、消費者のくらしと健康を守る運動に進化した。おおさかパルコープは約37万人の組合員で、供給高約500億円。対する紀ノ川農協は900人余りの組合員で、売上高は約18億円。規模の差は歴然だが、おおさかパルコープにとっても、食と農の大切さを学ぶ上で欠かせないパートナーだ。
(写真)
地域とのつながり深める収穫祭
【特集 日本農業の未来を創る 多様な現場から考えるJAの課題】
・【JA愛知県厚生連足助病院】「生き方」が地域をつくる (13.07.26)
・全国のJA流通ネットワークを 産地連携でグローバル化に対抗 (13.07.26)
重要な記事
最新の記事
-
 事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日
事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日 -
 高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日
高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -
 朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日
朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -
 水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日
水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -
 とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日
とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -
 米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日
米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -
 農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日
農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -
 地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日
地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -
 黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日
黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -
 道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日
道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -
 北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日
北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -
 氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日
氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -
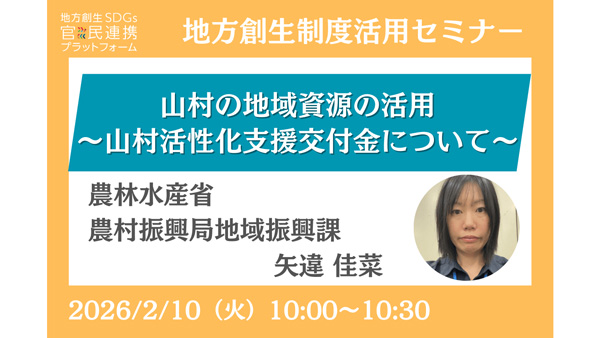 「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日
「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -
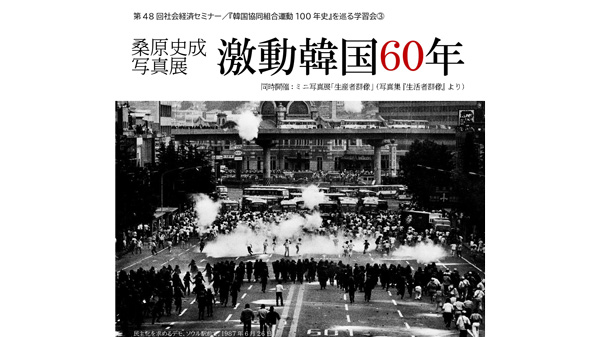 「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日
「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -
 日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日
日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -
 畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日
畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -
 大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日
大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -
 首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日
首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -
 原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日
原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -
 岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日
岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日




































































