JAの活動:今こそ農業界の事業承継を
事業承継は「農業界」最大のテーマ JA全農2018年2月27日
全農では、事業承継を農業界の最重要課題として捉え、「事業承継ブック」を作成するなど課題解決に向けた取り組みを着実に進めており、それは全国に広がりつつある。しかしながら、まだまだ農業者(経営者世代、後継者世代双方)や農業関係者の理解は十分ではなく取り組みが浸透しているとは言い難い。そこでこの特集紙を作成し、事業承継の重要性・必要性を啓発することで、農業界全体の取り組みにつなげたい。
○いますぐ始めよう!
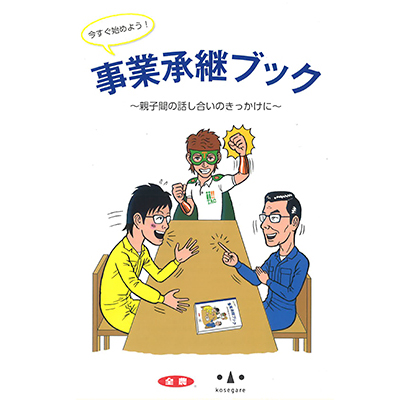 農業界に限らず、事業を営む全ての経営体は、事業を「継ぐ(承継)」か「売る(売却)」か「たたむ(廃業)」の3つの選択肢を選ぶしかない。これは、家族経営でも、法人経営でも、集落営農でも全て同じだ。昨年2017年は、団塊の世代(1947~49年生まれ)が70歳を迎え、2025年には全員が75歳を超える。「いつか」「そのうち」「まだ大丈夫」と先延ばしにしていた判断を、いよいよしなければならない時が確実にやってくる。決断をし、5~10年かかると言われる事業承継を今すぐに始めなければ、事業を後世につないでいくことは出来ない。大量離農時代が目の前に来ており、事業承継は待ったなしの状況だ。
農業界に限らず、事業を営む全ての経営体は、事業を「継ぐ(承継)」か「売る(売却)」か「たたむ(廃業)」の3つの選択肢を選ぶしかない。これは、家族経営でも、法人経営でも、集落営農でも全て同じだ。昨年2017年は、団塊の世代(1947~49年生まれ)が70歳を迎え、2025年には全員が75歳を超える。「いつか」「そのうち」「まだ大丈夫」と先延ばしにしていた判断を、いよいよしなければならない時が確実にやってくる。決断をし、5~10年かかると言われる事業承継を今すぐに始めなければ、事業を後世につないでいくことは出来ない。大量離農時代が目の前に来ており、事業承継は待ったなしの状況だ。
○広がらない農業界の現状
農林業センサス2015によれば販売農家戸数は133万戸だが、そのうち後継者がいるのは過半数割れの65万戸(49%)となっており、確実にその農家での事業承継を進めていくことが重要であるし、後継者不在農家については、その経営を誰にどうやって引き継いでいくのか、あるいは処分していくのかの結論を出さなければならない。
また、後継者がいると回答していても、同居後継者の従事日数0日が7万戸(18%)、1~29日が16万戸(41%)、非同居後継者が25万戸(19%)であり、本当に後継者になりえるかは不透明である。
更に農業法人の経営体数は増加しているものの政府目標には及んでいないし農の雇用事業の離職率は4割にもなる。集落営農数は横ばいで法人化は進んでいるとはいえ、解散するところも出てきており後継者不在が本質的な課題だ。
事態は本当に深刻であるが、事業承継に関する具体的な取り組みは広がりを見せていない。
○全国の経営者世代、後継者世代の声
全国の経営者世代からは、「わしはまだ元気で、代を譲るなんて話はもってのほかだ」「そろそろ継がせたいとは思うが、子供はその気があるのかどうかわからない」「親としては農業よりもサラリーマンの方が安定していて安心できるが...」「知識も経験もまだまだで、栽培のこともわかっていないのに息子は販売ばかり力を入れていて、けしからん」と言った声を多く聴く。
また、後継者世代からは「いつか継がなければいけないとは思うけど、正直...」「継ぐとは言ってるけど、何からすればよいのかわからん」「新たな品目に取り組みたいけど、親父がダメだとうるさい」「あれもこれもそれも全部親父が口出ししてきて、うざったい」「だけど、親父にはかなわない」「社長がいなくなったら、うちの農業は成り立つのかな」といった声が寄せられ、世代間のジェネレーションギャップも当然あり、どの経営体でも大なり小なり揉めるのは必至なのではないだろうか。TPPや農業改革などに関係なく、世代間の意識の共有が事業承継における最大のポイントになるのではないだろうか。簡単に見えるが、ここが最も難しいのかもしれない。
○キーワードは「向き合う」こと
継ぐ・継がないということを決断するということは、たやすいことではない。自分の人生設計はもちろん、結婚や出産・子育て、介護など家族のことも考えなければならない。更には人口減少や空き家増加など地域の社会課題にも目を向けざるを得ない。今まで目を背けていたことや判断を先送りしてきたことに「向き合う」ことが必要になってくる。その向き合うきっかけがあれば、事業承継は進む可能性が高い。
そして、向き合った結果であれば、「継がない」という選択肢は尊重したい。農家の子弟だからといって農業経営者として適任かどうかはわからないし、農業以外で活躍できる場があれば、そこに人生をかけることは良いことではないか。
とにかく「向き合う」こと。その機会を作ること。その中で経営者世代と後継者世代が合意形成をして、一つひとつの物事を決めていくことが大切なのではないか。
○事業承継ブックの活用を!
自らも事業承継の課題に直面する全農職員が、全国のJA青年部や4Hクラブ員、農家出身全農職員ら100名以上の声を聴いて作成した「事業承継ブック」は、準備編と実践編の2段階構成となっている。準備編では「気持ちを伝えるシート」を活用し、日頃言えない思いや考えをしっかり伝える。実践編では、事業承継ステップに基づき取り組みを進めていけば、各経営体の実態を踏まえた事業承継計画を策定出来るようになっている。
事業承継は、「きっかけ」と「ツール」がないからこれまで進んでこなかったと思われるが、事業承継ブックを活用することで、その課題が解決されるのではないか。
事業の内容は、全農HPで公開されており、実際の冊子はJAへ相談すれば、全農から配布することとなっている。事業承継は、親子や親族だけで取り組むと、大なり小なり喧嘩になってしまい進まないことが往々にしてある。だからこそ、第三者(JAや普及指導員)のアドバイスを受けながら進めることが望ましいだろう。
(関連記事)
【特集・事業承継】の関連記事は「今こそ農業界の事業承継を」をご覧ください。
重要な記事
最新の記事
-
 【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日
【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -
 【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日
【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -
 (474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日
(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -
 和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日
和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -
 築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日
築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -
 幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日
幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -
 「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日
「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -
 大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日
大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -
 築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日
築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -
 栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日
栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -
 秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日
秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -
 農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日
農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -
 日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日
日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -
 中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日
中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -
 持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日
持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -
 札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日
札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -
 高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日
高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日 -
 高校生が森・川・海の「名人」を取材「第24回聞き書き甲子園」受賞者を決定2026年2月20日
高校生が森・川・海の「名人」を取材「第24回聞き書き甲子園」受賞者を決定2026年2月20日 -
 機能性表示食品「ことばうっかりサポート えごま油の力」新発売 J-オイルミルズ2026年2月20日
機能性表示食品「ことばうっかりサポート えごま油の力」新発売 J-オイルミルズ2026年2月20日 -
 おやつにぴったりな5種mix「亀田の柿の種 トレイルミックス」期間限定発売2026年2月20日
おやつにぴったりな5種mix「亀田の柿の種 トレイルミックス」期間限定発売2026年2月20日









































































