【寄稿】酪農・チーズが創造する多様な地域共生(1) 蔵王酪農センター理事長・冨士重夫氏2022年3月3日
酪農をめぐる厳しい環境の中、宮城県の蔵王酪農センターは、地域と共生しながら飼料作りから乳牛の育成、販売力の強化などに取り組んでいる。酪農が抱える課題の克服に地域とともにどう向き合ってきたのか。冨士重夫理事長に寄稿してもらった。
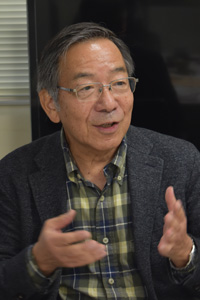 蔵王酪農センター理事長
蔵王酪農センター理事長
冨士重夫氏
(1)蔵王酪農センターとは何か
牛乳瓶で毎朝、各家庭に戸別に配達する飲用牛乳の仕組みを、テトラパックや1Lの紙パックでスーパー・量販店で売るという形で流通革命を引き起こし、「成分無調整、自然はおいしい、農協牛乳」というキャッチコピーを考案し、食品業界に意識改革をもたらし、「日本には各地に発酵文化があり、将来必ずナチュラルチーズの花が咲く」と説き、国産ナチュラルチーズの道を切り拓いた人物。われらの大先輩である、JA全中、初代専務理事となった山口巌氏が主導し、酪農家、JA、電気事業者が共同出資して1960年に、財団法人酪農電化センターが設立されました。
電化=機械化ということで、昭和30年代において将来の酪農を見通し、先進的な機械化酪農経営の実証農場としてスタートしました。
今は、一般財団法人蔵王酪農センターという名称となり、「電化」という文字は削除しましたが、台風や地震など災害のたびに、停電が発生し、搾乳機械が動かず、生乳の冷却ができず、牛乳工場、乳製品工場が稼働できず授乳できなくなり、結果、生乳の廃棄と乳房炎の乳牛の大量発生による減産といった事態に陥るのが酪農・乳業であり、まさに、電力は酪農・乳業にとって基本的なエネルギーとなっています。
この電力を自然の再生エネルギーによって、災害があっても確保でき、永続性のある安全でクリーンなものによって、地域ごとに各経営体ごとに担保して行くことは、重要な課題であり、将来再び、当センターの名称に「電気」が灯るかもしれません。
一般財団法人蔵王酪農センターは、宮城県の南部を地域とするJA仙南の正組合員であり。認定農業者です。また、みやぎの酪農協という専門農協の組合員でもあります。
「共存同栄」を経営理念として、協同組合的考え方によって事業運営を行っています。
現在の当センターの姿は、デイリーパイオニアセンターという酪農経営、キャトルセンターという哺育・育成経営、TMRセンターという総合飼料経営の3本柱による牧場事業と、ナチュラルチーズを中心とした乳製品の製造販売事業と、直売所やレストラン、体験館などを運営する観光事業といった、いわゆる6次産業化を展開している組織体となっています。
そして当センター最大の特長が人材育成事業です。研修施設を運営し、新規就農者やチーズ製造技術者、乳業関係社員、JA全国連など広範な人材の育成、研修事業を展開しています。
(2)飼料作りにおける地域共生事業
生乳10kg使ってチーズ1kgができ、9割は副産物としてホエー(乳清)です。チーズ製造において、このホエーの利活用、事業化がコスト・環境両面からみても極めて重要です。
大手乳業ではホエーを粉末にして、育児用粉乳の原料として使用していますが、小さなチーズ工房では、ほとんど排水処理しているのが実情です。
当センターではホエーと、飲料モルクや乳清ジャム、化粧品など様々な形で活用し、事業化して来ていますが、太宗は乳用牛飼料として牧草、配合飼料にホエーを入れてミキシングし、乳酸発酵させた総合混合飼料を当センターのTMRセンターで生産しています。
この発酵TMRは、当センターの酪農経営分だけでなく、蔵王町の酪農家7戸の牧草を各戸ごとに受け入れ、各酪農家ごとの仕様による独自の発酵飼料を作り供給して、乳牛の健康や乳量にも良いとされています。
現在、この発酵TMRの年間生産量は、当センター分が1500t、蔵王町酪農家分が2000tで、合計3500t程度となって来ており、ホエーの生産量、TMRセンターの施設能力から、最大限となっています。
(3)「もったいない大賞」蔵王爽清牛による地域共生事業
飲料メーカーの工場が白石市内にあり、この工場から「爽健美茶」など様々な茶がらが、産業廃棄物として処理されていました。この茶がらを乾燥処理し、当センターのホエーをミキシングした飼料を試行錯誤しながら苦労して、肉牛の品質にも健康にも良い独自飼料として作り上げました。
そして、この独自飼料を当センターで生まれた和牛を父、乳牛を母としたF1に給与して、肉質、食味などの検査を繰り返しながら仕上げた肉牛を、蔵王町のブランド「蔵王爽清牛」として確立し、仙台のホテルなどに供給しています。
なぜ、この独自飼料を給与する肉牛の対象をF1としたのか、それは黒毛和牛は、すでに「仙台牛」として飼料給与体系も含め、ブランドが確立しており、求められているのは、酪農経営から産出されたF1の、肉質を良くし、今以上においしい牛肉にできないかということで取り組むことにしたからです。
しかし今や、酪農経営における乳牛の後継牛は、雌雄産み分けの技術が確立されると共に、生乳生産継続のための2産以降の種付け繁殖は、ほぼ和牛の受精卵移植が太宗を占め、日本の黒毛和牛の3分の2は、乳牛であるホルスタインの子宮から生産されているが現状です。
酪農から生み出される乳雄やF1の頭数は年々減少を続け、拡大することは困難です。F1は、もはや極めて限られた肉用牛となっています。
重要な記事
最新の記事
-
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -
 シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日
シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -
 農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日
農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -
 ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日
ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -
 【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日
【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -
 全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日
全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -
 【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日
【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -
 【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日
【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -
 【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日
【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -
 【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日
【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -
 【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日
【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -
 【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日
【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -
 【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日
【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -
 【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日
【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -
 【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日
【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -
 【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日
【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -
 【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日
【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -
 2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日
2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -
 米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日
米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -
 【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日
【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日




































































