JAの活動:新世紀JA研究会 課題別セミナー
許可制から認定制へ 市場間の格差拡大も【野上昭雄・JA常陸代表理事会長】2018年4月5日
・生産農家の所得向上を第一に―卸売市場法の改正とJAの対応―
卸売市場法の改正案が、今国会に提出されています。食品の流通環境の変化に対応した効率的な仕組みに変えることを目的に、その核となっている卸売市場に対するさまざまな規制を緩和し、活性化しようというものですが、急な改革には特に出荷者であるJAに大きなとまどいがあります。新世紀JA研究会は、3月に開いた第17回課題別セミナーで卸売市場法改正を取り上げました。
 1923年に中央卸売市場法が制定されて以降、卸売市場が果たしてきた役割は集荷面では国産青果物の卸売市場経由率80%以上を占めているなど、分荷、価格形成、代金決済等の調整機能は食品流通の中で大変重要な役割を担っており、国民への食料安定供給に大きく貢献してきました。
1923年に中央卸売市場法が制定されて以降、卸売市場が果たしてきた役割は集荷面では国産青果物の卸売市場経由率80%以上を占めているなど、分荷、価格形成、代金決済等の調整機能は食品流通の中で大変重要な役割を担っており、国民への食料安定供給に大きく貢献してきました。
現在の卸売市場法も生鮮食料品の流通・取引の円滑化、価格の安定かつ統一的な価格形成を行い、農家の生産意欲を高めると共に国民生活の安定に資することを目的に制定されています。
(写真)野上昭雄・JA常陸代表理事会長
◆「地方」の民営化進む
しかしながら、今国会では卸売市場法の改正などを含む農業関連9法案が提出されており、2018年度予算が3月にも成立すれば、4月以降審議が本格化し、政府は6月20日までの会期内に成立を目指しています。
現行の卸売市場法では中央卸売市場を食品流通の中核に位置づけ、国は都道府県や人口20万人以上の市に限って開設を「認可」し、参入を制限してきました。今回の卸売市場改正案では「認可制」から開設者の制限を設けず、国が定める基本方針に適合する要件を満たす場合に認定する「認定制」へと変更することとしています。
それ以外の卸売市場は「地方卸売市場」として都道府県が認定することとなり、中央卸売市場と地方卸売市場が規模や品目数によって区分けされます。このため大きな地方市場が中央市場になったり、小さな中央市場が地方市場となったりすることも考えられます。
国としては、中央市場と地方市場の取引規制にほとんど差をつけない方向で進めているとのことですが、従来の卸売市場法と大きく異なるのは「受託拒否の禁止」の維持については引き続き中央市場のみであり、地方市場は任意で「受託拒否禁止」を入れることが出来ることです。また、地方卸売市場は開設者になっている市・町の財政環境が年々厳しくなっているため全国の地方卸売市場は民営化に向け大きく変化していくと思われます。
「第三者販売の原則禁止」については一律規制せず、卸売市場ごとに定めるとしていますが、廃止ということになれば市場と大手量販店との直接取引が拡大し、仲卸を介した取引がなくなる懸念があります。価格についても大手量販店との交渉で言い値となる恐れがあり、相場の乱高下が起こる可能性もあります。
さらに、市場も仲卸も自ら荷を引いて販売することになり、市場と仲卸の垣根がなくなって荷の取り合いになることも考えられます。現在でも第三者販売によって産地から大手量販店との直接取引も行われていますが、こういった取引形態はさらに拡大し、大手量販店に荷が集中し、中小スーパー、八百屋等がどのようになるのか心配されます。
◆値決め販売主流に
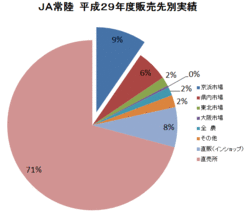 では、卸売市場法改正に伴って食品流通がどのような変化が考えられるか。まず、市場側は産地直接買い付けとなり受託販売から買い付け販売へと移行し、セリがなくなり、相対取引が加速して市場間競争が進み、市場間の格差が広がっていくことが考えられます。仲卸は市場との間で競争が激化し、生き残りをかけて仲卸同士での統合が進み、大手量販店は、量販店バイヤーが産地との直接契約に走り、工業製品同様の値決め契約が主となることが予想されます。
では、卸売市場法改正に伴って食品流通がどのような変化が考えられるか。まず、市場側は産地直接買い付けとなり受託販売から買い付け販売へと移行し、セリがなくなり、相対取引が加速して市場間競争が進み、市場間の格差が広がっていくことが考えられます。仲卸は市場との間で競争が激化し、生き残りをかけて仲卸同士での統合が進み、大手量販店は、量販店バイヤーが産地との直接契約に走り、工業製品同様の値決め契約が主となることが予想されます。
以上の現行の卸売市場法からの改正に伴い農業者やJAへの直接的な影響を考えると、まず販売力の弱い市場に荷が集まらず、一部の市場に集中することで価格が安定しないことがあげられます。次にセリの機能が失われてしまった場合は、値決め販売が主流となることや、産地契約・産地開拓が進み、企業間の争奪戦が始まる恐れがあります。また、大規模産地と小規模産地との格差、市場手数料の自由化の進行、農業経営の企業化や農家の仲卸等への直接販売の進行などの問題が考えられます。
(グラフをクリックすると大きなグラフが表示されます)
◆風評払拭の助けに
茨城県県北の11市町村を管内に抱えるJA常陸管内でも市場出荷は青果物販売流通上、大きなウエートを占めており、産地の形成及び生産者にとっても統一規格で出荷生産物の全量取り扱いは大きなメリットになっています。また、直荷引き禁止や商物一致の原則、第三者販売の原則禁止などについては地域、市場、量販店へ大きな影響が予想されます。産地並びに生産者へ直接不利益となる内容ではありませんが、注視していく必要があります。
最後に、茨城県県北の農産物は過去には1999年にJCOによる臨界事故の発生で風評被害を受け、また2011年の東日本大震災の影響による東京電力福島第一原発での爆発事故による農産物の出荷停止が、一部農産物ではあるものの現在も続いています。生産者が手塩にかけて育ててきた農産物が言われなき風評被害による影響を受けて翻弄されてきました。
その間の大変厳しい状況を乗り越えられたのは、市場側からの適切な情報やアドバイス等があったからこそであると考えています。今回の卸売市場法の改正については生産農家の所得向上が図られると共に、消費者にとってもメリットが感じられるような改正であるよう切に願い、今後の法案の内容について卸売市場と情報を共有していく必要があると考えます。
※このページ「紙上セミナー」は新世紀JA研究会の責任で編集しています。
新世紀JA研究会のこれまでの活動をテーマごとにまとめています。ぜひご覧下さい。
重要な記事
最新の記事
-
 日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日
日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日 -
 【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日
【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日 -
 加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日
加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日 -
 全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日
全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日 -
 鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日
鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日 -
 「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日
「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日 -
 「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日
「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日 -
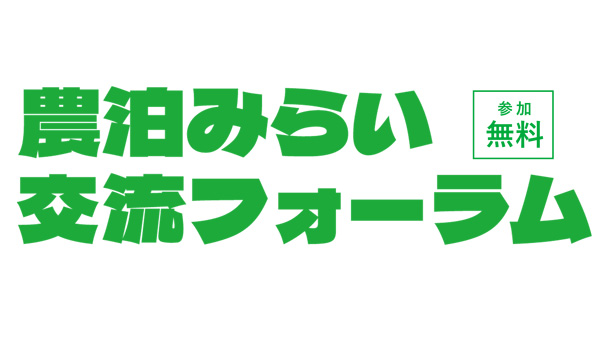 農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日
農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日 -
 冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日
冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日 -
 全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日
全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日 -
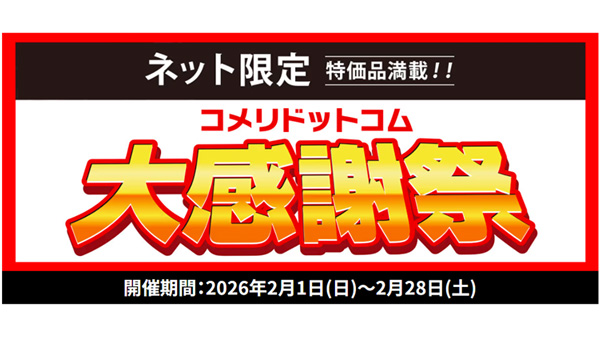 「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日
「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日 -
 「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日
「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日 -
 満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日
満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日 -
 生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日
生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日 -
 子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日
子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日 -
 国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日
国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日 -
 居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日
居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日 -
 ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日
ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日 -
 2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日
2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日 -
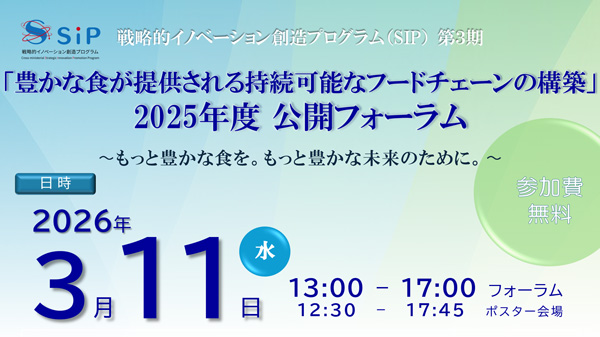 「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日
「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日






































































