JAの活動:第64回JA全国青年大会特集
【インタビュー・大澤誠農林水産省経営局長】「自ら変わる」発想で農協の新時代を(前編)2018年2月16日
農業者の所得増大と農業生産の拡大、地域の活性化を目標にJAグループは自己改革の加速化に取り組んでいる。今回は改めてなぜ農協改革が求められているのか、農林水産省の大澤誠経営局長に聞いた。大澤局長は日本社会の急激な変化のなかで農協のビジネスモデルの見直しが必要になっていると指摘したうえで、新しい時代に対応した農協の強みを創造していくべきだと強調した。また、准組合員制度について各農協がその位置づけと意義を社会に向けて発信することから議論を始めたいとの考えも明らかにした。
--JAグループは自己改革を進めています。改めて、なぜ今回「農協改革」が求められているのか、お聞かせください。
今、農業も農村も急激に変化していると考えていただきたいと思っています。この変化は農業や農村だけで起きているのではなく、日本社会全体、産業全体と連動して起こっていることです。
こういう状況のなかで、農協は今まで成功してきたビジネスモデルを農業、農村の急激な変化に即して考え直していくときが来ているのではないかということです。
農協は昭和23年に設立されて以来、農地改革の結果生まれた小規模多数の農業者に対して肥料、農薬などの生産資材を共同で供給したり、農産物をまとめて米卸売業者や卸売市場に出荷するといった、まとめていく力を非常に発揮して農業の発展に貢献してきたと思います。同時に農業者のための相互扶助的な信用事業、共済事業から発展し、今や地域住民の生活に不可欠なサービスの供給にまで成長してきたと思います。ところが、これからの新しい時代には、そうした事業はどうなのか、正念場を迎えているということだと思います。
◆農協に3つの正念場
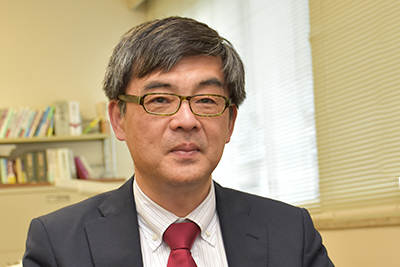 私は従来のシステムと現在の問題について3つに整理しています。
私は従来のシステムと現在の問題について3つに整理しています。
1つは、今までは小規模で同質的な農家が多数存在していたことから、地域共通の利益が見つかりやすかったのではないかと思いますが、今、地域では成長している比較的少数の担い手と小規模な農家がだんだん引退の時期を迎えているというように多様化し、また非農家も増え地域全体の合意を図っていくことが容易ではなくなったのではないか。つまり、地域全体の合意をどう形成していくか、これが第1の正念場だということです。
第2の正念場とは、生産地と消費地との間に距離があることを前提に農産物をまとめて安定供給するという流通システムを農協が担っていたわけですが、今や情報革命や生活のデジタル化、インターネットの普及とビッグデータの活用などによって生産地と消費地の距離が近くなったということです。それによって生産者も消費地の動向をリアルタイムで把握できるようになり、個々の消費者の情報に基づく差別化商品に取り組み、それをビジネスモデルに加えていこうという農業者が出てきているという変化が生まれています。
そして3つ目の正念場とは、日本社会全体の前提だった人口は伸びるという前提が減少に転じたことです。基本的には作れば売れていく時代でしたがそうではなくなった。もっとも農業については、もっと前からその傾向にストップがかかっており、人口増加が続いている時から食生活の変化によって作れば売れるということではなくなっていました。
今や、人口減少、成熟社会になり消費者の細かなニーズに対応する必要性もありますし、人口減は生産側にも大きな影響を及ぼし人手不足にどう対応していくのかという問題にもなります。
こうした3つの正念場を迎えているなかで、売り方でも買い方でも、同質的な多数の農家をまとめていくという従来のモデルをそのまま続けていくと、困ったときだけ農協に頼ればいい、それ以外は新しい技術を使い消費者の動向をつかんで自分のやりたい農業をやろう、ということになって農協としての機能を損なっていく怖れはないのかと、非常に心配になってきているわけです。
それが私の今の認識と農協改革の背景についての考えです。
(写真)大澤誠・農林水産省経営局長
◆農協改革は運動論
平成26年6月の農協改革のとりまとめを読むだけではこのような背景は分からないかもしれませんが、農協改革はけっして組織のあり方についての制度論だけに目を奪われるべきではないと思っています。あくまで農業、農村、あるいは日本社会の変化にどう対応していくべきなのかという一種の運動論を重視すべきだと思っています。
それはこれからの地域を支えていこうという人たちがどの部分を農協に期待しているのか、そこを真剣に議論していただくことです。農産物の売り方についても従来のままではなく、やはりきちんと売り先を見つけてくれるんだなと信頼される農協になる。そのために農協改革が求められているのだと思っています。
※この続きは、【インタビュー・大澤誠農林水産省経営局長】「自ら変わる」発想で農協の新時代を(後編)をお読みください。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日
シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -
 農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日
農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -
 【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日
【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -
 【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日
【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -
 (474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日
(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -
 和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日
和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -
 築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日
築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -
 幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日
幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -
 「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日
「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -
 大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日
大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -
 築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日
築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -
 栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日
栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -
 秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日
秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -
 農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日
農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -
 日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日
日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -
 中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日
中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -
 持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日
持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -
 札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日
札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -
 高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日
高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日









































































