【全中・経営ビジョンセミナー】伝統産業「熊野筆」と広島県信用組合に学ぶ 協同組織と地域金融機関の連携2025年9月18日
JA全中教育部は9月10、11日、広島県で「JA経営ビジョンセミナー」第2セッションを開いた。伝統的工芸品「熊野筆」のものづくりを視察し、地域の産業に寄り添う広島県信用組合の取り組みに学んだ。
 地元出身の姉妹デュオMebiusが歌で歓迎
地元出身の姉妹デュオMebiusが歌で歓迎
安芸郡熊野町の「筆の里工房」では、地元出身の姉妹デュオMebius(メビウス)が地元の「熊野筆祭り小唄」や、JA松本ハイランドのために制作した「ゆめピーちゃんのうた」で参加者を迎えた。
伝統的工芸品「熊野筆」の歴史と未来への挑戦
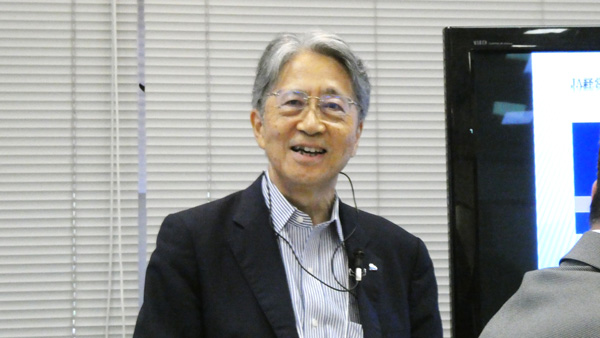 広島筆産業の城本健司社長
広島筆産業の城本健司社長
熊野町は書道筆、画筆、化粧筆で知られる国内最大の筆生産地。広島筆産業の城本健司社長が「伝統的工芸品のものづくりと地域金融機能 熊野筆の歴史と未来への挑戦」をテーマに講演した。同社は創業150年の筆製造会社で、三井銀行出身の城本社長は家業を引き継ぎ、16年間社長を務めている。
「伝統的工芸品」とは、100年以上の伝統技術を用いた製造などを条件に経産大臣の指定を受ける工芸品を指し、2024年10月時点で全国243品目が登録されている。しかし産業全体は生活様式の変化や海外製品との競合により、1983年の5410億円をピークに2016年には960億円へ縮小している。
熊野町は広島県西部の安芸郡にあり、広島市中心部からは車で40分ほど。江戸時代末期から筆生産が始まり、国内最大の産地として知られる。1947年に熊野毛筆商工業協同組合が発足し、現在は熊野筆事業協同組合として原料共同購入や販路支援、商標管理を担っている。組合員は76社・人(2025年3月末現在)で、城本社長も理事を務める。
 「熊野筆」で伝統的技術を体験
「熊野筆」で伝統的技術を体験
熊野筆の歴史は「常に社会課題への対応の連続」であった。戦後の習字教育廃止で需要が減ると画筆輸出に転じ、さらに化粧筆へと活路を求めた。1987年の男女雇用機会均等法施行による女性の社会進出が進み、化粧需要の変化に対応した。
生産は主要なものだけで22の工程に分かれ、町内の専門業者や内職(多くは女性)の職人が担う。「売上1億円未満の小規模事業者が大半で信用力が低い」ため、地域では古くから「頼母子講」(たのもしこう)と呼ばれる相互扶助金融が発達した。掛け金を出し合い順番に資金を融通し、銀行利用が難しい事業者の資金調達を支えた。販路拡大にも役立ち、地域に金融機能と絆を生んだ。
近年は筆のブランド化に取り組み、2004年に団体商標「熊野筆」を登録し、熊野の「K」をあしらったマークも作成。2013年には11カ国・地域で「Kumanofude」を商標登録し、「独自ルールを守る業者のみが名乗れる」仕組みを整備した。近年は植物由来素材の導入や新商品開発、オンライン販売による市場創出、「筆の里工房」などで地域振興にも注力している。
協同組合金融の本質を問う
 日下企業経営相談所の日下智晴代表
日下企業経営相談所の日下智晴代表
今回のセッションコーディネーターを務める日下企業経営相談所の日下智晴代表は「相互扶助精神の原点回帰から協同組合金融の本質を問う」をテーマに論点を提起した。日下氏は広島銀行から金融庁に転じ、地域金融企画室長などを歴任後、祖父が設立した相談所を再興した。
日下代表は、日本社会の人口減少と金融行政の規制緩和が進むなか、令和6年に成立した「事業性融資の推進等に関する法律」に基づく「地域金融強化プラン」が年内にも示される見通しであり、「地域の中小企業を守る仕組みが整う」と解説した。
今後は金融機関が支援する二つの軸「社会課題解決型(ローカルゼブラ企業)」と「規模拡大型(100億円企業)」のうち、「JAは持続性を重視するローカルゼブラ企業との親和性が高く、地域と共に価値を創造していく役割を担う」と提案した。
地域とともに歩む広島県信用組合
 広島県信用組合(愛称ケンシン)の深山春幸理事長
広島県信用組合(愛称ケンシン)の深山春幸理事長
広島県信用組合(愛称ケンシン)の深山春幸理事長は「地域と共に歩むケンシンは、深化し進化する 組合員や地域の近くにいるから力になれる」をテーマに講演した。
ケンシンは旧熊野信用組合を母体に5つの信用組合が合併し、県全域を対象とする組織へ発展。2024年3月末時点で預金3799億円、貸出2737億円、経常収益70億円を計上し、貸出金利息が収益の8割を占める。「投信や保険販売は扱わず、預金と貸出に特化」した金融機関だ。
経営理念は(協同組織である)組合、組合員、自己を愛する「三愛主義」を掲げる。職員には「組合員に奉仕するため自己研鑽に努める」ことを呼びかけている。2024年度からは「深化と進化」をテーマに第2次中期経営計画を進め、対面営業による結びつきの「深化」と「進化」するデジタルの各種取り組みの融合を図っている。
 講演に聞き入る参加者
講演に聞き入る参加者
深山理事長は、前身の熊野信用組合が熊野筆の業者によって設立され、「頼母子講」が現在も「ケンシン会」として続いていることを紹介した。そして、こうした取り組みこそ「信用組合の原点」と強調。金融危機のなかで何度も存続危機に直面した経験を振り返りながら、業績回復局面でも「組合員配当の回復が先、役員の報酬回復は最後でいい」という当時の経営者の精神に感銘を受けた経験も述べた。
また、かつて都市銀行から融資を断られた地元企業に対して融資を実行し、その後の大きな成長につながった経験を紹介。「協同組織金融機関として地域の中で必要な存在であり続ける」というケンシンの価値観につながっていることを強調した。また、「サンフレッチェ広島応援定期預金」など「地域密着」で開発した商品を紹介。「地域を支える」人材育成の重要性にも触れ、職員の自発的なMBA(経営学修士)取得、外部出向で大きく成長した事例などを挙げた。
最後に、60周年事業として桜を植樹した「ケンシン櫻の森」整備なども紹介し、「地域がなくなればケンシンもなくなる。限定された地域だからこそ協同組合にできることがあり、これからも地域と向き合う存在でありたい」と結んだ。
重要な記事
最新の記事
-
 百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日
百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日 -
 アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日
アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日 -
 振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日
振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日 -
 愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日
愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日 -
 葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日
葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日 -
 「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日
「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日 -
 初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日
初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日 -
 【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日
【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日 -
 農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日
農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日 -
 食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日
食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日 -
 まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日
まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日 -
 クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日
クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日 -
 「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日
「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日 -
 邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日
邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日 -
 藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日
藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日 -
 東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日
東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日 -
 鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月12日
鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月12日 -
 首里城再建 組合員からのカンパ金に感謝 沖縄県知事が生活クラブに来訪2026年2月12日
首里城再建 組合員からのカンパ金に感謝 沖縄県知事が生活クラブに来訪2026年2月12日 -
 坂ノ途中 国連開発計画(UNDP)スリランカ事務所とMOU締結2026年2月12日
坂ノ途中 国連開発計画(UNDP)スリランカ事務所とMOU締結2026年2月12日 -
 国産農業用ドローン普及拡大へ 住友商事とマーケティング連携開始 NTTイードローン2026年2月12日
国産農業用ドローン普及拡大へ 住友商事とマーケティング連携開始 NTTイードローン2026年2月12日





































































