JAの活動:米価高騰 今こそ果たす農協の役割を考える
【特別座談会】人を育てる食と農の力に自信を持とう(3)2025年11月4日
米価高騰が続くなか、米の需給の安定とともに、水田農業政策の見直しが今後農政の大きな焦点になっていく。現状をどう見てJAグループはどのような役割を果たしていくべきか、地域農業の持続的な振興策、消費者との連携、次世代のための「食農教育」などをテーマにJA茨城県中央会会長でJA全農副会長の八木岡努氏、東京農業大学副学長の上岡美保氏、文芸アナリストの大金義昭氏の3氏が議論した。
 文芸アナリスト 大金 義昭氏
文芸アナリスト 大金 義昭氏
大金 国内農業の再構築に向けたJAグループ茨城の取り組みは?
八木岡 農業生産の維持はもちろんですが、10年後を見据えて農業をする人を増やしていくことです。今、JAでは税務申告の記帳代行をしていますが、それによって見える個別経営の内容を踏まえ、第三者承継も含めた次世代をどう確保していくか。
県内の新規就農者には、県外からの人も増えています。例えばJA水戸の有機農業研究会は35人ですが、もともと農家ではなく県外からの人も多い。JAにとっても一気に正組合員が増えることになった。彼らが作ったものを売る「出口」として、JAが学校給食への食材提供や直売所などで支援する。学校給食における地場産物の活用は24年度の県平均で68・8%です。私が組合長になった10年前は20%程度でした。ですからやればできるということです!
それから有機野菜には収穫期間が短い野菜も数多くあります。さらにそれが温暖化によって一気に収穫しなければならず、逆にあっという間に無くなってしまいます。安定供給が非常に難しくなってきたことから、JAは有機野菜を冷凍保管する事業も始めています。JAの「強み」である総合事業を生かし、新しい担い手と地域との橋渡しをしながら農業をやりたい人に体験の場を提供し、農業の良さだけでなく大変さも伝えていく。お客さん扱いをしないということですね。子どもたちには農業体験をしてもらう。大事なのは「安心・安全」だけでなく「おいしい」という感動です。大人になったら、その「おいしい」農畜産物を提供する側になるんだと考えてもらえたらいいなと思います。
農業者を増やすことも重要ですが、地域のコミュニティーの理解者を増やすことも必要です。例えば効率的な水田をつくっても、水路の維持・管理には地域のコミュニティーの協力が欠かせません。JAの准組合員は地域農業の応援団ですから、このような人々も含めて「食農教育」などを通じて地域の暮らしを一緒に学んでいくことも私たちの仕事ですね!
上岡 地域農業と連携した学校給食は単なる「食材」ではなく、教育にとって大切な「教材」だと思います。
東京農業大学の使命という点でいえば、まずは国内生産基盤の強化につながる研究がもちろん大事ですが、人材育成も重要です。今、JAに対する理解があまり出来ていない学生が増えてきていると思いますので、JAの役割もしっかり伝えていくことが大事だと考えています。
また、教育では理系人材の育成が国の重要課題になっていますが、理系大学に進学した女子になぜ理系を選んだかというアンケート結果では、親や先生の影響という回答とほぼ同じ割合で幼少期からの自然体験、それが自分を理系に導いたと回答しています。
文科省でも探究学習やSTEAМ教育(Science, Technology, Engineering, Art,Mathematics)が重要だとしていますが、実はこれは農業体験で全部できることだと思っています。雑草や虫、気象の探究、さらには水利施設や農業機械などは工学系ですし、地域の神事や祭りは文化、芸術です。そして「郷土食」もあります。最終的には調理して食べる、そして健康や栄養の部分まで、五感を生かした体験や学びが可能です。
こう考えると農業は全部できるわけで理系人材育成は農業体験しかないのではないかとまで私は考えています。農業の「多面的機能」の一つとして教育効果も大きいということです。関係者の皆さんにはぜひこういう点も知っていただきたいと思います。
食料安保に JA不可欠
大金 包括的な指摘ですね。JAグループに寄せる期待は?
上岡 JA全農の経営管理委員として関わらせていただいて、食料安全保障のために侃々諤々(かんかんがくがく)の議論をし、どうしたら効率的に流通できるかも含めて考えていることがよく分かりました。ただ外からはそれが理解されていないということがあると思いました。
それでも消費者との接点はやはり「食」です。JA全農や各地JAは加工品や牛乳など最近は多くの商品を開発していますから、JAはこういうことをしているというアピールになると思います。それからJAグループの全国ネットワークも「強み」として生かしてほしいですね。
また、JA全農の海外事業の研修で豪州にも行き、現地の農業も見てきましたが、1経営体が2000haだと聞き、とても太刀打ちできるものではありません。だからこそ日本はやはり米が生産できるアジアモンスーン地帯ですから、しっかりと「多面的機能」を評価して農業をそして地域を守っていかなければならないと改めて思いました。
私は教育がとても大事だと思っています。JAも地域で子どもたちや消費者に向けた「食農教育」に取り組んでいますが、学生を連れて農家での体験をさせてもらった時にトウモロコシをその場でむいて食べる経験をしました。その味は衝撃でした!
こういうことを多くの皆さんに、地域農業のなかで体験してもらいたいと思います。
八木岡 JA全農の経営理念は「生産者と消費者を安心で結ぶ懸け橋」です。消費者と生産者の距離を縮めることが、今はいちばん大事です!
大金 「食と農」の正念場ですからね!
【座談会を終えて】
異例の米価高騰を巡っては、本紙にも昨年来、様々な立場から切迫した議論が数多く寄せられてきた。例によって〝猫の目農政〟は今また「増産」から「減産」へと揺れ動き、一寸先が見えない混迷の時代にあって腰の据わったブレない眼差しは貴重である。
人が生きていく上で欠かせない「食と農」について、八木岡さんは生産・流通の現場から、上岡さんは専門の「食農教育」の視点から透徹した眼差しを自然体で披露している。その気さくなやり取りの背後には、実践と学究の現場に賭けるそれぞれの確固たる信念や覚悟が隠されているように思われた。東京農業大学の同窓でもあるという二人からは、後進に託す限りない期待も感じられた。(大金)
重要な記事
最新の記事
-
 【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日
【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日 -
 (472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日
(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日 -
 山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日
山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日 -
 大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日
大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日 -
 栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日
栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日 -
 大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日
大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日 -
 業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日
業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日 -
 県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日
県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日 -
 まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日
まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日 -
 アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日
アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日 -
 「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日
「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日 -
 鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日
鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日 -
 農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日
農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日 -
 栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日
栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日 -
 調理技術教育学会「食品ロス!?」オンラインセミナー開催2026年2月6日
調理技術教育学会「食品ロス!?」オンラインセミナー開催2026年2月6日 -
 全ゲノム情報から赤色酵母サイトエラ属の系統分類学的位置が明らかに 東京農業大学2026年2月6日
全ゲノム情報から赤色酵母サイトエラ属の系統分類学的位置が明らかに 東京農業大学2026年2月6日 -
 春の彩りをひと袋に「春のつまみ種」期間限定発売 亀田製菓2026年2月6日
春の彩りをひと袋に「春のつまみ種」期間限定発売 亀田製菓2026年2月6日 -
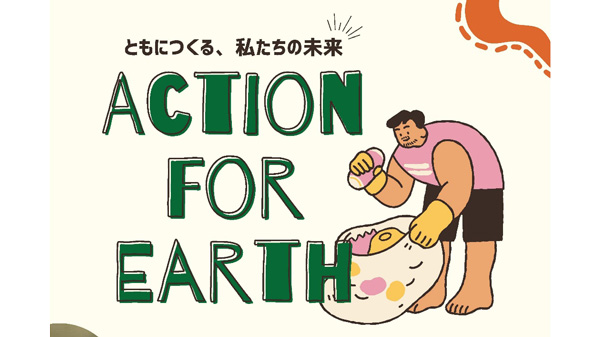 協同の力で地球環境の再生へ「Action For Earth 2026」開催 ワーカーズコープ2026年2月6日
協同の力で地球環境の再生へ「Action For Earth 2026」開催 ワーカーズコープ2026年2月6日 -
 ワインシティ推進支援で地域の魅力発信「地域おこし協力隊」を募集 長野県東御市2026年2月6日
ワインシティ推進支援で地域の魅力発信「地域おこし協力隊」を募集 長野県東御市2026年2月6日 -
 オリコン顧客満足度調査「食材宅配 首都圏」「ミールキット 首都圏」で第1位 生活クラブ2026年2月6日
オリコン顧客満足度調査「食材宅配 首都圏」「ミールキット 首都圏」で第1位 生活クラブ2026年2月6日






































































