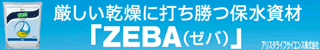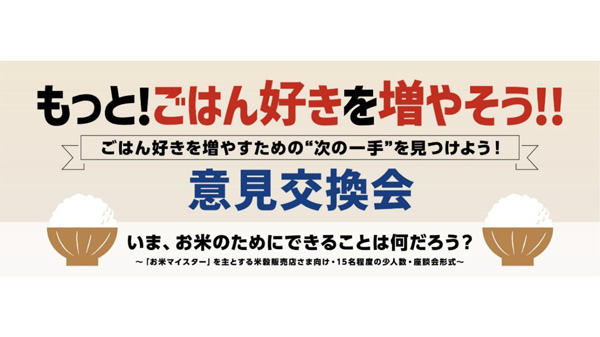作業受託で冷凍ホウレンソウ 農機への支援が課題 ジェイエイフーズみやざき2025年10月28日
農業者の減少が続くなか、現在の食料生産力を維持するため、農業現場を支援するサービス事業者の育成と活用が大きな課題となっている。10月20日には(一社)農林水産航空・農業支援サービス協会の設立式典が行われ、宮崎県の(株)ジェイエイフーズみやざきの業務部原料担当部長の伊豆元文博氏が「加工用ホウレンソウの作業受託の実践と課題」を報告した。
 伊豆元部長
伊豆元部長
同社は2010年に当時のJA宮崎経済連の関連会社として設立された。
背景には口蹄疫による飼料生産への打撃からの復興や、葉たばこ廃作に対する露地野菜の振興、残留農薬問題による国産志向の高まりなどがあった。消費地から遠いこともあって露地野菜の産地づくりと冷凍加工によって付加価値を高めた野菜の販売をめざして、産地づくりと加工に一体として取り組んできた。
冷凍工場では25年度は3600tを扱う計画で、このうちホウレンソウが2400t、小松菜が90tと葉物が全体の7割を占める。
ホウレンソウは12月から4月まで生産・製造する。24年度の実績では契約栽培している生産者は約50人。栽培面積は110haでこのうち23haを社員3人と実習生5人で自社生産している。
ホウレンソウ生産は土づくりから収穫まで120日間かかる。青果用の倍以上もある50センチ前後まで育てる。地面から10センチ前後の高さを刈ることで異物や雑草、傷んだ下葉などの混入を減らすことにもつながっているという。
土づくりは生産者自らが行うが、は種や中耕、防除といった機械作業は約7割の生産者が委託し、収穫はすべて受託している。同社だけでは収穫作業のすべてを請け負えないので他社に再委託している。
機械作業を受託することで生産者は機械を購入する必要がない。
設立当初は収穫作業には収穫機に2人、収穫物の積み込みローダーに1人の計3人体制だったが、収穫機の機械化(収穫物を抑える装置の機械化)を進め、2人体制を実現した。これによって人件費の削減と、受託費用の値上げの抑制にもつなげている。
ただ、課題も多い。栽培開始前には地区別に関係者が集まり意見交換を行っているが、多くの生産者の作業受託スケジュールの調整には苦労するという。とくに最近はは種時期の10月以降も天候が安定せず、栽培計画の修正など臨機応変な対応が求められている。
同社は作業受託という農業支援サービスを提供する立場だが、同時に提供したサービスを通して栽培された原料を購入し冷凍野菜を製造するという立場でもある。すなわちサービス価格の上昇は原料仕入れ価格の上昇につながり、また、サービスの質が低下すれば原料の収量や品質の低下、さらには翌年の作付け意欲にも影響することになる。
伊豆元部長は「生産者に提供するサービスと原料確保は密接に関係している」と同社の特徴を指摘し、「逆にいえばコスト削減でサービス価格を抑えることができれば原料価格の値上げを抑えることができる。また、サービスの質の向上が収量や品質の向上と翌年に作付け意欲にもつながる」と強調した。産地づくりから加工販売までの一貫した事業展開のなかでのサービス事業体の位置づけが明確だ。
ただ、課題の一つは収穫機など機械の移動。冷凍加工向上の周辺で栽培できれることが望ましいが、原料の安定確保のためには遠方の生産者の作業受託も引き受ける必要があり「車で1時間の地域まで機械を運ぶ」という。
年間の稼働率を考えて収穫機は2台備えているものの、その他の農機は複数所有はしていない。
こうしたなかで最近は作業の依頼があった場合は生産者が持っている機械を貸してもらって作業したり、あるいは生産者にオペレーターとして参加してもらうことなど「生産者への作業提案も行っている」。
生産者と協力することで受託を引き受けられるか、引き受けられないか、ではなく「どうしたから受託できるか」をお互いに協議するようになっているという。
同社は設立から10年以上となり機械の老朽化への対応も課題だ。高額なため簡単に購入できず、修理をしながら使っている。一方でオペレーターの確保も大切でメインオペレーターのほか、生産者との調整を行うフィールドマネージャーや、管理職なども機械を扱うことができるように努めており、社員のマルチスキル化で柔軟に対応している。収穫期にオペレーターに作業を集中させない労務管理の面からも重要だという。
散布用のドローンは2台あり、かんしょや大根の防除受託に利用しているが、ホウレンソウの防除に適用のある農薬が認められれば活用する。ドローン防除では現在のブームスプレーヤーによる防除の3分の1の時間に削減できるという。また、雨後すぐに防除できるなど病害の軽減と品質向上につながりそうだ。
伊豆元部長は今後も作業受託を通じて生産者の負担軽減と栽培面積の維持を図っていきたいと話し、政策的な支援としては機械の購入などへのサポートが必要だと指摘した。
重要な記事
最新の記事
-
 【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日
【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日 -
 【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日
【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日 -
 米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日
米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日 -
 2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日
2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日 -
 続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日
続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日 -
 第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日
第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日 -
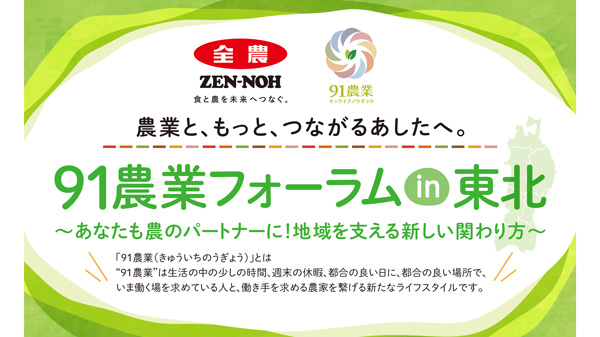 中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日
中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日 -
 希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日
希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日 -
 神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日
神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日 -
 フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日
フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日 -
 「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日
「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日 -
 東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日
東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日 -
 鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日
鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -
 鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日
鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -
 調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日
調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日 -
 佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日
佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日 -
 国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日
国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日 -
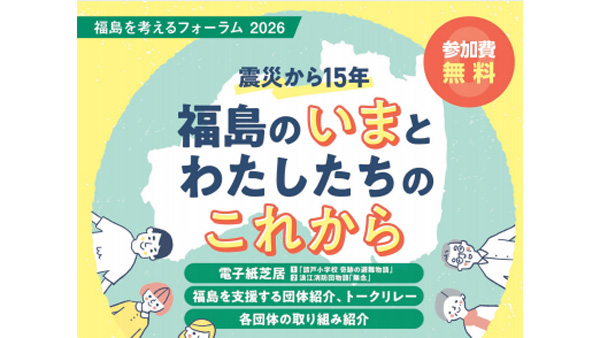 原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日
原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日 -
 牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日
牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日 -
 ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日
ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日