JAの活動:活力ある職場づくりをめざして
【活力ある職場づくりをめざして】「人が育つ経営」へ JA全中・村上光雄副会長に聞く2013年6月21日
・切れ目なく取り組む
・変わる組合員の要望
・支店中心の運営のために
・自ら考えるJA職員に
JAグループは第26回JA全国大会決議をふまえ、昨年末に「『次代へつなぐ協同』を担うJA人づくり」全国運動方針(JAグループ人づくりビジョン)を策定した。今年度はこの運動の初年度にあたることから、人づくり運動をテーマに「JA地域の生命線?活力ある職場づくりをめざして」と題してシリーズを掲載していく。第1回はJA人づくり推進委員長の村上光雄JA全中副会長に、この方針の柱である「人が育つ経営」への転換などについて聞いた。
「JAグループ人づくりビジョン」がめざすこと
◆切れ目なく取り組む
 ――改めて「人づくり」とはどういうものか、お話しください。
――改めて「人づくり」とはどういうものか、お話しください。
人づくりには、これで完成というものはない、ということです。やはり絶えず取り組まなくてはならない。
反省を込めていえば私も職員というものはだんだんと向上してくるものだろうと思っていました。自然にレベルが上がっていくものだ、と。しかし、そうではありません。
なぜかといえば、毎年新しい職員が入ってきて、毎年、何人かは辞めていく。その新しい職員に対して教育を絶えず積み上げていかないと、人づくりは蓄積どころか退化してしまう。とにかく継続して切れ目なく続けていくことが第一です。
◆変わる組合員の要望
――では、今なぜJAに人づくりの取り組みが求められているのでしょうか。
われわれにとってなぜ人づくりが必要になるのかといえば、JAの組織基盤が大きく変わってきたからです。正組合員が減って准組合員が増えているなかで、組合員の要望、地域の要望というものが非常に多様になってきた。たとえば、昔は農業のことを、それも米のことを知っていればいいという時代もありました。しかし、もうそれだけでは通用しない。農業のことであっても広く作物について知っていなければならないし、さらに組合員の要望が高度化している。それらにきちんと対応できる職員が育ってこないとJAとしても事業展開が難しいし、組織そのものについて理解をしてもらうことも困難になってきかねません。
このように多様化した組合員に対してJAらしい仕事をやっていくための職員教育にとりくまなければならない。そうした人づくりを通じてJAも変わっていかざるを得ないという状況にあるということです。
◆支店中心の運営のために
とくに第26回JA全国大会決議では、今後は支店を中心とした活動を展開していく、としており、その実現のためには職員1人ひとりが地域での協同活動をひっぱっていく、あるいはそれをコーディネートしていく役割を果たしていくことが求められます。そこをきちんと理解してもらわなければなりません。その理解がなければ「次代へつなぐ協同」という大会決議も成果をあげることもできないし、JAが前に進んでいくことができないと考えています。
それから、JAグループの問題として若い職員の離職率がかなり高いということがあります。ということは、JAグループの職場に魅力がないと思われていることでもあります。それは同時にJAとしても、これまでのその職員に対する教育が全部無駄になってしまうわけですから、損失になる。やはり職員が誇りを持って仕事ができるような職場にしていかなければならないということです。これを改めて考え直さざるを得ない時点にわれわれは来ているということです。
◆自ら考えるJA職員に
――どのような職員像、職場をイメージして取り組みを進めるべきですか。
今回の運動方針にも掲げられていることですが、これから育ってもらいたい職員のイメージとは、やはり自ら考えて行動できる職員であり、さらには、そうした職場風土になってほしいということです。
上からの指示がなければ仕事ができないようなことではとても臨機応変な対応、現場にあった取り組みはできないということになります。つまり、支店を中心とした取り組みとは、それぞれの支店の特色が違うことをふまえるべきだということです。支店には必ず個性がある。それに対して、たとえば支店の管理運営規定など型にはまったものを押しつけるだけではだめなのです。それぞれの支店長、さらには窓口対応する職員も、自ら考えて組合員、地域に対応していくことができるような職場風土が求められているのです。
さらにいえばそうならないと組合員に満足してもらえる本当のJAにはならないということです。 それに向けてどのような取り組みをしていくかですが、今回は県段階でも取り組みもすることにしています。ただし、重要なことはそれぞれのJAで独自の人づくりビジョンをつくってほしい、ということです。
――そのビジョンを「人が育つ経営」の観点から考えるということですね。
「人が育つ経営」とはこの運動方針のスローガンでもあります。その意味は、それぞれの職員が生き生きと活動するなかで、職員が人間としても育っていく姿だと考えています。
職員の育成にはJAの幹部職員だけでなく、やはり組合員にも担ってもらう、教育してもらうことが必要です。毎日の組合員とのつながりのなかで仕事をしていくことも教育訓練の場です。私は「組合員のみなさんもしっかりと教育してください。職員が育つ育たないは組合員さん次第です」といつも言っています。 これこそがJAらしい教育のあり方だと思っています。とくに職員には協同組合運動を理解している人間になってもらわなければいけない。
口では協同組合といいながら、仕事はてんでばらばらで助け合いもできないような職場であってはいけない。また、利己的な人間になってもいけません。やはり協同組合の仕事をさせてもらっているという職場にふさわしい人間に育ってもらわなければいけない。そうした意味でも人が育つ経営にならなければいけないということだと思います。
――JAトップ層に期待することは?
今回の運動方針の大きな特徴のひとつは、トップ層の役割の重要性を位置づけたことです。
組合長をはじめとしたトップ層が「人が育つ経営」ということを考えてもらうことが重要です。そうでなければさまざまな変化に対応できる人間は育たないということです。そこでトップ層に対して意識改革を訴える意味で「人が育つ経営」への転換を打ち出しているわけです。
まずはトップ層がめざすJA像を自分の言葉で語ることが大事です。そこが職員が誇りを持って仕事ができるJAの出発点です。
重要な記事
最新の記事
-
 「需要に応じた生産」でなく「攻めの増産」か 石破前首相のX投稿「米について」が波紋2026年2月5日
「需要に応じた生産」でなく「攻めの増産」か 石破前首相のX投稿「米について」が波紋2026年2月5日 -
 JA貯金残高 108兆4664億円 12月末 農林中金2026年2月5日
JA貯金残高 108兆4664億円 12月末 農林中金2026年2月5日 -
 「関東東海花の展覧会」は品評会の箱根駅伝【花づくりの現場から 宇田明】第78回2026年2月5日
「関東東海花の展覧会」は品評会の箱根駅伝【花づくりの現場から 宇田明】第78回2026年2月5日 -
 どんぐりと熊と人間【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第375回2026年2月5日
どんぐりと熊と人間【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第375回2026年2月5日 -
 ころんとかわいい冬野菜「静岡県産メキャベツフェア」6日から開催 JA全農2026年2月5日
ころんとかわいい冬野菜「静岡県産メキャベツフェア」6日から開催 JA全農2026年2月5日 -
 「鹿児島県産きんかんフェア」福岡県の直営飲食店舗で開催 JA全農2026年2月5日
「鹿児島県産きんかんフェア」福岡県の直営飲食店舗で開催 JA全農2026年2月5日 -
 高品質なウシ体外受精卵の効率的な作製に成功 農研機構2026年2月5日
高品質なウシ体外受精卵の効率的な作製に成功 農研機構2026年2月5日 -
 バイオスティミュラント含有肥料「アビオスリーF」を販売開始 シンジェンタジャパン2026年2月5日
バイオスティミュラント含有肥料「アビオスリーF」を販売開始 シンジェンタジャパン2026年2月5日 -
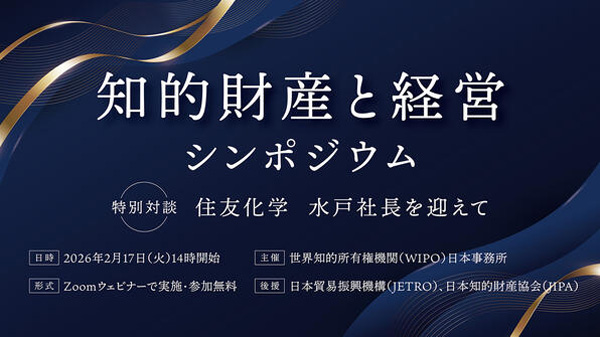 住友化学・水戸社長、「知的財産と経営シンポジウム」で特別対談に登壇2026年2月5日
住友化学・水戸社長、「知的財産と経営シンポジウム」で特別対談に登壇2026年2月5日 -
 外食市場調査 12月度2019年比92.6% 2か月ぶりに9割台に回復2026年2月5日
外食市場調査 12月度2019年比92.6% 2か月ぶりに9割台に回復2026年2月5日 -
 利用者に寄りそう応対を審査「パルシステムコンテスト」パルシステム東京2026年2月5日
利用者に寄りそう応対を審査「パルシステムコンテスト」パルシステム東京2026年2月5日 -
 道東カーボンファーミング研究会「サステナアワード2025」で優秀賞を受賞2026年2月5日
道東カーボンファーミング研究会「サステナアワード2025」で優秀賞を受賞2026年2月5日 -
 鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月5日
鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月5日 -
 組合員によるリユース・リサイクルとフードマイレージ運動 月次成果を公開 グリーンコープ2026年2月5日
組合員によるリユース・リサイクルとフードマイレージ運動 月次成果を公開 グリーンコープ2026年2月5日 -
 国産米粉で作ったGC「米粉サブレ(さつまいも味)」販売 グリーンコープ2026年2月5日
国産米粉で作ったGC「米粉サブレ(さつまいも味)」販売 グリーンコープ2026年2月5日 -
 宮城県加美町、タカラ米穀と包括的連携協定を締結 東洋ライス2026年2月5日
宮城県加美町、タカラ米穀と包括的連携協定を締結 東洋ライス2026年2月5日 -
 季節限定「野菜生活100本日の逸品 愛媛せとか&ポンカンミックス」新発売 カゴメ2026年2月5日
季節限定「野菜生活100本日の逸品 愛媛せとか&ポンカンミックス」新発売 カゴメ2026年2月5日 -
 フィジカルAIにより収穫性能向上に向けた開発検証を実施 AGRIST2026年2月5日
フィジカルAIにより収穫性能向上に向けた開発検証を実施 AGRIST2026年2月5日 -
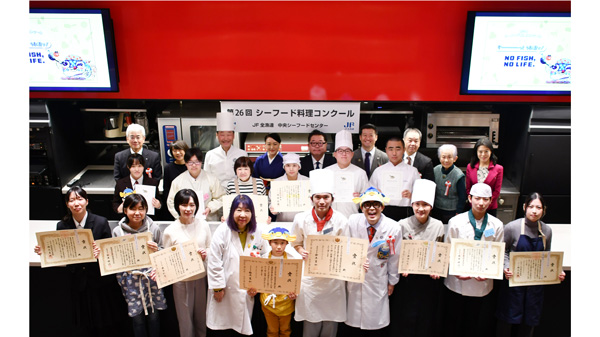 おさかなの1汁1おにぎりや20分レシピ「シーフード料理コンクール 」開催 JF全漁連2026年2月5日
おさかなの1汁1おにぎりや20分レシピ「シーフード料理コンクール 」開催 JF全漁連2026年2月5日 -
 「ひきこもりVOICE STATIONフェス」誰もが生きやすい地域を呼びかけ パルシステム連合会2026年2月5日
「ひきこもりVOICE STATIONフェス」誰もが生きやすい地域を呼びかけ パルシステム連合会2026年2月5日







































































