「経営資源」の確認、優先性、課題を明確にしよう!【JAまるごと相談室・伊藤喜代次】2023年8月1日
JAの事業・経営の革新を遅らせる「ロービーム思考」

経営コンサルタントだからといって、事業や経営について何でも知っていて、すぐに解決策が提案できる、というわけではない。それでも、相談の連絡をいただき、JAに赴き、最初の会議から、総代会資料などの資料を見せられて、「どこに問題がありますか」と聞いてくる役員がいた。
私の会社は小さいながらも、一つの案件に関して、社内のコンサル仲間との会議や先輩コンサルへの相談、書物・マニュル本の調査・確認、JAを退職された常勤役員への相談などを行う。最初の会議から得られた情報をもとに、コンサルプランを策定するのに、かなりの時間を要する。それなりに、苦労があるのだが・・・。
私は、JAの経営陣や幹部職員との初対面の席で、話を聞かせてもらう質問は決まっている。
「このJAの特徴はどんなことですか。」「このJAで自慢できることはどんなことですか。」の2問。それも、その会議に出席している役員、幹部職員全員に話を聞くことにしている。役員の顔色を伺いながら話す幹部職員もいれば、自分の意見を堂々と開陳する職員もいて、それはそれで、いろんなことが垣間見える。
それはともかく、JAのコンサルで感じることは、内部の会議も理事会でも、検討テーマの視野が狭く、近間を見ての議論が多いことである。会議に提出される資料を見れば明らか。まるで内部会議の推進実績資料のようなものが中心だ。議論になりにくいのか、中長期的な事業や経営に関する検討テーマは少なく、資料も少ない。その日暮らしの経営管理になっている場合が多い。
夜間の自動車運転時を考えてもらえば、わかりやすい。ライトには2種類あって、前方100メートル先が確認できるハイビームと、すれ違いや近くの人間などを確認するための40メートル先を確認するロービームである。経営会議や理事会での議論やテーマは、この両方を常に意識して検討しなければならない。
JAは、どちらといえば、ロービーム思考が強い。昨年度の実績対比で増えた減ったといった実績報告に時間が割かれ、肝心な構造的な問題やこの先顕在化するであろう問題は、定例の会議ではスルーする。
たとえば、中期計画や長期ビジョンの策定、支店の店舗再編や経済事業施設の統合などのコンサルの立場は、ハイビームで中長期先を捉えた問題を提示し、具体的に解決するための方法論を検討して提示する。ハイビーム思考の経営も必要なのである。
「経営資源」に関する問題共有・活用で課題解決へ
「経営とは、持っている経営資源を有効に活用して継続すること」で、事業が成長し、組織が発展する。有効な活用がなければ、経営資源は陳腐化し、衰退する。常に経営資源の問題をチェックし、有効に活用し、育成するのが、経営会議での検討であり、理事会での議論である。
たとえば、支店の再編計画の調査で、建築・オープンから何年経過し、建物の状態はどうなっているか、支店に登録されいる組合員数と平均年齢、口座数、組合員世帯数とメイン化率、新規の契約実績数の推移など、何も数値的な把握をしていないJAが多かった。組合員も支店建物も、支店の貯貸金もJAの経営資源である。それを調べるのが、私たちコンサルの仕事といえば、そうではあるが・・・。
昭和の時代の経営論では、「ヒト・モノ・カネ」の3つが、重要な経営資源であるとし、顧客・来店者、店舗・商品、資金・コストなどの数値をもとに問題を抽出した。現在のJAは7つの経営資源があると考えている(ヒト、モノ、カネ、情報、ノウハウ、時間、関係性)。もちろん、経営資源は企業によって異なる。
経営資源の確認が、事業の成長や問題に深く関係していることが理解いただけよう。それだけに、他の競争企業との違いや優位性を確認することもできるから、この経営資源の確認・共有は重要なテーマであり、せめて四半期ごとにチェックが必要だ。
JAの場合、もっとも重要な経営資源は、ヒトである。ヒトのなかには、組合員、一般利用者、JA職員、事業取引等関係スタッフの4種類がある。このヒトの変化がどうなっているか、数的質的な変化をチェックしたい。たとえば、組合員の人数と増減、年齢構成、JA事業の利用実態など。事業や経営が、安定して成長していくためには、経営資源が安定的で、育成を図ることが必要だ。表象的な事業実績の背後にある経営資源の問題に注意を向け、適宜、論じることの重要性に気づかされると思う。
たとえば、加入・脱退の組合員数。加入組合員の年齢や家族構成、脱退された組合員数と年齢別割合、脱退理由。これだけを四半期ごとに数値化してみるだけで、JAの問題が見えてくる。それを何年か継続でみれば、構造的な問題も明確になる。
私は、経営会議や理事会は、最低でも月2回開催し、1回はこの経営資源に関するテーマで数値化した資料を提出してもらい、結論は出さなくてもいいから、問題認識を共有し、議論を重ねてほしいと考えている。
JAの理事者や幹部職員には、ハイビームでの検討体制を定例化し、「将来への不安」の解消への議論をお願いしたい。組合員、職員が、もっとも望んでいることは、「将来への安心」だからだ。
◇
本コラムに関連して、ご質問、ご確認などがございましたら、お問い合わせフォーム(https://www.jacom.or.jp/contact/)より、『コラム名』を添えてご連絡ください。コラム内又はメールでお答えします。
重要な記事
最新の記事
-
 【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日
【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日 -
 経常利益4.5%増 25年度上半期総合JA経営速報 全中2026年2月6日
経常利益4.5%増 25年度上半期総合JA経営速報 全中2026年2月6日 -
 (472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日
(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日 -
 山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日
山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日 -
 大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日
大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日 -
 栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日
栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日 -
 大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日
大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日 -
 業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日
業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日 -
 県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日
県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日 -
 まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日
まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日 -
 アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日
アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日 -
 「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日
「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日 -
 鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日
鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日 -
 農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日
農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日 -
 栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日
栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日 -
 調理技術教育学会「食品ロス!?」オンラインセミナー開催2026年2月6日
調理技術教育学会「食品ロス!?」オンラインセミナー開催2026年2月6日 -
 全ゲノム情報から赤色酵母サイトエラ属の系統分類学的位置が明らかに 東京農業大学2026年2月6日
全ゲノム情報から赤色酵母サイトエラ属の系統分類学的位置が明らかに 東京農業大学2026年2月6日 -
 春の彩りをひと袋に「春のつまみ種」期間限定発売 亀田製菓2026年2月6日
春の彩りをひと袋に「春のつまみ種」期間限定発売 亀田製菓2026年2月6日 -
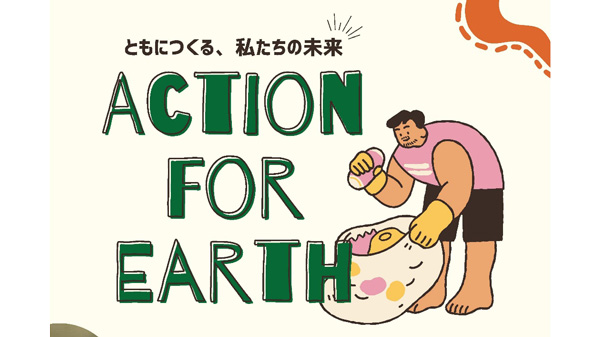 協同の力で地球環境の再生へ「Action For Earth 2026」開催 ワーカーズコープ2026年2月6日
協同の力で地球環境の再生へ「Action For Earth 2026」開催 ワーカーズコープ2026年2月6日 -
 ワインシティ推進支援で地域の魅力発信「地域おこし協力隊」を募集 長野県東御市2026年2月6日
ワインシティ推進支援で地域の魅力発信「地域おこし協力隊」を募集 長野県東御市2026年2月6日






































































