JAの活動:食料・農業・地域の未来を拓くJA新時代
「若手のホープ」に聞く 食と農と地域、JAへの思い (下)22019年7月22日
◆300年も続く落ち葉堆肥 無くすな"先人の蓄積"
大金 飯野さんに登場してもらった以上は、「三富新田」で江戸時代から続く「落ち葉堆肥農法」などの取り組みについてお話しいただきたい。「日本農業遺産」にも登録されていますよね。
飯野 私たちの地域は、1600年代の後半から1700年代の前半に行われた開墾によって切り開かれました。江戸の人口が100万人を超え、青果物が足りず、「関東ローム層」と呼ばれる火山灰土の原野の開墾が行われた。黒田さんのところと同じような土壌ですね。
火山灰土だから地球内部の噴出物でミネラル分は豊富なのですが、腐植がないので保水力や保肥力がない。ヨシやアシが繁茂する荒れ果てた「野っ原」を開墾し、野菜を作ることになる。幕府の公共事業として近隣の集落の次・三男が集められ、長方形の短冊状に区割りした土地を農地にしていきます。前方に雑木・落葉樹を植え、家の周囲には針葉樹の防風林をつくり、その間の土地を畑にする当時の行政指導が行われる。「クズ掃き」をし、雑木林などから出る落ち葉などと人ぷんを混ぜ合わせた腐植を畑に投入し、豊かな農地を造成したんですね。
黒田 北海道の開拓に似たような歴史があるんだね。
飯野 水の確保には、大変な苦労をしたという記録があります。当初はアワやヒエも育たず、草の根を食べて土地にかじりついたという話が残っている。堆肥は「寒肥」ですから、1月くらいの寒中に投入し、微生物がゆっくり働き、節分を迎えて地温がだんだん上がってくるころには熟成して分解が最大に進む。昔は被覆材なんてないから、春のお彼岸が過ぎ、霜が消えてからでないと、種まきの作業が始まらなかったでしょうね。4~5月の農作業の時期には「寒肥」が畑で完全に栄養化されているという手はずです。
先人のこうした取り組みが300年以上も続けられてきたのですが、300回しか堆肥を投入していないことにもなる。しかし、そんな汗の結晶の上で私は10品目以上の作物を栽培し、まあ大概のものは作れます。
大金 う~ん、300年という時間の物差しを持った経営なんだ。
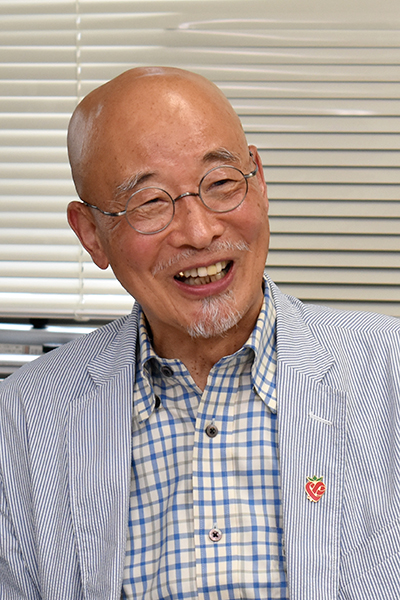 大金義昭氏
大金義昭氏
飯野 就農したころに失敗したのは、親父が取り組んでいた代々の農法を無視した結果だったんですよ。堆肥を振るのがバカバカしく、腐植を入れずに、化学肥料などの金肥に頼って効率のみを追い求め、机上の計算で金になる欲に走ったために、7年目くらいには土を完全に壊してしまった。先人たちの300年の蓄積を、たった7年くらいで枯渇させてしまったんです。
親父はよく言っていた。「俺がいま仕事をしているのは、俺のためじゃない。お前や子孫のためにやっていることなんだ」とね。若い時は、その意味が分かっていなかった。政府がいま考えてやっていることは、先人の蓄積を枯渇させていることなのだと僕は思う。
大金 なんか、人生哲学にも重なる話ですね。
飯野 お金の問題にしたって、母はよく言いました。「もうかったからといって、安易に使うものじゃない。必ずしぼむ時がくる。そして、しぼんだ時に空気を入れてくれるのが地域なんだ」と。親父も「来年生き抜いていくためにお金を貯める」という考え方で、農家はそういう考え方が多いのではないか。
大金 3年に1度の冷害に見舞われた歴史を持つ地域などでも、常に3か年くらいのスパンで経営を考えるべきだということが語られてきましたね。
◆蔵は「つながり」の象徴 支え合うのが本来の姿
大金 飯野さんにはこの際、明治の大火の時と聞いていますが、蔵づくりの話もちょっと聞かせてください。
 飯野芳彦氏
飯野芳彦氏
飯野 農家にとって、蔵は農具や作物の種子などを守り、保管する重要な施設です。地域で大火があり、財産を守るためには蔵が必要だということが集落の話し合いで決まり、焼失した時に、地域の農家がお金を出し合い、最も困っている仲間の家の蔵から順次建てていくというエピソードですね。みんなで協力し合い、みんなで建てて、それぞれの財産を守っていくことにより、農業や地域を次世代に引き継いでいくという発想なんです。昔の人たちの考えは深い。
でも、今となってはこの蔵を維持していくことが重荷になっている面もあります。瓦屋根を葺き替えるだけでも300万~400万円かかり、漆喰(しっくい)の壁を直すだけでも200万円かかるとか。僕は守っていきたいと思っているんですが。
大金 土蔵の風景などは、貴重な文化遺産でしょ。
飯野 先人たちの地域の「つながり」を象徴するような風景です。
大金 人間は、そんな「つながり」を大切に、地域で生きてきたということかな。黒田さんの哲学のキーワードには、「縁」や「つながり」や「思いやり」という言葉がありますね。
黒田 江戸の長屋の、もっとそれ以前から、人間はどこに暮らしていても「縁」や「つながり」や「思いやり」に支えられて生きてきた。それがきっと僕らの本来あるべき姿なんじゃないかと思う。携帯電話やスマホの時代になって、そうした自覚が人々から急速に失われ、忘れられていくとしたら問題です。
食べ物の問題でも、それは言えることですね。作る人と食べる人との間の「縁」や「つながり」や互いへの「思いやり」が希薄になっている。
 黒田栄継氏
黒田栄継氏
大金 そんな関係が逆に、「縁」や「つながり」や「思いやり」の大切さを浮上させている。ピンチはチャンスということで、農協の出番もそこにあるんじゃないかな。
「食と農」を介し、農協に何が出来るのか。「なぜ僕たちの声が届かないのか」と問う黒田さんの問題意識なども踏まえ、農協の役割や使命についてご意見を聞かせてください。
重要な記事
最新の記事
-
 【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日
【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -
 【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日
【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -
 (474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日
(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -
 和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日
和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -
 築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日
築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -
 幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日
幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -
 「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日
「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -
 大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日
大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -
 築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日
築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -
 栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日
栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -
 秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日
秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -
 農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日
農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -
 日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日
日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -
 中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日
中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -
 持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日
持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -
 札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日
札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -
 高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日
高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日 -
 高校生が森・川・海の「名人」を取材「第24回聞き書き甲子園」受賞者を決定2026年2月20日
高校生が森・川・海の「名人」を取材「第24回聞き書き甲子園」受賞者を決定2026年2月20日 -
 機能性表示食品「ことばうっかりサポート えごま油の力」新発売 J-オイルミルズ2026年2月20日
機能性表示食品「ことばうっかりサポート えごま油の力」新発売 J-オイルミルズ2026年2月20日 -
 おやつにぴったりな5種mix「亀田の柿の種 トレイルミックス」期間限定発売2026年2月20日
おやつにぴったりな5種mix「亀田の柿の種 トレイルミックス」期間限定発売2026年2月20日









































































