JAの活動:【農業協同組合研究会】どうなる どうする基本法改正
【農業協同組合研究会 報告③】生産者への直接支払いと公正な価格形成のバランスを 日本生協連 二村睦子常務2023年9月6日
農業協同組合研究会は9月2日、東京都内で「どうなる どうする基本法改正-『食料・農業農村政策の新たな展開方向』をめぐって」をテーマに2023年度第1回の研究会を開いた。農水省の杉中淳総括審議官、JAぎふの岩佐哲司組合長、日本生協連の二村睦子常務、研究会会長の谷口信和東大名誉教授が報告を行った。研究会の司会はJAおきなわ中央会・普天間朝重会長が務めた。
二村常務は5月に公表した基本法見直しに向けた同生協連の「意見書」の内容をもとに報告した。意見書では「財政支出に基づく生産者への直接支払い」が重要とした上で、再生産に必要なコストを単純に価格転嫁すれば、消費者が国産農産物を買わなくなる懸念があることから、生産者と消費者の両者へ配慮した公正な価格形成が大切だとした。
 日本生協連 二村睦子常務
日本生協連 二村睦子常務
日本生協連は全国の会員生協の代表で構成する委員会を作って議論し、意見を提出しようと昨年11月に「食料・農業問題委員会」を立ち上げた。基本法検証部会の委員でもあった私(二村常務)が検証部会での論点や意見を報告し、それぞれの生協の立場からの意見と交換するなかで、最終的には「消費者の立場」を重視した意見としてまとめた。
意見書は多岐にわたるが、5つを重点項目とした。1番目には「食料安定供給の確保に向けた国内農業生産の強化」を挙げ、あえて食料安全保障という言葉を使用しなかった。理由は食料安全保障と言うとあまりにも問題が大きくなり、実際に何をすべきかの重点が分かりにくくなるのではないかということである。消費者が望むのは不安定な国際情勢のなか、やはり食料が安定的に供給されることが一番であり、それもどこかの国から持ってきて安定的に供給されるということではなく、国内の農業が強くなってそれによって安定的に供給される状態をいちばん望んでいるということである。
ただ、現実的には輸入や備蓄も組み合わせないと安定的に供給されないだろうということから、輸入の安定化や備蓄の強化も盛り込んでいる。
国内の農業生産を強化するとはどういうことかを考えたとき、多様化する消費者の暮らしやニーズに対応して行われることが必要だと考えている。
米については意欲ある担い手への支援を中心に水田稲作の生産構造を強化していくとし、また、国内需要が高く輸入依存度が高い小麦や大豆、飼料については国産化が大事ではないかということも提起した。
2番目は「再生産と消費者の食料アクセスに配慮した透明で公正な価格形成」とした。当然、安いほうがいいと消費者は思うが、生産コストが上昇していることや、農業者が減少していることは理解しており、再生産可能な価格が必要だということは議論を通じて合意した。ただし、それを価格だけで補えるのかということを議論するなかで、すべてのコストを価格転嫁しては、かえって国産農産物を買えなくある、あるいは買わなくなるという状況を懸念し、財政支出に基づく生産者への直接支払いなどが重要になってくるのではないかと整理した。
3番目は「持続可能な農業・食料システムへの転換」。農業は多面的機能と環境に負荷を与えている面もあるという外部不経済をトータルに捉える必要がある。そのうえで環境に配慮した生産方式が大事だと理解されるべきだが、そのために手間をかけた農業生産をしているという理解が伝わっていけばある程度負担できる人も出てくると思う。しかし、全部を消費者が支えることは難しいので、価格転嫁だけではなく、炭素税・課徴金・補助金、排出権取引、公共調達、認証制度など様々な手段を活用して政策的に誘導することが必要だ。
4番目は「農村の維持・発展、都市と農村の共生」。人口減少のなか地域社会の維持については、地方の生協ではきわめて関心が高い。意見としては農村の持つ機能維持のため管理の担い手へ対価が支払われる仕組みを社会全体で運用していくことが必要だなどと提起した。
5番目は「消費者・市民社会の参画、消費者と生産者の相互理解と協力」。今回の意見集約に向けた議論のなかで、食料・農業の問題は農業者だけではなく、それ以上に消費者の問題だということが強調された。長期的な政策目標を明らかにし、分かりやすい目標や指標体系を整理することなどを提起している。
検討の過程で論点になったことの一つはやはり価格だ。生産者が再生産可能な価格と消費者が実際に手に取れる価格との差をどう補填すべきかが議論になった。また、生協は実際に店舗を経営しており、価格が上がれば消費が抑制される場面に度々直面している。価格で応援しようと思っても誰もが応援できるわけではない。そこで財政による補填という意見になった。
需要に応じた生産も論点になったが、自給率を上げていくということを考えると水田をうまく使いながら、たとえば飼料の国産化を進めるべきではないかという意見も出た。輸出の強化については、自給率がこんなに低いのになぜ輸出するのかという率直な意見も出た。一方、産直事業に携わっている現場からは産業としての農業が魅力あるものになって若い人たちが参入しようと思う農業にするためには大事だという意見が出て、それも意見書で提起した。
担い手問題では、地域や立場によって「農業者」、「生産者」のイメージがバラバラだということが分かった。たしかに大規模な農業者に農地が集約されていくことは必要かもしれないが、地域の人口が減るということも指摘され、「地域はどう成り立つのか」を議論する機会にもなった。
難しさを感じたのは「消費者と情報」の問題。一人一人の価値観や暮らしが違い、意識と認識にずれもある。国産は大事だと言っても高ければ買わないなどの現実がある。
「自給率」も難しい。たとえば国産の肉を食べても自給率は上がらないが、そこは理解されにくい。また、「農業者」や「農業」のイメージにも幅があって共通の理解が容易ではなく、議論が難しいと思った。
今後、正しい情報に基づく議論をしていくために食や農業についての正確な情報が共有されていく必要がある。それを届ける手段や関係者間の信頼もなければならない。さらに農業については品目別、地域別の実態をふまえた議論、環境問題では環境への負荷があることが「見える化」されたうえでの議論、また、都市・農村交流も生協としては非常に大事にしたい。
重要な記事
最新の記事
-
 【特殊報】ナス、キャベツにトビイロシワアリによる被害 県内で初めて確認 宮崎県2026年1月22日
【特殊報】ナス、キャベツにトビイロシワアリによる被害 県内で初めて確認 宮崎県2026年1月22日 -
 【特殊報】トマト黄化病 県内で初めて発生を確認 山口県2026年1月22日
【特殊報】トマト黄化病 県内で初めて発生を確認 山口県2026年1月22日 -
 成人式の花の需要はSNS時代の記念撮影文化【花づくりの現場から 宇田明】第77回2026年1月22日
成人式の花の需要はSNS時代の記念撮影文化【花づくりの現場から 宇田明】第77回2026年1月22日 -
 椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第373回2026年1月22日
椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第373回2026年1月22日 -
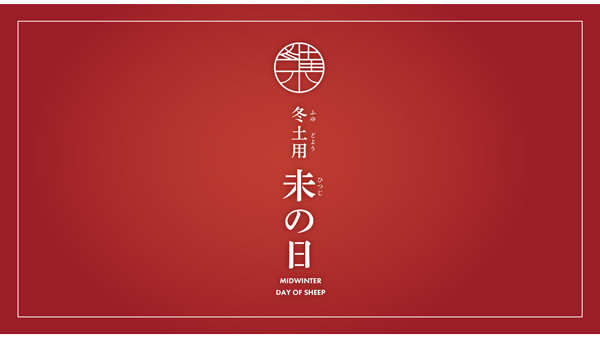 「冬土用未の日 」量販店や飲食店など連携で新たなマーケット創出 JA熊本経済連2026年1月22日
「冬土用未の日 」量販店や飲食店など連携で新たなマーケット創出 JA熊本経済連2026年1月22日 -
 安全性検査クリアの農業機械 1機種3型式を公表 農研機構2026年1月22日
安全性検査クリアの農業機械 1機種3型式を公表 農研機構2026年1月22日 -
 「トゥンクトゥンク」の「ぬいぐるみ」初登場 1月28日発売 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月22日
「トゥンクトゥンク」の「ぬいぐるみ」初登場 1月28日発売 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月22日 -
 精密農業の裾野を拡大 高性能農業用ドローン「P60」販売開始 バイエル クロップサイエンス2026年1月22日
精密農業の裾野を拡大 高性能農業用ドローン「P60」販売開始 バイエル クロップサイエンス2026年1月22日 -
 都内18拠点の精鋭が「宅配接遇力」競う「パルシステムコンテスト」開催2026年1月22日
都内18拠点の精鋭が「宅配接遇力」競う「パルシステムコンテスト」開催2026年1月22日 -
 店舗は前年超えも宅配は前年割れ 総供給高は前年未達 12月度供給高速報 日本生協連2026年1月22日
店舗は前年超えも宅配は前年割れ 総供給高は前年未達 12月度供給高速報 日本生協連2026年1月22日 -
 静岡県に「コメリハード&グリーン川根本町店」2月18日に新規開店2026年1月22日
静岡県に「コメリハード&グリーン川根本町店」2月18日に新規開店2026年1月22日 -
 静岡ガスサービスと農薬散布BPOサービスの実証契約を締結 レグミン2026年1月22日
静岡ガスサービスと農薬散布BPOサービスの実証契約を締結 レグミン2026年1月22日 -
 旬のおいしさ「紅まどんな&いちごフェア」開催中 アオキフルーツオンライン2026年1月22日
旬のおいしさ「紅まどんな&いちごフェア」開催中 アオキフルーツオンライン2026年1月22日 -
 ホタテや秋鮭など北海道の海の幸を満喫 生産者と郷土料理づくり パルシステム山梨 長野2026年1月22日
ホタテや秋鮭など北海道の海の幸を満喫 生産者と郷土料理づくり パルシステム山梨 長野2026年1月22日 -
 サカタのタネのジニア「Profusion Double White Improved」FS・AASで最高賞2026年1月22日
サカタのタネのジニア「Profusion Double White Improved」FS・AASで最高賞2026年1月22日 -
 鳥インフル ポーランドからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月22日
鳥インフル ポーランドからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月22日 -
 【特殊報】トマト黄化病 府内で病害発生を初めて確認 大阪府2026年1月21日
【特殊報】トマト黄化病 府内で病害発生を初めて確認 大阪府2026年1月21日 -
 一歩踏み出し地域を元気に【第71回JA全国女性大会特集】2026年1月21日
一歩踏み出し地域を元気に【第71回JA全国女性大会特集】2026年1月21日 -
 味噌で広がるコミュニティ JA成田市女性部 谷口まなみさん【第71回JA全国女性大会特集】2026年1月21日
味噌で広がるコミュニティ JA成田市女性部 谷口まなみさん【第71回JA全国女性大会特集】2026年1月21日 -
 想いをつなげ! 復活から歩む道 JAやまがた女性部 横山佳子さん【第71回JA全国女性大会特集】2026年1月21日
想いをつなげ! 復活から歩む道 JAやまがた女性部 横山佳子さん【第71回JA全国女性大会特集】2026年1月21日

































































