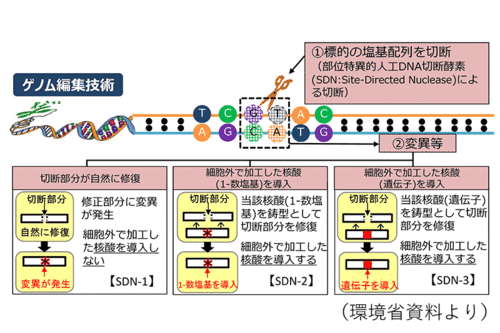ゲノム編集技術 一部を規制対象外へ-環境省2018年9月6日
環境省の中央環境審議会自然環境部会は、今年5月からゲノム編集技術に対する規制のあり方について審議してきたが、同審議会のもとに設置されれている専門委員会は8月30日の会合で、この技術のうち、外部から遺伝子が組み込まれない場合は規制の対象外とする方針を決めた。環境省はパブリックコメントを実施した後、秋に中央環境審議会に報告し正式に運用方針として決める。
◆ゲノム編集技術とは?
ゲノムとは生物が自らを形成・維持するのに必要な遺伝情報のことで、その情報はDNA(デオキシリボ核酸)のなかに収められている。
DNAが持つ遺伝情報は塩基配列のかたちで保持されており、その塩基はアデニン(A)、グアニン(G)、チミン(T)、シトシン(C)の4種類ある。
ゲノム編集技術とはDNAを切断する酵素を使って、この塩基配列を改変する技術だ。この技術を使えば狙った場所を切断し、塩基の置き換えや、欠損、または新たな遺伝子の導入を行うこともできる。
この技術は20年近く前に発表されているが、最近になって狙った場所を精度高く改変でき、しかも研究者・技術者が手軽に利用できる技術(CRISPR/Cas9、クリスパー・キャス・ナイン)が開発されたことから農作物の品種改良をはじめ、さまざまなライフサイエンス分野での利用が始まっている。
筑波大学生命環境系教授でつくば機能植物イノベーション研究センター長の江面浩氏によると、ゲノム編集技術とは▽目的の遺伝子を正確に探し出す技術、▽探し出した遺伝子に変異を入れる技術、この2つを組み合わせた遺伝子変異導入技術だと解説する。
品種改良との関係ではゲノム編集は「多様な品種改良技術のなかの1つ」であり、現在、日持ち性や高糖度などの形質を持つトマトやメロン、多収性のイネなどの開発が研究されている。
(写真)画像をクリックすると大きな画像が開きます。
◆カルタヘナ法とは?
このようにゲノム編集技術が利用されはじめたことから規制をめぐる議論も始まり、その皮切りとなったのが環境省によるカルタヘナ法の観点からの今回の審議である。
カルタヘナ法とは、日本国内で遺伝子組み換え生物の使用等について規制し、生物多様性を確保するための法律。遺伝子組み換え生物が生物多様性に影響をしないか事前に審査することや、適切な使用方法を定めており、安全性が確認されるまで屋外での栽培、生育は禁止されている。
環境省の専門委員会はこの法律から見て、現在のゲノム編集技術が法律の対象になるかどうかを検討してきた。
前述したように、ゲノム編集技術には標的とするDNAの塩基配列を切断することが基本だが、大きく3つの技術に分類される。
1つは標的とする塩基配列を酵素で切断するだけの技術。切断部分が自然に修復する際に元通りに戻らず、塩基が欠失したかたちで修復したり、塩基の置き換えが起きるなどを誘導して変異を起こす技術である(SDN-1)。
2つ目は標的の塩基配列を切断する際に、切断部分の塩基配列を一部変えたDNA断片(核酸)を細胞内に移入する方法である。切断部分が修復する際、その外来の核酸(またはその複製物)が導入される。(SDN-2)。
3つ目は外来遺伝子を組み込んだDNA断片(核酸)を細胞内に移入する技術。標的塩基配列を酵素が切断し、その後、修復するときに切断部分に外来遺伝子(またはその複製物)が導入されることを狙う技術である(SDN-3)。
◆情報提供を求め安全性確認
カルタヘナ法では遺伝子組み換え生物を外部由来の「核酸」が導入されているかどうかで定義している。
それに照らすと前述した3つのゲノム編集技術のうち、SDN-2とSDN-3はいずれも細胞外で加工した核酸であるDNA断片や遺伝子を導入をする技術のためカルタヘナ法の規制対象になる。
一方、DNAを切断するだけのSDN-1の技術は外部由来の核酸を導入する技術ではないことから、今回、専門委員会は規制の対象外とした。ただ、DNAを切断するハサミの働きをする酵素はタンパク質だが、ほかにRNAを活用する技術もある。RNA(リボ核酸)は核酸だが、切断部分が修復するときには消失してしまっており、組み込まれることはないため規制の対象外とされた。
環境省の担当者によると今回、外部由来の核酸を導入しないゲノム編集技術を規制対象外としたのは、あくまでカルタヘナ法上の「遺伝子組み換え生物」に該当しないとしたのであって「安全であるとは言っていない」としている。
もともと育種技術のひとつである放射線照射や化学物質による突然変異の誘導による作物は遺伝子組み換え生物としていない。DNAを切断するだけのゲノム編集技術についても自然界で起きている突然変異と同じであるという位置づけだ。
ただし、新しい技術には違いはなくまだ知見も少ない。DNAを切断するだけの技術といっても、標的とする部位が切断されているかどうか、あるいはハサミがあちこち切断していないかどうか、など検証していくべき課題は多いとの専門家の指摘もある。
環境省はこうした問題もふまえ、規制対象外にはするものの、屋外で栽培などをする場合は自主的な情報提供を求めるほか、ゲノム編集で作成された生物が生物多様性への影響が生じるおそれがあると判断したときには環境省や所管省庁は必要な措置をとることにしている。
(関連記事)
・果樹バイテク研究会を甲府で 農研機構(18.09.03)
・ウンシュウミカンの全ゲノムを世界で初めて解読 農研機構(18.02.22)
・1位はスマホで田んぼの水管理-農業技術10大ニュース(17.12.21)
・「金のいぶき」と「花粉米」、2つの機能性米(17.12.11)
・世界のGM作物栽培面積は1億8510万haに バイテク情報普及会(17.06.01)
・ラッカセイ祖先種のゲノムを解読 栽培種の品種改良効率化に期待(16.03.08)
重要な記事
最新の記事
-
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -
 シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日
シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -
 農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日
農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -
 ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日
ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -
 【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日
【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -
 全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日
全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -
 【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日
【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -
 【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日
【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -
 【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日
【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -
 【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日
【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -
 【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日
【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -
 【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日
【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -
 【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日
【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -
 【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日
【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -
 【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日
【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -
 【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日
【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -
 【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日
【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -
 2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日
2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -
 米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日
米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -
 【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日
【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日