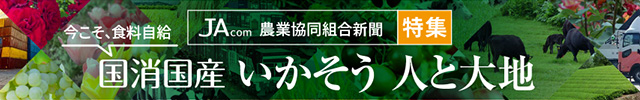農政:今こそ 食料自給「国消 国産」 いかそう 人と大地
【今こそ食料自給・国消国産】離島の維持に危機 過去の経験活かした支援を(1)JA沖縄中央会・普天間朝重会長2022年10月6日
資材高騰や子牛価格の急落などは、国境を守る離島を支え続けてきた沖縄県の農業も直撃している。農業経営はかつてない危機に直面し、農業予算の削減に農家の怒りが高まっている。離島の暮らしを守る役割を果たしてきた沖縄県のJAや生産者は、こうした状況をどう受け止め、「国消国産」推進にどう向き合おうとしているのか。JA沖縄中央会の普天間朝重代表理事会長に寄稿してもらった。
 JA沖縄中央会 普天間朝重代表理事会長
JA沖縄中央会 普天間朝重代表理事会長
経験したことない農業経営の危機
「離農するなら今かもしれない」。生産資材が高騰する中、農家のため息が聞こえる。農業経営の厳しい状況は何年も続いてきたが、これほどまでの危機はいまだ経験がない。
現在、我が国が抱えている問題は「3つの安全保障」だ。1つは国家安全保障、2つは経済安全保障、3つが食料安全保障。1については、ロシアによるウクライナ侵攻と中国の台湾海峡の危機、2は新型コロナウイルスによる世界的な物流の混乱と人の移動制限、それによる観光客の減少と急激な円安による物価の上昇など、そして3つ目の食料安全保障に関しては、1、2の影響を受けた輸入食料価格と肥料や飼料など生産資材の高騰である。
未曽有の食料危機は深刻の度を増している。
供給面では輸入食料や輸入品を原料とする食料加工品が大幅に値を上げている。小麦やトウモロコシ、大豆など穀物価格は北米など主要産地の不作で2020年から21年にかけてすでに上昇していたが、世界有数の穀物輸出国であるウクライナとロシアとの戦争が起きたことで、さらに価格が上昇した。国際的な価格指標である「FAO(国連食糧農業機関)食料価格指数」は20年には100前後だったが、今年3月には159.3と過去最高値を更新した。
需要面においても、世界的な人口増加、新興国の経済発展による食料需要増加、トウモロコシやさとうきびなどの食料用から燃料用(バイオエタノール)への需要転換という状況が続いている。特に中国では米中貿易戦争の懸念から21年末に策定した「第14次5か年全国農産物発展計画(21~25年)」において穀物の大幅増産と食料自給率向上の政策を打ち出しており、そのための肥料・飼料の需要はさらに拡大していくことが確実視されている。
年を取って温まりたい者は、若いうちに暖炉を作るべき
こうした状況に国連世界食糧計画(WFP)は「戦後最悪の食料危機」と警告を発しており、わが国でも10月からさらに値上げラッシュが起きている。世界規模で食料危機が深刻化する中、日本の食料自給率はわずか38%。約6割を輸入に頼っている。ウクライナ侵略で最も大きな影響を受けたのはアフリカ。アフリカは政情不安や先進国からの食料援助もあって食料を過度に輸入に依存したことが要因だが、アジアが緑の革命で食料増産を実現し、インドにおいてもガンジーの「国産愛用」の思想によって食料の自給自足を進めたのとは対照的だ。日本も今こそ改めて食料自給に目を向ける必要がある。年を取ってから温まりたい者は、若いうちに暖炉を作っておかなければならない。すぐに暖炉を作り始めるべきだ。
そういう中で、我が国の食料生産現場の実情はどうなっているのだろうか。
まず認識すべきは、農業は工業製品と異なり、需給調整が難しいということだ。工業製品の場合、景気が悪ければ機械の回転を緩めて在庫を減らし、景気が回復すれば機械の回転を速めて在庫を積み増し、製品供給量をコントロールする。しかし、農業生産は毎年限られた品目を一定量生産し、生鮮品であるがゆえに在庫としてストックできず、すべてを売りつくす必要がある。肥料や飼料の価格が高騰したからといって、投入をやめることはできないのだ。
コスト上昇分を販売価格に転嫁することもできない。沖縄県の基幹作物であるさとうきびの価格は大半が交付金で占められており、政府において交付金単価が決められる。需給によって決まるわけではない。
逆に、青果物においては、中央卸売市場でセリにかけられるため、価格はコストを反映することなく需給によって決まる。豊作であれば価格は低下し、天候不順などで生産量が落ちれば価格は上昇する。
コスト増なのに子牛価格暴落で収入が激減
肉用牛においても家畜市場でセリにかけられるため需給が反映される。本県の子牛の生産は全国4位の地位を占めるが、飼料の高騰を受け、主要取引先(購買者)である本土の肥育農家が飼料代捻出のため子牛の仕入れ頭数を減らしたことで価格が急落している。平均単価はこの数年で1頭あたり70万円から60万円、さらに50万円に下落し、直近9月のセリでは40万円台になっている。暴落だ。飼料などのコストが増加しているのに収入は激減している。
酪農においても、交渉によりようやく乳価の値上げが実現したものの、飼料価格の高騰にはとても追いつかない。しかもこれまで副収入であった乳用種(ホルスタイン種)の初生雄牛(ホル雄)などの子牛価格が平年の1割ほどに暴落しており、経営はさらに厳しくなっている。本県でも昨年から今年にかけて5戸の酪農家が廃業した。全国的にも酪農家の7割弱が赤字経営に陥っており、6割が経営継続困難という調査結果が出ている。
鶏卵農家も同様である。卵はスーパーでは特売品だ。価格交渉でもしようものならすぐに取引を打ち切られる。
農林水産省が公表している「農業物価指数(2020年=100)」では、本年8月の農産物価格指数(販売価格)が98.7と100を切っているのに対し、農業生産資材指数(投入費用)は肥料が144.5、飼料が147.5となっており、コストは上昇しているのに商品価格は低迷している実態が示されている。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日
シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -
 農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日
農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -
 【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日
【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -
 【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日
【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -
 (474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日
(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -
 和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日
和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -
 築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日
築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -
 幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日
幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -
 「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日
「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -
 大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日
大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -
 築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日
築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -
 栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日
栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -
 秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日
秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -
 農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日
農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -
 日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日
日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -
 中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日
中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -
 持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日
持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -
 札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日
札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -
 高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日
高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日