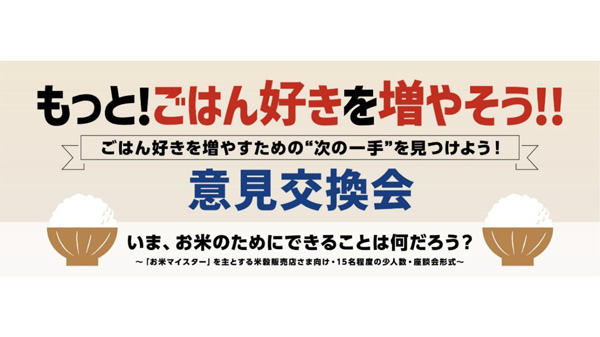農薬:サステナ防除のすすめ2025
【サステナ防除のすすめ2025】水田の刈り跡管理 多年生雑草の効率的防除を2025年10月2日
令和の米騒動後に新米の収穫期を迎えその収量と品質に大きな関心が寄せられている。作付面積が増加し、需給が緩和され価格も緩むのではないかと期待されているが、備蓄米の再度の積み上げが優先されるようであれば需給は締まったままだとの見方もあり、なかなか米の価格がどうなるか正確には見通せない状況が続くようだ。とはいえ、米の価格がどのようになろうと、高品質のものをできるだけ多く収穫し、消費者に届けたいと思うのが生産者の心情ではなかろうか。その収量・品質を保つためには雑草防除が欠かせない作業なのであるが、実は、水稲の刈り跡というのは、翌年の雑草の発生を抑えるのに有効な技術である。
以下、この技術を整理したので、年々雑草害に悩まされているようであれば参考にして頂ければ幸いである。

多年生雑草に多い難防除雑草
雑草というのは、いわゆる草であって、木のように固い体を持たず、地面より上にある部分は1年のうちに時期がきたら枯れてしまう。この時、次世代の繁殖期間として種子のみを残す雑草のことを一年生雑草といい、種子以外の地下茎(塊茎)や根を残すものを多年生雑草と呼んでいる。この多年生雑草は、体が大きいことや繁殖の方法が複数あるため防除が難しい。
このため、多年生雑草の多くが難防除雑草と呼ばれており、その代表的な雑草名は、クログワイやオモダカ、シズイ、ホタルイなどである。これらは、しばしば田んぼ内で優占化して水稲除草剤の効果が十分に発揮されずに問題となる。
地下30センチ以上からでも発生
多年生雑草が難防除なのは、主として、雑草の生態によるところが大きい。
例えば、多年生雑草の発生源の一つである塊茎は、地中のいろんな深さに分布しており、しかも、地下30cm以上もある深いところからも発生してくる力を持っていることが多い。このため、地上部に姿を現す時期がバラバラになり、残効の長いといわれる水稲除草剤でも効力が持たないほど長い期間発生し続けたりすることがある。
その他、塊茎が種子に比べれば図体が大きく、持っている栄養の量が多いので、地上部が枯れても地下部が生きていて再生してくること、種子なら枯らせる程度の除草剤の量では効果不足になることなどがあげられる。
また、多年生雑草はその生態から除草剤の淘汰(とうた)を長期間受けやすく、同じ作用性の除草剤を長期間使用し続けると抵抗性を持つ雑草が発生する可能性が高い。既に、スルホニルウレア系除草剤の抵抗性雑草が全国で発生しているのは周知の事実であり、多年生雑草の防除には同じ作用性の除草剤を連続使用しないことや他の作用性の異なる除草剤との混合剤で処理するなどの注意が必要だ。
今までよく効いていたのに年々雑草が残るようになったり、多く発生する雑草の種類が限られるような場合には、抵抗性雑草が発生している可能性もあるので、そういった場合には指導機関等に相談するなどして抵抗性の実態を確認するようにしてほしい。
発生源の塊茎を減らす防除法
まずは、自分の田んぼに生えている雑草の種類や抵抗性雑草の可能性などを確認し、その上で、その雑草に効果のある除草剤を選択するようにすると、多くの場合それだけで十分に除草効果があるはずである。
ところが、多年生雑草の場合は、本田で散布した除草剤の効果が薄れる頃に塊茎を形成させたり、肥大させたりして、しっかり翌年の発生源をつくることが多い。
このような特性があるため、難防除雑草を減らすためには、どうにかして翌年の発生源となる塊茎を減らすようにする戦略が必要だ。
具体的には、まず、秋から冬にかけて田起こしをすることである。これにより、地中にあった塊茎が地上に出てきて乾燥したり、寒さにあたったりして枯れてしまうのである。もちろん、たくさんある塊茎が全て表に出るわけではないので、田起こしだけでは完全ではないが、それでも翌年の発生源となる塊茎の量を減らすことができる。
もうひとつの方法は、刈り取り後の塊茎を肥大させる時期に、根部まで浸透する力をもった非選択性の茎葉処理除草剤(グリシン系)を散布して、地下部まで完全に枯らしてしまうことである。こうして、塊茎を肥大させずに枯らすことができれば、翌年の発生源を大きく減らし、翌年の発生量を少なくすることができるというわけである。
その他、水稲刈り取り跡に使用できる除草剤の特性を紹介するので参考にしてほしい。
また、現在水稲刈り取り跡での使用登録のある除草剤を別表に整理したので参考にしてほしい。
フェノキシ酸系除草剤(2,4―PA、MCP)の使用
フェノキシ系除草剤は、水稲生育中に使用するホルモン系の選択性除草剤で広葉雑草を得意とする除草剤である。マツバイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、オモダカ、セリ等にも効果はあるが、水稲生育中の処理では完全に枯殺することはできない。このため、他の有効な除草剤と組み合わせて使用されることが多い。
ただし、マツバイに対しては、稲刈り取り後の処理で効果的に防除することができるので、マツバイが優先している水田では、本剤の刈跡処理を試してみるとよい。
塩素酸塩除草剤(クロレート、デゾレート、クサトール)
塩素酸塩除草剤は、水によく溶ける性質があるため、根や茎葉部から吸収され、強い酸化作用によって細胞死を引き起こす非選択性の除草剤である。そのため、刈り取り跡に散布することで、刈り取り後に生育してくる多年生雑草を地下茎が発達する前に枯らすことで、翌年の発生源を減らすことができる。非選択性であるため、稲が無い刈り跡であれば、安心して水田全体に散布することができる。
石灰窒素
石灰窒素は、古くから窒素質肥料として使用されているが、ノビエ等雑草の休眠覚醒効果があることによって除草剤としての登録がなされた。
そのメカニズムは、石灰窒素に含まれる有効成分シアナミドが、水田などで発芽を待っている雑草の種子に接触すると、種子の休眠を覚醒させて強制的に発芽させるというものだ。厳寒期などに石灰窒素を処理すると、強制的に発芽させられた雑草が冬の寒さなどで枯死したり、すき込むことで物理的に雑草を枯らすことができる。また、翌春に発芽する雑草種子の量を減らせる効果もある。
重要な記事
最新の記事
-
 【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日
【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日 -
 【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日
【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日 -
 米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日
米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日 -
 2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日
2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日 -
 続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日
続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日 -
 第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日
第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日 -
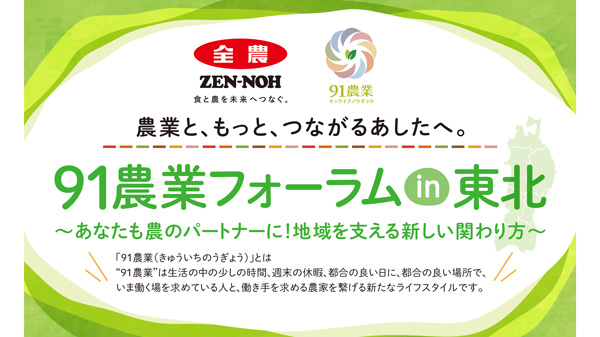 中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日
中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日 -
 希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日
希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日 -
 神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日
神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日 -
 フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日
フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日 -
 「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日
「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日 -
 東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日
東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日 -
 鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日
鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -
 鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日
鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -
 調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日
調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日 -
 佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日
佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日 -
 国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日
国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日 -
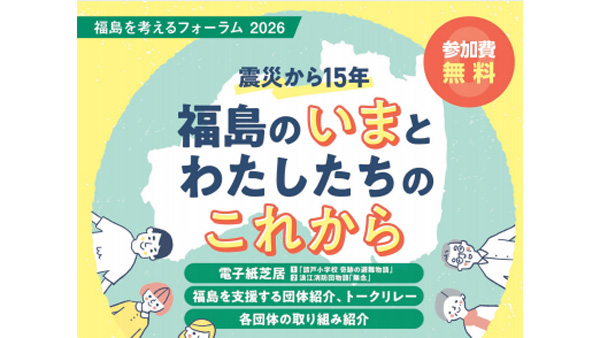 原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日
原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日 -
 牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日
牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日 -
 ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日
ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日