流通:加工食品の原料原産地表示を考える
加工食品の原料原産地表示を考える[9]食品表示、どうなるの? 消費者の感覚とズレも2014年4月3日
・何も変わらない!?
・生鮮か、加工か
・加工品はなぜ?
・実例示し議論を
昨年6月に公布された「新食品表示法」に基づく新たな食品表示のルールづくりに向けて、消費者委員会(※本文末)の食品表示部会は3つの調査会(栄養表示調査会、加工食品表示調査会、生鮮食品・業務用食品表示調査会)を設置して、昨年末から議論を始めている。3月26日には3調査会が中間報告をまとめたが、表示ルールの具体化にはまだ先送りされた問題も多い。
ここでは本紙もこれまで注視してきた、消費者が求めている加工食品の原料原産地の表示拡大をめぐる問題点のいくつかを改めて整理する。
原料原産地の表示拡大
国産品選択に必須
◆何も変わらない!?
新たに食品表示法が制定されたのは、JAS法、食品衛生法、健康増進法と、それぞれに目的の違う法律による現在の食品表示を一つの理念に基づいてルールづくりをするためだ。
その理念を食品表示法は「消費者の安全と消費者の自主的な選択の機会が確保され、必要な情報が提供されることが消費者の権利」と定めた。食品表示によって、消費者が必要とする情報を提供することは、消費者の権利を守ることだと明記されたといえる。
しかし、昨年11月、新たなルールづくりに向けて消費者庁が示した食品表示基準の策定方針では「消費者の求める情報提供と事業者の実行可能性とのバランスを図り」とされた。さらに「原則として表示義務の対象範囲(食品、事業者等)については変更しない」とも明記されている。
議論をスタートさせるにあたり「事業者の実行可能性」に配慮することに加え、表示の義務対象を広げることはない、と事業者寄りの検討をすると宣言したようなものである。
現行の表示制度が「分かりにくい」、あるいは「原料の原産地が知りたいのに表示義務になっていないのはなぜ?」といった声に応える議論が始まる、との期待があったとすれば、そもそも現在の議論のスタート地点がどこにあったのか、改めて認識しておく必要がある。
食品表示部会の委員であるJA全農の立石幸一食品品質・表示管理部長は「新しい法律が公布されたにもかかわらず、行政側に新たな理念に基づいて変えようとする意思が感じられない」と議論の姿勢に警鐘を鳴らしている。
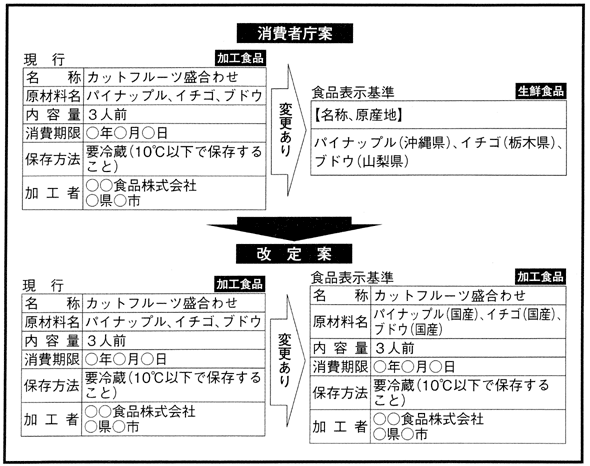
◆生鮮か、加工か
とはいえ、いくつかの新たな表示の考え方は示されている。
加工食品の原料原産地表示に関わる問題では、「生鮮品」と「加工食品」の区分の変更がある。 食品衛生法では食品を「カット((切断)」するだけでも“加工”としてきた。一方、JAS法では「カットしただけでは“加工”ではない」という考え方。JAS法の世界では加工とは「新たな属性を付加すること」だからだ。
そこで今回は表示ルールを策定するにあたり、「カット(切断)しただけの食品は生鮮食品」とすることが提案された。 ここで問題となるのが「異種混合」の食品。異種混合とは「カットフルーツの盛り合わせ」や「刺身の盛り合わせ」、「カット野菜ミックス」などである。
消費者庁は、さらにこの異種混合について、[1]焼き肉セットや刺身の盛り合わせのように「生鮮食品を単に組み合わせたり、盛り合わせたものは生鮮食品」、[2]合い挽き肉やサラダミックスのように「それぞれの生鮮食品が混合されて一つの商品として飲食、調理されるものは加工食品」と定義してはどうかと提案している。
つまり、異種混合の食品でも「生鮮」と「加工」があることになる。では、具体的にどのような表示になるのか。
◆加工品はなぜ?
現在、「カットフルーツの盛り合わせ」、「刺身の盛り合わせ」、「焼き肉セット」は加工食品扱いのため原材料の原産地表示の義務がない。しかし、これが「単に盛り合わせただけなら生鮮食品」との定義になれば、たとえばブリやイカについて“富山沖”“ペルー産”などと原産地を表示しなければならなくなる。ただし、加工品ではないため、加工者を表示する必要は必ずしもないことになる(水産物、食肉は製造所などの表示が必要)。
一方、「カット野菜ミックス」は「それぞれの生鮮食品が混合されて一つの商品?」だから加工食品、とされてしまうと材料であるキャベツ、タマネギなどの原料原産地表示はしなくてもいいことになってしまう。
この事例については調査会の議論でも「原料原産地表示がなくて消費者目線といえるのか」との意見も出たが、そもそも生鮮食品が原材料として使われているにもかかわらず、なぜ原産地情報が記載されていないのか、という素朴な疑問が消費者にはあるだろう。この定義に従えば、そうした疑問に応えることにはならない。
◆実例示し議論を
改めてこの問題を振り返ると、カットしただけの野菜や果物などを生鮮食品か、加工食品かに分類するところから、消費者感覚とずれるといえそうだ。
「カットして単に盛り合わせたもの」を生鮮食品としてしまうと、加工者を表示しなくてもいいことになることについて、調査会の議論でも「カットにも安全衛生面で問題がないことはない。加工者が表示されないのは不自然」といった指摘もあった。
こうした消費者の素朴な疑問や表示上の課題を解決するために立石氏が調査会に提案したのが、図のような表示だ。
考え方は、今回、問題となっている生鮮食品の異種混合については、すべてを加工品として位置づけ、原料原産地表示の対象とするというもの。ただし以下のような柔軟な提案もしている。▽国産品も産地名ではなく「国産」と記載しても可、▽輸入品についても「原産国名を記載する」というルールを見直し「輸入品」、「海外産」との記載も可、▽当面は原料原産地表示義務対象を重量順で4位までとしてはどうか、などである。事業者の実行可能性をふまえるとともに、少なくとも消費者が知りたい原料原産地についての情報提供は行っていこうというものである。せめてこの案をスタートラインにして議論することが必要ではないか。
そのほか、現在の加工食品では海外で半加工された原料を使用した場合は、原材料情報が表示されない問題もある。たとえばポテトチップスで米国製造のポテトフレークを使用していても、それが米国産であることは表示されない。消費者が国産ジャガイモを使用していると誤解している可能性は以前から指摘されてきた。この点についても、海外原料であることを枠外に記載するなどの具体的な案も示している。
消費者への情報提供は今後、国民から支持される日本農業にとって不可欠だ。消費者の知る権利に応える実践的な表示ルールに向け、着実な議論が求められている。
【消費者委員会】
独立した第三者機関として2009年9月に内閣府に設置。各種の消費者問題について自ら調査・審議を行い消費者庁を含む関係省庁の消費者行政全般に対して意見表明を行う。委員(10人以内)は内閣総理大臣が任命。本審議会のもとに食品表示部会のほか、新開発食品調査部会、公共料金等専門調査会、景品表示法における不当表示への課徴金制度に関する調査会などを設け、専門委員を置く。
重要な記事
最新の記事
-
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -
 シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日
シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -
 農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日
農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -
 ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日
ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -
 【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日
【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -
 全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日
全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -
 【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日
【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -
 【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日
【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -
 【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日
【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -
 【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日
【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -
 【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日
【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -
 【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日
【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -
 【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日
【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -
 【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日
【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -
 【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日
【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -
 【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日
【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -
 【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日
【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -
 2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日
2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -
 米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日
米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -
 【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日
【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日




































































