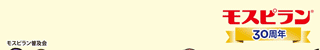【特殊報】ウメにクビアカツヤカミキリ 県内で初めて確認 千葉県2025年7月24日
千葉県農林総合研究センターは、ウメにクビアカツヤカミキリを県内で初めて確認。これを受けて、7月16日に令和7年度病害虫発生予察特殊報第2号を発表した。
 (提供:千葉県農林総合研究センター病害虫防除課)
(提供:千葉県農林総合研究センター病害虫防除課)
千葉県農林総合研究センターによると6月27日、千葉県北部のウメにおいて、クビアカツヤカミキリのフラス(幼虫の糞と木くずが混ざったもの)及び成虫が確認された(写真1)。
同種は東アジア原産で国内では、2012年に愛知県で初めて確認されて以来、15都府県で発生が確認。千葉県では、2024年10月にサクラで本種のフラスが初確認で、農作物への加害は今回が初めて。
ウメやモモ、スモモなどの加害情報はあるが、ナシやビワでは加害が確認されておらず、同虫の加害を受けにくいとされている。
クビアカツヤカミキリ成虫(写真2)の体長は2.5~4cmで、体色は全体に光沢のある黒色で、赤い胸部と長い触角がある。前胸背板の側方に1対のトゲ状隆起がある。
 (提供:千葉県農林総合研究センター病害虫防除課)
(提供:千葉県農林総合研究センター病害虫防除課)
同種は、サクラやモモ、スモモ、ウメなどの樹皮の隙間に卵を産み付ける。卵は2週間ほどで孵化し、幼虫は樹木内部を食害し、フラスを排出。幼虫期間は2~3年で春から秋にフラスが見られる。被害木は数年のうちに枯れ、成虫が近くの樹木に移ることで被害が広まる。同種は、産卵数が多く繁殖力が高いため早期発見、早期防除が重要。
同所では次のとおり防除対策を呼びかけている。
(1)特定外来生物に指定されているため、生きたまま持ち運ぶことは禁止されている。圃場内で本種を発見した際は、見つけ次第直ちに捕殺する。また、確認が必要な場合もあるため、捕殺個体は保管もしくは写真を撮っておく。
(2)疑わしいフラスを発見した場合、排糞孔(写真3)に登録のある殺虫剤を注入して内部の幼虫を駆除する。内部にいる幼虫には薬剤が届きにくいため、針金などでフラスをかき出し、排分孔に散布ノズルをできるだけ深く差し込んで殺虫剤を噴射する。多くの幼虫が穿孔して坑道がつながった状態になると、幼虫まで薬をいきわたらせることが難しくなるため、被害の軽微な木を対象に実施する。
 (提供:千葉県農林総合研究センター病害虫防除課)
(提供:千葉県農林総合研究センター病害虫防除課)
(3)成虫の脱出、分散を防ぐため、被害木を発見した場合は、目合い4mm以下の網を地際部から1~2m程度の高さまで巻き付ける。樹幹に網が密着していると成虫が網を噛み切って逃げる可能性があるため、網の糸は太いものを選び、余裕を持たせて巻く。
(4)詳細な防除対策は、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所の「クビアカツヤカミキリの防除法」を参照する。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日
シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日 -
 農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日
農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日 -
 米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日
米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日 -
 (471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日
(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日 -
 スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日
スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日 -
 【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日
【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日 -
 【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日
【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日 -
 【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日
【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日 -
 【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日
【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日 -
 令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日
令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日 -
 「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日
「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日 -
 2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日
2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日 -
 【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日
【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日 -
 福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日
福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日 -
 いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日
いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日 -
 三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日
三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日 -
 【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日
【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -
 【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日
【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -
 【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日
【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日