JAの活動:JA 人と事業
【JA 人と事業】第7回 周藤昌夫・JA斐川町代表理事組合長に聞く2013年8月30日
・転作で耕地利用率は117%
・振興区制度で政策徹底
・目指すは「1町1農場」
・販売起点の「ものづくり」を
・地域と農業守るJAの役割
島根県のJA斐川町は正組合員約3500人のJA、斐川町とともに昭和30年代の合併以来、枠組みの変動のなかった全国的にも珍しいケースだ。
出雲平野の水田地帯にあり、行政とJAが一体となって土地利用型農業を推し進めてきた。島根県経済連の島根ワイナリーの社長を経て地元の集落の営農組合長になり、麦やハトムギ、ヒマワリなどを栽培してきた周藤昌夫組合長に、「1町1農場」をめざす地域農業の取り組みを聞いた。
行政と一体で土地利用型農業
「農業が豊かになって地域が元気」
 ――JA斐川町の農業の特徴はどこにありますか。
――JA斐川町の農業の特徴はどこにありますか。
周藤 JA斐川町管内は、中国山地から宍道湖に注ぐ斐伊川の下流に水田が広がり、米を中心とした農業地帯です。昭和30年に6か村が合併して斐川村(40年斐川町)となった後、36年JAが合併しました。以来50年以上、1町1JAでやってきました。2年前、斐川町は出雲市と合併しましたが、これほど長期間、合併・統合もなく行政とJAの枠組み・組み合わせが変わらなかったところは珍しいのではないでしょうか。
それだけに町とJAが一体となった農業政策の推進はしっかりしています。農業が豊かになって町の商工業も元気になるのであって、その逆ではありません。町もこのことを理解し、農業を基幹産業として位置けてきました。その結果の一つが水田の圃場で、整備率は100%。30?1ha区画の水田に仕上がっています。灌・排水の施設も整備されており、水稲以外の作物の栽培も可能で、カントリーエレベーターやそれに付随する施設・設備も完了し、土地利用型の農業の体制が確立しています。
◆転作で耕地利用率は117%
さらに耕地利用率もあります。転作作物に麦、ダイズ、ハトムギ、ヒマワリなどの景観作物などを入れ、さらに不作地解消に加工用米を導入したことなどから、24年度の管内耕地利用率は、平成16年に比べて10ポイントアップの116.9%。これは中国地方のJAでトップクラスだと思います。
――具体的には、どのような形で行政と一緒に施策を進めましたか。
周藤 農政を推進する体制として、斐川町には農業振興区制度という独特の仕組みがあります。その基礎組織が複数の集落からなる「振興区」で、61人の振興区長が区長会を組織し、市行政とJA、農業委員会や農業共済組合などの農業に関係する団体や組織を網羅した斐川町農林事務局が提示した政策に集落の意見を反映させるというものです。
◆振興区制度で政策徹底
集落ごとに218人の振興区長補助員が配置され、区長と一緒に集落の営農座談会を開き、協議会が決めた政策を周知し、それについての意見をまとめるのです。昭和38年から取り組んでおり、これは政権が交替しても変わるものではありません。それが町やJAの政策に対する生産者・組合員の信頼を高め、JAの事業の伸びにもつながっているのだと思っています。
――水田が中心の土地利用型農業を進めていますが、どのような地域農業ビジョンを描いていますか。
周藤 土地利用型作物が作りやすい環境が整っていることから、24年3月末で、管内には認定農業者が75経営体、うち土地利用型が25経営体で、畜産が7経営体、特産・園芸が43経営体。それに集落営農組織が36経営体あります。認定農業者と集落営農を合わせた中核的な担い手がカバーする農地は69.1%に達しています。
◆目指すは「1町1農場」
地域水田農業ビジョンで掲げていますが、目指すは「1町1農場」です。その過程で、今後の地域農業の選択肢として、大型経営による担い手集積型、法人を含めた集落営農型、それに生きがい・楽しみ型農業の3タイプを提示し、集落営農座談会で議論を進めているところです。
いずれのタイプも農地の所有権と利用権の分離・見直しが必要で、この調整は斐川町農業公社が当たります。これも行政(出雲市)とJA、それに集落営農組合や土地改良区などからなる組織で、農地利用集積円滑化、農作業受委託あっせん、農業施設リースなどの事業を行います。
――地域農業ビジョンでは「売れるものづくり」を掲げていますが。
周藤 「売れるものづくり」は、水田農業ビジョンで掲げている「ものづくり」「ひとづくり」「しくみづくり」の中にある取り組み課題です。経済連時代を含め、専務・社長としての19年の島根ワイナリーの経験から、その重要さを痛感してきました。島根ワイナリーはワイン醸造と島根牛のレストランですが、よいワインを作ることはもとより、それをどう売るかが重要であって、山梨などの先進地のワイナリーを視察して学び、観光と結びつけた?観光ワイナリー?とすることで経営を軌道にのせることができたと思っています。ワイナリーでは販売面で大変勉強になりました。
◆販売起点の「ものづくり」を
水田農業ビジョンに掲げた「ものづくり」というのは単なるものづくりではなく、「販売起点のものづくり」であるべきだと考えています。うまく売ることができれば、作ることもうまくいくということです。主力の米は産地指定米50%を達成、ハトムギは8億円かけて麦と併用の乾燥調製施設を建設して生産量を増やし、発芽ハトムギ茶を販売。ヒマワリうどんも作っています。ハトムギは栽培面積が約80haあり、西日本ではトップの産地にすることができました。
2008年に設立した斐川町産地強化協議会で、当時29億円だった農業産出額を13%(3.7億円)アップすることを掲げましたが、こうした取り組みの結果、24年度は目標を達成することができました。全国の水田農業地帯では年――農業産出額が減っているなかで、この成果は行政と一体となった取り組みの結果だと思っています。
――地域と農業についてどのような思いをもって、取り組んでいますか。
周藤 管内の農家の生まれで、地域と農業に対する思いは人一倍持っていると思っています。町やJAが合併せずここまできたのは、農業の基盤がしっかりしていることから、町やJAへの信頼が高く、地域の絆が強いからだと思います。JAが運営する葬祭施設の利用率は94%。これはJAの地域密着度の高さを示すものです。
斐川町には、公社から分社化した有限会社「グリーンサポート斐川」がありますが、これは実際に農作業を行う会社で、農業公社の支援を受けて、農作業の受託、転作代行栽培、担い手農家のサポートなどを主な業務とします。実際は、条件の悪いところや受け手のいない農地の経営などに当たっているのですが、これまでの政策である地域に荒廃農地を出さないという町のJAの思いからきたものです。
◆地域と農業守るJAの役割
何度かスイスの農業を見る機会がありましたが、国民に地域の環境と農業を守るという意識が共有されていることが印象に残っています。環境保全、山間地整備などには直接支払いがありますが、平地にビニ――ルハウスがないのも感心しました。景観を損なわないということでしょうが、食生活に不自由があっても農産物は地元で生産したものを食べるという地産地消の考えが国民に浸透しているからだと思います。
日本では大震災や水害が続いたこともあり、農業の重要性が認識されつつありますが、単なる同情ではなく、食料と地域の環境を守ることが自分たちにとっても大事なことだということを知ってもらうため、JAは消費者の理解を深める取り組みを強めるべきです。TPP(環太平洋連携協定)問題などから最近、その必要性を特に感じています。
重要な記事
最新の記事
-
 【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日
【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日 -
 (472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日
(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日 -
 山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日
山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日 -
 大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日
大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日 -
 栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日
栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日 -
 大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日
大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日 -
 県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日
県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日 -
 まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日
まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日 -
 アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日
アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日 -
 「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日
「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日 -
 鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日
鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日 -
 農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日
農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日 -
 栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日
栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日 -
 調理技術教育学会「食品ロス!?」オンラインセミナー開催2026年2月6日
調理技術教育学会「食品ロス!?」オンラインセミナー開催2026年2月6日 -
 全ゲノム情報から赤色酵母サイトエラ属の系統分類学的位置が明らかに 東京農業大学2026年2月6日
全ゲノム情報から赤色酵母サイトエラ属の系統分類学的位置が明らかに 東京農業大学2026年2月6日 -
 春の彩りをひと袋に「春のつまみ種」期間限定発売 亀田製菓2026年2月6日
春の彩りをひと袋に「春のつまみ種」期間限定発売 亀田製菓2026年2月6日 -
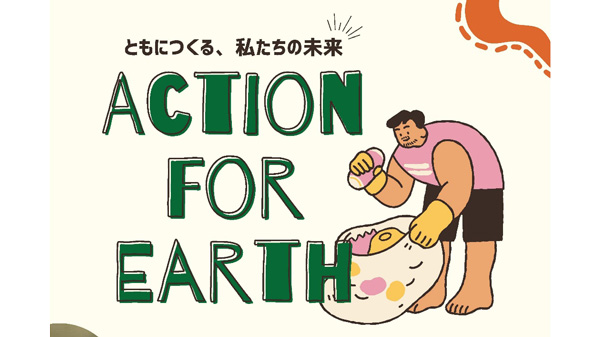 協同の力で地球環境の再生へ「Action For Earth 2026」開催 ワーカーズコープ2026年2月6日
協同の力で地球環境の再生へ「Action For Earth 2026」開催 ワーカーズコープ2026年2月6日 -
 ワインシティ推進支援で地域の魅力発信「地域おこし協力隊」を募集 長野県東御市2026年2月6日
ワインシティ推進支援で地域の魅力発信「地域おこし協力隊」を募集 長野県東御市2026年2月6日 -
 オリコン顧客満足度調査「食材宅配 首都圏」「ミールキット 首都圏」で第1位 生活クラブ2026年2月6日
オリコン顧客満足度調査「食材宅配 首都圏」「ミールキット 首都圏」で第1位 生活クラブ2026年2月6日 -
 オリコン顧客満足度調査 食材宅配東海で総合1位 パルシステム2026年2月6日
オリコン顧客満足度調査 食材宅配東海で総合1位 パルシステム2026年2月6日






































































